※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
細い網状の器の伸び縮みに合わせて、色彩がはっきりと面に見えたり、線になったり、縁のところは空気に溶けているようにも見える。ゆらゆらと軽やかな存在感の「空気の器」
 触ってみて、「ああ、紙か!」とわかってから一層、不思議な気持ちに駆られます。
触ってみて、「ああ、紙か!」とわかってから一層、不思議な気持ちに駆られます。紙、という身近な素材でありながら、見たこともないようなフォルムや使い方を、プロダクトとして提案する「かみの工作所」。
今回は、そのかみの工作所を運営している福永紙工株式会社で、営業担当を募集します。
会社にいる人みんなが、ものづくりの当事者。
営業も、ただ売るだけの仕事ではありません。
木曜日の朝、東京方面に向かう満員電車と逆のホームから、中央線で立川駅を目指す。
新宿から電車で30分ほど。駅に直結した百貨店や、新しい商業施設もあって駅前は賑わっている。
大通りを15分ほど歩いて、郊外らしい落ち着いた街並みに変わってきたあたりで、福永紙工の工場に到着。入口では大きなトラックが荷下ろしの最中だった。
 ここで、工場の製造担当と、営業企画の担当が一緒に働いている。
ここで、工場の製造担当と、営業企画の担当が一緒に働いている。工場に隣接したショールームで、常務の山田祥子さんに話を聞く。山田さんは、福永紙工の代表・山田明良さんのパートナーでもある。
 福永紙工は、立川で50年以上続く印刷加工会社。もとは山田祥子さんのお父さんの会社でもあった。「かみの工作所」というプロジェクトが11年前にはじまり、「空気の器」など、デザイナーと一緒にユニークな紙のプロダクトを多く手掛けてきた。
福永紙工は、立川で50年以上続く印刷加工会社。もとは山田祥子さんのお父さんの会社でもあった。「かみの工作所」というプロジェクトが11年前にはじまり、「空気の器」など、デザイナーと一緒にユニークな紙のプロダクトを多く手掛けてきた。「私も代表も、以前はアパレルの会社で働いていたんです。つくることが好きで、いまもずっと、つくる人の気持ちを理解したいという思いがあるんです」
依頼する限りは、デザイナーの仕事に口出しはしないという山田さん。
「デザイナーを信頼していなければものづくりはできないし、アイデアを大切にしてつくってみることで、本当に不思議ないいものができてくるんです」
売り先に合わせてものをつくるのではなく、面白いものができて、「さて、どこに売ろうか」というのが、福永紙工の営業のあり方らしい。
店舗の担当の方とコミュニケーションをとりながら製品を伝える場をつくっていくのが、営業の主な仕事。
売り場になるのは、百貨店から美術館、書店までさまざまだ。
ユニークな製品だけに、伝えることが難しいこともあるけど、売るための努力は惜しまない。
「誰にでも向き不向きはあるから、自分の得意なことを最大限発揮してほしいです。無理して心がポキっと折れないためにも、製品を心から楽しむ気持ちを大事にしてほしい」
一緒に働く営業のスタッフを、そんな思いで見守る山田さん。
普段から、すべての営業スタッフに、なるべくデザイナーとの打ち合わせに参加するように声をかけている。
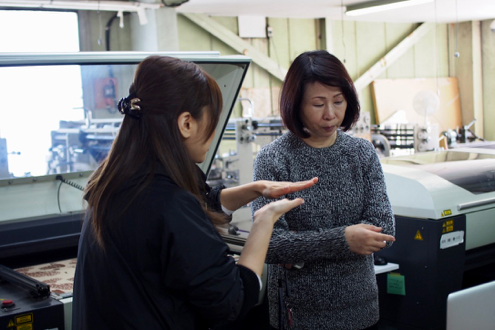 「自分の知らないところで生まれた製品を人に勧めることは難しいでしょ。営業は自分が感動したことを素直に伝えてほしいんです」
「自分の知らないところで生まれた製品を人に勧めることは難しいでしょ。営業は自分が感動したことを素直に伝えてほしいんです」デザイナーのアイデアに直接触れて、自分が感動したことをお店で伝える。
そこで人に楽しんでもらう仕掛けをつくるには、伝える相手の目線に立って考えることも大切。
お客さんの年代や関心に合わせたアイテム選び、目線の高さに合わせた什器の組み方、体の不自由な人でも気軽に入り込めるような動線づくりなど、ひとつの会場をつくるのに、山田さんたちはいくつもの視点から構成をチェックしているという。
 2018年の1月に開催された、地元立川の百貨店のフェアでは、駅から直結のエントランスが会場になっていた。
2018年の1月に開催された、地元立川の百貨店のフェアでは、駅から直結のエントランスが会場になっていた。高級ブランドに挟まれた、いわば百貨店の顔のようなスペース。
いい場所でやらせてもらう限りは、店舗側の期待にも応えたい。山田さんは、そんな思いで会場づくりに取り組んだ。
実際に立ち寄ってみると、パレットを積み上げた展示台を囲んで、幅広い年代のお客さんが集まっている。
中央に、空気の器が盛り盛りと広げられていて、みんな自由に手で広げたり触ったり楽しんでいる様子。見本がたくさんあるので、人が増えてきてもちゃんと一人ひとりの手に渡っている。
福永紙工のスタッフを囲んで、製品の説明を聞いているお客さんも、質問したり、友達同士で見せ合ったり、とにかく会話が多いのが印象的な会場だった。
「紙に親しんだ世代の方は、『知ってる、七夕の飾りでしょ!』って楽しそうに見てくれました。『立川にこんな会社あるのね』っていう声が、うれしかったです」
フェアは、製品を売る場であり、会社のことを知ってもらえる機会でもある。
営業が、自分のことばで会社のことを伝えられるのは、デザイナーと工場と普段から一緒にものづくりをしているから。
現場でのコミュニケーションのスピード感や、密度。
メーカーとしては珍しい三位一体のあり方だから、加工の面でも一般的には難しいアイデアを実現できる。
 だからこそ、大手の会社がたくさん扱っているオーソドックスなものや、フォルムが最初からある程度限定されてしまうような製品は、あえて自分たちがやるべき領域ではないと思っていたそう。
だからこそ、大手の会社がたくさん扱っているオーソドックスなものや、フォルムが最初からある程度限定されてしまうような製品は、あえて自分たちがやるべき領域ではないと思っていたそう。カードもそのひとつ。
「私は普段から百貨店や文具売り場によく行くんですが、あるとき、誕生日やクリスマスのカードって、どのお店でもなぜか一番いい場所に置いてあることに気がついたんです」
電話やメールで、ほとんどのコミュニケーションが成立してしまう時代だからこそ、特別な思いを伝えるときにはやっぱりカードを贈りたい。
今あらためてカードに根強い需要があるのは、そんな心理があるからかもしれない。
「それに、二つ折りで封筒に収まるものだけがカードじゃない。郵便で立体のものも送れるようになったし、今ならうちの会社らしいカードがつくれるような気がしたんです」
福永紙工らしいカード。
デザイナーの思いを伝えるために、紙の可能性を追求してきた会社だからこそ、人の気持ちを伝えるためのカードに、新しい一面を提案できるかもしれない。
そんなテーマが膨らんできたころ、入社してきたのが高橋さんだった。
 高橋さんは2015年、日本仕事百貨の「工場とデザインの橋渡し」という記事がきっかけで福永紙工に入社した。それまでは洋菓子メーカーで、パッケージデザインの仕事をしていたそう。
高橋さんは2015年、日本仕事百貨の「工場とデザインの橋渡し」という記事がきっかけで福永紙工に入社した。それまでは洋菓子メーカーで、パッケージデザインの仕事をしていたそう。入って間もなく、まだ営業の仕事もこれからというときに、任されたのが第1回ペーパーカードコンペ。
コンペ形式で作品を募るということも、会社としては前例のない試みだったので、募集から製品化までの運用そのものを一から考える必要があった。
入社してすぐに前例のないコンペを担当するのは大変そう。
「一番大変だったのは、作品の管理です。ひとつひとつチェックしてナンバリングしていくんですが、みなさん、熱い想いを持って応募してくださるので、開封しながら、すごく熱量を感じました」
 実は、このカードコンペにはもうひとつ、会社としてある思いに応えたいという意図があった。
実は、このカードコンペにはもうひとつ、会社としてある思いに応えたいという意図があった。当時かみの工作所を続けてもうすぐ10年になるころで、一緒に製品をつくりたいという、外部からの持込が増えてきていた。
デザイナーの発想に全幅の信頼を置くブランドだからこそ、最初にどんなアイデアを拾い上げて行くか、誰とやるか、ということに対しては慎重に考える必要がある。
一緒にやりたいという気持ちを嬉しく感じる一方、なかなか出会いを形に結び付けられずにいた。
だからコンペには、その意思に少しでも応えたいという思いもあった。
実際に募集をしてみると、プロのデザイナーから学生さんまで、160点を超える応募があった。
第一回のコンペで受賞した作品はすでに販売用に製品化されている。
学生さんの応募作品から新しい製品となった「星空の封筒」も、そのひとつ。
「ちょっと覗いて見てください」
と言われて真っ暗な封筒の中を覗き込む。
 二枚重ねた封筒の、内側の紙の穴から光が漏れてきて、内側に不思議な遠近感のある空間が生まれている。小さなプラネタリウムのようだ。
二枚重ねた封筒の、内側の紙の穴から光が漏れてきて、内側に不思議な遠近感のある空間が生まれている。小さなプラネタリウムのようだ。中に手紙を入れることもできるけど、封筒自体が贈り物としてとても印象的。
「私は割と筆不精なんですが、カードって、言葉が少なくても『あなたのことを大事に思っているよ』っていうのが軽やかに伝わっていいなと思います」
 たしかに、封筒の中に星空が見えたとき、誰かに見せたいと思った。
たしかに、封筒の中に星空が見えたとき、誰かに見せたいと思った。何かに感動したとき、とっさに思い浮かぶ人。
カードはその大切な人を思い出させてくれるツールなのかもしれない。
「星空の封筒」は今、福永紙工の主力製品のひとつになっている。
これまでの製品とはまったく違う経緯をたどって、製品が生まれることが新鮮だと高橋さんは言う。
2017年、2回目のコンペでは応募数も前回の倍以上に伸び、取り組みは広がりを見せている。
 「うちの場合はこういうコンペやワークショップなどいろんなことがおきるので、柔軟に対応できるほうがいいかもしれないですね。営業の仕事は本当にいろいろです」
「うちの場合はこういうコンペやワークショップなどいろんなことがおきるので、柔軟に対応できるほうがいいかもしれないですね。営業の仕事は本当にいろいろです」いろいろ。
「メインは店舗への発注業務や単発のフェアの会場構成ですが、デザイナーさんの展示のお手伝いや、空気の器を大量に吊るすような軽作業もあります。イラストレーターを使ってPOPのような販促ツールをつくることもあるんです」
高橋さんたちが仕事をするデスクと工場は、すぐに声をかけあえる距離にあり、相談もしやすい。
POPなど少量の印刷のときは、生産用とは別の社内の大型プリンタで、すぐに試作もできる。
「この端材もらっていい?」
取材している横で、こんな言葉が聞こえてきた。
こんなやりとりも、福永紙工ならでは。
 営業のスタッフは、普段から工場に出入りして製品ができていく様子を見ながら、今何が売れているかという話を共有したりする。
営業のスタッフは、普段から工場に出入りして製品ができていく様子を見ながら、今何が売れているかという話を共有したりする。営業が工場のことを知っているだけでなく、工場の担当もつくったものがどうやって人の手に渡るかを知っている。
目的意識を共有することで生まれる、一体感もある。
「普通の営業の感覚ではわかりにくいんですけど、うちの会社にとって大事なのは、たくさん売ることではなくて、世の中にこれが『ある』っていうことなんです」
今まで見たこともなかったものが、「できた!」という感覚。
いつも現場にいるからこそ、伝えられることばや視点があるような気がする。
 デザイナーと工場と、一緒に働く営業。
デザイナーと工場と、一緒に働く営業。ものづくりが好き、という気持ちに応えて余りある仕事だと思います。
(2018/1/25 取材 高橋佑香子)






