※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
一冊の雑誌。それは編集者の想いと、それに関わるいろいろな人の協力が実って形になったもの。
 取材を受けてくれる人、外部のクリエイター、そして、広告やタイアップを企画するクライアント。
取材を受けてくれる人、外部のクリエイター、そして、広告やタイアップを企画するクライアント。『Ollie』『GRIND』『nice things.』『PERK』などの雑誌を発行している、株式会社ミディアムには、その人たちと良好な関係を築き、一緒に“おもしろいこと”を実現するために働いている人たちがいます。
クライアントと雑誌、お互いのできることを最大限活かしながら、より良い付き合い方をプランニングする。
ときには誌面で伝えていることを体験できるイベントを企画することも。そうやっていろんなアウトプットの可能性を探るのがプランナーの仕事です。
今回は、そのプランナーと、編集者、フォトグラファーも合わせて募集します。
東京・西麻布。
メトロの表参道駅から、華やかなファッションブランドのウィンドウを眺めながら坂を下る。根津美術館を過ぎると、あたりは住宅街へ。株式会社ミディアムのオフィスは、その一角にある。
ミディアムの代表である谷合さん。30年前たったひとりで、雑誌の出版社をはじめた。
 「雑誌ってなんだろうっていうのを、我々はずっと考えていく必要があると思うんです」
「雑誌ってなんだろうっていうのを、我々はずっと考えていく必要があると思うんです」紙のマーケット、出版業界は年々縮小していく。目先の売り上げだけを考えていては、雑誌の存在意義そのものが危うくなってしまう。
「目的を持って情報を探す方法は、インターネットも含めていろいろあります。雑誌は、ただ情報を発信するのではなく、ライフスタイルに近いところで気づきになる、それで読者の情感が動くっていうことが大切だと思ってるんです」
気づき、ですか。
「ページをめくっていて、何かがふと目に止まるっていうことがありますよね。そこで、こんなおもしろい人がいる、こんな生き方があるって伝えられることが我々の考える雑誌の役割なんです」
 世の中にあふれる物事の中で、自分たちが何を選び、どんな生き方をしていくか。その出会いとなる雑誌をつくる編集者。谷合さんは一人ひとりに、意志を持って発信してほしいと考えている。
世の中にあふれる物事の中で、自分たちが何を選び、どんな生き方をしていくか。その出会いとなる雑誌をつくる編集者。谷合さんは一人ひとりに、意志を持って発信してほしいと考えている。ミディアムではこれまでも、そして今回も、採用時に経験を問わない。その理由を尋ねると、谷合さんは少し間をおいて答えてくれた。
「経験って、何でしょうね」
「出版文化って、主義主張を持つことからはじまって、その根底には自由と平等があるんです。そんな業界にあって、経験がないからって、人を締め出す必要はないと思うんです」
大切なのは、経験より考え方。
「同じ業界でも、まったく違う考え方で動いている人もいる。それに、技術だけでは伝わらないこともあると思いますよ」
そう話す谷合さんが5年前、会社の25周年のときに打ち立てたスローガンがある。
“雑誌の未来はミディアムがつくる”
「時代や環境の変化があっても、常に編集者自身が雑誌のあり方を考えて、小さなイノベーションを続けていくことが必要なんです」
雑誌の発行部数は、たしかに減っている。それは、一概にデジタルメディアとの競合のためではない。
「雑誌そのものの質の低下も関係していると思います。ページの中で、何を伝えたいかっていうのをきちんと考えていかないと」
「似たようなことはテレビ番組でもあって。番宣ばかりで、これは何かの告知のためにつくられたものなんだと、視聴者が気づいてしまうものはよくありますよね。この番組は何を伝えたいんだっていうのが、わからない」
雑誌をつくる上で、広告収入を切り離すことはできない。ただ、そこにおもねるばかりだと、媒体としての意志が見えなくなってしまう。
クライアントの窓口となるプランナーは、その良好な関係を考えていく役割がある。
『GRIND』の編集長代行として現場管理をしている本田さんは、昨年まで『nice things.』の事業部でプランナーをしていた。
 「誌面をつくる上で、読者からの信頼というか『この雑誌がいいっていうなら、いいものなんだろう』という思いを裏切ってはいけないと思うんです」
「誌面をつくる上で、読者からの信頼というか『この雑誌がいいっていうなら、いいものなんだろう』という思いを裏切ってはいけないと思うんです」世の中に何を伝えるべきか、それを一番に考えるのは編集者もプランナーも同じ。
「プランナーは広告枠を売るのではなく、クライアントになる人たちと『何か一緒に面白いことをやりましょう』っていう想いが基本なんだと考えています」
2017年に企画したのは、大阪の阪神百貨店との取り組み。
 「暮らしにいいもの百貨展with nice things.」は、雑誌『nice things.』で紹介した人、もの、に直接触れられる場をつくる試みだった。
「暮らしにいいもの百貨展with nice things.」は、雑誌『nice things.』で紹介した人、もの、に直接触れられる場をつくる試みだった。「誌面で伝えていることを、より立体的に。体験として伝える方法はプランナーの役割のひとつです」
ほかにも、メンズファッション誌『GRIND』では、Dr.Martinsのファッションショーや、FRED PERRY共催による、CosmoPykeというアーティストのライブなど、ファッションブランドと一緒にイベントを企画することもある。
 それぞれ雑誌が伝えてきたことを、誌面の外で実際に体験する。そのツールのひとつとして活用されるのが、オフィスの一階のスペース。
それぞれ雑誌が伝えてきたことを、誌面の外で実際に体験する。そのツールのひとつとして活用されるのが、オフィスの一階のスペース。取材や打ち合わせをすることもあれば、展示に使うこともできる。
 「ここは住宅街でもあるので、ギャラリーとして集客はそこまで見込めないし、僕たちも商業目的のスペース貸しをするつもりはないんです。読者と社会をつなげる接点として使えたらいいなと思って」
「ここは住宅街でもあるので、ギャラリーとして集客はそこまで見込めないし、僕たちも商業目的のスペース貸しをするつもりはないんです。読者と社会をつなげる接点として使えたらいいなと思って」「この前は塩津丈洋さんという園芸家の方が、ここで盆栽の展示をしました」
塩津さんと知り合ったのは、誌面の取材がきっかけだった。
 本田さん自身もそこで盆栽に出会い、今は紅葉の鉢を育てているそう。
本田さん自身もそこで盆栽に出会い、今は紅葉の鉢を育てているそう。「塩津さんは、もともと芸大で建築を学んでいた人で、展示の構成もすごくかっこいいんですよね。それに話を聞きながらひと鉢ずつ見ていくと、こいつはこう育っているとか、こいつにはこういう掛け軸を合わせたい、みたいにいろいろ世界が広がって面白いんですよ」
雑誌づくりを通じて知りあった人。その人たちを応援したいという思いが、企画のヒントになる。
「好きなお店や、場所、人。それを応援する意味は、好きだと感じている本人が一番わかっているはずだから、自分で考えて動ける人なら楽しめると思います」
好きなものをもっと伝えたい。プランナーも編集者も、興味や関心が一番の原動力になる。
「編集は、熱意でしかないと思います。あとは謙虚であればあるだけいい」
そう話してくれたのは、現在『Ollie』の編集長として2年目を迎えた鈴木さん。
 約10年前、鈴木さんと編集の仕事を結びつけたのは、バイクだった。
約10年前、鈴木さんと編集の仕事を結びつけたのは、バイクだった。「ハーレーダビットソンみたいな1940年代とかのバイクを買いたくて、職人をやっていました。8時〜17時とかの仕事で早く帰れるし、本読むのがちっちゃいころからすごい好きだったから、バイクの本とかを読んでました」
鈴木さんが読んでいたのは、当時『Ollie』で連載されていた“バイカーズボンド”というページ。見開きで古いバイクに乗っている人たちを紹介するものだった。
そこで新しいバイク雑誌をつくるために、編集者を募集していることを知る。
「バイクのローンも払い終わっていたし、職人を辞めてやってみようかなと思って」
「でも、その雑誌は諸事情ですぐ廃刊になって。僕にとって、編集のモチベーションはその雑誌でしかなかったので、会社を辞めました」
それから1年後。雑誌復刊の知らせと一緒に、会社に戻る流れに。
「その本には思い入れがあったし、社長に頭下げて戻ってきたんです。でも、今度は編集長が辞めてしまったので、結局それから4年間、一人で雑誌をつくってました」
古いバイクというニッチな業界の中で、ある意味、やりきったと感じていた頃。ストリートカルチャーを伝える雑誌『Ollie』がリニューアルのタイミングを迎え、編集長を務めることになった。
「僕は、ストリートの人たちが好きだし、そこらへんにいる市井の人が一番かっこよくて偉いって常に思っているんです。著名な人に話を聞いても、予定調和になりがちっていうか、あんまり魅力的だと思ってないですね」
 大切なのは、自分たちが誰よりも取材対象者のファンであること。
大切なのは、自分たちが誰よりも取材対象者のファンであること。「取材をさせてもらった人に言われたことがあるんです。『編集者って、俺らよりも俺らのことを理解してないと、伝わる純度が下がっちゃうからダメだよね』って」
SNSをはじめ、アーティスト本人から発信される思いを直接受け取ることもできる今日。わざわざ雑誌を介すことの意味ってなんだろう。
「自分たちは、誰よりもあなたのことが好きで、紹介させてくださいっていうのに尽きると思うんです。」
ラッパーの仙人掌さんも、鈴木さんが好きなアーティストの一人。
 「1年前、彼に『HIPHOPって何ですか』って聞いたら『力かな』っていう答えが返ってきて、そのことがずっと引っかかっていたんです」
「1年前、彼に『HIPHOPって何ですか』って聞いたら『力かな』っていう答えが返ってきて、そのことがずっと引っかかっていたんです」このやりとりからつけた特集のタイトルが“HIPHOPの力”。
いつもは、社長の谷合さんと相談しながら決める各号のタイトル。今回は、これでなければ伝わらないと、鈴木さんの強い希望を通した。
「特集のために取材をすることになったとき、『家でじっくり考えたいから、メールインタビューか、それに近い形で』と言われて。彼のことを知っている人なら、その言葉も『仙人掌さんっぽいな』ってわかると思います」
はじめはメールからリライトして編集する予定だった。ところが、返信された内容を見て、鈴木さんは考えを改めた。
ニュアンスをリアルに伝えるために、一切編集を加えず、メールで送られてきた原文のままの言葉で誌面を構成。もちろん、鈴木さんがメールで送った質問もそのまま。
「僕は正直、誤字脱字が悪いと思っていなくて、その人のキャラクターのひとつだと思うんです。書いた人の個性が、文章の良さだと思うから」
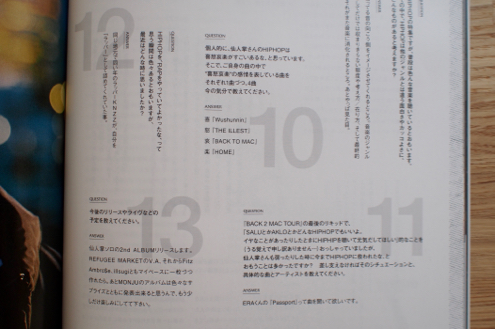 自身もストリートカルチャーの中で、多くの出会いを体験してきた鈴木さん。
自身もストリートカルチャーの中で、多くの出会いを体験してきた鈴木さん。「10〜20代の読者には、それをいつか卒業するものみたいに捉えて欲しくないんです」
「僕より上の世代で、昔は捕まったりした経験のある人でも、今は普通に働いて、家族を養って、それで今でも普通に朝までクラブに行って。それを両立している人もいるから、40、50でもそのままいけるって伝えたい。次は、そういう人たちを紹介する雑誌をつくりたいですね」
自分たちだから、伝えられる。
雑誌の未来をつくるのは、そんな熱量なのだと思いました。
(2018/6/8 取材 高橋佑香子)





