※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
今日も本屋を開ける。古い本を売るからこそ、一冊一冊を大切にして整理整頓したい。掃除をして、パイを焼き上げてコーヒーを淹れる準備。たちまちいい香りが店内に充満する。
オープンしてからしばらくすると、常連さんがやってきた。相手によって、適度なコミュニケーションを考える。気がついたら夜になって、バー営業のスタッフと交代。世間話ついでに、一杯飲んで帰ることにした。
 これは馬喰町にできる新しい本とコーヒーのお店「イズマイ」のお話。本はBOOK TRUCKの三田さんが選書したものが並びます。
これは馬喰町にできる新しい本とコーヒーのお店「イズマイ」のお話。本はBOOK TRUCKの三田さんが選書したものが並びます。ただ、まだオープンしていないから、話を聞いて思い描いたぼくの想像です。でもなんとなく、こういう毎日になるのだろうな、と思います。
昼はコーヒー店のマスターのように、夜はバーのバーテンダーのように。この場所を訪れる人に、心地よく感じられる場をつくる人を募集します。
東京の東にある馬喰町。表面しか見なければ、少し閑散とした問屋街にしか見えないかもしれない。でもよく見てみると、いろいろなギャラリー、カフェなどが集まっていることに気づく。実は仕事百貨でも、最近は東京で最も取材することが多いエリアです。
このエリアの中心とも言えるのが、泰岳ビルの1階にある「フクモリ」。
ここは山形の食材をいただくことができる定食屋さん。山形の3軒の旅館がオーナーである合同会社ハイタスと、K.K.H.K brand designというデザイン会社が一緒に運営しているお店。ちなみに、K.K.H.K brand designは、フクモリの螺旋階段を上がった2階にある。「イズマイ」もまた合同会社ハイタスとK.K.H.K brand designがはじめようとしている新しいプロジェクトであり、泰岳ビルと道路を挟んだ向かい側にできることになる。
それにしてもなぜこの場所に事務所やお店をつくろうとしたのだろう。普段は「ブランドデザイン」の仕事をしている、K.K.H.K brand design。普通に考えれば、青山や恵比寿なんかにできそうだけれども。
すると代表の小松さんは、はじめてこの場所に向き合ったときのことを話してくれた。
「まち全体としては元気のない感じが一瞬あって。ただ、東京R不動産の馬場さんに色々ご案内いただいて中を覗くと、いい意味で変化が起きていたんです。1つのコンテンツを掘り下げるという意味では、他のエリアよりも面白みがあるんじゃないかって。」
 「将来にわたって、開発などでまちが大きく変わることもなさそうだし、同じようなマインドの人たちが、自分たちでまちの人たちとゆるーい連動感を持っているんです。そうして一緒に何かをつくりあげて、このまちに根をおろしていく感じがすごい良かったんです。」
「将来にわたって、開発などでまちが大きく変わることもなさそうだし、同じようなマインドの人たちが、自分たちでまちの人たちとゆるーい連動感を持っているんです。そうして一緒に何かをつくりあげて、このまちに根をおろしていく感じがすごい良かったんです。」一方で、東京の南は嫌いではないけれども「間借りしている感じ」があるそうだ。
「はじめは、青山とか恵比寿を考えたけれど、根を下ろすことができない感じがして。でも、馬喰町でならまちのパーツになれそうな気がしました。間借りするというよりも、ここで果たさなければいけない重要な機能を、もしかしたら我々でできるんじゃないかと。とっさに浮かんだんですよ。」
小松さんはブランドをデザインする自身の仕事のことを、木を育てるようなものだと話す。それは種が芽を出し、しっかり根をはって、太い幹に育っていくようなもの。
根っこが生えていないにも関わらず、葉っぱだけがどんどん伸びていくようなものとは、まるで違う。
むしろ、枝葉は働く人やお客さんがつくっていくものだと、小松さんは考えている。
「ブランドを育てることが木に似てるというのは、結局まっすぐ伸ばしてやろうってあまり思わないことなんです。とにかく幹は太くありたいけれど、時代によって曲がることもあるし、ぐにゃぐにゃってなることもある。でも、それが自然じゃないですか。」
 フクモリで食事をすると、それを実感する。
フクモリで食事をすると、それを実感する。新しくお店ができたから!という感じで、一度だけ訪れたきり、足が向かなくなる場所ではない。まず食事がおいしいし、コンセプチュアル過ぎることもなく居心地がいい。何よりも働いている人から伝わってくる感じがいい。とても自然体というか。
ディレクターがコンセプトからすべてつくりあげてハコができ、オープン時こそ盛り上がるけれど消費されるだけの場所とは違うように思う。しっかりと軸が考えられているので強度があるし、そこで働いている人たちも自分ごととして関わっているから、できあがる「ムード」のようなものがある。
いわゆる「飲食コンサル」的な発想で言えば、不合格なお店なのかもしれないけれど。
この心地よさは、どこから生まれているのだろう?座り心地のいいソファや美味しい山形の食材だけではなさそうだ。
すると小松さんは、働く環境を整えることが大切だと語る。
「飲食業界の常識に合わせたくないんです。社会の常識に合わせるほうがハッピーだと思っていて。ちゃんと働く人にも休む時間があるから、お店の雰囲気もよくなるし、余裕が生まれる。」
するとお客さんもまた来たくなる。結果として売り上げも安定する。
「だから、木を育てるのも、種を植えたら育つのは自然に任そうと考えています。やっぱりそこにいる人の醸し出すムードが全てだと思っていて。」
ただ、本当は口を出したい小松さん。でもそれをこらえるから、いい「ムード」は自然と生まれる。もしすべて細かく口出ししてしまうと、その押しつけがましい感じは、お客さんにも伝わってしまうかもしれない。
基本的なことは共有しつつ、あとは何をすべきか自分で考えて働く。ある意味では自由なことだけれど、もちろん責任感を持ってもらわないと成立しないもの。
なぜこのような考え方が生まれたのか。それは小松さんの仕事の歴史を振り返ってみるとわかってくる。
「まず、メーカーである日本企業を6年経験して、たまたまアディダスジャパンが日本法人を設立することになり、お声をかけていただいて移りました。はじめは一次メーカー、アディダスでは二次メーカー、そして今はサービス業だから、三次メーカーをしている。そのプロセスが、図らずとも川上から川下まで経験することになったし、かつ外資の経験も大きくて。」
「その中で実感したことは、軸があればやりやすい、ということ。その軸を失っちゃいけない。しっかり構築しながらディティールもつくる。会社の内側にいることで、ビジネスも理解しながらプランニングできたのがよかったんです。」
すべてのことを頭の中に入れて、個人が考えに考え抜いたものは、チームで分業するよりも、強度が強くなることがあるように思う。
軸となる部分は小松さんたちが考えたので、あとはそれに共感してお店を育ててくれる人が来たらいい。「雇われ店長」的な発想ではなくて、あくまで自分ごととして考えられる人が向いていると思います。
「コンセプトに共感して、ちゃんとコミュニケーションの起承転結を考える。その上で自由があると思うんです。あとは人が好きな人がいいですね。書店なので本やアートや文化に知見があったほうがいいとも考えたけど、一番は人が好きってこと。本は三田くんが選書してくれるから。あとは話すよりも、聞くのが好きな人がいい。」
 たしかにお客さんによって、お店やスタッフは育つように思います。
たしかにお客さんによって、お店やスタッフは育つように思います。「そうですね。バーもそうですけど、シングルモルトってこうなんですよって、うんちくを語るお客さん、いるじゃないですか。そうやって店やスタッフは、お客さんに育てられると思うんです。」
大きな軸を考えるのが小松さんなら、枝葉を考えていくのが、ここで働く人であり、このプロジェクトを担当する笠井さんだと思う。
より具体的にお店のことについて、笠井さんに聞いてみる。
「店のコンセプトは、『風化しない価値を集める店』です。なぜ風化しない価値求めるのかというと、情報やモノとか、簡単になんでも手に入る時代だけど、結局我々はそれに流されていると思うんです。すごく受動的に体験させられている。」
 そんな時代に必要だと考えたのが、「コーヒー」であり、「本」だった。
そんな時代に必要だと考えたのが、「コーヒー」であり、「本」だった。「コーヒーは毎日買いにいくものだし、3〜400円で買えるもの。だから本は買わないかもしれないけれど、なんとなく来て、コーヒーを飲んで店員さんとおしゃべりして。知り合いを紹介してもらったり、なにか人の集まるきっかけとして、コーヒーってすごくいいと思っていて。」
たしかにふらりと寄る、という場所はもっと必要だと思う。たまには目的なく行動したいときがある。
「あとは、今だとフクモリに行こう、スターネットに行こう、だから馬喰町に行こう、となるのだけれど、いきなり馬喰町に行こう、って言ってもらえることが、次に大切なんじゃないかと思うんです。たとえば、代官山に行こうのように。」
多くの人にとって、馬喰町は目的なく訪れるような街では、まだないかもしれない。でもふらりと行きたい街には、目的なく歩いていても何かに出会えるような、「いい予感」がするものだと思う。
古い本を売ることにも、ちゃんとしたイメージがあるそうだ。
「今だからこそ紙の本だと思うんです。」と語る笠井さん。
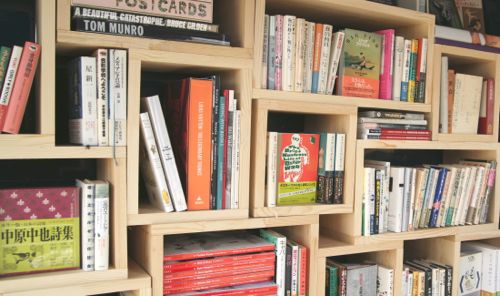 僕自身も少し前までは、すべて電子書籍になったほうが便利だと思っていた。いつでも読みたいときに本が読めるし、紙の本なんて懐古主義でしかないんじゃないかと。でも実際には、紙の本によって得られる経験は、電子書籍のそれとはまったく異なるものであるように感じる。
僕自身も少し前までは、すべて電子書籍になったほうが便利だと思っていた。いつでも読みたいときに本が読めるし、紙の本なんて懐古主義でしかないんじゃないかと。でも実際には、紙の本によって得られる経験は、電子書籍のそれとはまったく異なるものであるように感じる。たとえば、電子書籍を見ていると、そのほかのことも気になってしまう(twitterやメールをついついチェックしてみたり)。でも紙の本ならば、本に集中できる環境がつくりやすいように思う。結果として、言葉がしっかりと体に入ってくる。
「電子書籍とかウェブマガジンこそ流れていくものの代表じゃないですか。この場所でやる必要はまったくないと思います。そういうものは沢山の人が行き交うような、分母の大きい街でやればいいわけで。ここのデメリットは人が少ないことですけど、だからこそ流されずに自分たちで流れをつくっていけるメリットがある。」
 まるで茶室のようなお店になるような気がした。ゆっくりとコーヒーで客人をもてなし、それぞれが古い本を読む。
まるで茶室のようなお店になるような気がした。ゆっくりとコーヒーで客人をもてなし、それぞれが古い本を読む。便利なものや効率的なものに目を奪われてしまいがちだけれど、じっくりと何を心地よく感じるのか考えてみると、こういう営みをもっと大切にしなければいけないような気がしてくる。
もしここでじっくりと働いてみたい人がいたら、ぜひ応募してみてください。思いに共感できれば、素敵な毎日になるように思う。(2012/7/12 up ケンタ)

