※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
「僕たちに仕事百貨を紹介してくれた子が言っていたんですよ。仕事にはライフワークとライスワークがあると。ライスワークはご飯のために働くという意味だそうです。だから、ここで働く人も、この仕事をライスじゃなくてライフワークにできるような人がいいと思っています。」テミルの代表、船谷さんがこんな話をしてくれた。
ライスワークは、例えば時計を気にしながら仕事が終わるときを心待ちにするような仕事のことかもしれない。その一方で、時間が経つのも忘れて熱中してしまうような、ライフワークと呼べる仕事もある。
ライフワークでご飯を食べることができたら、それが一番の理想だと思うけれども、そんな仕事を見つけるのはなかなか難しい。
でも、この仕事ならだれかのライフワークになるかもしれない。そう思える仕事に会いました。
 都営三田線の芝公園駅を降りると、すぐ目の前はオフィスビルが立ち並ぶ日比谷通り。
都営三田線の芝公園駅を降りると、すぐ目の前はオフィスビルが立ち並ぶ日比谷通り。スーツ姿の人たちで賑わうコーヒーショップの角を曲がると、株式会社テミルのオフィスが入る5階建てのビルが見える。
テミルの由来は、「やってみる」「外にでかけてみる」「働いてみる」の「てみる」から。身体や精神に障碍(しょうがい)を抱える人は、外にでるのが億劫になりがち。船谷さんは、そんな人たちが外に出てみたくなる環境をつくりたい、という想いを込めて、6年前に創業した。
今、主な事業として取り組んでいるのが、お菓子の商品をプロデュースする「テミルプロジェクト」。
パティシエがレシピの提供と製菓指導を行い、福祉の授産施設が実際に製造する。そうして完成したお菓子を、絵本作家が描いたパッケージに入れて販売する。パティシエ×福祉施設×作家のコラボレーションで商品を産み出すという取り組み。
例えば、看板商品のひとつ「石けりコロロ」は、菓子工房アントレが監修し、福祉施設「hana」が製造し、絵本作家の村上康成さんがパッケージイラストを担当した。
 千葉県のマザー牧場で採れた牛乳を使い、スペインで古くから伝わる伝統菓子「ポルボローネ」をモチーフに、ひとつひとつ丁寧に丸めたお菓子。マザー牧場のおみやげとしても人気の商品となっている。
千葉県のマザー牧場で採れた牛乳を使い、スペインで古くから伝わる伝統菓子「ポルボローネ」をモチーフに、ひとつひとつ丁寧に丸めたお菓子。マザー牧場のおみやげとしても人気の商品となっている。他にも、世界的に有名な辻口博啓シェフが製造指導に入った「ハスカップマフィン」や、子供だけではなく大人にも人気の絵本作家、荒井良二さんがパッケージを手がけた「はっぴぃ ぷれいすBe ガレット」などがある。
パッケージだけで思わず手にとってしまいたくなる、心をくすぐる商品たち。福祉施設が売っているクッキーと聞いて思い浮かぶようなものとは少し違うように思える。
 そんな感想を伝えてみると、船谷さんがこんな話をしてくれた。
そんな感想を伝えてみると、船谷さんがこんな話をしてくれた。「よく、障碍者の福祉施設でパンやクッキーをつくって売っていますよね。実は、ああいった作業をされている方の平均工賃は1ヶ月1万3千円程度なんですよ。それはあくまでも厚生労働省発表の平均値であり、実際は月3千円の方もたくさんいるのが現状です。生活のハリを得るために働くということならば、そのくらいで良いという声もあるけど、工夫次第でもっと工賃は上がるのに、と思ったんです。それがこのプロジェクトのはじまりでした。」
障碍者の工賃を上げるため、船谷さんが目指したのは、「最高」のものをつくることだった。
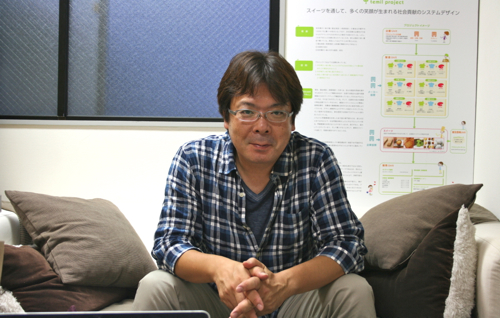 「福祉だから許される、は無し。ちゃんと味やパッケージに強みを持ち、何回も買いたくなるような商品価値をつくりたいんです。」
「福祉だから許される、は無し。ちゃんと味やパッケージに強みを持ち、何回も買いたくなるような商品価値をつくりたいんです。」「福祉」を売り物にせず、「商品の質」で勝負したい。そう思った船谷さんは、さっそくパティシエ、作家、福祉施設に呼びかけ、この事業をスタートした。
今では催事に呼ばれることも増えたし、ネットショップ「テミマ」もオープンして、事業は大成功。
昨年度には、障碍者の低賃金問題を解決する社会的な仕組みが評価され、グッドデザイン賞を受賞した。
「障碍者への差別や偏見は、知らないからあるんです。だから、商品を通して知ってもらいたいと思っています。賞をとったことも嬉しいけれど、協力してくれる人が増えてきたことが一番嬉しいですね。」
商品が売れれば、障碍者の工賃が上がる。「やってよかった」とパティシエや絵本作家に言ってもらえる。買う人には商品をきっかけに障碍者の賃金問題について知ってもらえる。だんだん、そんなハッピーな循環ができてきた。
 この会社を立ち上げる前のことを聞いてみる。
この会社を立ち上げる前のことを聞いてみる。船谷さんはもともと、公務員として福祉専門職の仕事をしていた。でも、入って3ヶ月で辞めようと思ったほど仕事が肌に合わなかった。やる気のない上司に腹を立てて、本気で怒ったこともあった。内側から変えようと組合に呼びかけたりもしたけれど、努力は実らなかった。
10年経ったころ、そんな船谷さんに松下電工(今のパナソニック)から声がかかった。
「介護事業の立ち上げを手伝ってくれないか、というお誘いがあったんです。そこで、訪問介護事業や福祉用具貸与事業の企画を自由にやらせてもらいました。CMをつくるマーケッターの人と関わることもあり、そこでものの魅せ方を学びましたね。」
「公務員のときは、収入は安定していたけれど、気持ちが安定しなかったんだよね。」と船谷さん。
一度福祉の外にでて、外から福祉に関わることで見えたものがあった。松下電工での日々は、今の仕事にも繋がる原体験になっている。
 これからの話を聞いてみた。
これからの話を聞いてみた。今やろうとしているのは、「テミカフェ」というカフェのフランチャイズ事業。
障碍者の方たちが運営しているカフェはよくあるけれど、やっぱり船谷さんが考えるカフェだから、普通とは違うこだわりがある。
「銅板で焼いた黄金色のホットケーキ食べたことあります?銅板で焼くと、均一に火が通るから綺麗な黄金色になるんですよ。それをメニューで出したいと思っています。せっかくならうちならではのメニューをつくりたいと思って、クラブハリエさんに相談したら、粉の配合をつくってくれました。つぶつぶのバニラビーンズがたっぷり入った黄金色のパンケーキを出す予定です。」
 パンケーキだけではなく、紅茶にパニーニ…と話は広がる。思わずにやにやしてしまいそうな、おいそうな話が続く。
パンケーキだけではなく、紅茶にパニーニ…と話は広がる。思わずにやにやしてしまいそうな、おいそうな話が続く。船谷さんは、食べ物の話をするとき、にこにこと楽しそうに話すのが印象的。
「やっぱり、おいしいものを食べると人の笑顔をつくるでしょう。僕もおいしいものが大好きなんですよ。」
でも、こんなふうにメニュー開発まで自分たちでやっていると、大変じゃないですか?
「コンサルティングとして失格だと言われました。むしろ実践者だろうって(笑)」
カフェをやるとなったら、店舗やメニュー開発、内装、食器を選ぶところまで全て関わる。
それは、カフェだけではなく全部に対して言えること。こだわりがあるから、細部まで手をかける。時と場合によって常にやるべきことは変わっていく。
だから今回募集する仕事も、「事務職」とか「デザイン職」とか、そんなふうには言い切れない。しいていうならなんでもやる!という「なんでも職」かもしれない。
新卒でこの会社に入り、今は入社6年目の中尾さんに、「なんでも職」の日々について話を聞いてみた。
 「最初は今のような事業ではなくて、障碍者や高齢者に商品の使いやすさについてアンケートをとるアクセシビリティの調査をやっていたんです。そこからお菓子のプロデュースになって、今度はカフェもはじめる。本当に、何があるか分からないですよ(笑)」
「最初は今のような事業ではなくて、障碍者や高齢者に商品の使いやすさについてアンケートをとるアクセシビリティの調査をやっていたんです。そこからお菓子のプロデュースになって、今度はカフェもはじめる。本当に、何があるか分からないですよ(笑)」この通りにして、というフォーマットがあるわけではない。ハプニングも当たり前。催事をやるとなったら売り場を回さなければいけないし、カフェだったらオープンに向けて店舗を探したり、紅茶の淹れ方まで勉強している。
だけど、それが楽しいんです、と中尾さん。
しんどいことはないですか?
「しんどいこともありますよ。色々な調整に追われるし定時には帰れなかったりするし。でも、ここだと何のために仕事をしているのか見失うことがないんですよ。自分がしていることが、人の役に立っていると感じることができるんです。」
「例えば、デパートでお菓子を売っていると、お菓子をつくった福祉施設の方たちが見学に来て、なんでそんなに飽きないの?というくらいずーっと、嬉しそうにお菓子が売れていくところを見ていたり。大変なことがあっても、そんな風に人が喜んで感謝してくれるところが見えると、また頑張ろうって思えますね。」
 中尾さんは、大学、大学院と6年間福祉を学んでこの会社に入った。だけど、新しく入ってくる人は福祉を専門にしていなくても構わないそうだ。
中尾さんは、大学、大学院と6年間福祉を学んでこの会社に入った。だけど、新しく入ってくる人は福祉を専門にしていなくても構わないそうだ。「福祉って特別なものではなく、社会の一部なんですよ。だから、バランスの良い人がいいですね。福祉というよりも人権感覚というか、1人ひとりに敬意が払えれば良いと思います。あとは、障碍者の低所得問題とか、そういうところにちゃんと問題意識を持っている人がいいです。」
「うちでやっていることって、福祉の世界ではめちゃくちゃ画期的なんですよ。これがモデルとなれば教科書に載るくらい。障碍者の低所得問題に対して、実際に解決する仕組みをつくっている。新しい仕組みを自分たちでつくっていけるのはすごい魅力的ですよ。」
想いを持っていれば、話をちゃんと聞いてもらえる環境もある。
「社長の船谷さん相手に、ときにはわたしが本気でぶつかっていくときもあります。わたしが言いたいことを伝え、船谷さんがなぜそういう決断をしたのかを知るためです。ときに納得できないことがあっても、私の話をとことん聞いて、なぜそうなのかを分かるまで説明してくれます。こんな環境はなかなかないと思います。わたしはこの会社に入って20代のうちにライフワークに出会えたので、ラッキーだったと思います。」
最後に、船谷さんがこんなことを言っていました。
「人の笑顔をつくる仕事だから、自分が笑顔じゃないとね。自分が幸せじゃないと人が幸せになるお手伝いなんてできないですから。だから、まずは自分を充実させてもらえたらいいな。元気で明るい人がいちばんです。」
 多分、この職場では、ありがとうの交換が沢山あると思う。感謝されたりしたりしながら働けるのは幸せなこと。それがこの会社でできそうだと思ったら、福祉の知識よりも大切なものがすでに備わっている証拠だと思う。
多分、この職場では、ありがとうの交換が沢山あると思う。感謝されたりしたりしながら働けるのは幸せなこと。それがこの会社でできそうだと思ったら、福祉の知識よりも大切なものがすでに備わっている証拠だと思う。だから、一歩踏み出してみてください。(2012/8/23up ナナコ)

