※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
つなげることに価値がある時代だと思う。ちょっと言い方を変えるならば「編集」することで、いろいろなものが組み合わさり、足し算というよりもかけ算のように価値が生まれていく。
世田谷サービス公社では、「世田谷くみん手帖」をはじめとして、様々なヒトとモノとコトをつなげていくことで価値を生む企画編集ディレクターを募集しています。ただ、役割としてはプロジェクトマネージャーとも言えるし、企画制作ディレクターでもあり。もっと言えば世田谷のまちづくりをすることになるかもしれない。それくらい幅広い役割の人を募集します。
 三軒茶屋駅を降りて、路面店の並ぶ茶沢通りを下北沢に向かって歩いていく。渋谷から伸びている淡島通りとの交差点に世田谷サービス公社の事務所がある。
三軒茶屋駅を降りて、路面店の並ぶ茶沢通りを下北沢に向かって歩いていく。渋谷から伸びている淡島通りとの交差点に世田谷サービス公社の事務所がある。もともと世田谷区の第三セクターとしてスタートし、総合福祉センター、区民センターなどの区民施設を維持管理してきた。その後は区民農園の管理や世田谷美術館に併設されているレストランなどの運営もするようになる。
さらに2012年からは三軒茶屋駅の地下にある広告スペース「三茶パティオ」の広告事業、屋根に太陽光発電を設置する「世田谷ヤネルギー」をはじめ、「エフエム世田谷」と経営統合もした。
そして「世田谷くみん手帖」というウェブサイトをはじめることになった。
 これは世田谷のヒト・モノ・コトが整理されて紹介されているもの。世田谷に暮らす人たちはもちろん、働く人など世田谷に集まってくる様々な人たちに向けて、目的別に情報を提供するとともに、まるで雑誌を読むような記事も掲載されている。
これは世田谷のヒト・モノ・コトが整理されて紹介されているもの。世田谷に暮らす人たちはもちろん、働く人など世田谷に集まってくる様々な人たちに向けて、目的別に情報を提供するとともに、まるで雑誌を読むような記事も掲載されている。たとえば美味しいビールが飲めるお店の紹介から”くみん”の方のインタビューまで。その内容は実に様々だ。
なぜこのウェブサイトをはじめることになったのか。世田谷サービス公社の山本さんに話を聞いてみる。
「もともと、区立施設の維持・管理っていう、ビルメンテナンスから始まった会社なんです。その中で施設を使ったいろいろなイベントであったり、地域向けの情報発信のようなことを実際やっているんですが、なかなか区民の方に伝わっていないっていう実情があって。せっかくいい施設を持ってるのに、もっと区民の人に利用してもらわなきゃ損ですよね。」
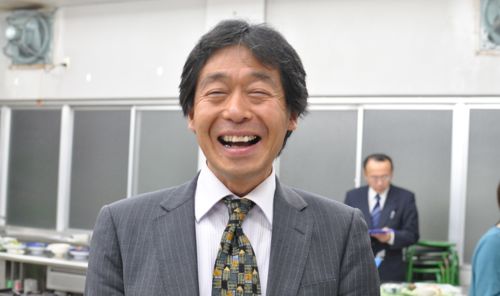 世田谷区が直接運営するものなら、なかなか民間の情報を掲載することは難しい。けれども世田谷サービス公社は株式会社。行政が直接手がけると手の届かない民間の情報まで自由に編集できる。あくまで世田谷で暮らす人、働く人、訪れる人、そういった『人』に対してあったらいいな!という情報を提供しているのだと思う。
世田谷区が直接運営するものなら、なかなか民間の情報を掲載することは難しい。けれども世田谷サービス公社は株式会社。行政が直接手がけると手の届かない民間の情報まで自由に編集できる。あくまで世田谷で暮らす人、働く人、訪れる人、そういった『人』に対してあったらいいな!という情報を提供しているのだと思う。それにしても、もともと区の施設を維持管理していたビルメンテナンスの会社が、なぜコミュニティデザインといった、人と人をつなげる仕事をするようになったのだろう。
こんな疑問を投げかけると、山本さんは次のように話してくれた。
「それはやはりですね、転換点は指定管理者制度になったからだと思います。」
いくら世田谷区が設立した法人で、筆頭株主が世田谷区だとしても、健全な競争が必要になるんですね。
「そうですね。だから大手の管理会社もたくさん参入してきているんです。」
そう言ってコンペで負けてしまった施設の話をする山本さん。
「ただ、私たちの仕事にはいろいろな要素があります。」
要素というと?
「いろいろな世田谷区の施設を運営・管理していますし、屋外広告やエフエム世田谷もあります。さらにくみん手帖などもつなげていけば、よりよいものを提供できるんじゃないかと思うんです。」
 今までは単体で考えていた事業をつなげていくと、相乗効果を生む。
今までは単体で考えていた事業をつなげていくと、相乗効果を生む。「たとえば1000人収容できる区民会館がありますが、今までは単に管理しているだけで企画なんて考えられませんでした。でもホールがなくて困っている人はたくさんいるんですよ。そこをつなげることができればもっと施設を有効活用できると思うんです。」
なるほど、需要と供給がつながっていなかったんですね。
「そうです。うまくつなげていけばいいと思うんです。そのために情報発信が必要です。でももともと私たちはビルメンテナンス会社だから、そういう経験をした人がいないんですよ。」
くみん手帖が生まれるきっかけがある。それが「世田谷パン祭り」であり、離島経済新聞などを手がける鯨本さんとの出会いだった。
「第1回のときでした。彼女がうまく広報してパン祭りを成功させていたんです。それでくみん手帖をつくろうというときに、真っ先に頭に浮かんで。もともとこの会社には広報の部門が全くなかったこともあって、これを機会に強化していきたいという思いもありました。」
 声をかけられた鯨本さんはどうだったのだろう。最初の印象を聞いてみる。
声をかけられた鯨本さんはどうだったのだろう。最初の印象を聞いてみる。「世田谷サービス公社という名の通り、世田谷区の区民に対するサービス的なことを提供しているということは何となくわかりますけど、どんなサービスを提供しているのか知られていないと思うんです。山本さんにはじめてお会いしたときも、障害者雇用の担当者でしたし。どんなことをするのだろうって思いました。」
そうですね。
「ただ、どんな商品も同じですけれど、知られなかったら売れないし、利用もされません。それでいろいろ知っていくと、いろいろなコンテンツがあることがわかったんです。くみん手帖以外にも、エフエム世田谷というラジオ放送もあるし、ラジネタという季刊3万部のフリーペーパーもある。運営管理している会議室やホール、レストランなどもあるし、春には池尻に健康増進施設が新しくできます。そういったものがうまく連動できれば、ものすごいことになると思います。」
 世田谷サービス公社が直接手がけているもの以外にも、世田谷区にはたくさんのコンテンツにあふれている。
世田谷サービス公社が直接手がけているもの以外にも、世田谷区にはたくさんのコンテンツにあふれている。世田谷区の人口は88万人ほどだから県の人口くらいある。商店街・商店会も200くらいある。そして世田谷区が交流している都市も何十とあり、世田谷ふるさと区民まつりには全国各地から出展者が集まるそうだ(もしかしたら、そういう地域と連携する企画も考えられるかもしれない!)。
鯨本さんはつづける。
「コンセプトとしては、世田谷区の人たちにいかに見てもらうか、ということなんです。せっかくコンテンツがたくさんあるのだから見てもらいたい。たとえば、世田谷区の人たちって、意外と隣町のことは知らないと思うんです。三軒茶屋に住んでいても、経堂のことを知らなかったりだとか。」
そうですね。東急、小田急、京王と、都心方向に伸びる沿線ごとに、地域特性があるように思います。
「面白いことがたくさんあるし、それを隣町の人たちが教えてくれたら、とてもうれしいと思うんです。」
 鯨本さんのように、一歩外から見ることができるような人だからこそ、世田谷区は宝箱のように感じるだろうし、それをつないでいくことこそ編集の力と言えるかもしれない。
鯨本さんのように、一歩外から見ることができるような人だからこそ、世田谷区は宝箱のように感じるだろうし、それをつないでいくことこそ編集の力と言えるかもしれない。たとえば、4月に池尻にできる健康増進施設では、隣にある食糧学院の方々と一緒にメニューを考えている。
「単に新しい施設ができる!と広報するだけでは弱いんですけど、一緒にメニューを考えているところを共有することで、少しでも読者の方は興味を持ってくれると思うんです。ちょうど先週から試食会をしているんですよ。」
 くみん手帖ではその様子をお伝えしたり、レストラン名称の募集もしている。それ以外にもあらゆるコンテンツやリソースをつなげていくことで、新しい価値を生むことができると思う。
くみん手帖ではその様子をお伝えしたり、レストラン名称の募集もしている。それ以外にもあらゆるコンテンツやリソースをつなげていくことで、新しい価値を生むことができると思う。そのためにどういう人がいいのか聞いてみると、鯨本さんは「総合的な企画制作ディレクターがいい」とのこと。
たしかに、基本的な業務は「広報」や「メディア運営」だけれども、もっと積極的にメディアを活かしていける人がいい。だからこそ、ときにはプロジェクトマネージャーにもなるだろうし、コミュニティに関わる仕事でもある気がする。
「編集などの経験もあったらいいのでしょうけど、編集員募集、という感じでもないんです。それよりもなんでしょうかね。大学でランドスケープや地域デザインを専攻していたような人のほうがピンとくるかもしれない。くみん手帖というメディア自体にも、コミュニケーションデザインみたいなことが含まれると思うんです。」
 あるものをいかに伝えるか、ということだけじゃなく、まだあまりつながっていないものを発見して引き出していくような仕事なんだと思う。
あるものをいかに伝えるか、ということだけじゃなく、まだあまりつながっていないものを発見して引き出していくような仕事なんだと思う。とはいえ、いきなりそんなことはできないだろうし、もう少し具体的に仕事内容を聞いてみると…
「まずは、くみん手帖にどんな記事を書いていくのか、区民エディターの方々と話し合いをして、取材を依頼したり。たとえばこういうイベントがあるから、こんな企画でいきましょう、というように話していきます。まずは進行管理をしながらつくっていくのですけど、だんだん色々なプロジェクトがあることがわかってくると思います。そこからまたいろいろ提案できればいいと思うんです。」
「あとは企画書をつくったり、くみん手帖の媒体資料とか営業資料や、プレスリリースの資料をつくったりとか。そういうことまでできたら、とても素敵ですね。」
編集者やPR担当というよりも、企画屋さん。もっといえばファシリテーターとも言えるかもしれない。
とはいえ、鯨本さん曰く、「何よりも大切なことは、読んでもらえるものにしないといけない」とのこと。世田谷にはレベルの高い読者の方々が多いそうだから、まずコンテンツのクオリティを高めていくことが基本にある。
 そのためには、地域に溶け込める人がいいと思う。単に取材しただけでは、良質なコンテンツは生み出せない。とことん入り込むことで見えてくるものがあると思う。知識や経験よりも大切なこと。
そのためには、地域に溶け込める人がいいと思う。単に取材しただけでは、良質なコンテンツは生み出せない。とことん入り込むことで見えてくるものがあると思う。知識や経験よりも大切なこと。だから、コミュニケーションができて、どの街に行ってもかわいがられるような、そんな人が入ったらいいと個人的に思います。そして世田谷のいろいろなヒト・モノ・コトをつなげていくことで、よりよい地域にしていってください。(2012/12/27up ケンタ)

