※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
東京・愛宕、東京タワーの近くに、形はないけれど、全世界に通じるノウハウを売っている会社があります。それがラーニングデザインセンター。行動を通して学ぶ、という学習法「アクションラーニング」を、企業や大学の人材育成の一環として広めている。
アクションラーニングは、現実の問題解決をおこないながら、実際の行動とそのリフレクション(振り返り)を通じて、個人とチームが学習していく手法。
その実践のフォーマットを「質問会議」という形にして展開しています。
ここで、広報や営業などを通して、形のないサービスを人に伝えていく人を募集します。
 地下鉄日比谷線の神谷町駅を降り大通り沿いを進んでいくと、愛宕グリーンヒルズMORIタワーが見えてくる。地上42階建てのビルのなかに、ラーニングデザインセンターのオフィスがある。
地下鉄日比谷線の神谷町駅を降り大通り沿いを進んでいくと、愛宕グリーンヒルズMORIタワーが見えてくる。地上42階建てのビルのなかに、ラーニングデザインセンターのオフィスがある。代表の清宮(せいみや)さんにお話を伺ってみる。
「学習って変化すること。成長すること。わたしたちは日々、学習していないということはありえない。生物は学習しなければ生きていけないんですよ。」
学習というと、学生には親しい言葉だけれど、大人になるとあまり馴染みがないような気もする。
「でも、学校を卒業した大人にとっては、職場というのが1番の学びの場だと思うんです。」と清宮さん。
 清宮さんが日々、クライアント企業にヒアリングをしていて感じるのは、上手くいかないところには学習不全が起こっているということ。
清宮さんが日々、クライアント企業にヒアリングをしていて感じるのは、上手くいかないところには学習不全が起こっているということ。個人が失敗から学んでいないとか、現場がもっている情報がきちんと全体に共有できていないとか。
「日々の体験から学ぶことができていない組織は弱いし、なにより組織の風通しが悪い。私たちがやっていることは、コンサルティングや研修を通じて一人ひとりのつながりを整えて、好循環が生まれるお手伝いをすることです。」
なにより、「質問会議」を通してアクションラーニングがまわりだした組織では、職場のみんなが上機嫌になるそうだ。
 清宮さんが実感をもって組織開発に当たれるのは、自身の会社員時代の経験が大きいという。
清宮さんが実感をもって組織開発に当たれるのは、自身の会社員時代の経験が大きいという。「大学で心理学を学び、新卒で入ったのは人材系のベンチャー企業でした。毎日とにかくずーっと働いていた。そんな感じですね。働くということを、頭じゃないところで体験を通して考えることができたんです。」
会社がどんどん大きくなっていき、30人から500人まで人数が増えていく過程を、まさにメインストリームを走りながら体験してきた。
会社を辞めることになるなんて、本人も周りも誰も思っていなかったけれど、あるとき転機が訪れる。
「夫がアメリカに留学することになり、一緒についていくことにしたんです。まだ子どもも幼かったし、夫と離れることが想像できなかった。みんなびっくりしていましたよ。でも、結果バージョンアップできたから良かった。そのまま会社にいて役員になる道もあったけれど、リスクをとらないのが1番リスクだと思っているので。」
英語は苦手だったけれど、なんとかTOEFLの点数をクリアし、アメリカの大学院に進学する。
専攻は、ヒューマンリソースディベロップメント(人材開発)だった。
「大学も心理学だし、会社も人材系だし、わたしの人生のテーマは『人』なんですよね。」
日本に帰ったら自分で仕事を起こしたいと考えていた。そんなときアクションラーニングという手法と、アクションラーニングの権威Dr.Marquardtに出会う。これを日本に持ってかえりたいと思うようになった。
 帰国後、外資系の金融機関で働きながら、ワークショップを開いたりなど、アクションラーニングに関する活動を始める。Dr. Marquardtからは、日本国内での展開の独占契約をもらった。
帰国後、外資系の金融機関で働きながら、ワークショップを開いたりなど、アクションラーニングに関する活動を始める。Dr. Marquardtからは、日本国内での展開の独占契約をもらった。徐々に活動の輪も広がっていき、清宮さんは起業することにした。それが10年前のこと。
「設立以来、本当にクライアントに恵まれました」
たしかに、サービスを提供した企業は、日本の名だたる大企業が並ぶ。
「担当者の方々には、単に会社というより、個人としても大変素晴らしい関わりをしていただきました。 周囲のみなさんのサポートのおかげで、ここまでこれたと思います。これからは、ここまでの蓄積を生かして、色々な事業を立てていきたいと思っています。たとえば、日本の企業だけではなく、海外や大学などの教育現場にも、アクションラーニングを取り入れられるのではないかとか。これからの展開を一緒に考えてくれる人に来てほしいと思います。」
新たな可能性は広がり続ける。そう清宮さんは考えている。
清宮さんとともに働く、藤田さんにも話を伺った。
藤田さんは、ここに勤めて3年になる。今は広報と営業を担当し、手法や会社全体について発信し、伝える役割を担っている。
もともと映像メーカーで広報の仕事をしていたけれど、知人を介してここで働きはじめた。
 「同じ広報でも、前の仕事とは全然違います。前は物があり、それを宣伝する仕事でしたが、今は物がないので。相手のニーズによって変化するため、すごく苦労します。物があれば言い訳にもなるし、自分が主体的にならなくても物事が進むこともあるんですよ。でも、ここでは自分が主体的にならないといけない。おかげで自立精神が培われてきました。」
「同じ広報でも、前の仕事とは全然違います。前は物があり、それを宣伝する仕事でしたが、今は物がないので。相手のニーズによって変化するため、すごく苦労します。物があれば言い訳にもなるし、自分が主体的にならなくても物事が進むこともあるんですよ。でも、ここでは自分が主体的にならないといけない。おかげで自立精神が培われてきました。」イベントの企画、新しいパンフレット、インタビューや取材のケア。決まったPR方法はないから、SNSを駆使したり、英語を翻訳したり、こういう使い方ができるんじゃないかとアイデアを出したり。PRというよりも、ほぼ企画の仕事。
「昨年、英語がメインのアジアALフォーラムという大きなイベントを東京で行なったのですが、そのイベントの運営を責任者として任せていただいたんです。日本だけではなく海外の方も対象にしたなかで、どんな風に伝えていくかを考えていくのは、とても貴重な経験でした。」
ものありきではないから、常に見え方を意識しながら。世の中に何が求められているのかアンテナを張る。それは、「自分を触媒にしてアウトプットしていく感じ」だそうだ。
藤田さんはこの経験を生かして、海外にもアクションラーニングの手法が求められていることを確信し、今後海外展開をしていきたいと思っている。そのために、この秋、海外派遣される予定だ。
「いいと思ったらすぐに進められるのはいいところです。人数が少ないので距離も近いですし、清宮とも席が隣なのですぐに話せます。ただ、その柔軟性が逆に仇になるというか、展開が早すぎて大変なこともあります(笑)。」
 「でも、もっとこうしたらいいんじゃないかって面白がれる人には向いていると思います。自分の背景が生きるんですよね。わたしもこの会社に入って、自分の強みが分かるようになりました。」
「でも、もっとこうしたらいいんじゃないかって面白がれる人には向いていると思います。自分の背景が生きるんですよね。わたしもこの会社に入って、自分の強みが分かるようになりました。」藤田さんの強みは、どんなところなんですか?
「わたしは人に会うのが好きで、色々な人とすぐに仲良くなれたりするんです。営業は苦手だと思っていたけど、日常のなかで営業のようなことを既にしていたんだなって気がつきました。」
隣の席の清宮さんからはフィードバックも多いし、あなたはどうしたいの?なにがしたいの?と聞いてもらえる。それによって自分の強みも見えてきたし、逆にいうと問題も見えてきた。
「わたしもここに入ってからずいぶん変わりました。」と藤田さん。
どんなふうに変わったんですか?
「今までは当たって砕けて、みたいな殺伐とした人生を送っていたのですが、軌道修正ができるようになってきました。それは、振り返るクセがついたからかもしれません。砕けても終わりではなくて、その原因や意味を考えると次に繋がる。そういうふうに捉えられるようになってきました。」
もう1人紹介したい人がいます。勤めて4年になる、西澤さんです。
西澤さんは、営業と研修のファシリテーションをしている。
もともとはアパレル関係の会社に勤め、店舗マネジメントをしていたそうだ。
まったく違う業界から、どうしてこの会社に入ったんですか?
 「前の会社は、大手で老舗の会社だったので、全部マニュアルで出来ていたんですよ。よく当時の上司に言われていたのが、『今のお前たちは30年前に頑張った先輩たちのおかげで飯が食えているんだぞ』って。頑張ったら結果が出るという達成感もなかったんですよね。」
「前の会社は、大手で老舗の会社だったので、全部マニュアルで出来ていたんですよ。よく当時の上司に言われていたのが、『今のお前たちは30年前に頑張った先輩たちのおかげで飯が食えているんだぞ』って。頑張ったら結果が出るという達成感もなかったんですよね。」B to Cの仕事をしてきたけれど、B to Bのビジネスにも興味があった。企業に対して何か商品やサービスを独自の切り口で提供する仕事がしたい。そういう軸で仕事探しをするなかで、この会社を見つけた。
以前とはまったくの異業種だと思うけれど、働いてみて、なにかギャップはありましたか?
「形のない知識やサービスを売るわけですから難しいなと思います。でも、それがお金になるのですごいですよね。資料を使って説明して、それでも伝わらなかったら自分の言葉で伝える。人と本気で付き合って、仕事とプライベートを分けずに付き合うような感覚があって。前と比べて、自分をさらけ出して仕事をしている気がします。」
営業もして研修のファシリテーションもして、大変ではないですか?
「大きな会社ではないので、兼任しないと回らない。みんな必ず営業は兼任しながら、それぞれの役割を持っている感じです。でも、色々繋がる感じがあるので、両方やっていた方がいいことが起こる気がするんですよね。」
いいことってどんなことですか?
「営業でお客さまと会うときと研修で会うとき、全然見せてくれる一面が違うんです。分業してしまうと、色々な角度から情報が得られなくなってしまうと思います。」
研修では、お客さん自身がリフレクションを通して気付きを得ていく。そこに立ち会うことで、その人の新しい面に出会える。自分の担当の導入企業に良い効果が現れていくところを見ると、嬉しくなる。
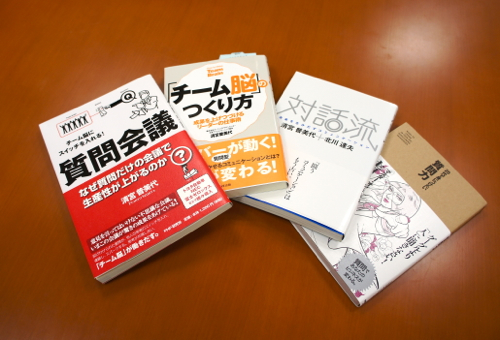 それから、みんなに問いかけたはずの質問が、自分はどうなんだろう?と自分に返ってくることもあるそうだ。
それから、みんなに問いかけたはずの質問が、自分はどうなんだろう?と自分に返ってくることもあるそうだ。行動のその理由を突き詰めていくと、無駄だと思っていたことが実は無駄じゃなかったり、無意識に自分で選択しているんだなと気付いたり。
「少しずつですが、視野が広がってきているように思います。日々、課題が見つかるので、それをクリアしていきたい。その気持ちを繰り返して4年間やってきました。」
「アクションラーニングを売るってことは、すごくハードルが高いことだと思うんです。売る人が学習していなかったら、やっぱり説得力がない。意識し続けることが大事だと思います。常に振り返る。自分を疑ってみる。」
藤田さんも西澤さんも、ここで働くことで気付きがあり、変化しているように思う。
ここは、お客さんだけではなく、サービスを提供するスタッフも成長できるハブなのかもしれない。
 最後に、清宮さんがこんなことを言っていました。
最後に、清宮さんがこんなことを言っていました。「今の自分に満足していなくて、変わりたいと思っている人。バージョンアップしたい人。手に入れたいと思っているものがある人。より良く生きていくことに責任を持ってる人。そういう人に来てほしいと思っています。」
「仕事って、人生の価値観がでるんですよね。自分の時間と会社の時間を重ねるなかで、会社も自分も成長させていきたいと思う人と働きたいです。この秋に、海外への派遣含め会社も新しい展開を予定しています。営業も広報も自分で切り開いでいく、ガッツのある人の参加を求めます。」(2013/5/20up ナナコ)

