※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
「学ぶ」という言葉は「真似ぶ(まねぶ)」という言葉から生まれているそうだ。そう考えると、魅力的な人の生き方や考え方を真似することで、子どもは大きく成長できるのかもしれない。なりたい自分になっていけるのかもしれない。
だけど、ロールモデルが親と先生くらいしかいない子どもも多いと思う。実際、自分もそうだった。大人になった自分を想像することができないまま、就職活動の時期を迎えてしまったように思う。
そして、そういうことは決して珍しいことではないそうだ。
今回募集するのは、そんな子どもたちの未来を変えるために、学校の外の世界に触れられる機会や仕組みをつくる「キャリア教育コーディネーター」の仕事です。
 愛知県の教育委員会による緊急雇用創出事業の一環なので、はじまりとしては9ヶ月の期間限定の仕事になる。ただ、継続して雇用される可能性もあるし、そうならなくても、自分の今後を見つめ直す機会にもなると思います。
愛知県の教育委員会による緊急雇用創出事業の一環なので、はじまりとしては9ヶ月の期間限定の仕事になる。ただ、継続して雇用される可能性もあるし、そうならなくても、自分の今後を見つめ直す機会にもなると思います。東京から名古屋まで新幹線で約2時間。梅雨の中休みで、とても空高く晴れ晴れとした日。名古屋駅に降り立つと、日差しが強いせいか街の輪郭がくっきりして見えた。
中央本線に乗り1駅。金山駅に降り立つ。歩いて10分ほどの場所にある愛知私学会館。その3階が「アスクネット」の事務所になる。
「アスクネット」は、愛知県を中心に市民参加の教育づくりをすすめるNPO法人。学校という舞台を使いながら、地域の魅力的な人の力を借り、子どもと社会の出会いの機会をつくっている。
学校に通う子どもたちにとって、学校や家庭以外での大人との出会いはなかなかない。昔に比べて地域社会とのつながりも薄れ、子どもたちが外の世界から学びを得る機会は、本当に少なくなっている。
一方で、産業界や地域のなかでも、教育CSRに興味があるという声が聞かれる。だけど、どうやって学校とつながればいいのかが分からない。
学校と社会のお互いの困りごと、そしてニーズをつなげることができれば、子どもたちに新しい学びの場を生み出すことができる。
 アスクネットが進めているのは、そんな社会全体を巻き込む「キャリア教育」。
アスクネットが進めているのは、そんな社会全体を巻き込む「キャリア教育」。企業に勤める人を社会人講師として学校に招いたり、職場見学やプロジェクト学習、インターンの派遣など、さまざまな事業を生み出し実践している。
「子どもたちは社会にある課題を知ると、それに対して『解決したい』というスイッチが入るんです。教科書では学べない現場の生の声を聞くことで、社会に対して主体的に学びたいという考え方が芽生えてくるんですね。」
そう話すのは、代表の白上さん。
白上さんは、5年前にアスクネットの代表を引き継いた。勤めて今年で8年目になる。その前は、保険会社で法人営業の担当としてバリバリ働いていたそうだ。
 アスクネットに興味を持ったのは、30歳を前にした時のこと。
アスクネットに興味を持ったのは、30歳を前にした時のこと。「このまま、この仕事を続けていていいのかな?」担当していたお客さんの死に目に遭遇したとき、悲しんでいる周囲の人を前にして、何もできない自分がいた。
人に励ましを送れる存在になりたい。もっとみんなが笑顔になれる仕事がしたい。
そんなとき、たまたま新聞で見かけたNPOのイベントに参加する。そこで、当時のアスクネットの代表と出会い、ボランティアスタッフに誘われる。
ボランティアといっても、行ったその日から即戦力扱い。あれよあれよという間に、ボランティアから正規スタッフへ。新規事業の企画から営業まで、全てを任せられるようになる。
ここでは自分で新しい仕事を作り出さなければいけないし、生まれた仕事の全体管理もしなければならない。それまでスキームのできあがった組織で働いてきた白上さんにとっては、毎日がギャップの連続だった。
でも、分からなかったら聞く、というスタンスでなんでも関わり、乗り越えてきた。
「現場に出ていた当時は、今も続く事業のほとんどの立ち上げに関わっていたので、色々な肩書きを持っていました。だから、代表になった今でも、実際現場はこうだろうな、という勘所は持てます。大変でしたが、すべて今に活きていると思います。」
きっと、現場がなくて枠組みだけをつくっているようなポジションだったら、ここまでのモチベーションは出なかったでしょうね、と白上さん。
現場もしくみも自分でつくる。だから面白かったし続けられた。
しくみやネットワークができてきた今でも、現場から新たな仕事を生み出していく、という姿勢はずっと変わらない。
 実際、今回募集する仕事は、9ヶ月のなかでどんなことをするんですか?
実際、今回募集する仕事は、9ヶ月のなかでどんなことをするんですか?「愛知県内の学校から社会人講師を招く授業がしたい、という依頼が来るんですね。それに対して、どんな授業にしたいのかヒアリングをして要望を汲み取ります。そして、目的や目標を明確にしながら授業をプランニングしていきます。必要に応じて、地域の企業や経営者、技術者に、講師として来ていただけるように呼びかけたりなどして、授業を実現させるための準備を整えていきます。」
講師は、最初から決まっていたり、アスクネットのリストからピックアップすることもあるのだけれど、自分で1から探す機会もある。
依頼をしたら、その後は学校と企業の間に立ち、スケジュールなどの連絡調整をする。そして、授業当日のサポートや機材準備など、運営にも関わるそうだ。
去年同種の事業を担当して、キャリア教育コーディネーターとして活動した、村瀬さんにも話をきいてみた。
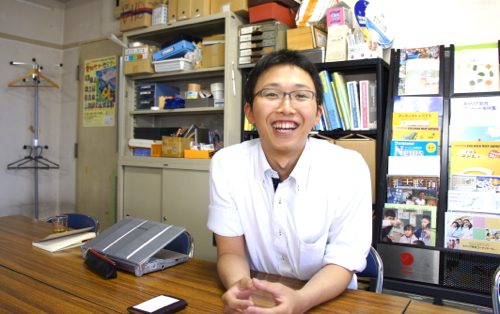 村瀬さんは、もともと教育学部の出身。学生時代からアスクネットとも関連の深い「アスバシ教育基金」の活動を手伝っていた。9ヶ月前にアスクネットの契約職員として採用されて、今は正職員として働いている。
村瀬さんは、もともと教育学部の出身。学生時代からアスクネットとも関連の深い「アスバシ教育基金」の活動を手伝っていた。9ヶ月前にアスクネットの契約職員として採用されて、今は正職員として働いている。9ヶ月を振り返ってみて、どうでしたか?
「学校の先生や企業の人、色々な想いのある方に出会いました。自分が探してきた講師の方が生徒の前で熱く語っていたり、授業が終わったあとに生徒からいい感想を貰えたりしたことは、嬉しかったですね。授業をつくるってすごくクリエイティブなことなんだと感じました。」
楽しかった反面、反省もあった。
「授業をつくる、というところまではできたのですが、そこから先の展開までつくることができなかったんです。講師の依頼を通して、せっかく企業に勤める方と繋がることができたのに、そのつながりを次に活かすことができなかったんです。」
つながりを次に生かすって、例えばどんなことがありますか?
「アスクネットでは、大学生の長期実践型インターンシップや、企業の教育CSR、高校生のインターンシップ、子どもたちへの教育に対する寄付など、企業と連携させて頂いて、子どもたちの教育を支援する枠組みが多くあるんですよ。」
そういった活動を飛び込み営業で伝えても、なかなか協力を得ることはできない。でももしかしたら、社会人講師の依頼を受けてもらった企業ならば、すでに現場を見て子どもたちと触れてもらっているからすぐに趣旨を理解してもらえることもあるかもしれない。
たんなる授業づくりではなく、授業を通してアスクネットの活動を地域や企業に知ってもらう機会にするということ。
 村瀬さんも、だんだんやっていくうちに意識が変わってきたそうだ。
村瀬さんも、だんだんやっていくうちに意識が変わってきたそうだ。もっと色々な形で企業・地域と協力していかないと、子どもたちを育てていく環境はつくれない。だから、授業づくりを通して若者の教育機会の必要性を呼びかけるコミュニティーをどんどんつくっていこう。
そして、そんな視点を持ちながら働いてみると、新しい仕事の種は会話の中にたくさん転がっているもの。
「少年野球のユニフォームを作っている会社があるんです。今、だんだん子どもが運動しなくなっていて、少年野球が衰退しているんですね。でも、野球はチームワークが学び、お互いの人間性を高めるにはもってこいのスポーツだと。その会社は、野球の魅力を広めたいと思っていらっしゃるんですね。そういう話を聞いて、じゃあ小学校の体育の授業で、元プロ野球選手の方をお呼びして授業をやるのはどうか、という話が出ているんです。」
村瀬さんが楽しそうに教えてくれた。
ただ、そういう話を聞き出すには、きっとある程度技術が必要だと思う。学生時代から企業の方と接する機会の多かったという村瀬さんだからできることなのかもしれない。
実際には、企業だけではなく行政の方とも話すことになるだろうし、柔軟なコミュニケーション能力が求められると思う。
すると、隣で聞いていた白上さん。
「どちらかというと、話す力よりも聴く力の方が必要かもしれません。」
そうなんですか。
「この仕事で危険なのは、思い込みです。これがいいんだ!と決めつけてはいけない。実際に現場を見て、色々な人の声を聞くことが大事です。」
学校・企業・行政・市民などさまざまな人たちと連携しなければ、授業は成り立たない。だから、それぞれの困りごと・要望を聞きだし、それに対する提案をしていかなければならない。
「そこでわたしたちは、持論を展開してはいけないんです。彼らを巻き込むには、彼らを語らせないと。そのために大事なのは、話すよりも聞くことなんですね。」
 教育って、夢や理想が先行してしまうイメージがあった。もちろんそういうのも大切だけど、自己満足で終わってしまってはだめだということ。
教育って、夢や理想が先行してしまうイメージがあった。もちろんそういうのも大切だけど、自己満足で終わってしまってはだめだということ。ちゃんと、そこにいる人の話を聴く。学校の職員には職員の理想があり、企業には企業の希望がある。
聴くことで、そこから自分の動き方が見えてくる。つくるべき授業のかたち、事業のかたちが見えてくる。
教育に対して何かしら問題意識を持っている人にとっては、9ヶ月という短い時間のなかでも、確実に見えてくることがある気がする。
「9ヶ月を終えたあとは、村瀬のようにアスクネットでそのまま働くことになる方もいると思います。でも、たとえそうならなかったとしても、民間企業で人材のコーディネートをしている人、大学の事務で働いているという人など、みなさん歩む道はさまざまです。なかには、この仕事を通して自分は教師に向いていると改めて感じた、と教師を目指されている方もいます。」
アスクネットが12年かけて教育コーディネーターとして地域にコミットしてきたノウハウを、自分の地域に持って帰る、という意識の人でもいいかもしれない。
 「ここで働くことで、小学校から大学まで、一連の成長の流れが見えるんです。あんなに前向きで積極的だった少年が、だんだん受け身になって就職が決まらないと悩みはじめるところまで見えてしまう。そこを、どうしてそうなってしまうのか、と検証しながら、丁寧に繋ぎ直していく。現場のつながりが社会のしくみになるんです。新しいものが生まれるところを感じてもらえると思いますよ。」
「ここで働くことで、小学校から大学まで、一連の成長の流れが見えるんです。あんなに前向きで積極的だった少年が、だんだん受け身になって就職が決まらないと悩みはじめるところまで見えてしまう。そこを、どうしてそうなってしまうのか、と検証しながら、丁寧に繋ぎ直していく。現場のつながりが社会のしくみになるんです。新しいものが生まれるところを感じてもらえると思いますよ。」日々の仕事だけ追っていたら、ただの連絡調整係になってしまう可能性もある。だけどそこに、ちゃんと子どもたちの未来をイメージできていたら、きっとどんどん色々な人やことと結びついて、面白くなっていくと思います。 (2013/6/14up ナナコ)

