※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
面白い人たちが集まって、新しいことが生まれている。そのハブになっているのがブレインズスタジオという場であり、ソーシャルブレインズという団体だと思う。
 鹿児島の天文館(てんもんかん)という街に、オフィスをシェアするだけではなく、地域に新しい価値を生み出そうとする多様なメンバーが集まる拠点がある。
鹿児島の天文館(てんもんかん)という街に、オフィスをシェアするだけではなく、地域に新しい価値を生み出そうとする多様なメンバーが集まる拠点がある。ローカルの課題は色々あるけれど、それに対して中でなんとかしようとするだけではなく、外からの知恵も借りながら活性化していく。
定期的にイベントを開催しながら、鹿児島に暮らす人、そして鹿児島にやってきた人が集う場をつくっている。
鹿児島で何かがしたい!と思っている人は、ここに来れば何かきっかけに出会えるかもしれないし、外から来た人にとっては、鹿児島の面白い人に出会える場所になるかもしれない。
何かを企んでいるもの同士が出会い、そこから何かが生まれる。そんな場づくりだったりプロジェクトを企画していく、ソーシャルブレインズの事務局長を募集します。
 東京から鹿児島までは飛行機で2時間ほど。鹿児島空港からバスに乗り、1時間ほどで天文館へ到着。天文館は鹿児島市内にある、南九州一大きな歓楽街。
東京から鹿児島までは飛行機で2時間ほど。鹿児島空港からバスに乗り、1時間ほどで天文館へ到着。天文館は鹿児島市内にある、南九州一大きな歓楽街。アーケードが網の目状に連なり、そこには古くからの個人商店やカフェ、ショップなどが立ち並んでいる。
アーケードを抜けて道なりに進むと、ブレインズスタジオが見えてくる。
目をひく茶色の建物の3階に上がっていくと、三方窓に囲まれた明るいスペース。真ん中にテーブル、奥にキッチン。
ここは、シェアオフィスの入居者が打ち合わせをしたり、ご飯を食べたりする日常のスペースであり、イベントのときはイベントスペースとして機能する。
 オフィスには、サクラ島大学や過去に仕事百貨で取材させていただいたK&Kだったり、鹿児島という地と結びついた仕事をしている人たちが多いのが特徴。
オフィスには、サクラ島大学や過去に仕事百貨で取材させていただいたK&Kだったり、鹿児島という地と結びついた仕事をしている人たちが多いのが特徴。ブレインズスタジオをつくったのは、運営するNPO法人ソーシャルブレインズの理事である、末吉(すえよし)さん、永山さん、井上さんの3人と、現在は監事を務める福山周作さん。
3人は、それぞれに会社を持つ経営者でもある。
代表理事は、末吉さん。
末吉さんは鹿児島の出身で、東京に出てリクルートに勤務していた。
「地方にも飛び込み営業をしていました。どんな媒体を使うのか、何回転なのか、そんなことを話すのが普通だと思っていたのに、地方に行くと『まぁお茶でも飲んでいきなさい』みたいな。地域の人と触れ合うなかで、そういう温かさは大事にしたいなと思いました。別に東京だけが全てではないと。」
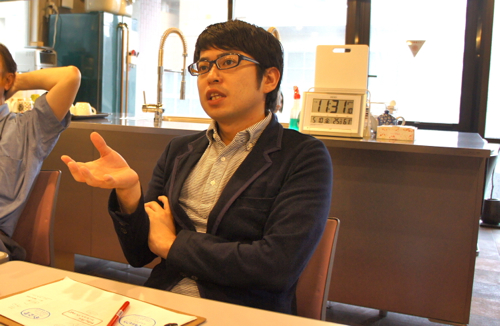 色々な地域を見たことで、広い視野でものごとを見られるようになった。
色々な地域を見たことで、広い視野でものごとを見られるようになった。鹿児島に帰ってきた末吉さんは、2年前から「マチトビラ」という組織を経営しはじめた。
大学生を期間限定の戦力として、鹿児島の企業とマッチングする長期実践型インターンシップ事業をコーディネートしている。
「企業に対して営業をしていると、自分の愛着のある鹿児島で、こんなにも情熱のある人がいるんだ、と感動してしまうことがよくあるんですよ。鹿児島だからできないよ、と嘆くのではなく、鹿児島だからこそできると思うんだよ!と企てる人もいる。そういう話を聞くとワクワクしてしまいます。」
鹿児島にも様々な課題に取り組む挑戦者や魅力的な経営者は沢山いる。そして、そんな人たちが往々にして抱えているのは、人材不足の悩み。
その一方で、そういう仕事があることを知らずに「鹿児島には仕事がない」と思っている若者も少なくない。
 そこにマチトビラが間に入ることで、Win-Winの関係を作り出し、挑戦を後押ししたり次世代の挑戦者を生む仕掛けをつくりたいと思っている。
そこにマチトビラが間に入ることで、Win-Winの関係を作り出し、挑戦を後押ししたり次世代の挑戦者を生む仕掛けをつくりたいと思っている。「学生がインターンに入ることで変わっていくのを見られるのは嬉しいですね。僕が嫉妬してしまうこともあるくらいです。それくらい将来が楽しみ。20年後には、育っていった学生たちに食べさせてもらいたいですね(笑)」
末吉さんは、事業をはじめて2年で、年間50人の学生を企業に送り出す仕組みをつくってきた。
2人目の理事、永山さんも、色々な地域に入って鹿児島の人やまち、企業を元気にする活動をしている。
永山さんは東京の銀行に就職し、コンサルティングと投資・融資の業務で地方を飛び回っていた。
今は自分の生まれ育った鹿児島を拠点にし、「Ten-Lab(テンラボ)」を経営している。
 Ten-Labの取り組みは、都市から離島まで幅広い地域に入り、コミュニティの再生、再構築を手伝うこと。人と人の関わり方をつくること。
Ten-Labの取り組みは、都市から離島まで幅広い地域に入り、コミュニティの再生、再構築を手伝うこと。人と人の関わり方をつくること。もともと天文館で、家と職場以外の第三の居場所をつくろうと、おすすめの本を持ち寄って集まるイベントを続けていた。
そのうち行政から声がかかり、中山間地域や離島のコミュニティの再生に関わるようになる。
「地域に入ってみると、過疎の結果、コミュニティが崩壊していることがあるんです。人口が多ければ、組合や商工会ができて情報交換や相互に協力する仕組みができるのですが、少ないとそういうグループが機能しない。横のつながりがなくなってしまうんです。そこに入って、もう1度地域と未来を考えましょう、という機会をつくっています。」
今は4つの地域へ定期的に通い、コミュニティのメンテナンスをしている。
「銀行員時代、リーマンショックの後は本当に辛かったです。融資したいけどできない。そんなもどかしさとしんどさがありました。今は物理的なしんどさはあるけれど、人を信じることが仕事なので楽しいです。人と人や、人と地域の関わり方を再構築することで、幸福度や生産性は大きく変わるんですよね。」
3人目に紹介するのは、井上さん。
 井上さんも、東京の広告代理店に勤めたのち鹿児島に帰ってきたUターン組。
井上さんも、東京の広告代理店に勤めたのち鹿児島に帰ってきたUターン組。最初に就職したNPOでは事業部長を務め、地域や社会の課題をビジネスとして解決する「ソーシャルビジネス」での人材育成や事業開発・運営に力を入れてきた。
その後、「典型」プロジェクトをはじめ商品開発の企画を進めながら、マーケティングやプロモーションのスキルを活かし、企画会社「創企堂」を立ち上げた。
「最終的には、プロデューサーを育てていきたいと思っているんです。鹿児島には資源は沢山あるのに、それを組み合わせて価値をつくれる人が少ない。だから、そういう役割を担える人を育てる場をもっとつくっていきたいですね。」
3人とも、鹿児島という地に強い思い入れがあり、鹿児島を元気にしたい、面白くしたいと思っている。
一緒にソーシャルブレインズを立ち上げることになったそもそものきっかけは、鹿児島を拠点にするNPO法人ネイチャリング・プロジェクトだった。
同僚として働いていた3人は、その後それぞれ独立。
独立後もたまに集まって近況報告をする中で、一緒に課題を解決できるやり方があるのではないかという話から、ソーシャルブレインズが生まれていったそうだ。
たとえば、これまでにソーシャルブレインズとして取り組んだのは、社会課題を解決するNPOや団体を紹介し活動のための支援を募る冊子「キクカゴブック」の作成やそのWeb版である「キフカゴネット」の運営。
そして、月に1回様々なゲストを呼んでトークやワークショップ、パフォーマンスなどを行う「ブレインズナイト」の運営など。
そうした取り組みを通して、だんだんと鹿児島の人に「ここに来れば何か解決してくれそうな面白い人に会える」と思ってもらえるような場をつくってきた。
 ここに専属で関われるスタッフがいれば、集まってきた人やコトを繋げて、もっと多岐にわたる課題を解決できるのではないか。そんな想いから、今回の募集に至った。
ここに専属で関われるスタッフがいれば、集まってきた人やコトを繋げて、もっと多岐にわたる課題を解決できるのではないか。そんな想いから、今回の募集に至った。「今回募集する事務局長には、僕たちを含めたソーシャルブレインズの会員、そしてブレインズスタジオに入居する会社や、ここに集まる人たちがそれぞれに持っているリソースを組み合わせて、価値を生み出していってほしいんです。コラボレーションの担い手やプロジェクトをつくる仕掛け人になっていただけたらいいですね。」と末吉さん。
地域課題の解決を持続可能なものにするためには、高いビジネスマインドが必要になる。
資金を集めるには営業がいるし、人を集めるには広報がいる。想いやアイデアだけでは続いていかない。
「企業や行政、学生やまちの人。幅広い人たちと会うことになりますから、高いコミュニケーションスキルが求められると思います。それから、自ら動き、試行錯誤を繰り返す起業家精神。」と永山さん。
「この前のブレインズナイトで、末吉さんが言ってたんですよ。東京だとフローの仕事だけど、地方に来るとストックの仕事だって。まさにそうだと思いました。だからやめられないんですよね。」
ストックの仕事。
「東京だと、プレイヤーも多ければマーケットも大きいので、1回仕事した人とはもうそれっきりだったりして、点の仕事も少なくない。だけど、鹿児島だと特定の少ないお客さんとの濃厚なコミュニケーションになることが多い。だから、一生ものの仕事になるんですよ。」
 それが地域の仕事の醍醐味なんです、と永山さん。
それが地域の仕事の醍醐味なんです、と永山さん。それを大変さと捉える人もいると思うのだけれど、永山さんは本当に楽しそうに話す。
「時期によってはすごく忙しくて、ここに泊まり込みで作業することもあります。シェアオフィスで泊まりこむなんて、あまり歓迎されることじゃないんだけど。でも、そんなときはメンバー同士でお互いの状況を気遣いながら、場面に応じてサポートしあったり。」
「それぞれのメンバーが自分で会社を持ちながらもここに参加しているのは、ここがひとつの濃厚なコミュニティになっているからだと思うんです。」
オーナーの意向でもともとここにあったという大きなキッチンでは、たまに井上さんがみんなに料理を振る舞うらしい。それが、パンチが利いていてとっても辛いらしい。
このキッチンを生かして、料理や飲食をテーマとしたイベントも頻繁に行われるそうだ。
そうすると、ふだん集まる人とはまた違う層の人がやってきて、新しいきっかけが生まれたりする。
 “地域ならでは”というよりも、”ブレインズスタジオならでは”のことが、ここでは沢山起こるのだと思う。
“地域ならでは”というよりも、”ブレインズスタジオならでは”のことが、ここでは沢山起こるのだと思う。まずはこういう催しを企画していくことからはじめてもいいのかもしれない。
つなげることが価値を生む。求められるのは、ロマンを持ちながらビジネスとして継続していくことなんだと思う。
もちろん、そのためのサポートだってある。
井上さんは企画立案のプロだし、末吉さんは鹿児島中にネットワークがある。永山さんは銀行員だったから事業計画をつくるときに助けてくれると思う。
 何かをしようと思ったときに、それが実現できる環境がここにはある。これからのブレインズスタジオを一緒に考えていく、4人目の経営者を求めています。 (2013/6/3up ナナコ)
何かをしようと思ったときに、それが実現できる環境がここにはある。これからのブレインズスタジオを一緒に考えていく、4人目の経営者を求めています。 (2013/6/3up ナナコ) 
