※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
村に行くと、当たり前に行われていることに驚くときがある。自然との関わり方であったり、「こんなものしかないけれど、どうぞ」と出される料理がおいしいことだったり。村にとってのふつうは、外から見ると実はすごいことだったりする。
 「脈々と受け継がれてきたものは、どの地域にもあるんですよね。僕自身、自分の村を、何もないところだって思ってましたよ。でも、外の人が触れると、その価値は全然違って見えるんだなと気づいた。」
「脈々と受け継がれてきたものは、どの地域にもあるんですよね。僕自身、自分の村を、何もないところだって思ってましたよ。でも、外の人が触れると、その価値は全然違って見えるんだなと気づいた。」そう話すのは、中山間地域に特化して地域の計画づくりを行う藤原啓(けい)さん。
代表を務める株式会社シーズ総合研究所では、働く人を募集します。
広島駅から路面電車に揺られて10分ほどで袋町の駅に到着。小学校の向かいにシーズの広島事務所が見えてくる。
 なかに入り、さっそく話を聞かせていただく。
なかに入り、さっそく話を聞かせていただく。シーズは啓さんの父、洋さんが1999年に立ち上げた会社。
役場職員として、島根県雲南市旧吉田村(市町村合併により、現在は吉田町)の地域づくりに取り組んだことがはじまりだ。
かつては、日本独自のたたら製鉄の中心地として栄えた村。日本で唯一たたら製鉄炉が現存し、国の重要文化財に指定されている。しかし、洋さんが地域づくりに着手する前の1980年頃までは、住民からも忘れ去られている状況だった。そこで地域の資産を再評価する「鉄の歴史村」という構想を立てる。
「鉄というモノの保存はもちろんのこと。製鉄を支えてきた自然環境、人々の暮らしも含め、村全体を生きた博物館として伝えていきたいと考えたんです。」
 モノに限らず、村に焦点をあてる視点は、たたら製鉄やその民俗に造詣の深い映画監督に、学者。村外の人たちが提案をしたもの。
モノに限らず、村に焦点をあてる視点は、たたら製鉄やその民俗に造詣の深い映画監督に、学者。村外の人たちが提案をしたもの。当時は吉田村を何もない村、と思っていた啓さんにとっては驚きだった。
「視点を変えることで、村のふつうが価値を持つということが新鮮でした。そのことがきっかけで、活動を手伝うようになります。」
 一度は東京の出版社に就職するも、やはり地域のなかで仕事がしたいという思いが募る。
一度は東京の出版社に就職するも、やはり地域のなかで仕事がしたいという思いが募る。一方の洋さんは鉄の歴史村づくりに専従するため、役場を退職。全国各地の農山村の地域づくりを支援するコンサルタント事業を起業する。依頼も増えつつあるなかで、啓さんが働きはじめる。
現在の主な事業であり、今回募集するのも、地域計画づくりを手がける人。
計画づくりに対する姿勢はいまも変わらないという。
「地域の人にとっての当たり前のなかに、魅力があります。そこを地域と一緒に深掘りして、ほんとうの価値を見つけていくんです。」
お客さんとなるのは国・県・市町村といった行政だ。
「たとえば少子高齢化であったり、産業づくりであったり。困ったことがあってなんとかしたいけれど、どうしたらいいのかわからない。そんな状態で相談を受けることが多いです。」
そこで調査を行い、課題を洗い出し、地域の将来像を報告書という形にしていく。
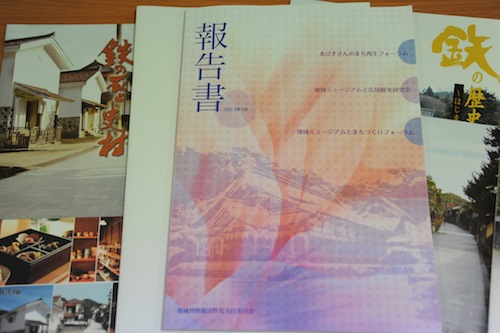 シーズが心がけているのは、地域の人と一緒につくりあげていくプロセスだという。
シーズが心がけているのは、地域の人と一緒につくりあげていくプロセスだという。どうしてだろう?
「報告書をつくること自体が目的ではなくて。大事なのは計画づくりのプロセスで、地域が、人が変わっていくこと。そして、計画が地域の手で実行されていくことなんです。」
ここで、スタッフの藤原麻子さんにも話に加わってもらう。
 地域でのフィールドワークを行っていた学生時代。民家を訪ねては話を聞き「面白いな、楽しいな」と思ったそう。こうしたことを仕事にできたらと思っている矢先、シーズと出会う。いろいろな地域の人を訪ねたいという思いから働きはじめた。
地域でのフィールドワークを行っていた学生時代。民家を訪ねては話を聞き「面白いな、楽しいな」と思ったそう。こうしたことを仕事にできたらと思っている矢先、シーズと出会う。いろいろな地域の人を訪ねたいという思いから働きはじめた。麻子さんは、ある自治体の事例を聞かせてくれた。
「住民と役場が対立をしている自治体で。けれど、住民の意見を計画に取り入れいと思う役場から、お声かけいただいたんです。はじめての会議に行ったときは、『何しにきたんだ』と言われるような状態だったんです。」
そこでどうしたんですか?
「『役場も住民の声を聞こうとしているので、チャンスなので、話し合っていかないとみなさんの地域にとっていいことにつながりません。』と伝えました。一つのテーブルにつくところからのスタートでした。回数も重ねて丁寧に進めていきました。最終的には、住民の声を提言書という形にまとめて、役場に渡したんです。役場もそれを計画に反映して。一緒にこの地域の未来を考えていきましょう、となりました。」
 話を聞いていけば、両者には、はじめから対立があったわけではない。それぞれに地域をよくしたいという思いはあって、話し合いも、さまざまな取組みもしてみた。
話を聞いていけば、両者には、はじめから対立があったわけではない。それぞれに地域をよくしたいという思いはあって、話し合いも、さまざまな取組みもしてみた。けれど、方法論が違ったりと、なかなかうまくいかず「何をやってもダメなんだ」とあきらめムードになり、あつれきも生まれるようになった。
「2者だけでは、どうしても行き詰まってしまうときもあります。でも『地元をよくしたい』という思いはみんな一緒なんですよね。そこで将来を一緒につくることに向かっていけるよう、少しずつ人を結んでいきます。」
そこで大事になるのが場づくり。
はじめに住民一人一人の声を聞くワークショップを行う。
かつては、役職のある男性ばかりが集まることも少なくなかった。
そんなときに麻子さんは、「女性や若い人も入れてください」と行政に伝えたり、参加しやすくなるための工夫をしてきたという。
「地域づくりって、どうしても役職持ちの方や、声を大きく挙げる人の意見を中心に進みがちです。でも、ふつうに暮らしているお母さんだったり、若い人だったり。普段あまり話さない人の声こそ大事にしたいんです。実はそこに大切な気づきがあったりします。」
 ようやく会場に来てくれても、はじめは「私が発言してもいいの?」という状態のことも。話しやすい場づくりが大切になる。
ようやく会場に来てくれても、はじめは「私が発言してもいいの?」という状態のことも。話しやすい場づくりが大切になる。「住民会議をファシリテートすることもあれば、静かに聞き役に徹することも。地域や場の雰囲気によって『こうした方がいいかな』って関わり方を変えていきます。大事なのはみんなが主体となって話せるようになることです。わたしはそのお手伝いをしているんですね。」
ある地域でうまくいったからと、同じようにしてもなかなかうまくいかない。「今日はよかったな」「雰囲気がもう一つだったな」。日々その積み重ねだという。
そうして聞き出した住民の声をもとに、報告書という形にしていく。そこでも住民と一緒に取り組むことを心がけている。
「体裁のいい報告書をつくって役場に提出して、終わり。は、私たちが一番望んでいないことです。計画づくりに関わった地域の人が、誰より思いも理解も持っています。その人たちが、次のアクションにどうつなげていくかを大事にしたいです。」
だからこそ、ワークショップ報告会を開くこともある。
そこで話すのは、自治体職員やシーズではなく、参画した住民自身。
「話し合いの成果を発表することで、「他人ごと」ではなく「自分ごと」のプランだと感じてもらえたら。実現するかどうかは、そこに生活する人たちにかかっていますから。さらに、発表を聞いた人たちを自分も関わりたいと、巻き込んでいけたら。そうして自然に思いを伝えあい、共有していける雰囲気を過疎と高齢化に悩む農山村にもつくっていきたいんです。」
これから地域づくりを頑張っていこう。そういう機運をつくるところまでがシーズの仕事なのだと思う。
 さらに、手がけた計画の実行段階の支援を委託されることもある。
さらに、手がけた計画の実行段階の支援を委託されることもある。「もともとが吉田村で計画づくりから実践まで行ったのがはじまりの会社です。実行まで一緒に関わってほしいという思いで、お声かけいただくことも少なくないです。」
麻子さんは、7年間関わり続けている自治体があるそうだ。
「自分が関わった計画が少しずつ実現していく達成感もあれば、地域の人たちと一体となって取り組んでいく楽しさもあります。」
2人にとって、村ってどんなところなんだろう。
「僕は、農山村集落に学ばせてもらうことがほんとうにたくさんあるんですよ。みなさんの暮らしぶりに、地域の企業。あるいは若い人が入っていく姿。そこには、自分たちになかった視点、気づきがあります。そして、その気づきや価値を都市の人たちにも伝え、共感してもらえる人たちとのつながりをつくっていくお手伝いもしていきたいと思います。」
「わたしは、ついついその地域に入れ込んでしまって(笑)。交通の便も良くないし、生活や働く場所としてすごく恵まれているわけではない。けれど、その土地に脈々と暮らしてきた人たちが、積み重ねてきたものがあるんです。そのことに対する敬意はいつも忘れずにいたいと思っています。」
 続けて村の現在について、話してくれた。
続けて村の現在について、話してくれた。「役場の職員も、そこにやってくる住民も、家に帰るとみんなご近所さんということは一つの特徴かな。しがらみと絆の深さの両方があると思うんです。」
そんな地域も変わりつつあるところ。
「人口が減り、少子高齢化が進む中で、もっと開かれたものにしようという声が上がってきています。シーズには都会で生まれ育ったスタッフもいるんですけどね。『よく来てくれたなぁ』って。歓迎してくれますよ。」
いただいたご飯がおいしいこと、えんがわから見た夕焼けが美しいこと。
感じたことを素直に伝えると、向こうも喜んでくれて。ささいなことの積み重ねから関係は築かれるんだと思う。
 もちろん大変なことだってある。
もちろん大変なことだってある。「住民との話し合いは基本的に夜です。車で移動して、ときには泊まって。体力的にはしんどいんですよ。でも… 」
「わたしは一緒に、ということを大事にしたいんです。住んでいるからこそできること、役場だから、企業だからできること、わたしも、外にいるからできること。それぞれに役割があって。みんなが持っているよいものを、同じことのために発揮できたら、一人ではたどり着けない所にも行けると思っています。」
 計画づくりのプロセスで自分を発揮できるからこそ、一人一人も変わってくる。
計画づくりのプロセスで自分を発揮できるからこそ、一人一人も変わってくる。「あきらめかけていた地域の人たちも『自分たちに、まだまだできることがある』って、言葉が、顔が変わってくるんです。その場面に、ぜひ立ち会ってほしい。大変なときがあっても頑張れることを実感してもらえると思います。」
きっと、変わっていくのは住民だけじゃない。働く人自身も、そこに役割があって、人に必要とされることで変わっていく。自分をいかしていける仕事が、村にはあると思います。
村が変わりつつあるなかで、シーズにもこれまでとは違った役割が生まれてくるようです。新しい種を、育てていくのはあなたかもしれません。(2013/9/26 大越はじめup)

