※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
「美郷町はこの30年で人口が、1万人から、6000人になりました。でも、これは悲観することではないと思うんです。これから日本のどこであっても人口は減っていく。だから、僕はこのまちにいる人が、これからこのまちを育てていけばいいと思っています。」宮崎・美郷町(みさとちょう)。まちの93%を山が占め、耳川という川幅の広く水量の豊富な川が東西を流れる。訪れたのは12月。まちのあちこちに金柑の橙色や、南天の赤い色が散りばめられていた。色彩が鮮やかな場所。
 宮崎空港から太平洋沿いを走る電車に揺られ、北へ1時間。美郷町の最寄りの日向市駅に到着する。駅まで美郷町役場の甲斐さんが迎えにきてくれた。そこから車で40分ほどかけて美郷町へ。最初の言葉は、車の中で甲斐さんが話してくれた言葉。
宮崎空港から太平洋沿いを走る電車に揺られ、北へ1時間。美郷町の最寄りの日向市駅に到着する。駅まで美郷町役場の甲斐さんが迎えにきてくれた。そこから車で40分ほどかけて美郷町へ。最初の言葉は、車の中で甲斐さんが話してくれた言葉。住む人たちでこのまちを育てていく。そのために今取り組んでいることは、美郷町のもっている資源を最大限に活かして、産業をつくり、まちの中はもちろん、外へも美郷町を広げていくこと。
今回募集するのは、まちの直売所を拠点に、美郷町の資源をモノやイベントとして東京や福岡など「外へ広めていく人」と、直売所の中でパンやスイーツなどの商品を「考えてつくる人」。
 美郷町は2006年に、それまであった、北郷(きたごう)村、南郷(なんごう)村、西郷(さいごう)村が合併してできたまち。北郷は日本三大備長炭である、うなま備長炭の産地。南郷はお米。西郷は、春にはお茶、秋には栗、ゆず、梨、冬には椎茸などが採れる。農産物が豊かなまち。
美郷町は2006年に、それまであった、北郷(きたごう)村、南郷(なんごう)村、西郷(さいごう)村が合併してできたまち。北郷は日本三大備長炭である、うなま備長炭の産地。南郷はお米。西郷は、春にはお茶、秋には栗、ゆず、梨、冬には椎茸などが採れる。農産物が豊かなまち。2年前にはそれぞれの村にあった直売所がまとまり、一つの会社となった。村ごとのカラーは残っている。その境界をすこしずつゆるやかにし、現在は、それぞれの地域の資源を活かしながら、『美郷町』として商品開発を進めている。
今回入る人の拠点となるのが、まちを流れる耳川沿いにある、西郷の直売所『美郷ノ蔵』。石峠レイクランドという温泉施設や、宿泊施設、レストランのあるレジャー施設内に、その直売所はある。
 美郷ノ蔵に入ると、地域の野菜や商品とともに、香ばしい匂いのするパンが並ぶ。
美郷ノ蔵に入ると、地域の野菜や商品とともに、香ばしい匂いのするパンが並ぶ。直売所のとりまとめや商品の開発は、美郷町役場の甲斐さんが今まで一人でおこなってきたという。これまでどんなことをしてきたのだろう。
「僕は14年前に農業振興課の担当になりました。農家の手取りを増やすことを考える仕事です。どうしたら農家の人にお金が還元できるか考えたときに、農地の面積を増やす、農作物の種類を増やす、単価をあげる、この3つがあるなと思いました。」
 その3つのうち甲斐さんにできることは、農産物の単価をあげることだと考えた。そのために、卸しを通さず、直接自分たちで福岡などに販売してまわっていたそうだ。でも、なかなか継続的な結果は出ない。
その3つのうち甲斐さんにできることは、農産物の単価をあげることだと考えた。そのために、卸しを通さず、直接自分たちで福岡などに販売してまわっていたそうだ。でも、なかなか継続的な結果は出ない。「いろいろと試行錯誤している時期に、まちに栗の加工場ができたんです。それまでは、農産物をそのまま原料として卸したり、販売していました。けれど、その工場で加工して販売することで、単価があがることがわかったんです。」
例えば、栗の値段。1キロ500円の価値のある栗を、原料としてそのまま製菓メーカーに卸すと、手数料や輸送費で、手元に戻るお金は200円程度。けれど、その栗を自分たちでその場で加工して、商品として売ると、500円の価値を保ったまま売ることができた。そして、『国産の栗』ではなく『美郷町の栗』として自分たちの名前ごと売り出していける点も大きく違った。
「このまちの中で加工して販売できれば、生産者にちゃんとお金が返ってくる。まずは栗をメインに売り出していこうと思っています。栗の栽培面積は、この高齢化が進む中でも増えているんですよ。」
 加工場がきっかけとなり、従来のように農作物をつくって販売するだけでなく、6次産業化して、自分たちで原料をつくり、加工し、販売までする方向へ向きはじめた。
加工場がきっかけとなり、従来のように農作物をつくって販売するだけでなく、6次産業化して、自分たちで原料をつくり、加工し、販売までする方向へ向きはじめた。「自分たちでいい製品はつくれる。それはわかりました。ただ、それをどうやって外に売り出していけばいいのかが、わかりませんでした。商品にしても、売り物としてのつくり込みが甘かった。いい製品ではあるんですけど、売れる商品ではなかったんですね。」
そこで出会ったのが碇(いかり)さん。美郷町のものづくりのアドバイザーをしている。このまちは、地域の資源が豊富なのに、まだまだ活かしきれていないし、そもそも価値に気付いていない人が多いと話す。
「東京だと、栗って高級品じゃないですか。けれど、このまちの人にとっては栗は拾うものなんです。買うなんて考えたこともない。僕は最初に『栗きんとん』として売り出すことを提案しました。でも、みんなに話してもピンときていなかったんですよ。『それ、売れるの?』って。」
 外からの視点を持つ碇さんの提案をもとに、3年程前から栗きんとんの製造・販売がはじまった。百貨店などから取り扱いがはじまり、現在は全国から注文が入る人気商品となっている。
外からの視点を持つ碇さんの提案をもとに、3年程前から栗きんとんの製造・販売がはじまった。百貨店などから取り扱いがはじまり、現在は全国から注文が入る人気商品となっている。栗きんとんというと、お正月に食べる芋の餡の中に、栗の甘露煮が入っているものを思い浮かべる人も多いと思う。けれど、美郷町でつくられる栗きんとんは原材料が『栗』と『砂糖』のみ。わたしも試しに頂いたのだけど、全体的にほくほくとした食感がして、一口噛んだ瞬間に栗の香りが口全体に広がる。本当に美味しかった。
 この栗きんとんをつくっている加工場のことを、甲斐さんはこう話してくれた。
この栗きんとんをつくっている加工場のことを、甲斐さんはこう話してくれた。「果菓子屋(かかしや)という加工場で地元のおばちゃんたちが5、6人でつくっています。3年前までは年間の売り上げが1,000万円に届かなかったのですが、今は3,000万円を越えてきています。がんばってつくっても一日200本が限界で、製造が追いついていない状況です。」
まちの産業として軌道に乗ってきた栗きんとんづくり。けれど、作り手の方のほとんどが70代の方。
 「継続的にこの事業を続けていきたいんです。そのためにも、ある程度は工場化したい。工場ができれば、若い人への雇用も生み出せます。現在のすべて手作業のやり方のままだと、売り上げも3000万円が限界です。けれど、マネージメントをしっかりやれば、5000万円でも、1億円にも届くと思っています。全然夢物語を言っているつもりはありません。」
「継続的にこの事業を続けていきたいんです。そのためにも、ある程度は工場化したい。工場ができれば、若い人への雇用も生み出せます。現在のすべて手作業のやり方のままだと、売り上げも3000万円が限界です。けれど、マネージメントをしっかりやれば、5000万円でも、1億円にも届くと思っています。全然夢物語を言っているつもりはありません。」栗の加工を通して、美郷町の産業の基礎ができはじめてきたことを感じている。けれど、甲斐さんは役場のほかの仕事もあるために、すべての時間をこの事業にかけることが難しい。
「外に売りにいく機会があっても、全てに対応しきれていないんです。次のステップに行くためにも、時間をかけて、本腰を入れてやっていきたいと思っています。だから、仲間が欲しいんです。」
「外へ広めていく人」は、美郷町の商品が売れる機会をつくることが仕事になる。
栗以外にも、お茶、ゆず、金柑、梨、餅など、たくさんの資源が美郷町にはある。今回このまちの資源を外に広めていく人も、栗はもちろんのこと、ほかの素材の商品開発も、果菓子屋の方や、まちの人たちと協力してつくっていって欲しいそうだ。
ひとつひとつ掘り起こして、外からの目線でその資源を見つめ直すことで、できることはたくさんある。まずは甲斐さんと、新しい商品を一緒に考え、まちの加工場の方たちと話していくところから。
この仕事をする上で大切になってくるのは、どんなところなのでしょうか。
「感覚ですかね。東京で売れるものはなにか、そういう感覚を把握することが必要になってきます。」
「あとは、つくり手とよく話すことかな。自分から現場にはいっていかないと。加工場のおばちゃんたちから寄ってくるってことはないですから。話しかけること。仕事のことじゃなくて、日々のことでいいんです。そうやってコミュニケーションとって、同じ目線で製造の現場に入り込めるかどうか。自分から、入っていこうという心構えかな。」
今度は、美郷町の資源をパンやスイーツなどの商品を「考えてつくる人」について話を聞く。
美郷ノ蔵のパンのテーマは『地産地消』。美郷町の米粉を使ったパンがメインにつくられている。
 2年前のオープン時からこの直売所で働く、山崎さんにお話を聞いた。明るく、気さくな雰囲気。わたしが会った美郷町の女性は、なんだかみんな明るかった。
2年前のオープン時からこの直売所で働く、山崎さんにお話を聞いた。明るく、気さくな雰囲気。わたしが会った美郷町の女性は、なんだかみんな明るかった。「米粉は100%美郷町のものです。中の具材もなるべくは美郷町のものをつかっています。製造のスタッフが毎日3、4名で30種類ほどのパンを焼いています。ここの直売所で売るだけでなく、移動販売でパンを売ったりもしていますよ。」
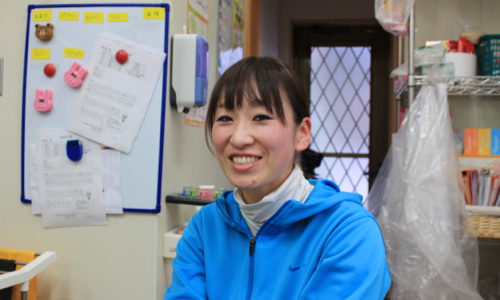 美郷ノ蔵でパンをみていると、地元のおばあちゃんから、温泉施設を利用しに来た方まで、幅広い年齢層の人が訪れていた。土日は、家族連れも多いそうだ。
美郷ノ蔵でパンをみていると、地元のおばあちゃんから、温泉施設を利用しに来た方まで、幅広い年齢層の人が訪れていた。土日は、家族連れも多いそうだ。パンというと、専門的な仕事に感じてしまうけれど、経験は必要になってきますか?
「みんなはじめはパンを焼けませんでした。最初は覚えることがたくさんあると思います。けど、お菓子や料理をつくることが好きな人であれば、大丈夫ですよ。」
ちょうどこの日は、外に売っていく商品の試作品が出来上がった日。
果菓子屋でつくられた栗の渋皮煮をつかって焼かれたパウンドケーキ。端から端まで、ぎっしりと栗が入っている。パンを焼くことが日々の仕事になってくるけれど、町の外にも販売できるような商品の製造や、メニューを考えていってほしいそうだ。
 美郷町のこれからのことを甲斐さんはこう話してくれた。
美郷町のこれからのことを甲斐さんはこう話してくれた。「将来的には、ここが美郷町の窓口、拠点になるようにしていきたいです。新しい商品の企画や、製造・注文の管理、そしてそれを外に売り出すこともしていきたい。やっとここまで礎ができてきました。もちろん僕らも一緒に考えます。けれど、どういう形でこのまちの魅力を外へ出したらいいのか、考えるところが弱いんです。そこを一緒に考えていける人にきてほしいですね。」
いいものはつくれる。
外からの視線を持ちながら、求められる形にして、美郷町をまちの外に広げていく。ゆくゆくは、工場もつくって雇用も生み出せるように。まちがまちとして自立する仕組みをつくり上げていくことが仕事なのだろうな。
美郷町に来たことがない人も、甲斐さんがいるのでまちに入り込みやすい環境だと思います。
「もちろん受け入れ側もちゃんと協力していきます。でも、来る人も中に入り込む気構えは持ってきてほしいですね。移住の相談にも乗りますよ。」
まずは、美郷町を訪ねたり、甲斐さんと話すところからはじめてもいいのかもしれません。このまちを見ること、まちの人と話すこと、つくること、届けること。楽しんでできる方の応募をお待ちしています。
(2014/02/11 吉尾萌実)

