※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
地域に根ざすことで、見えてくるものは多い。渡り鳥のように、全国を訪ね人に出会うたびに感じます。
思いや言葉の一つひとつが深くて。「かなわないなぁ」とうならされることもしばしば。
机の上でどれだけ考えてもわからない。地に足をつけてはじまるものがあります。
今回訪ねたのは、静岡県富士市の吉原。
 まちの起こりは、いまから約300年以上前。東海道14番目の宿場町として栄えたところから、商店街へと展開していきます。
まちの起こりは、いまから約300年以上前。東海道14番目の宿場町として栄えたところから、商店街へと展開していきます。地元の方からは「静岡のガラパゴス」そんな言葉も聞こえ、独自の発展を遂げてきたようです。
現在は一両編成の岳南(がくなん)鉄道が走り、600mほどのエリアに商店が軒を連ねます。
けれど、少しずつ活気を失いつつもある。
住民とともに、そして外の人を巻き込みながら、あらたなにぎわいを生み出そうとするのが、NPO法人東海道・吉原宿(よしわらじゅく)です。
“まちではじめたい人”に火をつける事務局長を募集します。
富士市は、25万人が暮らす静岡県第3位のまち。
農林業も営まれていれば、駿河湾に面しているため漁業も盛ん。豊かな地域です。
また、水に恵まれていることから製紙業が栄えてきました。JR吉原駅からは、工場の間をすり抜けるように岳南鉄道が進みます。
 5分ほどで吉原本町駅に到着。
5分ほどで吉原本町駅に到着。向かったのは、商店街の入り口に位置する「富士市民活動センター コミュニティf」。吉原宿が指定管理を行っています。
エレベーターを降りると「大越さん!?」と元気な声で呼びかけられた。
この方が、“見習い”センター長の西川有希さん。
 お隣富士宮市の出身。
お隣富士宮市の出身。事務の仕事を経て、吉原宿で働きはじめた。移住したのは昨年のこと。
「お肉も野菜もお魚もお布団も、なんでも商店街で揃うんですよ。次第にこのまちが大好きになり、気づいたら住んじゃいました(笑)。」
取材中も絶えない笑顔が印象的な方だ。
少し遅れて、吉原宿代表の佐野さんが見えた。
佐野さんは、商店街でテナント業を営む4代目でもある。
どうして吉原宿を立ち上げることになったのだろう。
「僕が30歳のころから、商店街に空き店舗が目立つようになりました。これは将来エリアとして厳しくなるだろうな、と思ったんです。」
はじめは商店街の青年部に入った。けれど、上を見て「これじゃ変わんないなぁ」と思ってしまったそうだ。
「話の進め方は年功序列に多数決… 昔はよかったんでしょうね。けれど現状に対応しきれていない。それならば飛び出して、あたらしい活動をはじめてしまえ!と2003年にNPO吉原宿を立ち上げたんです。」
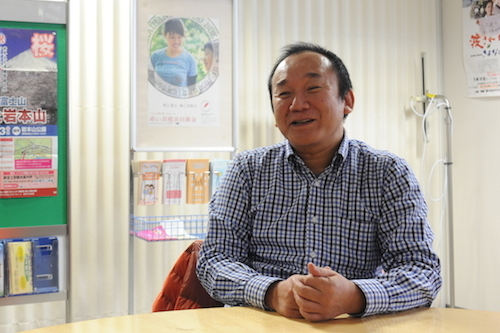 はじめは右も左もわからず、手探りで進めてきたという。
はじめは右も左もわからず、手探りで進めてきたという。活動の中心となる吉原商店街はどういう場なのだろう。
「宿場時代から業態を変えずにいるのは、18代続く宿一軒です。あとはせいぜい120年続く和菓子屋さん。宿場町って、一旗揚げてやろうとあたらしい人が集うチャレンジングな場所だった。血の入れ替わりがあったんだよね。」
けれど、ここ20年ほどは出て行くばかり。その間に、入りづらいところだと思われるようになってしまった。
吉原宿は活動をはじめて11年目。まちの雰囲気も変わりつつある。
「コンスタントに企画を打ち出すことで、『いつも吉原商店街って何かやってるよね。』『あそこに行けばなにかできるんじゃない。』そういう雰囲気が醸成されてきたと思います。やる気があれば誰でも自由に踊れる、はじめられる場にしたいんです。まちって、そういう器だと思います。」
 吉原宿がこれまでに手がけたプロジェクトは「吉原バル」に「シャッターアート」「コミュニティカフェ」… 10をこえる。
吉原宿がこれまでに手がけたプロジェクトは「吉原バル」に「シャッターアート」「コミュニティカフェ」… 10をこえる。事業の核となるのが、5年前から管理運営しているコミュニティf。
まちで何かしたいと思う市民をサポートしていくスペースだ。
当初は年間10,000人程度だった利用者も、現在は3倍まで伸びてきた。
こうした場所は、立派な設備の割に若い人には近寄りがたかったり、一部のまちづくりに熱心な人だけが利用するイメージが強かった。
けれど、コミュニティfはちょっと違うようだ。
取材中も子どもの声が聞こえたり、隣の部屋では同世代と見える人たちが集まっている。
西川さんはこう話してくれた。
「ふらっと来る方が多いんですよ。お子さん連れで弁当を食べに来る人。鉄道待ちの時間に、お買い物ついで。日本中のNPOセンターも見て回ったんですけど、入りやすさは自信がありますね。我ながらステキなところだと思います(笑)。」
どうしてだろう?
「スタッフの姿勢かな。相談に見えた人に“教える”よりも“一緒に考える”といった方がしっくりきます。わからないときは『ちょっとわかりませんねぇ』とすなおに言ってしまいます(笑)。一緒に調べていきましょうよ。その方が本人にも火がつきますよね。」
 運営をはじめて気づいたことがあるそうだ。
運営をはじめて気づいたことがあるそうだ。「生活している人って、それぞれまちで何かしたいと思っているんですよ。実はアイデアも温めていて。でもきっかけがなかったり、ちょっとハードルが高く感じられるんだと思う。うちは近しい感じがするので『わたしもやってみようかな』とはじめやすいのかな。」
そして11年目に入る今年、吉原宿は新たな階段を上ろうとしている。
佐野さんに再び聞いていく。
「イベントをきっかけに、普段から人が訪れる流れを加速させたいんです。そこから出店や移住する人も出てくると思います。あたらしいことをはじめる醍醐味が一番感じられるとき。きっと面白くなりますよ。関わるならいまじゃないかな。」
そこで、まちにあたらしい息吹を吹き込む事務局長を募集している。
どんな仕事をするのでしょう。
「まずは、日々走っているプロジェクトをマネージメントすることです。編集して一つひとつをよりうまく組み合わせることで、吉原への人の流れをつくり出したいんですね。」
そして、人と人の間をつなぐこと。
たとえば、昨年の夏には20代建築家の勝亦(かつまた)さんが、Uターンを考えてコミュニティfを訪れた。
商店街ににぎわいを生むため、空き物件のリノベーションを提案してきたそう。
とは言え、どこからはじめたらよいのかわからない。
そこで吉原宿は不動産のオーナーさんや地元のデザイナーさんを紹介して回った。
「いまは建築に不動産にデザイン。すべて分業制になっていますよね。住んでいる人の顔がわからない大家さんに、リノベーションの提案をする。まちにデザイナーがいて、ケーキ屋さんのパッケージデザインから下着屋さんのショップデザインまで手がけていく。チームが回ったら面白いよね。みんな幸せになれるじゃない。」
人のつながりがきっかけとなり、勝亦さんは「立体駐車場に暮らしたら、どうなると思う?」をコピーとしたイベント“商店街占拠”を企画実施した。
 ここで佐野さんは、空き店舗の目立ちはじめた商店街をフロンティアだと話す。
ここで佐野さんは、空き店舗の目立ちはじめた商店街をフロンティアだと話す。「身の丈にあった小商いをスタートするなら、償却が済んで自由にいじれる古いビルこそ武器になるでしょう。空き店舗のシャッターの数だけチャンスがあります。1フロア借りるのが難しければ、シェアからはじめてもいい。そのときに、色んな人をつなぐ存在が大事なんです。」
タウンマネージャーや家守(やもり)と呼ばれる仕事だ。
「日本中歩いて見たんですが、商店主だけで商店街活性化に取り組むのは限界に来ています。専門性を持ってエリアをマネジメントしていく人が必要です。」
 まちづくりってきれいな言葉に聞こえるかもしれないけれど、実は地味だったり、泥臭いことも多い。十人十色、いや百人百色の人が生活するまち。当然色々なことが起きる。
まちづくりってきれいな言葉に聞こえるかもしれないけれど、実は地味だったり、泥臭いことも多い。十人十色、いや百人百色の人が生活するまち。当然色々なことが起きる。これから働くのは、どんな人がよいのでしょう。
「プロジェクトを進める上では、きちんと利益が出るのか。あるいは、利益は出なくてもやる意義があるのか。金勘定も大切です。商店街の人との調整もあります。ときにはきついことだって、言わなきゃならない。」
「根が不真面目なぐらいがちょうどいいかな(笑)。全員の合意を得てから動くんじゃなくて、3人集まったら行っちゃえ。だって、誰からも好かれようとしていたら、画期的なことはできないよ。」
日々仕事をする上で大切なことだと思う。
なかなか言葉にしづらいことでもあるけれど、包み隠さないのが、吉原宿の魅力だと感じた。
これから働く事務局長も、長い目で見れば理解されるというか。むしろ感謝されたり、信頼されたり。実は好かれていく存在のように思う。
ここで再び見習いセンター長の西川さん。
「わたしは吉原宿に関わって夢が持てるようになった。生きる、未来… なんて言うのかな、うまく言葉が見つからないな(笑)。夢を実現してやろうという気持ちになりました。」
彼女はニコニコしながらも、きちんと人を見ているのだと思う。
「それからね、見ての通りうちは女の人が多いです。収入に不安があるとか、NPOに共通することかもしれません。男の人は色々なものをしょっている、って思い込みがあるのかな。でも、きっと脱いでも大丈夫ですよ。」
自分で仕事をつくっていくこともできるでしょう。
このあとはみなさんの案内のもと、商店街を歩いてみた。
 コンパクトなまちなかには、全国からお客さんの訪れるフルーツゼリー店に、夜になったら訪れてみたい雰囲気のよいバーも。
コンパクトなまちなかには、全国からお客さんの訪れるフルーツゼリー店に、夜になったら訪れてみたい雰囲気のよいバーも。下校途中の小学生とは立ち話が弾み、なかなか前に進めない。
そしてシャッターアートをはじめとする、吉原宿の取組みが目につく。
「わたしはこのまちが好き。」
そう話すのは杉本さん。吉原宿の運営するチャレンジショップ吉商本舗の1期生だ。
 吉商本舗にて・右が杉本さん
吉商本舗にて・右が杉本さん
吉商本舗は、地元の高校のビジネス部が部活動として運営するチャレンジショップ。企業と提携し、地元の名産品を活かした商品開発も行っている。
一度は公共施設で事務の仕事をした後に吉原宿へと入った。
現在はリノベーションのプロジェクト事業を担当。現在進行中の物件を前に説明をしてくれた。
「いまは商店街でもリノベーションがトレンドになりつつありますよね。もう10年経つと『ここもそういう感じでやったんだね。』と埋もれてしまう可能性も。だから、ただちょっとおしゃれな感じではなくて。周りに『えっ、あそこがこんな風になるんだ』と影響する建築作品にしていきたいです。」
 シャッターアートのプロジェクトリーダーも、いまでは静岡を代表するグラフィックデザイナーとして活躍しているそうだ。
シャッターアートのプロジェクトリーダーも、いまでは静岡を代表するグラフィックデザイナーとして活躍しているそうだ。立上げ期の活動が着実に、実を結びつつあるようです。
いいまちって、人に紹介したり、連れて行きたくなるように思います。
吉原はまさにそうでした。
プロジェクトを編集して、これからの10年をつくっていく人を探しています。
(2014/3/4 大越はじめ)

