※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
これからどこに暮らし、どんな仕事をして生きていこうか。そんなことを考えている人は増えていると思う。生まれ故郷に戻る道もあれば、新しい場所に住むという選択肢もある。特にどの場所とも縁がなく、何かきっかけを待っているという人もいるかもしれない。
そんな人に、この街のことを知ってもらえたらいいなと思いました。まずは、町を知ることからはじまる仕事です。
 今回は、若狭湾に面した海辺の町、京都・伊根町の「地域おこし協力隊」を募集します。
今回は、若狭湾に面した海辺の町、京都・伊根町の「地域おこし協力隊」を募集します。「地域おこし協力隊」は、地域力の維持と強化を目的に、総務省と地方自治体が行う取り組み。
任期は1年から最長3年までなのだけど、その間は役場の嘱託職員として仕事をすることになる。
具体的には、海外からの観光客に向けたツアーを企画する「インバウンド推進担当」と、旅行商品の企画・販売や特産品開発をする「ツアー企画担当」の2つの役割が求められる。
いつまでにこれをしなければいけない、という決まったプログラムは無いので、町のなかに入って自分で仕事をつくっていってほしいそう。
任期を終えたとき、自分だけで進めていけそうな仕事が見つかれば、そのまま独立することもできる。
そこには今まで知らなかった京都が広がっていました。どんな町なのか、ぜひ知ってみてほしいです。
 京都というとすぐに浮かぶのは、碁盤の目の町並みのなかに、寺社仏閣が点在する情景かもしれない。
京都というとすぐに浮かぶのは、碁盤の目の町並みのなかに、寺社仏閣が点在する情景かもしれない。けれど、北へのぼっていくと、若狭湾に面して沢山の海辺の町があることがわかる。
丹後半島のなかに、耳のようなかたちで突き出しているのが伊根町。地形が南に向かって折れているため、日中の伊根湾には、太陽の光がぞんぶんに注がれる。
ここは、古くは島根の出雲の方から海を渡ってきた人々が住み着き、町を形成してきたという言い伝えがある。港町として栄え、江戸時代からは舟屋がつくられはじめた。
舟屋とは、1階が船のガレージ、2階が居間という造りの建物のこと。海辺の際に建てられているため、海から見ると海に浮かんでいるように見える。
1階のガレージは、海を一望できるテラスのようでもある。どこにいても波のゆらめく音と光を感じられる。
 だんだん漁業をする人が減り、使われなくなった舟屋は、カフェや宿、ギャラリーとして生まれ変わり、今でも伊根湾周辺には、230余りの舟屋が軒を連ねている。
だんだん漁業をする人が減り、使われなくなった舟屋は、カフェや宿、ギャラリーとして生まれ変わり、今でも伊根湾周辺には、230余りの舟屋が軒を連ねている。その珍しい景観から、NHKの朝連続ドラマや「男はつらいよ」「釣りバカ日誌」などの舞台になったことも。情報番組の特集で取り上げられる機会も多い。
とくにミシュラングリーンガイドに2つ星で取り上げられてからは海外からの観光客も増え、年間25万人の観光客がやってくるようになった。
年々増加する観光客に、町の対応が追いつかない。そこで今回の募集に至ったそうだ。
京都駅から特急に乗り込み天橋立駅に到着すると、伊根役場の前田さんが迎えてくれた。
3kmに及ぶ松林が海の真ん中を通る天橋立の風景を横目に、車で海岸沿いを進んでいく。
 行く道すがら、前田さんに話を聞く。前田さんは京都府の職員で、人事交流として2年限定で伊根町へ派遣された。そして、もうすぐ任期を終えるのだそうだ。
行く道すがら、前田さんに話を聞く。前田さんは京都府の職員で、人事交流として2年限定で伊根町へ派遣された。そして、もうすぐ任期を終えるのだそうだ。前田さんに、伊根町での暮らしはどうだったか聞いてみた。
「伊根って魚屋がないんですよ。八百屋もコンビニもない。」
それでも、食べ物はじゅうぶん手に入る。
「魚は、防災無線でその日獲れた魚の情報が流れるんです。そうすると、バケツを持って近所のおばちゃんたちが集まってきて、キロいくらで魚が売られるんです。魚の種類にもよりますが、1キロで200円とか、すごく安いんですよ。」
山に入れば米どころ。農家さんがとれたての野菜を売りにきて、魚と物々交換することもある。自分で野菜をつくりたいなら、貸してもらえる土地もある。
「お洒落大好きでいつでもショッピングがしたい!という人にとっては退屈かもしれませんが、楽しめる人には楽しめる場所だと思います。」
 前田さんに、伊根の地域おこし協力隊としてどんな人に来てほしいか、聞いてみた。
前田さんに、伊根の地域おこし協力隊としてどんな人に来てほしいか、聞いてみた。「自分でこれがしたい!って自主的な発想で動ける人。今日なにしたらいい?って聞かれたら困ってしまいます。でも、これが売れると思うんです!とか、こんなツアーがつくりたいんです!と言ってくれれば、こちらからも具体的なアドバイスができると思います。」
たとえば、海外の人に向けてこの町の魅力を知ってもらうためのツアーコースを考えたり、町のお母さんたちに聞き込み調査をして、美味しい食材や、加工の方法を学んだり。
まずは、自分が町の魅力を知ることからはじまると思う。想像だけれど、一日中町を歩いて人と話して終わってしまうような日もあるのかもしれない。それだって仕事のうち。
ただ、なにもかもひとりでやらないといけないというわけじゃない。町の観光協会や、個人の方が立ち上げた「伊根浦創造塾」という地域団体もあり、活動をサポートしてくれるそうだ。
 とくに「伊根浦創造塾」は、30〜40代の伊根町の若手たちの拠点になっていて、定期的にイベントやワークショップなどが開かれているそう。そこに参加してみれば、町の人と顔がつながってネットワークづくりのきっかけになるかもしれない。
とくに「伊根浦創造塾」は、30〜40代の伊根町の若手たちの拠点になっていて、定期的にイベントやワークショップなどが開かれているそう。そこに参加してみれば、町の人と顔がつながってネットワークづくりのきっかけになるかもしれない。Iターン、Uターンで移住してきた人が多いのも伊根町の特徴。自分から動けば仲間は見つかると思う。
伊根町に実際に暮らす人たちを、何人か紹介してもらうことにした。
最初に紹介したいのは、鍵さんと奥さんの美奈さん。おふたりは、6年前に舟屋が体験できる宿「鍵屋」を開いた。
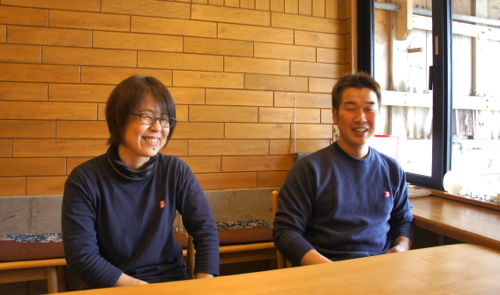 それまでは、14年間、奥さんの実家がある茨城でお寿司屋さんを営んでいたそうだ。
それまでは、14年間、奥さんの実家がある茨城でお寿司屋さんを営んでいたそうだ。他の場所での暮らしが長いぶん、客観的に伊根のことを見ることもできる。ふたりは、伊根への移住を考えている人たちの窓口にもなっているそうだ。
「みんな心配しすぎ。何もないから心配なんだろうけど、車があればだいたいのものは揃うよ」と鍵さん。
「バイパスができてから、どこ行くにも早くなったよね。どうしようもないのはネットでも買えるしね。」と美奈さん。
美奈さんは、茨城からのIターン。はじめは慣れないこともあったけれど、今はすっかり伊根の暮らしが板についてきた。
今日も、干物の干し方を近所のお母さんに教わったそうだ。
「近所のあちこちでやってるから。聞けば教えてくれるし。」
こちらにきてから、干物をさらに天日干しにすることに驚いた。でも、そうすることで、さらに風味が増してカリッとすることが分かった。比べ物にならないほど美味しいらしい。
「話を聞いてるだけで、商売の匂いがするでしょ?」と笑う鍵さん。
美奈さんのように、興味を持って町の人と話してみると、それがツアー企画や商品開発につながっていく可能性もあるかもしれない。
 最後に、ふたりにこんなことを聞いてみた。
最後に、ふたりにこんなことを聞いてみた。ここにしかないものってなんだと思いますか?
「景色だよね。いまだに帰ったら、おお、伊根に住んでる!って思うもん。」
「同じ料理でも、ここで眺めながら食べるのはほかと全然違うと思う。ここでコーヒー淹れて飲みながら外に出ると、味が変わっていくのが分かるくらい。たぶん、気持ちの問題だよね。外でBBQやるとおいしいのと一緒かな。」
この景色と、素材そのものの良さを活かした料理とを、合わせて食べてもらう。それが、これからも続けていきたい鍵さんの仕事。仕事というより、生業なんだと思う。
「自分探しにきても、多分ここにはなにもないよ。自分の得意技を推し進めていきたい人なら、いいと思う。だって、それについていきたいって人、いるもん。こういうことしたい!って言えば、ちゃんと聞いてくれる。」
「とりあえず、やりたいことやったらいい。やってだめならだめなんだ。そしたら違う方向でもう一回考えればいい。大人に怒られたらやめればいいよ。」
 大人の鍵さんがそんなことを言うのが、なんか可笑しかった。もちろん、みんながみんな鍵さんのような考え方じゃないとは思うけど、こういう考えの人もいるんだということ。
大人の鍵さんがそんなことを言うのが、なんか可笑しかった。もちろん、みんながみんな鍵さんのような考え方じゃないとは思うけど、こういう考えの人もいるんだということ。この景色を味わうだけじゃなくて、この景色を活かして何ができるか考えたい人なら、その熱意が伝われば、きっと色々な人が巻き込まれてくれると思う。
もうひとり、紹介したい人がいます。
鍵屋さんの対岸で、台湾茶葉の専門店「靑竈(チンザオ)」を営む橋本さん。
「ガラガラって戸を開けたときに見えた風景に、あっ、と思って。それで引っ越してきてしまったんです。」
台湾から直接買い付けてきたというウーロン茶を淹れながら、橋本さんはそう話す。
 偶然お店に来ていた近所の方が言う。「橋本さんって、漫画とか絵本に出てくるような人でしょう。」
偶然お店に来ていた近所の方が言う。「橋本さんって、漫画とか絵本に出てくるような人でしょう。」たしかに。なんだかすごくオーラというか、雰囲気がある。
橋本さんは、東京で長いこと役者をやっていたそうだ。京都に拠点を移し、6年前からここでお店を営んでいる。
お茶は香りを楽しむもの、と橋本さん。渡されたグラスに鼻を近づけると、音楽のように香りが変化していく。
お茶と向き合う上で、海沿いだけれど潮の香りが強くないこの場所は、とても適しているそうだ。
橋本さんがここへ引っ越す決め手となった風景へ、案内していただく。
お店の奥の扉を開けると、そこは舟のガレージ。机と椅子が並ぶスペースの奥はすぐ海で、水面がキラキラ光っている。
 お客さんはここで、足を水につけてお茶を飲むこともできる。夜には月が出て、海ほたるが光ることもある。朝焼けはたまらなく美しいそう。
お客さんはここで、足を水につけてお茶を飲むこともできる。夜には月が出て、海ほたるが光ることもある。朝焼けはたまらなく美しいそう。お茶とこの景色を求めて、全国からお客さんが訪ねてくる。
橋本さんがこんなことを言っていた。
「もっと色々な人にきてほしい。ここは、人が集まることで良くなる可能性があると思います。町の人と話すと、なんとなく、顔つきが個性を感じさせる人が多いんです。でも、まだまだひとりひとりの個性を生かしきれてはいないように見える。お互い主張しあえるコミュニティがつくれたら、もっと変わってくると思います。」
 橋本さんも鍵さんも、「地域を元気に」とか「地域活性化」とか、そういう言葉を一切使わなかったのが印象的だった。
橋本さんも鍵さんも、「地域を元気に」とか「地域活性化」とか、そういう言葉を一切使わなかったのが印象的だった。それよりも、自分のやりたいことを実現できる場所を見つけられたからワクワクしている、という感じ。
雇ってくれる仕事が沢山あるとは言えないこの町には、だからこそ、自分で仕事をつくっていける人たちが自然と集まってくるのかもしれない。
そういう人たちがそれぞれに取り組んでいる活動を、つなぎ合わせたり外へ伝えていくのも、今回の仕事の役割のひとつだと思う。
町を知るには、もってこいの仕事。期間限定でも、きっと他ではつくれないネットワークがつくれるし、ゆくゆく自分の生業をつくることもできるかもしれない。
海の京都から、自分の仕事をはじめてみませんか。
(2014/4/18 笠原ナナコ)

