※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
江戸時代から続く、仕出し折詰弁当「日本橋弁松(べんまつ)総本店」。その味は160年にもわたり多くの人々に愛されてきました。深夜からの仕事は大変ですが、伝統を受け継ぐ誇りも感じられるはず。今回は製造スタッフを募集します。
深夜0時を回るころ、隅田川にかかる永代橋(えいたいばし)のたもとにある製造工場に集まる人々。弁松総本店のスタッフたちだ。
 つくり置きせず、翌日の納品分を深夜から朝にかけてつくる。その数、およそ1,000〜2,000食。予約注文分のほか、都内の大手百貨店にも納品している。
つくり置きせず、翌日の納品分を深夜から朝にかけてつくる。その数、およそ1,000〜2,000食。予約注文分のほか、都内の大手百貨店にも納品している。弁松の歴史は古く、現存する弁当屋ではもっとも長いという。
ルーツは文化7年(1810年)、初代の樋口与一が日本橋に開業した食事処「樋口屋」。当時の江戸は魚河岸が日本橋にあった(関東大震災で築地へ移転)から、いそがしい仲買人が利用する食堂だった。
樋口屋は、盛りの良さに加え、残った料理を竹の皮や経木(薄い木の皮)に包んで持ち帰れるサービスがウケて大繁盛。最初からテイクアウトする客も多くなった。
そこで三代目の樋口松次郎は、折詰弁当一本でいこう!とリニューアル。屋号を弁当屋の松次郎、すなわち「弁松」としたのが嘉永3年(1850年)だった。
それから160年あまりが経ち、八代目の樋口純一さんが現在の社長だ。
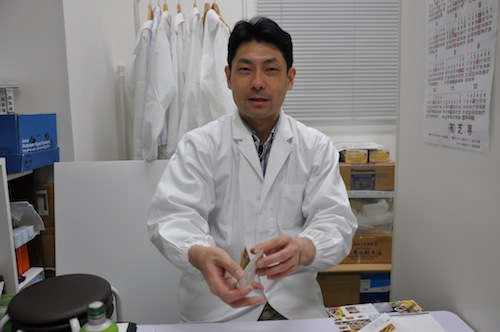 1971年生まれの42歳。お子さんはふたり。大学卒業後、親戚のもとで2年間修行をした後に入社。先代が急死したことで、わずか半年で跡を継いだ。だから、社長になってもう17年近い。
1971年生まれの42歳。お子さんはふたり。大学卒業後、親戚のもとで2年間修行をした後に入社。先代が急死したことで、わずか半年で跡を継いだ。だから、社長になってもう17年近い。「同世代の若旦那をみると、先代や先々代が健在で、自分のやりたいことができない人も多いです。父には長生きしてほしかったのですが、若いうちから自分のやりかたができた点は良かったです。」
自らの代で工場を新しく移転拡張し、日本橋の本店も建て替えた。
「自分がやる大きな設備投資は、これで終わりです。今後は労働環境を改善していくのが目標です。夜中からの仕事は変えられないけど、社員が自分の生活と仕事を両立して、健康にも気を使ってはたらけるようにしたい。そこがよくなっていけば、自然と人も集まってくると思いますから。」
仕出しのお弁当を取り巻く環境も、以前とは変わった。
「同業者だけではなく、デパ地下やカフェなども弁当を売っていて、いまは競合がたくさんあります。おなかを満たすための食事は多いですが、それとは別物と考えています。」
「コンビニのお弁当はバリエーションもあるし、毎日食べようと思えば食べられる。うちの弁当は値段が高くなるとおかずの種類が増えたり、魚が大きくなったりするだけで、基本は1つの路線。毎日食べるものではなく、ここぞというお祝いや会合のときに食べていただくものです。」
僕は、数年前に弁松のお弁当を初めて食べた。それは日本橋室町エリア再開発にかんする、記者発表の席だった。
街に伝わる味として紹介された弁松の折詰弁当には、冷めた状態で美味しい濃い味つけの野菜の甘煮(うまに)と、弁当箱から松の香りがほんのり移ったツヤツヤの白飯が。豆きんとんや玉子焼の甘さからは、なつかしさと洗練さを同時に感じて驚いた。
「お客様の8割は昔から食べてもらっています。『このお弁当を食べるたびにお婆ちゃんの顔を思い出す』とか、二代、三代続く人たちは当たり前。お客様の思い出の中の風景、小道具のような感じで残っていることが多いんです。」
それが、この“濃ゆい味”なんですね。
「ええ。お醤油と砂糖、多少の調味料を使っているだけでシンプルですが、うちがやめてしまったら出せない味です。つくる側の意志として、この弁当は江戸から続いている文化の1つだととらえています。」
 社長になった直後、世間に減塩ブームがおとずれた。味を薄くしようか悩んだ時期もあったという。
社長になった直後、世間に減塩ブームがおとずれた。味を薄くしようか悩んだ時期もあったという。「あるかたに『流行に乗って味を薄くしたら、味がボケただけになる』と言われました。そのとき、うちの弁当は理由があってこの味になっているのだから、このままでいこうと吹っ切れたんです。」
深夜1時になったところで、樋口さんと製造現場へ移動した。
白い作業服を着て、帽子をかぶり、マスクをして、長靴をはく。そして、よく手を洗ってアルコール消毒。衛生観念があることは、採用の必須条件だろう。
 ホコリを落とす「エアーカーテン」に入ってから、いざ調理場へ。
ホコリを落とす「エアーカーテン」に入ってから、いざ調理場へ。まずは、「焼方(やきかた)」のフロア。魚をオーブンで焼いたあとに手作業で照りを塗ったり、玉子焼を手焼きで1本1本つくったりする持ち場だ。
照り焼きの香ばしいかおりと、玉子焼の甘いかおりが漂い、ワクワクする。
 一度につくる量が多いので鍋も大きい。オーブンやガス台、テーブルの周りをテンポよく移動して調理するスタッフたち。
一度につくる量が多いので鍋も大きい。オーブンやガス台、テーブルの周りをテンポよく移動して調理するスタッフたち。バタン、バタンと、小気味よく玉子焼を焼く社員に話をうかがった。
木村浩二さんは、入社6年目の45歳。それまでは町工場の機械で、製造業にたずさわっていた。
 「もともとなにかをつくるのが好きで、調理をやってみたいという思いもあったんです。いまの仕事は楽しくやらせてもらっています。」
「もともとなにかをつくるのが好きで、調理をやってみたいという思いもあったんです。いまの仕事は楽しくやらせてもらっています。」話をしながらも、鍋に手ばやく油を塗り、玉子焼を焼き上げていく。
重たそうですね。力は要りますか?
「この卵だけで1kgです。具の入ってない普通の玉子焼1本から、17切れがつくれます。初めて食べたときは驚きました。ほとんど醤油と砂糖だけの味わいで。食べているうちに、昔ながらの味だと感激するようになって。」
会社の雰囲気はどうでしょう。
「仕事中はあまりしゃべらないですが、チームワークがありますね。お弁当を出荷してから、みんなで朝ご飯をつくって食べます。仕事終わりも一緒に飲みにいきますよ、たまにですけど。生活時間が逆なので、なかなか機会がないんです。」
今後は、別の調理にも挑戦したいという。
「ここは『焼方』の持ち場で、自分は『煮方(にかた)』のレベルにはまだないです。なかなか煮方にはなれないですからね。」
ちなみに、煮方のフロアはこのような感じ。夏場の暑さは相当なものだろう。
 2時間かけてじっくり煮ることで、弁松の独特な甘煮ができあがる。ベテランの職人が指導しながら、味を継承している。
2時間かけてじっくり煮ることで、弁松の独特な甘煮ができあがる。ベテランの職人が指導しながら、味を継承している。もうひとり、小山友二さんにもきいた。入社5年目の43歳、卵を焼いて3年くらいになる。以前はリフォーム会社の営業職をしていた。
 ふだんのお仕事を教えてください。
ふだんのお仕事を教えてください。「玉子焼のほか、焼き魚も担当します。弁当箱に詰める作業もやりますね。全般的につくるほうだけでなく、箱に詰めて納品したり、クルマで配送したり、お客さんのところに商品を届けるという仕事もありますから。」
話をしていても、卵を焼く手は休めない。焼き色を見ながら、火加減を微妙に調節する。
「始業の1時間半前に起きるので、夜11時くらいが朝です。夜中だと電車はないので、自転車やバイクのほか、クルマで通勤する人もいますね。」
仕事の終わりは、何時ごろになりますか。
「お昼までに納品に行きます。その間、残ったスタッフは仕込みの作業です。配達から帰ってきたら片づいているので、いまは昼の1時には帰れる体制にはなっています。」
ローテーションがくずれると、それだけ拘束時間が長くなってしまう。
「人が充実してきたら、そのぶん楽になるでしょう。家族や趣味にかける時間があまりないのが悩みです。いまは帰って見逃したテレビを見るくらいしかできないので。」
 ふたたび、社長の樋口さん。時間がないという悩みは多いですね。
ふたたび、社長の樋口さん。時間がないという悩みは多いですね。「当日調理したものを当日詰めたいという姿勢は変わらないし、それには早朝から働くことが必要です。でもスタッフの人数がそろっていけば、上がる時間を早めることもできる。会社として申し訳ないのが、工場の中にいる人間はお客様となかなか接点が持てないこと。配達に出たりするとあるのですが、生の声をきく機会が少ないんです。」
それは残念ですね。
「せっかく江戸に関係する会社なので、時間と予算に余裕が出てきたら5人くらい歌舞伎に連れていって、自分が座席についたときのシチュエーションでどういう弁当がいいのか考えてもらうのもいいですね。味や価格だけでなく、どういうシーンで、どういうものが出たらお客さんがよろこんでくれるか。そんな知識をつける時間を増やしたいです。」
社員のかたからは、チームワークがある職場とうかがいました。
「ここ10年くらいかけて、社内の協力体制がスムーズになったように思います。昔からの職人にも見てもらっていますが、世代が違うと考えかたが違う部分もありますから。まだ先輩的な人もいるけれど、これからは若手が中心になるので一歩下がってもらっています。」
老舗の経営者としては若手にあたる樋口さんだが、この会社の舵取りをしてきた自負がのぞく。
製造や配送、デパートの販売員なども含めると、スタッフは総勢50人ほど。社員の平均年齢は40代後半。徐々に若手を増やしたいという。
今回の募集では、どんな人にきてほしいですか。
「大きな鍋を運んだりするので、力仕事ができないと難しいですね。ただ、始発で来ていただいて、弁当を詰めたり、包装紙にハンコを押したりという軽作業もあります。」
弁当を詰める作業ではアルバイトも多い。女性も多く明るい雰囲気。ミャンマー、ベトナム、中国などからの留学生だという。
 「採用してしばらくは、朝6時から昼14時30分まで来ていただく予定です。そのうち調理も任せたいので知識はあったほうがいいですが、うちの味を覚えてつくってもらうことになります。」
「採用してしばらくは、朝6時から昼14時30分まで来ていただく予定です。そのうち調理も任せたいので知識はあったほうがいいですが、うちの味を覚えてつくってもらうことになります。」どちらかと言えば、食の仕事に興味がある未経験を優遇するようだ。調理師免許はなくても大丈夫ですね。お休みや待遇についてもきかせてください。
「週1日休みで、そのほか月2日の休みがあります。深夜勤務になると、込みの残業代以外にも手当てがつくパターンが多いので、給与は実質30万円台になるでしょうか。」
人手が足りないと自ら調理場に入る樋口さん。伝統の味を受け継ぐ意志を持ちながら、これからの経営を伝統の枠にしばられない。
他社とのコラボ商品や新ブランド展開のアイデアもある。「なぜなに べんまつひみつ図鑑」のような楽しいパンフレットも紹介したいところだけれど、気になったかたは、面接できいてください。
僕は弁松の味のファンだし、なにより実家が同じ仕出し弁当店(小さいし歴史は浅いけれど)という親しみがある。きっと、特に夏場や冬場にしんどい仕事場だろうと想像します。
でも、口にするものをつくって、手わたし、人によろこんでもらえる仕事は、素朴でやりがいがあるのも確かです。
 「たまに『こんなスゴい著名人が食べてくれているんだ』と驚きます。自分たちが思っている以上に『弁松』の名は認知されていると感じますね。」
「たまに『こんなスゴい著名人が食べてくれているんだ』と驚きます。自分たちが思っている以上に『弁松』の名は認知されていると感じますね。」百聞は一食にしかず。まずはお弁当を買って、ぜひ食べてほしいです。
(2014/5/16 up 神吉弘邦)

