※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
里山の荒廃、全国で200億円にものぼる野生動物による農作物被害(獣害)の増加、そして猟師の担い手不足。日本全国の中山間地域が抱える課題に、まずできることから取り組んでいこう。体を動かしながら、なにより楽しみながら!
そんなノリと勢いから、岐阜県郡上市で産声を上げたのが“猪鹿庁”です。webページには次のような言葉が。
 —岐阜県郡上市に13個目の省庁「猪鹿庁」ができました!(嘘)—
—岐阜県郡上市に13個目の省庁「猪鹿庁」ができました!(嘘)—
立ち上げたのは、猪も鹿も見たことがなかった当時20代の移住者たち。
「郡上に片思いをしたんです。ここにある資源を活かし、どうやったらずっとずっと暮らしつづけられる郡上をつくれるだろうと考えたんです。」
そうして見つけたのが、豊かな自然と獣でした。
猪鹿庁の輪は広がり、いまでは地元の方も仲間に加わって活動しています。
地域にあるものから仕事をつくり、暮らしていくメンバーを募集します。
郡上市は、名古屋駅から飛騨高山行きの高速バスに乗って一時間ほど。
バスには、外国人観光客の姿もちらほら見える。新緑の続く景色を抜けて、郡上八幡インターへと到着した。
「こんにちは〜」とバンで迎えてくれたのは猪鹿庁・長官の興膳(こうぜん)さん。
 車は清流・長良川沿いを進み、郡上八幡の市街地へ。
車は清流・長良川沿いを進み、郡上八幡の市街地へ。「毎年7月から9月にかけて、32夜の郡上おどりが行われるんです。」
この時期になると、地元の人はもちろんのこと、帰省する人や観光客でまちはにぎわう。なかでも8月に行われる4日間の徹夜踊りには、25万人もの人が訪れる。
「郡上おどりの魅力は、みんなで一緒に踊れること。はじめて来た人でも楽しめるんですよ。そのお陰かな。外から人が入りやすい地域だと思います。」
 そう話す興膳さん自身も、福岡からの移住者。
そう話す興膳さん自身も、福岡からの移住者。「もともとは博多に住んでいました。まちづくりを学びたくて、岐阜大学に進んだんです。そこで、長良川流域の地域づくりをしているNPO法人ORGANの蒲(かば)さんと出会います。活動を共にしていくなかで、地に足のついた暮らしをしたいと思うようになりました。」
上流に位置する郡上市へやってきたのは7年前のこと。
「人に惚れたんです。郡上に片思いをして、ずっと振り向かせたくて、あの手この手で取り組んできました。」
郡上は、面積の90%を森林が占め、修験道である白山信仰の地として知られる土地。
取材前は厳しいイメージを持っていたけれど、訪れると印象はがらりと変わった。
 鵜飼いで知られる長良川。ここ採れる鮎は、日本一とも評される。6月になると、河原は鮎釣りをする人で溢れかえるそうだ。
鵜飼いで知られる長良川。ここ採れる鮎は、日本一とも評される。6月になると、河原は鮎釣りをする人で溢れかえるそうだ。川の水を育むのは、林業が営まれてきた山。実は、郡上は猪の三大産地でもあるそうだ。
さらに車を走らせると、畑や田んぼに人の姿が見える。
手で田植えをする人に、野焼きをする人。庭に腰かけて景色を眺める人も。
下校中の子どもたちの姿が見えると「郡上の子どもたちは、信号をわたるとおじぎするんですよ。」と興膳さん。
「自然もあれば、おどりをはじめとする文化、そして人。豊かな土地だと思います。だからこそ色々な可能性がありえます。いまは西粟倉に江津、海士町… 全国で盛り上がっている地域がありますよね。みんなの姿も見つつ、自分たちはどこに向かっていくのか、考えているところです。」
現在、興膳さんは子どもキャンプや泥んこバレーボール大会、イラスト田んぼ、農林業体験を行う「NPO法人メタセコイアの森の仲間たち」(以下、メタ森)の代表を務めている。
猪鹿庁は、メタ森の一事業にあたる。
けれど移住して数年は、2足のわらじの生活だったという。
当時メタ森は、春から秋の期間雇用だった。仕事がなくなる冬季は、スキー場でのアルバイトで生計を立ててきた。
冬にできる仕事として見つけたのが、“猟”だった。
 いまでこそ担い手は減少したけれど、かつて猟は農閑期の生業だった。
いまでこそ担い手は減少したけれど、かつて猟は農閑期の生業だった。時期を同じくして移住した仲間たちと罠猟・狩猟免許を取得。地元の方に師事した。
また、地域で深刻になっていたのが獣害。
行政レベルでも取り組みはされてきたけれど、対応が追いつかない現状があった。
「郡上で豊かに暮らし続けていく。それって、面積の90%を占める山と一生付き合っていくことです。猪や鹿を“害”ではなく、“資源”として捉えられないかと思いました。」
そうして、2009年に猪鹿庁は発足した。
 「何より楽しくやりたかったんです。猟のフィールドである里山を育てる山育課、猟師育成を行う捜査一課、天然のお肉を美味しくいただくジビエ課、そして郡上の猪のブランド化を目指す広報課… 6つの課で活動をはじめました。」
「何より楽しくやりたかったんです。猟のフィールドである里山を育てる山育課、猟師育成を行う捜査一課、天然のお肉を美味しくいただくジビエ課、そして郡上の猪のブランド化を目指す広報課… 6つの課で活動をはじめました。」猪鹿庁は、まず地元での猪・鹿のイメージを変えることに取り組む。
「とにかく猪や鹿は嫌われものです。特に、農業の中心である60、70代の人にとっては『カタくて臭くて食えたものじゃない』と、マイナスのイメージが強すぎたんです。」
そこで、鹿ジャーキーや猪フランクを開発。地元でイベントが開かれるたびに、試食販売を実施。
 地道に活動を重ねることで、はじめは見向きもしなかった人も食べるように。
地道に活動を重ねることで、はじめは見向きもしなかった人も食べるように。口に入れると、意外とおいしいことに気づいた。
次に、手軽に捕獲できる罠“肉の畑”を開発。農家に貸し出した。
一見変わったネーミングにはこんな思いがあった。
「自分の畑ぐらい自分で守ってほしいんです。農作物に被害を受けるだけでは “獣害”です。けれど、売れるようになれば獣肉は“資源”ですよね。『うちの畑では野菜も肉も採れるぞ』。獣害対策に前向きに取り組むようになってほしいんです。」
 メタ森の一事業である猪鹿庁は、メンバーがそれぞれに仕事を持ちながら、助成金ベースで活動してきた。
メタ森の一事業である猪鹿庁は、メンバーがそれぞれに仕事を持ちながら、助成金ベースで活動してきた。6年目を迎える今年、はじめての専属スタッフを募集します。
ここで話を聞いたのは、猪鹿庁捜査一課の永吉剛(ごう)さん。
神戸出身の剛さんは、仕事で郡上を訪れたことがきっかけで移住。現在はメタ森の理事を務めている。
興膳さんが大きなビジョンを語るアイデアマンとすれば、剛さんは実行に落とし込んでいくプランナー。
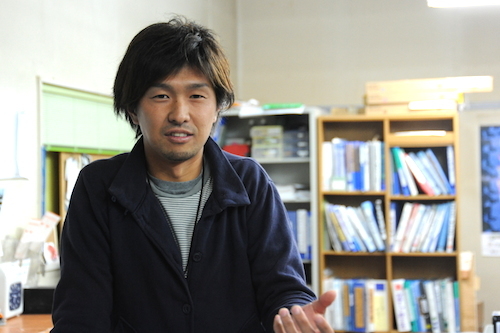 「猪鹿庁を自立事業にしたいんです。収益を上げ、活動を継続していくことが地域に役立つことにもつながります。いま、猪鹿庁には狩猟のプロに食材加工のプロ… ありえないくらい恵まれたメンバーが集まっています。コンテンツとなる人がいるからこそ、うまくコーディネートしていってほしいんです。」
「猪鹿庁を自立事業にしたいんです。収益を上げ、活動を継続していくことが地域に役立つことにもつながります。いま、猪鹿庁には狩猟のプロに食材加工のプロ… ありえないくらい恵まれたメンバーが集まっています。コンテンツとなる人がいるからこそ、うまくコーディネートしていってほしいんです。」事業の軸としては、獣肉商品の開発販売、獣害対策事業、そしてエコツアーの3つが挙げられる。
今後大切になるのは、外との交流を増やしていくこと。
「鹿フランクは、話のネタにしやすいんですよ。たとえば近隣地域のイベントで販売をしつつ、その地域の獣害対策事業受託に結びつけていくことも考えられるでしょう。」
「また商品を都市部で販売する際に、あわせてツアーの案内を行っていくことも考えています。モノから地域に興味を持つことがあると思うんですね。一緒に考えて、仕事をつくっていきたいです。」
外との交流が増えることは、郡上の自信にもつながってくる。
「たとえば猟体験のツアーを企画すると、意外に若い女の人が訪れるんです。彼女たちが楽しむ姿を見ると、地元の人たちが喜ぶんですよ。『鹿肉って意外とおいしい』『郡上っていいところですね』。そうした声を聞くことが、郡上で暮らす誇りにつながるんじゃないかな。」
 次になじみの薄い獣肉について、ジビエ課の三島さんに話をうかがいました。
次になじみの薄い獣肉について、ジビエ課の三島さんに話をうかがいました。郡上出身の三島さんはハム屋さんで修行した後、独立。
工房をたずねると、まさに獣肉の加工がされているところ。
「釜で焼いているのが鹿肉のフライッシュケーゼ、腸詰めせずに型に入れて焼き上げたソーセージですね。日本ではなじみが薄いけれど、ドイツでは身近な食べものです。それからボイルしているのが、鹿肉のハムです。」
 ところで、獣肉の魅力ってどういうものだろう。
ところで、獣肉の魅力ってどういうものだろう。「猪を食べやすいように品種改良したのが豚です。肉の味では敵いません。猪や鹿は、変化球なんですよね。」
でも、と三島さん。
「豚は品種から商品まで出尽くしています。一方、獣肉はこれから市場をつくっていくところ。一番を狙えるんですよ。」
野生鳥獣の肉はフレンチにおいてジビエと呼ばれる。貴族の伝統料理として好まれてきた高級食材だ。
ワインの普及もあって、最近は日本でもジビエを口にする機会が増えている。
山を駆け回り、自然の餌を食べて育った肉は森のご馳走とも言われる。身が締まり、栄養価も高い。
 取材後に東京でBBQをすることがあり、お土産にいただいた猪肉を持っていったところ、珍しさもあり、あっという間になくなった。
取材後に東京でBBQをすることがあり、お土産にいただいた猪肉を持っていったところ、珍しさもあり、あっという間になくなった。先入観が少ない分、どんなストーリーを描くかが大きく鍵を握っていると思う。
来年度以降は、白鳥地区に飲食店を開く構想もあるそうだ。
くわえて、携わるのは加工販売だけに限らないようだ。
「ぜひ罠猟・狩猟免許は取得してほしいです。自分で猟を楽しむから、気づくことが多いんですよ。猪鹿庁には、狩猟道具から自分の手でつくるメンバーもいます。彼に教わることから、ツアーも生まれてくると思うんですね。」
日も沈みかけて訪ねたのは、メタ森の事務所。
ここで猪鹿庁のメンバーたちに話を聞きました。
 郡上に生まれ育った女性メンバーの餌取(えとり)さんは、移住者の存在に影響を受けて、ネパールを旅してきた。
郡上に生まれ育った女性メンバーの餌取(えとり)さんは、移住者の存在に影響を受けて、ネパールを旅してきた。「旅の途中で何度も思ったんです。郡上の水が飲みたい、って。ここには何もないけれど、ゆっくり流れる郡上時間がありました。」
最後に話を聞いたのは移住6年目のモミさんこと、籾山さん。
モミさんは郡上に来てから獣解体の技術を身につけ、現在では年に100頭を捌くまでになった。
 この4月からはいちご農家を開業する。
この4月からはいちご農家を開業する。これからやってくる人に伝えたいことがあるという。
「遊ぶことで郡上のよさがわかると思います。」
自身の体験をこうふりかえる。
「春になって外で遊んでいたら、田植えをしているおばちゃんに声をかけられて、手伝いをしたり。川で遊んでいたら、ラフティングの仕事に誘われたり。そうやって自分が楽しむなかで、ツアーを思いついたりするんですよ。」
だから、と続ける。
「僕らもバタバタしているんですけど、剛でも餌取でもつかまえてみてください。そのまま家に泊まらせてもらったりもあるんで。」
 もちろん仕事をつくることは大切。同じくらいに遊ぶことが大切。
もちろん仕事をつくることは大切。同じくらいに遊ぶことが大切。「僕も気づけば6年目です。郡上を好きになることがはじまりじゃないかな。色んな人に出会うことだと思います。まずは来て、郡上に出会ってください。」
(2014/6/10 大越はじめ)

