※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
春は桜を楽しみ、夏になれば向日葵がまちを彩る。秋には枯れ葉を踏みながら、すすきで月見。寒さで動くのがおっくうな冬はラナンキュラスが心を和ませてくれる。 四季折々の花が暮らしを彩るのは、日本の文化の一つ。
四季折々の花が暮らしを彩るのは、日本の文化の一つ。そんな日本の花も、生産者と伝える人、販売する人、そして花を楽しむ人がいることで成り立つもの。
生産者と花屋さんの間に立ち、花業界を下支えする “仲卸し”という仕事があります。
「お客さんである花屋さんの要望を聞き、市場から花を仕入れます。たとえばピンクのバラでも、生産者によって色味が全然違うんですね。『あの花屋さんだったら、この花を好むだろう』と考えていきます。ときには生産者を訪ね、その魅力を花屋さんに伝えることもあります。」
 東京で仲卸しを行う株式会社フローレツエンティワン。花のすべてに関わる仕事です。経験や現時点での知識は問いません。
東京で仲卸しを行う株式会社フローレツエンティワン。花のすべてに関わる仕事です。経験や現時点での知識は問いません。東西線の西葛西駅から車で10分ほど。
葛西臨海公園の観覧車を望む葛西市場。この中にフローレツエンティワンの葛西営業部はあります。
迎えてくださったのは若い常務の竹内さん。
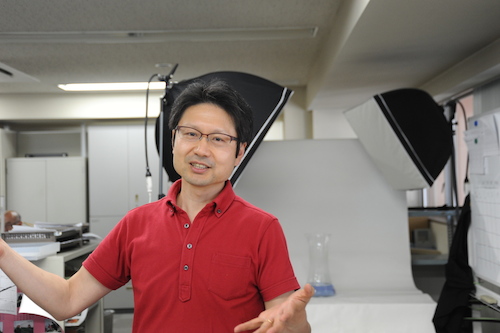 世界から見た日本の花について話をうかがう。
世界から見た日本の花について話をうかがう。「日本の花は、一本一本に生産者の色がよく出ます。その美しさは世界一なんですよ。」
十年に一度、オランダで開かれる世界一の花品評会である“フェンロー国際園芸博覧会”、通称フロリアード。
2012年には、日本の花が金賞の大半を受賞したそうだ。
日本の花は、海外の富裕層たちに高く評価されている。欧米に加え、近年増えつつあるのが、香港、ベトナム、中国といったアジア向けの輸出。
一方日本人は、日本の花を意外に楽しめていないのかもしれない。
「世界を見れば、花を一つの工業製品と見なす国もあります。たとえばコロンビアはカーネーション、韓国はバラ。広大なプランテーションで単一品種を栽培します。日本にも安価な輸入品は増加しています。」
たしかに、日々の生活で花を買う機会は限られているかもしれない。ましてや、口に入れる食品は国産にこだわっても、「花がコロンビア産か静岡産か」を意識することはなかった。
「大きな話をすると、僕らは日本の花の魅力を伝えることで、日本の花づくりを支えていきたい。生産者の“おじちゃんたち”につくり続けてもらいたい。だからね、一緒に働く人は、花に興味を持っていてほしい。同時に、商売という視点も大事にしてほしいです。」
ここからは、井上リーダーに日々の仕事をうかがう。人見知りなんですよ、と言いながらも笑顔で受け答えをしてくださった。
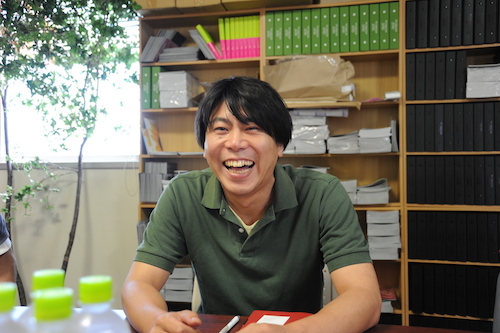 市場と花屋の間に立つ仲卸し、その勤務時間は独特なものでした。
市場と花屋の間に立つ仲卸し、その勤務時間は独特なものでした。「週のはじまりは、日曜日の昼前です。11時頃に市場に集まり、仕事が終わるのは21時ごろ。事務所で仮眠をとり、3時から仕事がはじまります。そして夕方の16時頃に仕事が終えて帰宅します。」
市場では、花の競りがある月水金を“表日(おもてび)”、競りのない日火木を“裏日(うらび)”と呼ぶ。裏日と表日を合わせた2日で1組と考えると、イメージが湧くかもしれない。
休日は土曜日、そして平日の週2日。
取材を行った金曜の夕方は、休みを前にして気持ちが一番落ち着くときだという。
「市場と花屋さんの間をつなぐ勤務形態。これが仲卸しという業界の現状です。働いてみるとシフトには慣れていきますよ。休みには家族との時間も過ごせていますしね。ただ、体力的にしんどいのは事実です。これが当たり前のことだとは思っていなくて、今後は勤務形態も見直していきたいんです。」
仲卸しという仕事は勤務体系、そして仕事内容についても、大きな過渡期にあるのかもしれない。
仕事内容を聞いてみる。
井上さんは、仲卸しの仕事を「かっこよく言えばバイヤーでありキュレーターですね」と話す。
はじめにバイヤーの仕事について紹介したい。
物流を順に追うと、生産者—市場卸売—仲卸—花屋—生活者となる。
お客さんは大きく2つに分けられる。“宴会屋さん”と呼ばれる冠婚葬祭向け。そしてまちの花屋さんにホームセンターの花コーナーといった“花屋さん”。
市場には“競り取引”のイメージがあったけれど、現在ではその姿も変わりつつある。主流となるのは、卸売業者と一対一で交渉を行う“相対取引”。
バイヤーの仕事は、お客さんのオーダーに基づき、市場で花を仕入れて納品すること。
「魚にたとえるとわかりやすいでしょうか。マグロに大間のマグロも、冷凍ものもあるように。花にもランクがあります。お客さんの予算の中で、一番質のよい花を揃えていきます。」
 花における質は、第一に美しさ。そして、鮮度を長く保てること。
花における質は、第一に美しさ。そして、鮮度を長く保てること。数多くの生産者の中から、よりよいものを選ぶのがバイヤーとしての腕。
「生産者にも色々な人がいます。花を出荷した時点で自分の仕事が終わったと思っている人。そして、花を手にとった人がどんな気持ちになるかまで考えている人。両者で、花の質はまったく違うものになります。」
「もう一つ大切なことは“季咲き”と呼ばれる花の旬を見ること。季節によっても最適な生産地は異なります。たとえばダリアの場合、3月初旬には千葉県から。8月下旬であれば、長野県のものを揃えたいですね。」
仕入れた花は仕分け、検品を行い、発送準備をしていく。
「体力も使いますが、花に一番触れられる仕事です。花が好きな人には楽しいと思いますよ。いい花に出会えるとうれしいですし、思うような花が手に入らないときもあります。」
 一通りの仕事を終えたときに、トラブルが起きることがある。
一通りの仕事を終えたときに、トラブルが起きることがある。花屋さんの注文に漏れがあった。出荷した花の輸送状態が悪く、途中で傷んでしまうことも。
そんな対応には、なかなか手間も時間もかかるもの。
たとえばこんなことがあった。
結婚式で、花嫁のブーケにどうしても必要な花の注文漏れが発覚した。
「同業他社にも相談しつつ、なんとか花を探していきました。それでも見つからなくて… 最後は車を飛ばして福島の生産者まで花をいただきに行ったんですよ。さすがに疲れましたね。一方で、生産者と話せるのは実は楽しみでもあるんです。」
 この話からもわかるように、これまで仲卸しに期待されたのは、とことんお客さんの声に応えること。
この話からもわかるように、これまで仲卸しに期待されたのは、とことんお客さんの声に応えること。一方で、花の業界は変わりつつある。
そうしたなか、いま仲卸に期待されるのは、キュレーターとしての役割かもしれない。
生活者にとっての窓口である花屋さんはかつて、知識豊富な職人気質の方も多かったという。最近では、アルバイトなども増えるように。
花をすすめるときに『かわいいから』と伝えることも出てくる。
「いま、季咲きの花は何か。どうすれば花はきれいな状態で楽しむことができるのか。そうしたことを花屋さんが伝えるのは大切だと思います。」
空輸貨物の進歩で、日本の季節とは関係なくさまざまな花が世界中から輸入されるようになった。さらに、日本の生産技術の向上でいままでは出荷がなかった季節にも花を咲かせることができるようになってきた。
「野菜や果物に旬があるように、花にも旬があります。日本の四季に合った花がそれぞれあるんです。」
 ほしいものがいつでも手に入ることは、一見便利でよいことに思えるけれど。
ほしいものがいつでも手に入ることは、一見便利でよいことに思えるけれど。「かつて季咲きの花は高値で売れたんです。けれど、その文化が忘れられることで、生産者の収入も減ってしまいます。『来年からイチゴをつくろう』と話すバラ農家さんも実際に出てきているんです。」
海外に輸出すれば、日本の花は高い評価を受けるけれど、日本で親しまれることこそ大切だという。
「評価されるのはうれしいことですが、長い目で見ると、日本のものを日本人が楽しめなくなると思うんです。花という日本の文化を、日本人が失ってしまう時代が来るかもしれません。」
文化はその土地で親しまれるからこそ、魅力が生まれてくるもの。日本の花の魅力を、日本できちんと伝えていくことが大切なのだと思う。
実は井上さん自身、仲卸の仕事に就いて、はじめて花を好きになったという。
前職でもブライダルに生け込みと、花に関わる仕事をしてきた。
きっかけは生産者を訪ねて話したこと。
「どんな人がつくっているのか。同じ品種も気候や風土によって花の育ち方が異なります。見た目だけでなく、花をちゃんと知るようになって、面白さを感じるようになったんです。」
取材中にこんな出来事があった。
あるお客さんから、「明日急きょ花を納品してほしい」という内容の電話。
対応したスタッフの草柳さんは「2日前には注文をいただけるとありがたいです。」と話した上で、こう説明をした。
「花は日中に光合成を行い、栄養を蓄えます。そして夜に成長します。花が一番元気で美しい朝採れの花を届けたい。生産者の方からも、そう聞いています。」
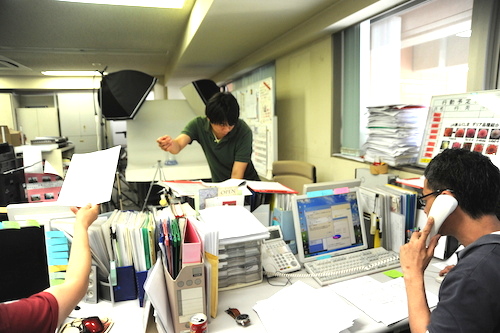 再び井上さんに話を聞く。
再び井上さんに話を聞く。今後は、企画の提案にも力を入れていきたいという。
「花屋さんは、どうしても毎日の注文がマンネリ化しがちです。僕ら仲卸から『こんな花もありますよ』『こうした組み合わせも考えられます』と提案をすることで、新たな価値を提供していきたいんです。」
すでに取組みははじまっている。
月ごとの季咲きの花。そして、生産者の思いをまとめた冊子「東京植物図鑑」を制作。お花の仕事に携わる幅広い人に紹介している。
 とは言え、仲卸しがキュレーターを目指していくのは今後の話。
とは言え、仲卸しがキュレーターを目指していくのは今後の話。これから入ってくる人は、まずバイヤーとして一人前になり、お客さんに信頼されることからはじまる。
これまで紹介してきたように、仲卸しは楽な仕事ではないかもしれません。同時に、花業界にこれほど関わっていける仕事もそうそうないと思う。よい機会かもしれません。
「いまはぶっちゃけ大変な面もあります。けれども、僕らも環境を変えていきたい。大きく言えば、花業界のこれからを一緒につくっていきたいんです。」
今回は葛西で働くみなさんに話をうかがいました。他の支店にも色々な人がいるそうです。
新卒で入社した20代の方。花屋から転身した人。事務の仕事を経て、花農家に住み込んだ後、仲卸へ飛び込んだ人。
 話が終わり、出口へと向かう途中。出荷を待つ花がところ狭しと並ぶ市場で、井上さんの話したことが印象的でした。
話が終わり、出口へと向かう途中。出荷を待つ花がところ狭しと並ぶ市場で、井上さんの話したことが印象的でした。「花を家に飾るようになったんですよ。花は人を幸せにできる。それはやっぱりあるなぁと思って。そういったことを、もっと伝えていきたいですね。」
(2014/7/7 大越はじめ)

