※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
HIROSHIMAというアームチェアを知っていますか?とてもいいデザインの椅子です。今回はこの椅子をつくっているマルニ木工の募集です。 マルニ木工の家具を海外に広めていく「海外営業」、最新の技術とアイデア、そして積み重ねた歴史をまとめながら工場をつくりあげていく「技術スタッフ」、そしてより現代的なスタンスで、会社の顔となる「広報」の担当者を募集します。
マルニ木工の家具を海外に広めていく「海外営業」、最新の技術とアイデア、そして積み重ねた歴史をまとめながら工場をつくりあげていく「技術スタッフ」、そしてより現代的なスタンスで、会社の顔となる「広報」の担当者を募集します。日本から海外へ広がりを見せているHIROSHIMA。そこにはたくさんの人がわが子を育てるように関わった物語がありました。
広島駅から車で50分ほど。市街地を抜け、森の中を通って、山の上のほうへ車を走らせると、大きな工場が見えてきた。車を降りると、乾いた木の香りがしてくる。
 事務所の中は、歴史ある会社にしては想像以上に垣根がなく明るい雰囲気だった。
事務所の中は、歴史ある会社にしては想像以上に垣根がなく明るい雰囲気だった。マルニ木工の前身となる「昭和曲木工場」は1928年に設立された。創業当時から「工芸の工業化」というモットーを掲げて、革新的な技術を次々と取り入れてきた。
1960年代には彫刻入りの家具の工業化に成功し、大ヒット商品も生まれた。その商品は国内における洋家具史上空前のベストセラーとなり、日本を代表する家具メーカーになっていった。
マルニ木工の代表を務める山中さんが入社したのは2001年。それまでは銀行で大量の不良債権処理を進める毎日だった。
「今の会長である叔父に『東京行くけど時間あるか?』って聞かれて。そしたらマルニ木工がしんどい状況だと。『銀行は何言うとるか分からん。今までは借りてくれ借りてくれと言ってたのが、返せ返せ、資料出せと。』ぼくは専門だったから、その状況が目に浮かびましたけど。」
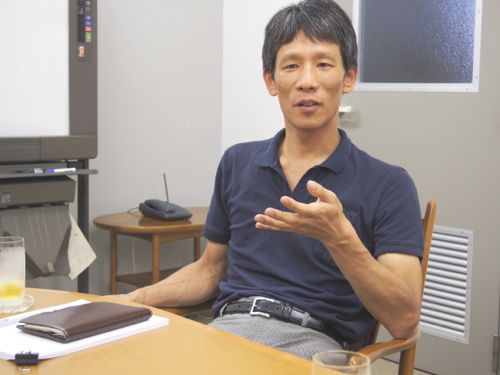 会社に戻ってみると、いろいろな慣習にびっくりするような毎日だった。
会社に戻ってみると、いろいろな慣習にびっくりするような毎日だった。どうにかして会社を変えないといけない。そんなときに当時の常務が言っていた言葉が身に染みた。
「彼は『会社を変えるのは人しかいない』とずっと言ってました。」
人しかいない。
「メーカーは商品開発で変わるんですが、それをつくるのは人なんです。」
最初の5年は「無借金経営、経常利益率10%」という目標を掲げた。ただ、だんだんとそういうことではないんじゃないか、と思うようになった。
「すごくいい技術があって伝統もあるのに、なぜ立ち行かなくなるんだろうと。よく考えたら欲しい家具はひとつもなかった。もしかしたらデザインがそれを変えるチャンスになるんじゃないかと思って。」
 まずはnextmaruniというプロジェクトを立ち上げ、いろいろなデザイナーにデザインしてもらう機会をつくっていく。今までのやり方を無視して、デザイナーの言う通りに家具をつくりつづけた。その中でも大きな転機となったのが、深澤直人さんとの出会いだった。
まずはnextmaruniというプロジェクトを立ち上げ、いろいろなデザイナーにデザインしてもらう機会をつくっていく。今までのやり方を無視して、デザイナーの言う通りに家具をつくりつづけた。その中でも大きな転機となったのが、深澤直人さんとの出会いだった。2004年に深澤さんが工場を訪れたあとに、もらったメールがずっと心にひっかかっていた。
「せっかく素晴らしい技術があるのに、最後に塗料をベタベタ塗ってしまうのはもったいない」という内容だった。
その後、深澤直人さんにデザインをお願いして生まれたのがHIROSHIMAだった。華美な装飾などはなく、背もたれの木のカーブが美しく、手触りがよい椅子だった。マルニ木工がもっている技術と深澤さんのデザインが融合した瞬間だった。
 「でもはじめは売れなかったですよ。最初に興味を持ってくれたのが新宿の伊勢丹さん。みんな『いい椅子出したね』って言ってくれるんですけどね。やっぱりすぐには売れない。」
「でもはじめは売れなかったですよ。最初に興味を持ってくれたのが新宿の伊勢丹さん。みんな『いい椅子出したね』って言ってくれるんですけどね。やっぱりすぐには売れない。」「でもよく見ていると、みんな肘から背の部分をさわっていくんです。本当に、みんなが。だから、確信めいた可能性の様なものは感じていました。すると、ようやく徐々に売れるようになって、そのあとはつくるのが大変でしたけどね。」
どれほどつくるのが大変なのだろう。HIROSHIMAがつくられている工場を見せてもらうことになった。
案内してもらったのは生産本部長の三井さん。たくさんの木材が積み上げられた最初の工程からスタートする。まずは板材の木目、欠点をチェックしてカットする。
 「HIROSHIMAの肘は、深澤直人さんのほうから木目が対称になるように、という条件が出されている為、実際には倍の長さがあったものを真ん中でカットして、木目が対称になるようにしている。」
「HIROSHIMAの肘は、深澤直人さんのほうから木目が対称になるように、という条件が出されている為、実際には倍の長さがあったものを真ん中でカットして、木目が対称になるようにしている。」つづいて木を曲げる工程。
木を曲げる方法は主に2つある。無垢の板材を蒸して曲げる方法と、薄板を積層して接着して曲げる方法があり、マルニ木工では後者の方法を多用しているそうだ。
「積層で曲げるほうが安定するんですよ。また板材を蒸して木に熱を加えると木の色が変わる事があるんです。木の味をそのまま活かし、ナチュラルな色に仕上げるのであれば、積層の曲げのほうがいい。これ、3枚貼ってあるのわかりますか?」
…うーん、わからない。
ほかにも色んな加工を見せてもらった。
その中でも「5軸同時制御の自動切削加工でHIROSHIMAの背もたれを加工している」ところが印象的だった。
…5軸同時制御?
「これは私どもの技術力を象徴するものです。3次元加工です。私どものものづくりは、木の切削、切断、穴明けといった、物理的に決められた形状、寸法に加工することは極力自動化する。人が触ったりした時の手触り感、綺麗な仕上げ、曲線の滑らかさといった感性に訴えるところの仕上げは職人の手で仕上げる。」
 まるで3Dプリンターが形をつくっていくように、少しずつ自動で削り取られて、だんだんと姿を現した。
まるで3Dプリンターが形をつくっていくように、少しずつ自動で削り取られて、だんだんと姿を現した。「でもこういったことができるようになったのも、今までクラシック家具で培ってきた技術の賜物なんですよ。他社ではなかなか真似できないことだと思います。深澤直人さんと一緒にものづくりができたのも、私どものものづくりが認められたことが一つの要因だと思います」
「こういった技術を組み合わせて、工場全体を考えられるような技術系の人に来てほしいんですよ。」
長年培ってきた技術を学び、それを効率よく組み合わせる。ときには今までの考え方を根底から覆して、新しいやり方にトライしてみる。
HIROSHIMAもはじめは月に40脚しかつくることが出来なかった。けれども今では多い月で600脚を生産できるようにまでなった。
その理由は主に3つ。
ひとつは加工機械のレイアウト変更、ものの流れをとことん改善したこと。もうひとつは5軸同時制御加工の加工精度を改善して、人の手による磨きの工数の減少。そして生産を続けるにしたがい職人たちの習熟度もあがっていったこと。
はじめは現場も生産が大変であったけれども、だんだんとHIROSHIMAの市場評価が高いことが伝わってきたことで、職人たちに奮起をもたらした。
工場内には世界中で使われているマルニの家具の写真が並んでいる。
 オーストラリアの国際法律事務所に500脚以上納品したり、シンガポール国際空港のファーストクラスのラウンジなど…
オーストラリアの国際法律事務所に500脚以上納品したり、シンガポール国際空港のファーストクラスのラウンジなど…たしかに自分たちがつくったものが喜んで使われているところを見るのはうれしい
この写真を貼り出しているのが、海外営業担当の神田(こうだ)さん。写真を新しくすると、すぐに反応があってうれしいという。
「ちょうど海外から帰ってきたばかりで、新しい写真を社内に貼り出したんです。そしたら変わったことに気づいた職人さんがずっと読んでいましたよ。」
 神田さんは2009年にマルニ木工に入社する。それまでは商社で海外のブランドを輸入してくる仕事をしていた。
神田さんは2009年にマルニ木工に入社する。それまでは商社で海外のブランドを輸入してくる仕事をしていた。なぜマルニ木工に入社することになったのだろう。
「えらそうな言い方をすると、国内メーカーには自分が欲しいと思うデザインの家具がなかったんです。車でもエレクトロニクスでも、日本から海外に出ているのに、なぜ家具メーカーは1社もないのか。まさにデザインの問題だったわけです。」
そんなときに様々なデザイナーとコラボレーションして、デザインの問題点を乗り越えようとしているマルニ木工に興味をもった。さらにHIROSHIMAという椅子が生まれる。
「あれを見たときに、間違いなく海外でも競合できるプロダクトだと感じたんです。」
入社してすぐ、世界で最も有名な家具の見本市であるミラノサローネに行くことになった。それまでは本会場の外にギャラリーを借りて展示をしていたけれども、はじめて本会場へ出展したときだった。
「当時はまだまだ問題があって売れなかった。辺鄙なところにあるブースだったのだけれども、目の優れた人が入ってきてくれて。『これは素晴らしいプロダクトだ。お前たちなんて名前だ?』『マルニだ』『マルニ?全然聞いたことないぞ』みたいなところからスタートしました。」
話をしていると、自分たちに何が足りないのかわかってきた。帰国して役員会議で話し合い、世界で勝負をすることになった。
「ミラノサローネで信頼できると感じたディーラーを何社かまわりました。『あのとき問題だと言っていたことを、3つのうち2つクリアした。だからやってみないか?』と話したんです。」
 そのときに縁があったのが4社。実は業界の中でも信頼されている有名な会社ばかりだった。
そのときに縁があったのが4社。実は業界の中でも信頼されている有名な会社ばかりだった。そこから取引先は広がって、今では欧米を中心に26カ国にまで増えた。
「自分の目が間違っていなかったことがうれしかったです。日本にも家具メーカーがたくさんありますが、歴史上1社も海外で自社のブランドが確立できたところってないですから。今、我々に問題があるとすれば完全にマンパワーが足りていないことなんです。」
こんな話がある。とある海外のディーラーとのやりとり。
「国内営業何人いるの?」「20人ちょっと」「海外営業は?」「1人だよ」「逆じゃない(笑)なんであんな小さな島国に20人いて、全世界を見るのが1人なの??」
今は欧米をケアすることがやっとのところなのに、アジアでのニーズが急速に伸びている。上海では最も有名なディーラーとパートナーになったし、韓国ではソウルの一等地に東京よりも大きなショールームができた。
 「普段の貿易実務はアシスタントが担当しますけど、基本的に事業に関わるあらゆる事を、なんでも自分でやるんですね。ロジスティックのスキームも、PRも、すべて自分で考えないといけない。」
「普段の貿易実務はアシスタントが担当しますけど、基本的に事業に関わるあらゆる事を、なんでも自分でやるんですね。ロジスティックのスキームも、PRも、すべて自分で考えないといけない。」「だからルーティンをこなすだけの人には難しい。論理的に考えながら、枠にとらわれずに力を発揮してほしい。私が海外にいることも多いので、ときには自分でジャッジしなければいけないことだってあります。あとは英語や中国語などもできてほしいです。」
気がついたらあっという間に取材が終わってしまった。
日本にはいいものがたくさんある。でもそれをつくる技術も、世界中に伝えることも、そしてデザインも、人がいなければ成り立たない。
広島から世界へ、家具を広めていく人を募集しています。
(2014/09/30 ナカムラケンタ)

