※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
演劇やダンスなど、はなやかな舞台に憧れたことのある人は多いと思います。けれど、その劇場をだれがプロデュ―スしているのか、考えたことはありますか? 株式会社シアターワークショップは、劇場をつくるところから管理運営や改修まで、劇場のすべてをプロデュースしていく会社です。
株式会社シアターワークショップは、劇場をつくるところから管理運営や改修まで、劇場のすべてをプロデュースしていく会社です。今回は、劇場のハード(施設計画)やソフト(管理運営計画)を担当するコンサルタントと、実際に管理運営を行っている施設のひとつであるヒカリエホールで働くスタッフを募集しています。
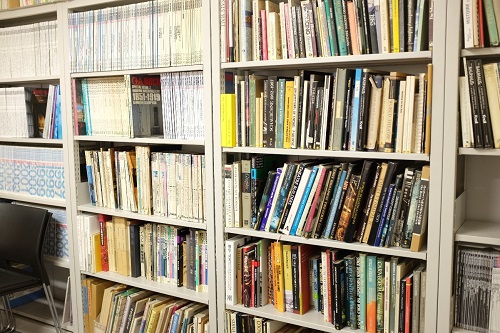 会社があるのは、渋谷区の桜丘町。オフィスの応接室には、ホールや舞台に関する洋書が、たくさん並んでいます。オークションで手に入れたという、俳優のサイン入りの机なども。
会社があるのは、渋谷区の桜丘町。オフィスの応接室には、ホールや舞台に関する洋書が、たくさん並んでいます。オークションで手に入れたという、俳優のサイン入りの机なども。「日本で一番、シアターに関する資料が揃っていると思いますよ」
そう教えてくれたのは、代表取締役の伊東(いとう)さん。2008年には、職能としての劇場コンサルタントを確立したことが評価されて、日本建築学会賞を受賞されたそうです。
「もともと芝居が好きで、劇場をつくりたかったんですね。大学では建築学科を出て、大学院では小劇場や移動型のテント劇場の研究をやって論文を書いていました。ドクターまで大学にいましたが、文化庁が新国立劇場をつくることになり、手伝いに来いと言われて、準備室で仕事をさせてもらったのです。」
 「それがきっかけで、シアターワークショップを設立したんです。それまで、劇場コンサルティングという仕事は日本にはありませんでした。」
「それがきっかけで、シアターワークショップを設立したんです。それまで、劇場コンサルティングという仕事は日本にはありませんでした。」会社をつくったら、全国各地のホールから、手伝ってくれないかと声がかかるようになったそうだ。
「ところが、せっかくホールをつくっても、実際はうまく使われないことも多いんです。箱だけじゃなくてソフトの部分もあわせてやろうということで、建設やハードのコンサルティングに加えて、管理運営などソフトのお手伝いもやっていくことになりました。」
たとえば、手がけた施設のひとつが、長野県にある茅野市民館。
市民35名と設計者が協働で、ワークショップや会議を100回以上実施して、つくったそうだ。
 「管理計画をただ作成するだけではなく、市民と一緒に、施設を運営する組織をつくっていく。そのためには全国から専門家を集めたり、地域の人を育てていったりする必要がありました。この市民館は建築としても評価されていますが、最も評価されているのは、これをつくっていくプロセスなんです。」
「管理計画をただ作成するだけではなく、市民と一緒に、施設を運営する組織をつくっていく。そのためには全国から専門家を集めたり、地域の人を育てていったりする必要がありました。この市民館は建築としても評価されていますが、最も評価されているのは、これをつくっていくプロセスなんです。」「生活に密着して、人が気軽に集まる場をつくっていく必要があるんですよね。アートの展示をしてもいいじゃないかとか、クリスマスにイルミネーションをやろうとか、日常的にひとが楽しんでもらえる場にしないと。ただの劇場づくりじゃすまないんです。ときには、市長や商工会議所を説得したりね。」
ほかにも、北海道から沖縄まで日本全国で150くらいのホールを手掛けてきたそうだ。海外から仕事がくることもあれば、むかし手掛けたホールの改修を頼まれることもある。
 現在進行している物件は70ほど。他にも営業中の物件があったり、自治体のコンペへ提案をしたりと、やることはたくさんある。スタッフも、終電まで仕事をする日もあるそうだ。
現在進行している物件は70ほど。他にも営業中の物件があったり、自治体のコンペへ提案をしたりと、やることはたくさんある。スタッフも、終電まで仕事をする日もあるそうだ。「自治体のお役人さんや設計会社さん、照明担当や舞台装置をつくる業者さんなど、全部を調整しながらやらなければいけないから、すごく大変なんですよ。お金も計算しながらやらなければいけない。すごく神経を使うし大変なんだけれど、面白い仕事です。」
今回募集するポジションのひとつは、そうした劇場のプロデュースを担うコンサルタント職だ。ハードを担当する施設計画担当と、ソフトを担当する管理運営計画担当の、両方を募集している。
「ただ建築だけを学んできましたというのではダメなんです。うちのスタッフも、多様な経験をしてきた人が多いですよ。」
新卒で入社し、主に施設計画を担当してきたという林(はやし)さんにお話を聞いてみた。
 「小さい頃からピアノをやっていたこともあり、大学受験では音楽の道を目指していたのですが、結局は建築学科に進むことになりました。音楽と建築の融合って劇場だよなと思って、大学では劇場の研究をやっていたんです。違う大学だったんですけど、伊東さんの授業にもこっそりでていましたね。」
「小さい頃からピアノをやっていたこともあり、大学受験では音楽の道を目指していたのですが、結局は建築学科に進むことになりました。音楽と建築の融合って劇場だよなと思って、大学では劇場の研究をやっていたんです。違う大学だったんですけど、伊東さんの授業にもこっそりでていましたね。」その後、研究論文を書くときに伊東さんと再会したこともあり、大学院修了後にシアターワークショップの扉をたたいたそうだ。
「入社してしばらくは他のスタッフの下について仕事していましたが、3年目くらいではじめてメインで物件を担当しました。千鳥ヶ淵にあるインド大使館のホールなんですけど、最初は平土間のホールだったのが、客席が欲しいし映画も見たいしと、最後にはまったく違うものになって。思い出深いですね」
大変なことも、ありますか?
「はじめはやっぱり慣れない部分がありましたよね。自分がやってきたことが活かされるまでには、結構長い時間がかかりました。あと、少ない人数の会社なのですが、物件数がすごくいっぱいあるので、同時進行で複数の物件をやらなければいけない。それをうまく回していくのは結構大変なところではありますね。」
それでも「やめられない」と林さんは語る。
「日本を代表するような建築家・設計会社の技術者たちや、建築だけをやっていたら接点のない人たちと仕事ができるので、面白いですよ。そうした人たちとアイデアを出して楽しみながら、ひとつの空間をつくっていけるのは、私たちの仕事の醍醐味だなと思います。やっぱり、劇場をつくるというのはすごく夢のある仕事だと思うので。」

難しそうな仕事でもあるけれど、みんなどうやって仕事を覚えていくのだろう。
林さんの話を横で聞いていた伊東さんがこう答えてくれた。
「1年目はただの見習い。2年目で少しずつ仕事ができるようになって、3年目からが本当の意味でのチームかなと思います。ハードを担当する人は建築の基礎がわかっていてほしいけれど、最初は劇場についてわからないことも多いでしょうし、いろいろな案件に携わって、誰かの下で教えてもらって蓄積していく部分もあると思います」
伊東さんにとって、この会社は“ファミリー”なのだそうだ。
「みんなが同じ方向を見て、同じように考えながらやっていく、大家族のような組織にしたいんです。仕事は、物件ごとにチームをつくって動くのだけど、その中でアイデアも出していくし、技術的な解決も考えていく。これをやれと上から命令することは、ほとんどない。みんなが、根底でちゃんと共有している部分があるということが大事です。」
今回募集するもう1つのポジションが、シアターワークショップが管理運営を行っているヒカリエホールやカンファレンスではたらくスタッフだ。
4年前に転職してきたという、ヒカリエホールの統括マネージャーの丸山(まるやま)さんにも、お話を聞いてみた。
 「高校時代に演劇部に入っていて、大学でも演劇をやろうと思っていたんです。でも、役者は才能の世界なので、自分はそこでは勝てないなと。裏方でなにかできないか考えていたときに、伊東さんに出会ったんです。卒論指導をしてくれたのも伊東さんです。」
「高校時代に演劇部に入っていて、大学でも演劇をやろうと思っていたんです。でも、役者は才能の世界なので、自分はそこでは勝てないなと。裏方でなにかできないか考えていたときに、伊東さんに出会ったんです。卒論指導をしてくれたのも伊東さんです。」大学時代にポルノカルチャーにはまったこともあり、卒論はストリップ劇場の研究。卒業後に最初に就職したのは、アダルトビデオの製作会社だったそうだ。
「宣伝部でテレビ番組やラジオ番組を立ち上げたりつくったりと、仕事はおもしろかったんですが、『もっと面白い仕事があるよ』と伊東さんに誘われまして。都市開発のプロジェクトをやろうとメーカーへ転職したんです。ただ、震災があってその開発の話が立ち消えてしまって、どうしようと思っていたときに、ヒカリエホールの立ち上げの話が来て。」
 これまでに、109のファッションショーやTEDxTOKYOなどの若者向けのものから、車や新製品の発表会など、さまざまなイベントが開催されてきたそうだ。ホールだけでなく、打ち合わせなどに使うための貸し会議室も用意されている。
これまでに、109のファッションショーやTEDxTOKYOなどの若者向けのものから、車や新製品の発表会など、さまざまなイベントが開催されてきたそうだ。ホールだけでなく、打ち合わせなどに使うための貸し会議室も用意されている。「都内の主要駅に直結している1000㎡の平土間型のイベントホールって、なかなかないんです。日本一のイベントホールだと自負して、はたらいています。」
そして、お客さまに場所を貸すだけでなく、時季によっては自分たちで興行を企画する場合もある。
「GWや夏休みなど、長期休みはビジネスで利用されるお客さまが減るので、自主企画をやります。たとえば、ネコの写真展を開催したときは9万人以上の来場者がいらっしゃってうれしかったです。興行は博打なので、大ゴケすることもあると思いますけどね。」
 たまたまイベントがない日だったので、誰もいないホールを案内してもらった。
たまたまイベントがない日だったので、誰もいないホールを案内してもらった。ここの内覧・予約・事前打ち合わせ・本番立会い・ケータリング等の手配など、イベントの企画時から撤収までをお客さまと伴走していくのが、仕事だそうだ。
「ホールの仕事は、毎日が勝負。毎日違うお客さまが来ますが、同じ価値を提供しなければいけません。たとえば、10年かけて開発した商品をヒカリエホールで発表するようなお客さまもいるかもしれない。その想いを最大化するお手伝いをしたい一方で、翌日には別のお客さまにも、ちゃんとした品質のサービスを提供しなくてはいけない。施設の保全や安全管理面を考えて、ときには無理を言ってくるお客さまに対して冷静に注意し、説得しなきゃいけない場面もあります。」
ヒカリエホールの事務所は、本社から10分ほど歩いた渋谷ヒカリエ内にある。ここで働くスタッフには、どういうひとが向いているんだろう。
「仕事には雑用も多いですよ。僕も、翌日のイベントのために、お客さまが汚した床を拭いたりするときがあります。雑用を苦と思わずに楽しめる人、お祭りを支えていける縁の下の力持ちタイプの人がいいですね。」
現在、二子玉川で新しいホールがオープンする予定だそうで、そちらの立ち上げや管理運営に参加する可能性もあるそうだ。
 本当の意味でのプロデューサーって、企画だけではなくて、時間・お金・人・ものなど、すべてのことを調整するものなんだろうなと思う。
本当の意味でのプロデューサーって、企画だけではなくて、時間・お金・人・ものなど、すべてのことを調整するものなんだろうなと思う。はなやかというよりは、地味と呼べる業務の方が多いかもしれない。そうしたプロセスの中でも、楽しみつづけられる人におすすめです。
(2015/3/21 田村真菜)

