※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
あらゆる商品には、それが生まれる背景を語れるストーリーがあります。 藤巻百貨店は2012年に故・藤巻幸大によるプロデュースではじまったインターネット通販サイト。
藤巻百貨店は2012年に故・藤巻幸大によるプロデュースではじまったインターネット通販サイト。ただ、取り扱う商品に注目してみると、その特徴に気づきます。
どれも日本を意識された品揃えで、一つ一つの商品の背景にストーリーを感じられるのです。
そんな藤巻百貨店がこの春、銀座に実店舗を構えます。
今回はそんな「藤巻百貨店」を運営する株式会社caramoでスタッフを募集します。
募集は大きくわけて店舗スタッフ、運営ディレクター、編集者の3つ。
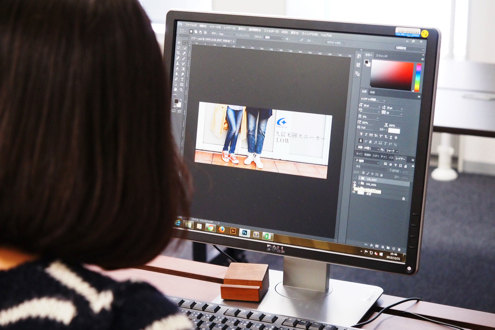 それぞれ役割は異なりますが、基本となる軸はどの働きかたも同じようです。
それぞれ役割は異なりますが、基本となる軸はどの働きかたも同じようです。「お客さまというファンに最高のサービスを提供したい気持ちと、世の中にいる職人のものづくりを世界中に発信していきたいという想いが重要ですね。そこに面白みがあると思うんです」
そう話すのは代表の中村さん。
商品が生まれる物語を提供する。そうすることで、お客さまに商品の見た目や機能以上のものが伝わり、職人の思いを届けることができる。
そんな物語を発信する百貨店が藤巻百貨店です。
最寄りの渋谷駅からは歩いて2分ほど。トランスコスモス社の一角にオフィスはあります。
 はじめに代表の中村さんに話をうかがいます。
はじめに代表の中村さんに話をうかがいます。
元々、モバイルを駆使したサービスに関わっていた中村さん。
モバイルコマースは売上高を大きくするために、価格の値引きを中心とした販売手法に力を注いでいた。
 しかし、値引きによる魅力ではなく、商品そのものがもつ魅力を活かした定価販売でインターネット通販を実現できないかと考えるように。
しかし、値引きによる魅力ではなく、商品そのものがもつ魅力を活かした定価販売でインターネット通販を実現できないかと考えるように。「そうしたら、ちょうど僕らのグループ会社の中に藤巻幸大さんがいらっしゃって。一緒に何かできませんかという話のなかで、こんな話が出てきたんです」
日本には優れた職人さんがたくさんいて、技術がある。
素晴らしい商品が数多く存在するのに、なかなか日の目を見る機会が少ない。
そういった商品を、インターネットを駆使してもっと表にだしていけるようにできないか。
そうして生まれたのが藤巻百貨店でした。
「サイトの特徴として、コンテンツ仕立てで、つくり手に取材をおこなっています。写真もオリジナルのものを撮ります」
なぜこういったモノが出来上がったのかを考えると、そこにある素晴らしい物語を大切にしようと思うように。
「そして、商品選定のコンセプトを『日本を感じるもの』『ストーリーがあるもの』『元気・豊かな気持ちになれるもの』の3つに設定しました」
日本を感じるとは?
「日本の産地や日本の職人、海外で活躍する日本人がつくる商品等々、様々な角度から日本の素晴らしさを伝えられたらと考えています」
「とはいえ、最初から多くの商品があったわけではないんですよ。藤巻百貨店オープン時は、1アイテムからのスタートでした」と言って、その商品を見せてくれた。
「二宮五郎商店さんの『風琴マチ』という技術を用いた財布です。通常マチって内側に折っているんですが、外側に折る技術が使われている長財布です。当時財布は長財布のブームもあったので、当時の流行を読み取り、このあっと驚くような風琴マチの技術をピックアップしようと考えました」
 それから1ヶ月以内には10商品に増え、徐々に拡大していった。
それから1ヶ月以内には10商品に増え、徐々に拡大していった。そしてこの春、銀座に出来る新施設「東急プラザ銀座」内に、藤巻百貨店のお店がオープンする。
リアル店舗として初めての旗艦店をかまえます。
「今のサイトは、まるで商品に触れているかのようなテキストや写真にこだわり、一定の成果をあげているとは思うのですが、やっぱり実際に確認したいというお客様の声が高まり、リアルに手に取れる場所が欲しいと思ったんです」
「藤巻百貨店の商品はどこにでもあるわけではないですから、お客様の拡大と共にそういったサービスも必要になってきたというわけです」
 具体的にはどういった働き方になるんでしょうか。
具体的にはどういった働き方になるんでしょうか。「いわゆる販売員なんですが、インターネットで展開される藤巻百貨店の世界観をお店で表現していただくことが特徴だと考えています」
たとえば、お客様との間で商品のストーリーを中心とした会話がおこなわれ、その商品を手に入れる。
実務的には商品理解をはじめ、お支払いからお店に関わるレイアウト、体験型ワークショップなどのリアルイベントの実施なども。
店舗運営全般とクリエイティブな企画業務など、仕事の内容は多義にわたります。
「また、店舗発信のFaceBook等の運営もしてもらおうかと考えています。店舗のリアルな動向を反映するには、お店にいるスタッフだからこそ出来るスピード性と温度感があると思います」
ウェブとの連動性を意識する一方で、物流対応やCS対応もあるそうだ。
「おそらく、どの職種も垣根を越えた働き方になると思います。たとえばバイヤーの人でも時には販売応援をするかもしれないし、店舗スタッフは自らの店舗でおこなうイベントの企画やプロモーションを考えたりもするかもしれません」
「それこそお客さまが持ち帰るのが大変だったり、その場に在庫がなかったりしても、店舗で商品を確認し、その場でネット購入といった方法でお買い物を楽しんで頂くのも良いと思っています」
新しい買い物体験を提案する。そういったなかで、実店舗を構えることも、ECサイトも大切にしていることは変わらないと話します。
「僕らの根幹にあるのは、お客様さまとつくり手をどれだけ思えるかということです。だから、社名の由来も僕らのポジションを意味しているんです」
「職人さんやお客さまのどちらかに偏るのではなくて、お客さま『からも』、職人さん『からも』愛されるような存在を目指して、『caramo(カラモ)』という名にしました」
今後新しいチャンネルの拡大を目指して、ITをうまく活用した新しい買い物体験が生まれるのかもしれない。
そのひとつの方法として、今回の店舗があるのだろう。
「お客さまや取引先が満足してもらえるようなことを実現する。そのためには新しい価値を常に考え、提供し続けることが僕らの役割で。それをやりきろうと思っています」
「人はみんな、それぞれに目指したい姿、活躍する姿を持っていると思うんです。たとえば、自分が持っているスキルを活かしたい。自己実現をしたい。それが私たちと関わる中でできると感じれる方ならこの仕事に向いていると思います」
続いて話を伺ったのは大里さん。
 「実は決まった肩書きを持っていないんです。サイト全体の動きから、スケジュール管理、どんな商品をフェイスブックにあげるのかなどのソーシャルコミュニケーションのクリエイティブ制作もおこないます」
「実は決まった肩書きを持っていないんです。サイト全体の動きから、スケジュール管理、どんな商品をフェイスブックにあげるのかなどのソーシャルコミュニケーションのクリエイティブ制作もおこないます」おそらく今回募集する運営ディレクターは、大里さんのようなポジションになるとのこと。
「ウェブサービスの店長的な役割というか、サービスの起点となる藤巻百貨店のコンテンツづくりや、お客さまを集めるためのPRづくり、それに販促の進行管理もおこなうと思います。また、サイトの進行管理から簡単なコードやサービス自体の修正までおこないます」
「ウェブサイトだけでなく、ときにはお客様の顔をイメージするために店舗でも働くので、全体を横断するような仕事になると思います」
実店舗とウェブ、両方を見る働き方は、コツが必要かもしれない。
「藤巻百貨店も見た目の価値観・世界観、ものづくりを大事にしているサイトですが、裏ではものすごく数値を大切にしてロジックに基づき動いています」
「どんなことでも、そこに理由が必要です。お客さまの反応がいいほうが優先される。求められていることに対して役割の垣根を越えてすぐに動ける柔軟性が求められますね」
続いて話を伺ったのは市山さん。現在はバイヤーを務めている。立ち上げの年から関わり、現在3年目。
 「それまではIT業に縁のない世界で働いていましたし、バイイングも経験がありませんでした」
「それまではIT業に縁のない世界で働いていましたし、バイイングも経験がありませんでした」
うまくいかないことも多かったのでは?
「メーカーさんによってはインターネット通販のような実体がない場所でモノを売るのに抵抗がある取引先様もいらっしゃいます。“目利き ”というよりも、交渉能力が求められていたように思います」
「私たちの想いに賛同していただき、大切な商品をお預かりさせていただく。その積み重ねが今日の姿だと思っています」

最後に、ふたたび中村さん。
「藤巻百貨店は常に新たな価値・満足をお客様に提供していきたいと考えています」
既存の枠にはまらないことを実現する上で、何よりも気にしている事があるという。
「たとえば、一般的に言われる職種の業務範囲に限定すると固定概念にとらわれ、新しいアイデアが出づらいと思っています。極端なことをいうと、バイヤー経験がない方のほうが、実は新しいバイヤーの在り方を創造できるのではないか。逆にバイヤー経験者が店頭で接客すると、商品知識がお客様を虜にするのかもしれません」
「ゼロベースでアプローチすることで、新しい価値をお客様に提供できるのではないかと考えています」
商品にあるストーリーをお客さまに届けられるような熱い姿勢と、既存概念にとらわれすぎない本質を見る目が、今回募集するどの職種にも必要なのかもしれない。
「経験があるよりも、その人のモチベーションや仕事への取り組み方を大事にします。会社に就職するだけで満足な人ではなく、その会社で新しい価値を創造していくことに喜びを感じる人たちにぜひ来てほしいですね」
 職人さんが手がける商品と、その物に宿る「ことば」を提供する新しい百貨店のかたちが、ここにはありました。
職人さんが手がける商品と、その物に宿る「ことば」を提供する新しい百貨店のかたちが、ここにはありました。(2016/3/4 浦川彰太)

