※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
ヌプカとは、アイヌ語で「原野」という意味をもつ。地平線が見えるほどに広い十勝平野には、どんな可能性が眠っているんだろう。
 今年の早春、北海道十勝地方の中心である帯広市の街中に「HOTEL&CAFE NUPKA (ホテル&カフェ ヌプカ)」というホテルがオープンしました。
今年の早春、北海道十勝地方の中心である帯広市の街中に「HOTEL&CAFE NUPKA (ホテル&カフェ ヌプカ)」というホテルがオープンしました。「ホテルの名前に“原野”とつけたのは、ありのままがうつくしいことをみんなに思い返してほしいと思ったから」
そう話すのは、ホテルヌプカの支配人となる坂口さん。
 自然、天候、食、馬文化… さまざまなものに恵まれたゆたかな十勝。
自然、天候、食、馬文化… さまざまなものに恵まれたゆたかな十勝。とくに、カロリーベースの食糧自給率は1200%を超え、食の分野では圧倒的な存在感をもつ。NUPKAは、「クラフトフード」をキーワードに十勝の食の魅力を表現することで、観光促進と街自体の活性をしようとしています。
地域の外の人に対しては、旅をする拠点として。地域に住む人に対しては、ふらりと訪れる街のリビングとして。
ホテルを舞台に、両者をつなぎ、なにかがおこっていく。
今回は、そんなNUPKAで触媒のようにはたらくホテルスタッフを募集します。
NUPKAの立ち上げには、代表の柏尾さんをはじめとし、さまざまな人が関わっている。
企画には日本仕事百貨でおなじみのBAUM宇田川さん、プロジェクト構想は都市再生や不動産開発をしている吹田さん、そして現地で働く支配人の坂口さん。
 NUPKAはどんなホテルなのだろう。
NUPKAはどんなホテルなのだろう。お話しを伺うため、東京の三田にある吹田さんの事務所へお邪魔しました。お会いしたのは、柏尾さん、吹田さん、坂口さんの3人。
はじまりは、柏尾さんのこんな思いからでした。
「40歳を超えたころ、地元である十勝と帯広に対して何か貢献したいという思いがでてきました」
 柏尾さんは帯広で生まれ育ち、今は東京で弁護士をしている方。
柏尾さんは帯広で生まれ育ち、今は東京で弁護士をしている方。「十勝に活力を、と思ったとき地域経済の範囲だけで変えることは難しい。そこで、成長するアジア圏から観光へ来てもらおうと、十勝の魅力を伝える映画をつくったのが始まりなんです」
それが、「マイ・リトル・ガイドブック」。台湾旅行代理店の新人女性社員が、未開発の観光地「十勝」へ送り出され、十勝の景色、人、食べ物に出会って成長していくというストーリーだ。
 クラウドファンディングで資金を集め、東京在住で十勝生まれの映像作家・逢坂芳郎さんが監督。YOUTUBEで配信すると、1週間で1万回再生されたり、国際短編映画祭での受賞作品に選ばれるなど、反響は大きかった。
クラウドファンディングで資金を集め、東京在住で十勝生まれの映像作家・逢坂芳郎さんが監督。YOUTUBEで配信すると、1週間で1万回再生されたり、国際短編映画祭での受賞作品に選ばれるなど、反響は大きかった。「次は、観光客をどう迎えるか、ということになりました。十勝の入り口である帯広市の中心街は今、昼間はとても閑散としています。生まれ育った街なので、なにか新しい地域のあり方を考えたいという思いも強くありました」
そんなとき、吹田さんの書かれた本「グリーンネイバーフッド」と出会い、ポートランドにあるエースホテルの事例を知る。
それはホテルでありながら、街のリビングのようだった。
昼はノマドワーカーが集う場として、夜はイベントスペースとして、旅人と住民が混ざりあい街中であたらしいカルチャーを生んでいるというもの。
「帯広でもホテルを中心として新しい地域のあり方を提示できるんじゃないか」
柏尾さんは、街中の一等地にありながら営業を終了していた「ホテルみのや」の建物と土地を譲ってもらい、吹田さんに構想の協力をお願いすることに。
吹田さんにもお話を伺う。
「生まれ故郷になにか貢献したいという彼の強い思いがあったことと、僕自身、街中の再生が生業ですからね」
 一緒に考えたコンセプトは“ホテル・アーバニズム”。ホテルが街をいじって行くカタリスト(触媒)になる、というもの。
一緒に考えたコンセプトは“ホテル・アーバニズム”。ホテルが街をいじって行くカタリスト(触媒)になる、というもの。そして、ホテルが牽引する帯広のまちづくりの切り口をガストロシティ(=美食都市)としました。
「十勝は農業王国でよい食材がたくさんあります。でも、これまではBtoBが産業の中心。これからは食材を生かして料理を提供し、日本で一番美味しいレストランが数多く集まっている街になれば、世界中から人が訪れると思いました」
具体的な軸となるのは、“クラフトフード運動”。
「たとえば、地産地消のブームはサンフランシスコの街から始まり、全世界へ広まっていきました。同じように、手塩にかけて食材をつくり、手間をかけて調理して食べるクラフトフード運動を帯広から世界に発信する。NUPKAは、その本拠地になると思っています」
外の人が集まる一方で、街の人にとってNUPKAはどういう場所になるのだろう。
「情報と人をつなぐ触媒になります」
ホテルが触媒になる?
「うん。NUPKAは街のリビングルームとして、地元の住人がふらりと訪れる。一方で、NUPKAには外から文化の異なる情報も入ってくる。その情報が現地の人と混ざったとき、あたらしい気付きやアイディアが生まれます。自然と、ホテルが情報や交流を得る場と機会の働きをするんです」
聞いていた坂口さんも話に参加してくれた。
「どの街も、クリエイター層が集まり始めるとどんどん面白い人が集まってきます。すると、『住んでみようかな』と思う人が出て、街は少しずつ変わっていく。わたしはここで、面白い人を集める係になろうと思っているんです」
 坂口さんも帯広出身。とても気さくな方で、大学在学中に飲食店の経営をはじめ、今では都心部を中心に9軒のお店の経営に携わっています。
坂口さんも帯広出身。とても気さくな方で、大学在学中に飲食店の経営をはじめ、今では都心部を中心に9軒のお店の経営に携わっています。「人と接するのがすごく好きなんです。お店に立っている時間も長かったせいか顔見知りが増えて。最寄り駅からお店までくるまでにお客さんと会ってしまって、すごく時間がかかっちゃうんです(笑)」
東京で働く十勝出身者の集まりで柏尾さんと知り合い、NUPKAのプロジェクトに勧誘されました。
すでに、クラフトフード運動の動きがあるそうです。
「移住されて農業を営む人たちや、農家の2代目など若い子たちの中には、良い食材を小さくつくり始めている人たちもいるんです」
「農薬だったり、遺伝子組み換え作物の問題もありますよね。いいものをちゃんとした値段で売っていく、という考え方が定着し始めていると感じています」
翌日、北海道・十勝帯広の街を訪れました。羽田空港から十勝帯広空港までは、2時間ほど。思ったよりアクセスがよくて驚いた。
空港で迎えてくれたのは、坂口さんと、これから一緒に働くことになるみどりさん。みどりさんは、10年間帯広の六花亭につとめた後、2年ほど海外を転々としていた。
「外国から帰ってきて、十勝の環境がすごくいいなとあらためて感じました。十勝のよさを伝えたかったし、自分も旅をしてきたので、ここで旅人を受け入れられたら、と思って」
 「そんなとき坂口さんに会い、ここでやろうとしていることを聞いて、面白そうだなと思ったんです」
「そんなとき坂口さんに会い、ここでやろうとしていることを聞いて、面白そうだなと思ったんです」お話を聞いているうちに、車はホテルヌプカのある西二条通りに入った。
「ここはむかし、アパレルショップの連なる賑やかな通りでした。今はかわりに飲食店が入るようになって夜は賑やかですが、昼間は閑散としてしまってるんです」と坂口さん。
車社会で車移動が当たり前の十勝では、日中でも街中を歩く人の影はまばら。
車を降り、NUPKAを見させてもらった。
 一階はホテルのロビーであり、カフェやバーにもなる。入り口には薪が置かれ、薪ストーブの暖かさを想像させる。奥にあるカウンターでは、十勝産大麦100パーセントで作られるクラフトビールも出す予定だそう。
一階はホテルのロビーであり、カフェやバーにもなる。入り口には薪が置かれ、薪ストーブの暖かさを想像させる。奥にあるカウンターでは、十勝産大麦100パーセントで作られるクラフトビールも出す予定だそう。2階はドミトリー、3階から5階が個室。全部で26部屋47ベットというホテルとしては小さな規模。
「スタッフには、チェックイン、チェックアウトなどの基本的なホテルの仕事のほかに、『農と暮らしの委員会』や『農女子の会』など十勝で頑張っている人たちや、滞在するお客さんとも情報をやりとりしてもらえたらと思っています」
今回募集するスタッフは、レシピ開発と衛生管理をする人、カフェスタッフ、クラフトビールの管理責任者、ホテルスタッフ兼農家のヘルパーをする人の4つ。とくに、食の街として発信していくため食材にこだわりがあったり、調理も美しさに心配りができるような人が来てくれると嬉しいそうです。
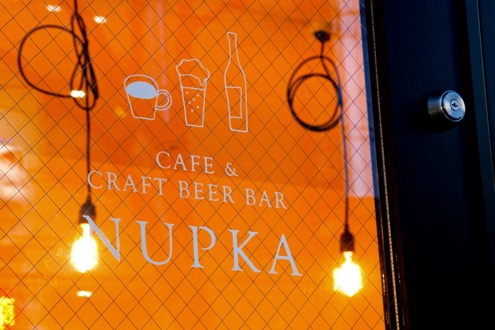 それぞれに役割はあるけれど、共通しているのはここで触媒のように働けること。
それぞれに役割はあるけれど、共通しているのはここで触媒のように働けること。「もてなすことと、人に伝えること。十勝を楽しみながら情報をあつめて提供したり、人同士をつないでいける人だといいですね」
十勝にはどんな人がいるんだろう。
坂口さんは、畑ガイドツアーをしている「いただきますカンパニー」代表の井田さんを紹介してくれました。
井田さんは、夏には畑で収穫・調理・食べるという畑ツアーを、冬は学校で食育の授業をしています。
 畑のツアーは東京や海外からの個人旅行者が多く、年々参加者が増えているそうです。
畑のツアーは東京や海外からの個人旅行者が多く、年々参加者が増えているそうです。なぜ畑のツアーをはじめたんでしょう。
「農業がどういうものであるかを知って欲しいと思っているんです」
「作物は生きものですから、経済的な計算でうまくいかないことってたくさんあるし、昨日まで順調に育っていた作物が台風でぜんぶ倒れてしまうこともあります。現場をみてもらうことによって、本来食べものがお金を出せば食べられるものではないということをわかってもらいたいんです」
すると、坂口さん。
「企業は四半期ごとに数字を出し、利益を追求しないといけません。でも、いつまでも残っていてほしいものや将来的に利益を生んでいくものって、そんなに短いスパンでは対応できないですよね」
美食の街として有名になったら、こういったメッセージも大きく伝えていけるかもしれない。
もう一人。坂口さんが「ものづくりをしている人はこうあってほしい!」と尊敬している、十河(そごう)さんにお会いしました。
十河さんはひとりでビールをつくっている方。メキシカンレストランの裏にある小さな醸造所に入ると、少し焦げたような甘い匂いがする。
「ここの設備はとてもシンプルで、すべて機械化されてない人力に頼る装置でつくっています」
 十河さんも、帯広生まれ帯広育ち。あるとき、長年勤めた映画会社をやめフランスへ旅に出ます。そこで出会ったのがクラフトビールでした。
十河さんも、帯広生まれ帯広育ち。あるとき、長年勤めた映画会社をやめフランスへ旅に出ます。そこで出会ったのがクラフトビールでした。「村ごとに小さな醸造所があるんです。そこで飲んだビールがとっても美味しくて。帯広に戻ってきてからビールの醸造所に勤めました」
勤めていたビール醸造所が廃業してしまった後は、出向先だったこの小さな醸造所でひとり、ビールをつくっています。
「酵母って生き物なんですよね」
「子どもが家の中にいると子どもの発するエネルギーでこちらまで元気になるように、酵母からもエネルギーをもらっているなと感じます。大麦から酵母へ、生き物が生き物をつくり変えている。ぼくはただその様子を見守っているだけなんです」
食べものを通して、生き物にふれる。美味しいだけじゃない、十勝のいのちのうつくしさを垣間見た気がしました。
原野の可能性は、まだまだたくさんありそうです。
発見されていない価値をみつけ、表現し、世界につないでいく。
 NUPKAを舞台に、なにかを生み出す媒介になってみませんか。
NUPKAを舞台に、なにかを生み出す媒介になってみませんか。(2016/3/7 倉島友香)

