※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
「大きなビジョンとして、生産者の方を応援したい、地方再生をしたいっていう思いがあります。そういった思いがなければ、どこで働いても変わらないですからね」「さらに、人材不足や労働体制など、飲食業が直面している問題は山ほどあります。そんなネガティブを、一緒にポジティブに変えていける仲間を探しています」
食材選びから食事をいただく空間まで、お店によってこだわりはそれぞれあると思います。
けれども、こだわりが伝えきれていなかったり、ネガティブな面が強く見えてしまったりと、厳しい現実があるのも事実です。
今回取材した焚火家も、話を聞いてみると強い熱意とこだわりを感じました。
株式会社アールハウスが運営する炭火焼「焚火家」は、800gのお肉の塊『肉のヒマラヤ』で話題となった炭火焼屋です。
 今回はここで働く運営スタッフを募集します。
今回はここで働く運営スタッフを募集します。さらに将来、独立を考えている人や自分のお店を持ちたい人にとっては、またとない機会だと思います。
渋谷駅から歩いて2分。明治通りの方面に歩いていくと、焼肉店「焚火家」が見えてきます。
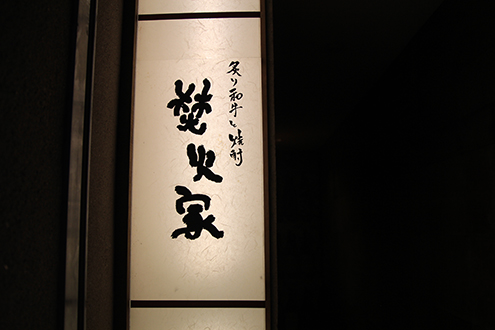 階段を降りていくと、店内は隠れ家のような雰囲気が広がっていました。
階段を降りていくと、店内は隠れ家のような雰囲気が広がっていました。「お店の規模は決して大きくないですが、本当に信用できる人とライフワークとしてやっていけるような環境にしていきたいんです」
そう話すのは運営受託としてお店と関わっている蔵石さん。場の空気を和ませつつも、言葉からは熱い思いを感じます。
 ライフワークとして働けるような環境を増やしたいのには、理由があるといいます。
ライフワークとして働けるような環境を増やしたいのには、理由があるといいます。「バイト経験があるから働こうとか、深く考えないで飲食業界にいると、なんのために働いているか分からなくなる人が多い気がするんです」
「それで、ある程度の経験が身についてきたら独立しようと考えるんですが、『なぜ独立したいか?』という話しになると、ライフワークではなく『自分が楽になるため』だとか『お金儲けのため』になってしまう方が意外と多いのだなと気づきました」
「それを否定するわけではないのですが、そんな気持ちで働いている意味あるのかなって思ったんですよ」
今回の募集も、ゆくゆくは焚火家のライセンスを使って独立を目指して欲しいと話します。
 しかし、どうしてそんなに働き方や飲食業にこだわりがあるんですか?
しかし、どうしてそんなに働き方や飲食業にこだわりがあるんですか?「もともとは飲食業のコンサルタントをしていました。経営体制を数値分析することで売上をあげたり、就業規則や労働時間などのコンプライアンス面を管理するといった内容の仕事でした」
「ただ、いろいろ分析して勉強しているうちに、飲食店以外の仕事にも興味を持ちはじめたんです」
そこで、飲食業から離れてファンド会社のサポートをはじめたという蔵石さん。投資をしてもらっていく中で、徐々に大きな利益を生み出していったそうだ。
「でも、ファンドで投資してもらっても素直に喜こべなかったんですよ。ファンドに限らず、出来上がったものを販売するのは面白くないなと思ったんです」
「僕自身の好みの問題だと思いますが、自分がつくらないものを売ることがこんなにも面白くないとは思いませんでした」
楽だけど楽しくない働き方に違和感を覚える中、2011年3月を迎えます。
「震災後、ファンドで関わっていた人と連絡がとれなくなったりして。考えてみれば、そのとき一緒に仕事していた人とはお金に関する話しかしてこなかったなと。あらためて、『働く』ということについて考え直しました」
自分の見渡せる距離感でやりたいことをやろうと思ったとき、素直に出てきた選択肢は飲食業でした。
 一度離れた世界に再び戻ってきた蔵石さん。いざお店を運営してみると、現実はそんなに甘くはなかったそう。
一度離れた世界に再び戻ってきた蔵石さん。いざお店を運営してみると、現実はそんなに甘くはなかったそう。「お店を軌道にのせるまでは、2年ほどかかりました。自分がコンサルティングで関わっていた時代とは移り変わっていて、飲食店でも広告が効きにくくなっていました」
そこで、思わず写真をとりたくなるような、美味しくて楽しいをコンセプトにした『肉のヒマラヤ』を目玉商品として売り出すことに。
「いきなり大ヒットしたわけではなく、徐々に注文が増えていきましたね。この商品を広めてくれた常連さまやスタッフの力があってこそだと思っています」
さらに、通販の納品仕入れも一筋縄ではいかなかった。
「テレビにも出る人気商品になっていたので、すぐに提携がきまると思っていましたが、どこの生産者さまもなかなか首を縦にふってくれなかったんですよね」
 冗談めいた表情で話していたけれども、言葉からは苦労が伝わってくる。
冗談めいた表情で話していたけれども、言葉からは苦労が伝わってくる。「もう、直接会いに行って話をしました。工場見学をして、牛を見て、仕事が終わったら飲みに行って。やっとの思いで交渉できることが決まったんです」
「正直、生産者さまの話を聞いたことで、売り上げを伸ばそうという気持ちよりも、生産者さまの想いを届けたいという気持ちの方が強くなっている自分がいたんです」
自分たちが直接その場の空気を感じて、苦労を味わったからこそ、飲食と向き合う気持ちにも変化があったんだろうな。
決して楽とは言えない飲食業の世界で、蔵石さんを動かす熱意やこだわり、現状を変えようとする強い意志を感じました。
「飲食で働ける環境はたくさんあります。そういった強い思いがなければ、わざわざ僕らとやることもないのかもしれません」
ただ、その気持ちに賛同してくれる人は決して多くはないのも現実としては立ちはだかっていると話します。
「たとえば、このお店を出すことによって生産者さんを応援することやアピールする機会となり、来てくれたお客さまと生産者さまをつなげるなど、たくさんの役割があると思うんです」
 「そう考えたときに、お金を稼ぎたいからという理由で働く人を集めても、うまくいかないと思っているんです」
「そう考えたときに、お金を稼ぎたいからという理由で働く人を集めても、うまくいかないと思っているんです」地方再生や生産者の声を届けるための方法が飲食ということだった。
「だから、飲食の経験はあまり気にしていなくて。焚火家は炭火焼なので、特殊な調理技術等はほとんど必要ありません。むしろ、こだわった食材を探すことのほうが重要です」
お店の使い方だったり、スタッフやお客さんとの関わり方だったり。お店そのもののあり方を考えられる人が向いていると感じます。
蔵石さんの思いに共感し、現在焚火家の店長とマネージャーを担当している上倉さんにも話を伺います。
 今回募集する方は、ゆくゆくは上倉さんと同じようなポジションでお店を動かしていく立場になるとのこと。
今回募集する方は、ゆくゆくは上倉さんと同じようなポジションでお店を動かしていく立場になるとのこと。「ここでの働き方は特殊な環境だと思います。通販の立ち上げから肉の仕入れ先へ挨拶に行くことまで、仕事内容は多岐にわたるので、刺激は多いですよ」
いろんな飲食店で働いてきた経験があるという上倉さん。しかし、飲食業で働くことに嫌気がさしたこともあったそうです。
「以前の飲食店で働いていたときは、同業者と飲んでいても他店舗の評価や比較する話ばかりだったんです。話や関係性に、広がりがなかったんです」
その後、別の環境で働きたいと考えていたときに見つけたのが、ビストロ店の応募でした。そのお店に関わっていた人が蔵石さん。
「面接のときに、ビストロよりも焚火家のほうが合うと言われて働くことになりました。ただ、ライセンス化や通販事業など、初めてのことばかりで苦労しましたね」
「そもそも肉を扱った経験がなかったので、業者の方とやりとりするのも一苦労でした。しかも、いろんな肉の部位があれば、値段変動もある。細かく見てないと告知なしで値段が上がったりするんです。業者も複数あるので、常に全体を把握するイメージで働いています」
特に焚火家のお肉は、特殊なお肉を扱っている分、デリケートな部分が多いと思います。
 「物によっては一年で五百円も高騰することもあるんです。それは無視できないですよね」
「物によっては一年で五百円も高騰することもあるんです。それは無視できないですよね」でも、同じくらい意識しているのはスタッフの働く環境です、と続けて話します。
「仕入れのルートや値段なんかはゴールがわかっているんです。だけど、働いているアルバイトスタッフや社員スタッフについてはゴールがないじゃないですか」
「スタッフに対して常にアンテナをはってあげることも、お店の店長としての役割だと思っています」
空気感ひとつにしても居心地のいいお店づくりをするために、お店全体を動かす関わり方からスタッフ一人ひとりの関わり方まで共有することもあるそうです。
 「お店に立っているときは、極力スタッフと会話するよう心がけています。仕事のこともプライベートのことも根掘り葉掘り聞くわけじゃないですが、なるべく聞くようにして言葉の音をできるだけちゃんと聞こうとしています」
「お店に立っているときは、極力スタッフと会話するよう心がけています。仕事のこともプライベートのことも根掘り葉掘り聞くわけじゃないですが、なるべく聞くようにして言葉の音をできるだけちゃんと聞こうとしています」言葉の音?
「言葉尻に影響ってでるんですよね。『あれ、いつもと喋り方がちょっと違うな』とか、直接話すとわかることが多いんですよ。実際に現場で動いてもらうのは、アルバイトの方やスタッフがメインじゃないですか。その軌道修正をしてあげることは結構大きな仕事かなと思っています」
何の目的もなく働くよりも、扱う食材にこだわりを持ったり、お店の環境に意識を向けたり。
そんな人が集まってくれば話も進めやすいし、高いモチベーションが保たれるように思います。
「それが伝わってない人と働く日々って、不安と戦っているようなもんだと思うんですよ。正直、日々の仕事内容は他の飲食業と変わりません。朝出社して、仕込みして、開店の準備して。空いている時間で通販に関する業務をやっています」
「だからこそ、飲食経験よりも目指すビジョンが一致している人のほうが向いているのかもしれません」
実際に行動に移しているお二人の姿や言葉には、スタッフのあり方や生産者の思いを胸に働く、焚火家の熱意を感じました。

「同じビジョンに向けてがんばれる人が一人でもいれば、確実に独立できるようなサポートやシステムづくりにしっかり力を注いでいくつもりです」
「『この店だったら絶対いけるのでやりましょう』っていうお店をつくっていきたいです。そのためにも、まずは自分たちが頑張れる環境をつくっていければと思います」
これから加わる人も、焚火家の熱意を形づくる重要な一員になると思います。
ぜひ一度、肉のヒマラヤを食べに行ってみてください。
そこで焚火家に少しでも可能性を感じた方々は、ここでできることがたくさんあるように思います。
(2016/7/22 浦川彰太)

