※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
課題の根っこを解決するには、これまでのやり方にとらわれず、柔軟な考え方が必要になるように思います。岐阜県・東白川村にある株式会社ふるさと企画は、もともと村おこしのための企画や運営をする会社でした。
「たとえば、村の野菜をつかって開発した特産品の売上は、20年経った今でも好調を保っています。村の農業に関しては、農産物を売ることで応援してきたんです」
「けれど、商品が売れるだけじゃ、もう村に元気がでない。そもそもの農作物をつくる農業が元気になることを考えないとだめなんです」
そう話すのは、代表の安江さん。
ふるさと企画では、今年から農業の担い手を育てる事業を始めました。
 ここで、就農する人の住むところから独立までをサポートし、村に農業の雇用をつくっていく人を探しています。
ここで、就農する人の住むところから独立までをサポートし、村に農業の雇用をつくっていく人を探しています。食べていくのが簡単ではないと言われる農家。けれども、ここではちゃんと生計が立てられる形を生み出しています。
この土地ならではのモデルだと思うので、農業に関心のある方もぜひ続けて読んでみてください。
東白川村までは、名古屋から電車と車で2時間ほど。
村には、一級河川・白川が1本の道のようにゆったりと流れています。
 古くは養蚕でさかえ、昭和に入り養蚕が斜陽になると、“白川茶”として知られる茶畑がつくられました。
古くは養蚕でさかえ、昭和に入り養蚕が斜陽になると、“白川茶”として知られる茶畑がつくられました。この場所に合う農業を試行錯誤しながらつくりだしてきた場所です。
「東白川の野菜や米がうまいのは、何よりも土がよいから」
村の内外を問わず、そんな声を耳にしました。
ふるさと企画では、そんな村の農作物や開発した特産品を販売したり、都市との交流を図るため田舎体験ができる施設「こもれびの里」を運営しています。
まずは代表の安江さんに、詳しく話を伺いました。
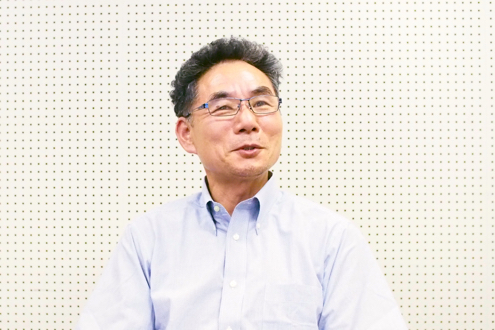 「いろいろなことをしているんですけど、事業の柱としては、特産品のトマトジュースの製造販売があります」
「いろいろなことをしているんですけど、事業の柱としては、特産品のトマトジュースの製造販売があります」「どうぞ」と出してもらったつめたいトマトジュースを飲んでみると、生のトマトそのままの味がする。
「27年前の開発のときから着色料や保存料を入れないでつくっているんです。無添加ということが評価されて、安定して売れている商品なんですよ」
 リピーターは添加物に気を使う都心のお母さん方。口コミでじわじわと広まってきたんだそう。
リピーターは添加物に気を使う都心のお母さん方。口コミでじわじわと広まってきたんだそう。「土がしっかりしていれば、そんなに農薬を使わんでも作物は元気に育ちます。この村は、昔から健康志向なのかもしれませんね(笑)。今ほど無添加が有名でないころから、有機肥料・低農薬はふつうのことだったんです」
村のこだわりが、だんだん時代のニーズにあってきたという感じ。
「ふるさと企画は、村の人が株主の村ぐるみの会社です。ミッションは、地域おこしなんですね。今までは、販売することで農業を応援してきました。でも、その程度じゃもうだめやなって」
村の基礎産業となる農業は担い手の高齢化がすすみ、大切にしてきた農地も手が入らなくなってきた。
そんなとき、村長から「農業を事業化して、農地保全につなげよう」という話があった。
「これからは、農家さんがつくったものを販売するだけでなく、自分たちで農業の担い手をつくっていかなあかん。それをふるさと企画で担っていこうというのが今回の募集なんです」
 「どこから来た人でも、農業をやりたいという人があれば、まずはうちで雇用というかたちで受け入れます。そこで1年、もしくは2年で栽培技術を習得してもらい、その後独立してもらう流れです」
「どこから来た人でも、農業をやりたいという人があれば、まずはうちで雇用というかたちで受け入れます。そこで1年、もしくは2年で栽培技術を習得してもらい、その後独立してもらう流れです」ふるさと企画で教えているのは、名産の夏秋トマト。
このあたりのトマトは少ない面積でも利益がでるから、独立後の生計が立てやすい作柄だそう。
「どういうふうにつくったらいいのか、どのくらいの面積で生計が立つのか。まずは受け入れる側がそういったことを勉強してもらいます」
具体的には、農家になりたいという人の村内の移住先の家探しにはじまり、助成制度や補助金の提案、技術を教える農地の管理、独立後の農地の確保まで、専業農家として食べていくためのサポートをしていきます。
「なるべくスムーズに農家として暮らしていけるような仕組みをつくっていくのが、私たちの仕事です」
新しく入る人は、まずは地域おこし協力隊として入ることになる。けれど、この会社の人たちは社員として迎えたいと思っています。
今年からはじまったこの取り組みでは、すでに4人の方を受け入れました。
新規就農として愛知県から家族で移住してきた長谷川さんもその一人。
お話を聞きに伺うと、ちょうどトマトのビニールハウスで作業をしているところでした。
 長谷川さんは、17年間リサイクルショップで販売をしてきたそう。
長谷川さんは、17年間リサイクルショップで販売をしてきたそう。どうして農業を始めたくなったんでしょう?
「生産者になりたかったんです。食べ物をつくるって、ほんとうに大事な仕事だと思います。それに、販売の仕事をしているころ、自分たちで庭に野菜をつくっていたんですけど、それが楽しかったんですよね」
「けれど、農業だけで食べていくのは厳しいと言われていて。どうしたら生計が立つかと調べるうち、トマトなら小さな面積で収益がでることがわかったんです」
そこでトマトが名産である岐阜県を中心に就農先を探した。
「新規就農者への支援は地方自治体によって違います。なかでも、東白川村の補助はとくに手厚かった。それで、とりあえず来てみようと村を訪ねたんです」
訪れてみると「ここならできるんじゃないか」と感じたそう。
「なんていうんだろう、第一印象なんですけど、受け入れてくれる感じがすごく伝わってきたんです」
受け入れてくれる感じ。
「最初は役所を訪れて、そこからいろんな人に出会って。移住して就農したいんです、と話すと『じゃあ来なさい』って助けてくれるというか」
「表情や言葉からもそうですけど、何よりも住むところや農地のこと、お金のこと… “ここで暮らす”ってことに対して、すごく具体的に話を進めてくれたんですよね」
とくに助かったのが、ふるさと企画のあたらしい取り組みだったそう。
「やっぱり暮らしていくには、無収入というわけにはいかない。ここで雇ってもらいながら研修させてもらうこの仕組みは、ほんとうに有り難いことです」
 すると、安江さん。
すると、安江さん。「うちの思いと、長谷川さんの思いはマッチしているんですね」
「農業をやりたいという方の受け皿となってここで技術を磨いてもらい、村で農業をはじめていただく。これは、私たち村の人間としても望んでいたことなんです」
長谷川さんにはお子さんがいるから、それもまたうれしかったという。
家を探すときも、学校から通いやすいところを探したのだとか。
ふたたび、長谷川さん。
「子どもも、学校にすぐ慣れて友だちができて。村の子は、ほんとうに穏やかなんですよ。きっと、大人たちが穏やかだからだと思うんですけど」
 あたらしく入る人が担うのは、こんなふうに暮らしていくためのサポート。
あたらしく入る人が担うのは、こんなふうに暮らしていくためのサポート。トマト栽培の技術は、トマト農家の方や県の職員である技術指導員の方が教えています。
「ぼくにも師匠がいるんですけど、とても優しくて厳しい方です」
厳しいんですか。
「うん。でも、来年から一人立ちすることを考えると、その厳しさがなくてはやっていけない。とても勉強になっています」
すると、ちょうど県の技術指導員の方が長谷川さんのトマトの様子を見にいらした。
お名前は、永田さん。取材です、と言うと、畑に座り込んで座談会になった。
 永田さんは農大の大学院を卒業後、指導員として岐阜県内をあちこち回っている方。
永田さんは農大の大学院を卒業後、指導員として岐阜県内をあちこち回っている方。「この村はアットホームな雰囲気ですよ。村の人どうし距離が近くて、ぼくもこの村の村長さんとお話しをすることがあるくらいなんです」
「長谷川さんは、すごいなと思います。やっぱり家族で越してくるって、半端な覚悟じゃないと思うから」
大変は大変ですよ、と笑う長谷川さん。
「ただ、トマト農家は、食べてはいけると思います」と永田さん。
「岐阜のトマト生産って、すごくゆるい見方をするとフランチャイズなんです」
フランチャイズ。どういうことでしょう?
「“ももたろう8”という品種で、決まった農薬と肥料を使い、規格を揃え、農協でまとめて出荷するんです。販売ルートがしっかりあって、儲かる仕組みができているから、トマト農家は収益が見込めるんですね」
「この辺りの農家さんの働き方としては、夏と秋は20アールの畑でトマトを2回収穫する。プラス、冬は林業。東濃桧(とうのうひのき)という木が有名で林業がさかんな村ですし、仕事はあります。そのふたつで生計を立てている人が多い印象かな」
加えて、出荷できない規格外品のトマトはふるさと企画でトマトジュースになる。
これなら、新規就農希望者にトマト農家のモデルをしっかりと説明できそう。
「でね、ぼくは彼のお子さんに大学に行って欲しいんです」
せっかく村に人が増えるのに、どうしてですか?
「モデルケースになってもらいたいんです。村でトマトをつくって子どもを大学まで出せるとなったら、あとの人間が続くでしょう。農家でもそのくらいの生計が立つと証明できる。だから大学に送り出してほしいんです」
永田さんもそうだけれど、この取り組みに関わる人で印象的だったのは課題を解決するために考える人がとても多いこと。
 できることをしっかりやって、繋いでいこうという気持ちがつよく感じられる。
できることをしっかりやって、繋いでいこうという気持ちがつよく感じられる。来年退職するという安江さんも、ひっそりとこんな野望をもっていた。
「販売ルートがあっても、相手は自然物。村じゅう同じもんつくってたら、だめになるときは一斉にだめになってしまう」
「わたしは、ここを卒業した人たちにそれぞれの地域でちがうものをつくってもらって、何かあっても対応できるような仕組みをはじめたいんです」
聞けば、ほかにもまだまだ種をまきたいことがあるのだとか。
まずは就農する人をサポートして、村に人を呼びこんでいく。
ここには、夢物語に終わらない、力強さがあると思います。
(2016/8/10 倉島友香)

