※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
地域の「資源」って、いったい何のことを言うのだろう?歴史的な建造物やおいしい特産品、美しい自然環境。
それもあるかもしれません。
けれども、地元の人が当たり前と思いながら続けていることが「資源」ということもあると思います。
香川県まんのう町。
市街地である高松市や丸亀市、“こんぴらさん”の琴平町などと比べ、あまり知名度も高くないこの町。ここには、まさにそんな「資源」があふれていました。
 まんのう町の「資源」に光を当て、発信していく地域おこし協力隊を募集します。
まんのう町の「資源」に光を当て、発信していく地域おこし協力隊を募集します。“協力隊”とひとくちに言っても、その役割は少し特殊かもしれません。
今回は地元ケーブルテレビ局に出向し、番組制作やWebメディアを立ち上げ発信していく人の募集です。
現地を訪ねてお話を伺ってきました。
成田空港から高松空港まで、飛行機で1時間半。空港からはリムジンバスでまんのう町へと向かう。
新緑の木々が窓の外を流れていくのをぼんやりと眺めていると、30分ほどで「まんのう町役場前」のアナウンス。ボタンを押して停まったのは、住宅地に据えられた小さな停留所だった。
そこから3分ほど歩けば、役場の立派な庁舎が見えてくる。
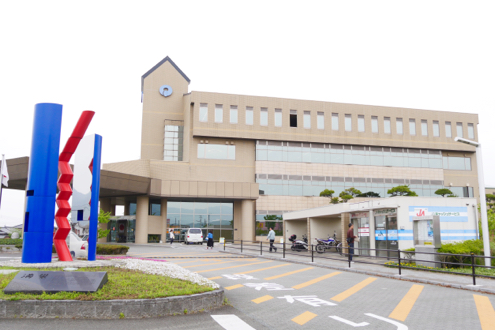 迎えてくれたのは、企画観光課の萩岡さん(写真左)と阿宅(あたく)さん(写真右)。
迎えてくれたのは、企画観光課の萩岡さん(写真左)と阿宅(あたく)さん(写真右)。おふたりとも、やわらかな物腰の内に熱を秘めている方だ。
「お互いに多趣味というか、新しいものに興味があるんです。あとはやっぱり『何か起こさないかん』という気持ちを共通で持ってる」
 地元のカフェでマルシェを手伝ったり、コンサートを企画したりしている阿宅さん。
地元のカフェでマルシェを手伝ったり、コンサートを企画したりしている阿宅さん。地域の文化祭や夏祭りを盛り上げるため、バンドを組んで演奏している萩岡さん。
「楽器はベースです。譜面も読めないんですけど、やってます(笑)。そういうのもやっぱり、『地域を盛り上げていかないかん』という気持ちがもとにあるんですね」
ただ、プライベートを離れた行政の立場から新しいことに挑戦するとなると、なかなか一筋縄でいかないことも多い。
そこで行政と民間の間で動ける人材を募るため、地域おこし協力隊を募集しはじめたのは昨年度のこと。
結果として、まったく応募がこなかったという。
「ええもんはあっても、その情報発信を十分にできていなかったんです。そもそも、意外と町民が知らないことも多いんですよね」
町の人が知らないこと?
「我々は行政の立場上、PRせないかんということで知っているんですけれども、町のなかであまり知られていない取り組みが意外と多くて。外に向けてだけでなく、内側にも知らせていくことがまず大事なのでは?という話もしています」
たとえば、ひまわり。
まんのう町では15年ほど前からひまわりの栽培をはじめ、夏になると辺り一面が黄色く染まる。フォトコンテストが開かれ、池坊100選にも選ばれるなど、鑑賞の対象としての知名度は徐々に上がってきているという。
 しかし、その種を搾ってつくるひまわり油や、搾りかすを食べて育ったひまわり牛のことについて、ほとんど認知が広まっていないそうだ。
しかし、その種を搾ってつくるひまわり油や、搾りかすを食べて育ったひまわり牛のことについて、ほとんど認知が広まっていないそうだ。「香川県といえばオリーブオイル・オリーブ牛がブランドとして定着していますが、それに比べて、実はひまわりのほうがオレイン酸を多く含んでいて、ビタミンも豊富だということがわかったんです。これはちゃんと研究所に出して、実証済みのことです」
さらにお話を伺っていくと、他にもまだまだ「資源」がありそうなことがわかってきた。
「まんのう町は、旧満濃町と旧琴南(ことなみ)町、旧仲南(ちゅうなん)町が合併してできた町なんですが、その旧仲南地域では毎年夏にバレーボール大会をするんですよ」と阿宅さん。
「もう50年以上続いてるのかな?その地域の人がほとんど参加して、前は200チームぐらい出よったんですよ。今は減ってますが、それでも100チームぐらい。小さな子どもから上は80歳ぐらいの人まで、みんなで一緒にバレーをやるんです」
 各家庭の敷地も広々としているので、わざわざ出かけなくても人を呼んでバーベキューができるし、ちょっと出かければ川魚も獲れる。DIYだって特別なことじゃない。
各家庭の敷地も広々としているので、わざわざ出かけなくても人を呼んでバーベキューができるし、ちょっと出かければ川魚も獲れる。DIYだって特別なことじゃない。雑誌に紹介されるような「田舎暮らし」は、ここに当たり前のように存在している。
「あえてお金出してせないかんことがあまりないというか。そういうところはうちの武器になるんじゃないかなと思ってますね」
ここで、「“モンバス”ってご存知ですか?」と萩岡さん。
突然の若者風な響きに、一瞬戸惑う。
「『MONSTER baSH』っていう夏フェスで、町内の国営讃岐まんのう公園でやるんですけれど。有名なアーティストさんもきたりして、結構盛り上がるんですよ」
 当初は地元のバンドだけが参加するイベントだったそうだけれど、次第に規模も大きくなり、今年で17年目を迎えるという。
当初は地元のバンドだけが参加するイベントだったそうだけれど、次第に規模も大きくなり、今年で17年目を迎えるという。「2日間の来場者数が5万人ですよ。人口の2.5倍です(笑)」
そんなにたくさんいらっしゃるんですか!?
「ええ、そうなんです。ただ、町内に宿泊施設があまりないので、フェスが終わると高松や琴平に流れていってしまうんですよ。そこをどうするかも考えていかんとね」
大きなフェスがあったり、地域で50年以上続くバレーボール大会があったり。規模も性質も異なるさまざまな「資源」がここにはあるような気がする。
と同時に課題もある。新しく入る人には、外からの新鮮な感覚を持って取り組んでほしいという。
途中から輪に加わった秋吉さんは、香川県の地域おこし協力隊。日本仕事百貨での募集を通じて入り、現在は各市町村と連動した活動を展開している。
 「いろいろな自治体の方と関わる機会があるのですが、おふたりはすごく気さくにお話しできていいなあと感じています。ほっとかないというか」
「いろいろな自治体の方と関わる機会があるのですが、おふたりはすごく気さくにお話しできていいなあと感じています。ほっとかないというか」ほっとかない。
「町の中枢にいる方々でありながら、一緒に考えて動いてくださるので。協力隊として、とてもありがたい存在だと思います」
今回の協力隊募集に向けておふたりがどんな準備を重ねてきたのか、秋吉さんが「さぬきの輪web」という地域おこし協力隊ポータルサイトにまとめている。
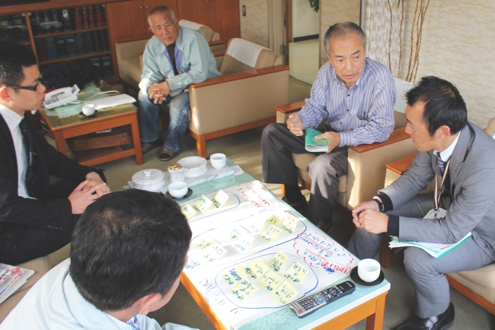 「どうして協力隊を募集するのか?」「協力隊と一緒にどんなことをしていきたいのか?」
「どうして協力隊を募集するのか?」「協力隊と一緒にどんなことをしていきたいのか?」本気で議論を交わし合ってきた様子が伝わってくる。
「協力隊の活動には3年間という期限があります。その後のことを考えても、ここでの経験はきっといい次へのステップにつながると思いますよ」
庁舎をあとにし、今度は地元ケーブルテレビ局「中讃テレビ」の支店へ。
事業推進部地域連携部長の山地さんにお話を伺う。
広告代理店、出版社と続き、この会社で3社目。昨年までは営業担当を務めていた。
 これまで中讃テレビでは、地域のさまざまなトピックを毎日4、5件取り上げ、取材・編集した番組をケーブルテレビで放送してきた。
これまで中讃テレビでは、地域のさまざまなトピックを毎日4、5件取り上げ、取材・編集した番組をケーブルテレビで放送してきた。「そうすると、だいたい年間で600本ぐらい流しとることになるんですよ。これってすごいコンテンツですよね」
ただ、従来は番組を流したらそれで終わり。せっかくのコンテンツが残らないのはもったいない。
そこで今、新たにWebメディアを立ち上げる計画があるという。
「中身は豊富にあるわけですから。これをアーカイブ化してWeb上で発信することで、町外の方々がまんのう町のことを知るきっかけにもなりますし、ここを離れて別の場所に暮らす出身者が今のまんのう町を知ることにもつながると思っています」
新しく入る協力隊は、約半年間かけて映像の撮り方や編集の仕方などのレクチャーを受けたり、取材に同行して学びながら、ゆくゆくは自ら番組をつくったり、メディアの立ち上げに力を発揮してほしいと山地さんは話す。
 それにしても、年間600本も取り上げられる内容ってあるのでしょうか?
それにしても、年間600本も取り上げられる内容ってあるのでしょうか?「ありますよ!たとえば、お蕎麦屋の奥さんがつくっている漬物がめちゃくちゃうまいんです(笑)。ほぼ無農薬の野菜をご自身で育てて、もう30年ぐらい漬物されてるんですわ。伸び放題になったタケノコの穂先をちょんと切って、それを漬物にしようっていう取り組みもされていて」
「ただ、半端ちゃいますよ。びっくりするんですけど、キャリーに20杯ぐらいわっさー!って運んで、全部おひとりで皮むいて切って、2週間ぐらい天日干し。普通できないですよ」
こんな話がそこらじゅうに転がっているらしい。地域のおばちゃんたちとの井戸端会議に参加していると、自然と次の取材予定が決まっていくという。
「『今度うちきてや』『何かできるんですか?』『こんなのつくっちょるわい』『ほんまでっか!?』みたいな(笑)。あとは、『あんたテレビ出とったな』ということで会話が広がっていったり。やっぱりそこが原点ですかね」
そんな山地さんもよくお世話になっているという、ひまわり農家の岩倉さん。
ひまわり以外にもさまざまな作物を育て、自治会長など地域の役職をいくつか兼任している、パワフルな方だ。
 作付けから栽培、搾油に至るまでのノウハウを積み重ねてきた岩倉さん。
作付けから栽培、搾油に至るまでのノウハウを積み重ねてきた岩倉さん。「油こしらえて売れんのではいかんからね。出口をちゃんとせんといかんと思う」
PRの面に関しては、新聞やテレビなど、岩倉さんが継続的に関係を築いているメディアもあるという。
「昨日は農業新聞に『マコモダケ今日植えるぞ。はよこい』言うたら、9時ごろに写真撮りにきた。今日も別の新聞社に電話して、『お前あのサツキが咲いとるけん、ちょっと新聞に出せ!』言うて(笑)。ひまわり祭りの1週間前には、各社に情報も流しますよ」
「“使う”言うたら語弊あるけど、向こうも記事探しとるきに、そのところうまくできたらね」
たとえば、これから地域での起業を考えている人にとっては、地域特有の行政やメディアとの付き合い方を直に学べるいい機会になるかもしれない。
「あんまり言葉遣いは上手でないんやけど、来たらとにかく大事にしますわ。まんのう町に来てつらかったなとか、人とのつながりがなかったなとかいうことがないようにはします。あとは、来てくれた人の努力次第ということです」
 岩倉さんの言葉にある通り、まんのう町では協力隊を受け入れ、共にいい時間を過ごせるよう、準備をしてくれている人が多いように感じました。
岩倉さんの言葉にある通り、まんのう町では協力隊を受け入れ、共にいい時間を過ごせるよう、準備をしてくれている人が多いように感じました。この町の資源を自分なら活かせると思った方は、ぜひ応募してみてください。
(2016/8/10 中川晃輔)

