※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
東濃ひのきの産地として知られる岐阜県白川町。町内面積の約88%を森林が占め、見渡すかぎり緑豊かな景色が広がります。
この町で、地元の優良材である東濃ひのきを使った建築木材の加工や、間伐材を使った土木資材の加工、そして建築廃材・木くずを利用したバイオマス発電を行うのは、東濃ひのき製品流通協同組合。
 「安く買うのが商売では当たり前。でも、林業や木材に関して言えば、地元でうまく回そうとしたら、目線を変えて10円でも高く仕入れてやろうぐらいの考え方に切り替えんと。自分と職員と、さらにそのまわりの組合員さんや同業者の方々が、この先も食べていける仕組みはつくれないんじゃないかな」
「安く買うのが商売では当たり前。でも、林業や木材に関して言えば、地元でうまく回そうとしたら、目線を変えて10円でも高く仕入れてやろうぐらいの考え方に切り替えんと。自分と職員と、さらにそのまわりの組合員さんや同業者の方々が、この先も食べていける仕組みはつくれないんじゃないかな」そう話すのは、参事を務める大島和之さん。
先代が残してきた森林も、町の基幹産業である林業も、そして日本の山も。受け継いできたものを次の世代に渡していく。
今回は、地域おこし協力隊として、協同組合での業務をこなしながら、林産業全体を盛り上げていく人を募集します。
山と向き合い静かに闘う人たちが、日本の美しい風景をつないでいました。
名古屋駅から高山本線に乗り換えて1時間半ほどで、白川口駅につく。
車で15分ほどのところに東濃ひのき製品流通協同組合はありました。
 事務所の向かいには、木材のプレカット加工場や、廃材をエネルギーに変えるバイオマス発電施設が整っている。
事務所の向かいには、木材のプレカット加工場や、廃材をエネルギーに変えるバイオマス発電施設が整っている。参事の大島さんに事務所でお話を伺いました。
 大島さんは、白川町の近く可児市出身。ゆっくり静かにお話をする言葉の端々に、山や地元に対する思いが感じられる方でした。
大島さんは、白川町の近く可児市出身。ゆっくり静かにお話をする言葉の端々に、山や地元に対する思いが感じられる方でした。林業の学校を卒業後、工務店で働いていたそう。当時は、お客さんに売りやすいユニットバス・システムキッチン・トイレの3点セットを高く売って、木材は安い外材をセットにして売るというやり方が主流だった。
「山仕事や日本の木材をないがしろにしたやり方だよね。ふと、昔の同級生たちと集まって飲んどると、『俺何やっとるんやろ』と思って。これじゃだめだって、会社でいろいろ話をして。それでも方向性が違うなと思って会社をやめて、それで山仕事をやった」
親方が亡くなり、働く場所を探していたとき、組合に入ることに。今から14年前のこと。
昨年からは参事として、製品部門をはじめ、さまざまな部門をみているそう。
東濃ひのきの特徴は、強度的に優れている点。ただ硬いのではなく、ねばりとしなりと強度があるといいます。
さらに、天然乾燥させて製品にしていた昔は、東濃ひのきといえば美しいピンク色も魅力の一つだったそう。
 良質な木材をもとめて、全国から業者さんが買いにくる。
良質な木材をもとめて、全国から業者さんが買いにくる。一方で、それは原木価格が下がったことが背景にあります。
「十数年前は、原木価格が今の2〜3倍してた。それがどんどん下がってきて、半分以下になってしまったんよね」
木材価格は下落し、建築需要も減った。木材産業や林業を継いでいく人は不足して林業全体が活力を失ってきている。それによって山林の荒廃が進んでいます。
製品流通協同組合も、今でこそ経営状況が立ち直ってきたけど、7年前には債務超過に陥った。
「そこではじめて『何やっとるんや』という話になって。そこからやっと再建する動きが出てきた。組合ともいろんな言い合いをして、むちゃくちゃ荒れた総会をやって。その結果、なんとかしないかんやろと、職員それぞれが思った。そこから一つひとつ順番に問題を解決していったんです」
当時は毎月の売上や利益の計算もしっかりとはできていなかった。まずは、全部門ごとに経理を管理するように変えていったそう。
それから、岐阜県産材に特化せず、売れるものや利益の多いものを売ろうと外材を多く扱っていた営業を見直した。
「商売としては成り立っているけど、全然地元に貢献していない。だから地元の木材を扱うように仕組みを変えていったんです。ちょうど国産材が徐々に重宝されるようになってきた時代にも後押しされてね」
前任の参事の方が仕切っていたところから、製品部門を切り離して大島さんに任せてもらったそう。
「10年かけて、今は取り扱う木材の95%ぐらいが岐阜県産や町内産のものになっている。自分のやりたい仕事ができていて、非常にやりがいがあります」
 大島さんには、地元を大事にしたいという思いが根っこにあるのでしょうか。
大島さんには、地元を大事にしたいという思いが根っこにあるのでしょうか。「そうですね、地元がやっぱり。うちの組合だけじゃなくて、組合のまわりもふくめて成り立たないと先はないですから。そこは第一に考えています」
「うちの組合はいま赤字だけど、黒字にしようと思えば仕入れ先を叩けばいい。でも、仕入れ先を叩いて地元の木を安く買うということは、林業にとってマイナスになる」
だから、製品流通協同組合では、製品の利益が昨年の10%よくなれば、仕入れ値を5%上げるというやり方をとっているそう。
 「自分一人が食べていければいいという感覚なら、こんなことする必要ない。これから林業や木材業をよくしよう、まわりと一緒にがんばろうと思ったら、当然こういう考え方になる。どこまでやれるかわからないけど、現在はうまく回せているから、もう少し頑張りたいなと」
「自分一人が食べていければいいという感覚なら、こんなことする必要ない。これから林業や木材業をよくしよう、まわりと一緒にがんばろうと思ったら、当然こういう考え方になる。どこまでやれるかわからないけど、現在はうまく回せているから、もう少し頑張りたいなと」実際に働くとなると、どんな仕事をしていくのでしょう。
「一つは営業に特化した仕事です。提案営業をしていくためには知識がないとできません。入った当初はいろんな作業を体験してもらって、一連の流れを把握して、そこから営業という形になる。3年ぐらいは工場勤めをしないとダメかな」
営業ではどんな提案をするんですか?
「どの木が何に向いてるか。柱・梁桁・筋交いなど建築構造上この木を使ったほうがいいという使い方ですね。その説明をできる人が少ない。お客さんもわからないから、今まで通りに米松とか外材を使うんやね。それをヒノキや杉に変えられるよと言ってあげないと」
「下地材も、貼り付ける外壁が重いものであれば丈夫なヒノキにしてあげて。軽いものであれば、単価の安い杉にしてあげるとか」
一般的には100本単位でしか出荷されない木材を、小分けにして出荷したり。場所によって、見た目・構造・予算の優先順位を変えたり。
細かな部分も提案していくことで、木材をバランスよく使っていけるといいます。
ほかにも、大島さんをはじめ、白川町の林業関係者の方々は、東北の震災が起きた直後、仮設住宅で協力できないかと「木づなプロジェクト」というプロジェクトを立ち上げた。
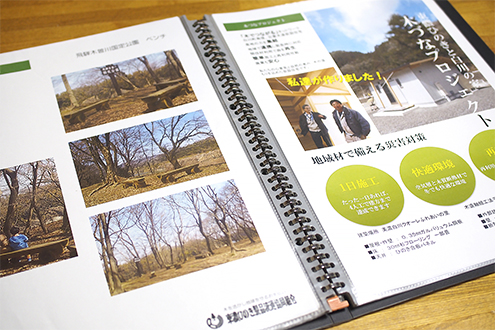 機械がなくても大工さんが簡単につくれるような仕組みになっていて、実際に建てるのも説明する人が1人いればつくることができるという仮設住宅。結露やカビも起こらないように計算されているそう。
機械がなくても大工さんが簡単につくれるような仕組みになっていて、実際に建てるのも説明する人が1人いればつくることができるという仮設住宅。結露やカビも起こらないように計算されているそう。「なおかつ壊したあとのことも考えて、燃やしてエネルギーに換えたり、外して一般家屋にも対応できるようにしたり。中もバリアフリーにして」
今も東北で、大島さんたちがつくった住宅がモデルにされているといいます。
ただ、職員さん一人ひとりが2役3役もこなしているため、日々の仕事に追われて、なかなか営業に力を注げていないのが現状だそう。
ものの売り方には答えがないから、自分なりに考えてやってほしいと話す大島さん。
「既製品がメインにはなってくるけど、基本ベースの知識を身につけたら、自分の感性でお客さんに合わせてアレンジしていける。原木の状況を見て、何をつくろうかというイメージが100人いれば100通りある。手間はかかるけど、そこらへんが面白いところ」
一方で、難しい部分も出てくる。
「うちの場合は、いいものをつくって高く売らないといけない。よそより価格は高いけど、お客さんがついてきてくれるような営業をかけていくことがいちばん必要なこと。ものの良さや付加価値をうまく説明していくことが大切です。そこが難しくもあり面白いところかな」
お客さんのおよそ90%はリピーターになって仕事をくれるそうです。
これから先、知識のほかに必要なのは、新しい視点からのアプローチ。
「たとえばこの業界は完全な男社会なんよね。業界の知識もしっかり勉強したうえで、女性目線でアプローチをかけてもらえると、もっと裾野が広がりそうな気がするんやね」
力仕事が多いし、実際にはかなり難しい部分もあるけれど、女性が働きやすい環境をつくることで、業界がよくなっていく兆しになるかもしれません。
これから入る人も業務をこなしつつ、建築土木以外の使い方を考えたり、若い感性をもって大島さんたちにないアイデアを出していってほしいといいます。
組合員さんが出資してつくってくれた協同組合のなかで、先代の方の意見も尊重しつつ、林業や木材業全体をよりよくしていくような仕組みに変えていく。並大抵のことではないかもしれないけれど、大島さんはそうしたことに向き合っています。
 大島さんは、どんな人に来てほしいですか。
大島さんは、どんな人に来てほしいですか。「環境をよくしたいとか今の社会と向きあって、自分がなんとかしてやろうという前向きな考えを持った方にできれば来てほしいですね」
「それからやっぱり第一は、山が好きな人」
好きと言っても、便利さとは程遠いところにあるし、泥臭い仕事もしなきゃいけない。本当の意味で山の豊かさを分かっていないと続かないといいます。
「実際にこの日本の山が全部裸山になったらさ、水も生まれんし。島国でそんなことになったら、誰も生きていけんくなるよ。そこをなんやかんや田舎の人たちががんばっとる」
 今ある暮らしは自然の恵みがあるからこそ。
今ある暮らしは自然の恵みがあるからこそ。先代からつづく山の恩恵を受けて生きていることを実感している言葉だと思いました。
地元の木材資源を活かすことで、次の世代へと森林を受け継いでいく。
気になることがあったら、一度、白川町を訪れてみませんか。自然と人がともにつくってきた風景が待っています。
(2016/8/31 後藤響子)

