※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
「おせっかいに近いのかな。できる限りその人のことを考えて、ほかの人が受け取りやすいものをつくる。クリエイティブを通して『人と人』が手を取りあうような循環をつくりたいです」 鎌倉にある、テトルクリエイティブを訪ねました。
鎌倉にある、テトルクリエイティブを訪ねました。Webや映像の制作、DTPなどを手がける広告会社です。NPOやNGOの広報に力を入れてきた一方で、中小企業のブランディングなど、すこしずつ手がける幅を広げています。
今回は、経験のあるマークアップエンジニアを募集します。
相手に寄り添い、人と人をつなぐようなものをつくりたい。そんなふうに思っているとしたら、ぴったりの場所かもしれません。
まずはぜひ、テトルクリエイティブがどんな会社なのか知ってもらえたらと思います。
鎌倉駅を降り、鶴岡八幡宮へ向かうように参道を歩く。5分ほどでテトルクリエイティブの入居する建物が見えてきた。
3階のシェアオフィスには、以前紹介させていただいたウェブ制作会社の村式と手仕事のギャラリー&マーケットのiichi、そしてテトルクリエイティブが入っている。
 参道に面しているため、昼間は陽のあかりが入る。明るくていい場所だな。
参道に面しているため、昼間は陽のあかりが入る。明るくていい場所だな。「よかったら外でお話しませんか」と誘われ、毎週月曜日にミーティングをしているというカフェへ案内してもらった。
この日お会いしたのは、代表の平田さん、デザイナーの広瀬さん、マークアップエンジニアの東崎さんの3人。
「場所にとらわれない仕事だから、いい環境でしようと思って。3年前に渋谷から鎌倉へオフィスを移転したんです」
 そう話すのは代表の平田さん。広告代理店を経て、デザイナーとしてフリーランスで働いてきたそう。当時のことをこう振りかえってくれた。
そう話すのは代表の平田さん。広告代理店を経て、デザイナーとしてフリーランスで働いてきたそう。当時のことをこう振りかえってくれた。「はじめは好きなことを仕事にしているという感覚でした。けれど、フリーランスでやるうちに仕事の効率ばかり考えるようになってしまって。お金を得るためとはいえ、こんなふうに取り組んでいていいのだろうかと考えるようになりました」
そんなとき、フリーランス仲間であり、テトルクリエィティブの前代表である谷岡さんから会社をつくりたいという話を聞く。当時谷岡さんは、タイのチェンマイでHIVに母子感染した孤児たちが暮らす施設”バーンロムサイ”の広報活動に取り組んでいた。
「NPOやNGOの人って、いいことをしているんです。けれど世に出す手段や方法を知らないことが多い。『いいことしています』というだけでは、受け取る方もなかなか理解できない。そのギャップをクリエイティブでつなぐことができるんじゃないかと思ったんです」
「僕らがもっているクリエイティブの能力を、社会にちゃんと還元する仕事をしていこう。そんな思いで、一緒に会社をつくってきました」
平田さんたちはバーンロムサイを寄付に頼らない組織にしようと、Webサイトを制作。施設でつくった服などを販売した。すると、より多くの人に知られ資金も集まるように。
半年ほど経ってタイの現地へ行ったとき、こんなことを実感したそう。
「孤児院なので、そのへんで走ったり笑ったりしている子どもがいるんですよね。それを見たとき、『あ、この子らの飯になってんのか。この子らに必要な薬を生み出すために俺はやっているんだな』ってリアルに感じて。お客さんだけでなく、その先にいる人やコミュニティもつないでいく実感を持ったんです」
 それからは、どのお客さんに対しても同じような感覚でつくることができるようになったといいます。
それからは、どのお客さんに対しても同じような感覚でつくることができるようになったといいます。「僕らは、『手をとる』みたいなことを大事にしているんです」
テトルクリエイティブの名前の由来にもなっているけれど、“手をとる”とはどういうことでしょう。
「うーん…。僕は、ほんとうに困っている問題を、他者が完璧に理解してどうにかすることはできないと思っていて。『手を取る』というのも、結局は僕らの自己満足なのかもしれない。だから僕たちがやるのは、勝手にその人たちの手を取ることだと思うんです。ただ、その人たちのことを僕たちができる限り考えて、やる」
「そこにクリエイティブが入ることがすごく大事だと考えます。自分がいいなと思ったことをそのまま相手に渡そうとしても、うまく受け取ってもらえなかったりする。だからこそ面白いものに変えたり、受け取りやすいものに変える。そうすると、いろんな人が気軽に手に取ることができると思います」
「勝手に」と平田さんはいうけれど、手を取り歩み寄ってもらったおかげで助けられた人は少なくないと思う。ちょっとしたことでも「その人のために」と思える人だったら、同じ気持ちでつくっていけるんじゃないかな。
「そんな思いを軸に、その時代ごとに必要なものをやっていきたいと思っています。いまはウェブや紙が中心だけれど、最近すこしずつ中小企業のブランディングもお手伝いさせてもらっています。10年後、20年後同じことをしているとは限らない。会社がどうなっていくかまで一緒に考えられたらいいですね」
デザイナーの広瀬さんにもお話を聞いてみた。
広瀬さんは入って3年目になる。美大を卒業後、グラフィックや印刷の会社に勤めていたそう。
「小さいころから絵やデザインが好きで、デザインの仕事につきました。そのうちに、どんなビジョンをもって、どういう人たちとやっていきたいかを考えるようになったんです。そんなときにテトルを知って、会社の成り立ちや、根本的な考え方に共感して入社しました」
 入ってみてどうですか?
入ってみてどうですか?「全員で8人の会社だから、自分が考えて決める部分も大きいです。描いたデザイン案がお客さんや社会にとっていいものであるか、プレッシャーを感じることもあります」
Web制作の案件では、まず平田さんがお客さんからお話を聴き、プランニングをする。ディレクター・デザイナー・マークアップエンジニアが話し合ってどんなサイトにしていくかを設計し、デザイナーがデザインを調整、最後にマークアップエンジニアがサイトの構築をしていく。
いちばん目に飛びこんでくるところだから、デザイナーとしてはすごく考えるところだと思う。
「でも、それは自らやっていきたい大変さなので、いいんです」
おっとりしているけれど、はっきりという広瀬さん。テトルは半分が女性の方。みなさんが思いをきちんと伝えるため、フラットに話し合いのしやすい雰囲気があるそうです。
一番印象に残っているという鎌倉の歯医者さんのサイトを見せてもらった。
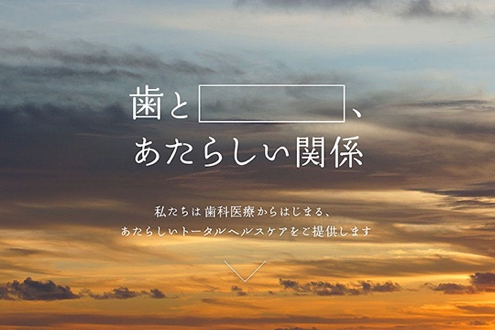 「鎌倉という土地柄、患者さんの生活まで見ているんです。歯という一部分だけじゃなくて、食生活をふくめ、からだ全体を健康にしていこうと考えていらっしゃって。その歯医者さんらしさが伝わるように、鎌倉の写真を使いました」
「鎌倉という土地柄、患者さんの生活まで見ているんです。歯という一部分だけじゃなくて、食生活をふくめ、からだ全体を健康にしていこうと考えていらっしゃって。その歯医者さんらしさが伝わるように、鎌倉の写真を使いました」「やっぱり『よかった』って言ってもらったり、ユーザーさんの反応をいただけたときはうれしいですね」
「僕もこれ印象にのこっているなあ」と、画面を覗き込んだのはマークアップエンジニアの東崎さん。
 「この『歯と〇〇の関係』っていうコピーは僕が考えたんです。歯医者さん自身が新しい軸で健康と歯を見ていらっしゃったので、多様性を表せたらな、と。社内でも評判が良かったし、お客さんにもよろこんでいただけました」
「この『歯と〇〇の関係』っていうコピーは僕が考えたんです。歯医者さん自身が新しい軸で健康と歯を見ていらっしゃったので、多様性を表せたらな、と。社内でも評判が良かったし、お客さんにもよろこんでいただけました」東崎さんは、もともとメッセンジャーをしていた方。独学でコーディングを始め、テトルの雰囲気に惹かれ入社したそう。
今回募集する人は、はじめは東崎さんと進めていくことになります。
「ユーザーが見ているのは、平田さんのプランニングや広瀬さんのデザインではなくて、『サイト』そのものなんです。たとえば、僕の最終的なコーディングが甘くて、読み込みが遅かったり動きが鈍かったり、そういう部分の感触がよくないとユーザーは見てくれなくなって、みんなが頑張ってつくったものをつぶしてしまう可能性もある」
「逆にそこのクオリティを上げられたら、そこまでの流れをさらに拡大できる。責任もあるけれど、やりがいもあります。最終的には自分が届けるんだ、と思っていますね」
つくっている途中で気になる部分があればフィードバックし、お客さんに伝えてやりとりしていく。そのなかで、気づくこともあるといいます。
「はじめてコーディングを担当したお客さんのサイトで、コラムの更新性を高めるためにCMSというシステムを入れました。それまで、コーディングは自分の勉強のためと思う部分もあったのですが、更新するのはお客さん自身なんですよね。その方がどのくらいウェブの知識があるのか、どんな管理画面だったら使いやすいか。お客さんを軸にした見方でシステムをつくるようになりました」
 「実際にお渡しすると、使いやすいという意見と、使いにくいっていう意見があって(笑)。お客さんがフランクにお話ししてくれる方だったので、『ここはよくなったけど、ここは課題があるね』と一緒に改善したりもできましたね」
「実際にお渡しすると、使いやすいという意見と、使いにくいっていう意見があって(笑)。お客さんがフランクにお話ししてくれる方だったので、『ここはよくなったけど、ここは課題があるね』と一緒に改善したりもできましたね」お客さんとの距離が近いぶん、提供できることも、学ばせてもらうこともあるのだと思います。
すると、平田さん。
「それぞれ人間的に考えてもらえたらと思っているんです。できるだけみんな一度はお客さんに会ってお話をして、どんな人でどんな思考をもっているか、ちゃんと相手をみてもらいたい。その上で、お客さんの向かいたい先を理解し、共感し、できることを提供する。おこがましいかもしれないけれど、お客さんと僕たちの関係がパートナーのようになれたらと思います」
「そういう意味だと、よく人のことを考えていたり、おせっかいやきな人だとうまくいくかもしれないですね」
そっと手をとり、その人の思いをかたちにする。できあがったものは自然と誰かの手に渡り、どんどんと広がっていく。
お話をきいた帰り道、そんなイメージを持ちました。
 クリエイティビティをそんなふうに役立てたいと思える方はぜひ一度、鎌倉のテトルクリエイティブを訪れてみてください。
クリエイティビティをそんなふうに役立てたいと思える方はぜひ一度、鎌倉のテトルクリエイティブを訪れてみてください。この環境だから生まれるものが、きっとあると思います。
(2016/9/20 倉島友香)

