※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
「人を育てるというのは、ただ単に何かを教えるということではなくて、能動的な主体者になってもらうということ。関わり合いの中で、変化を引き出していくことが大切なんです」仕事をしていると、理想があってもうまくいかないことや、がっかりしてしまうことってたくさんあります。
一方で、働く中で想像もしていなかった自分の成長を感じることも。
まだ何ものでもない学生のときに、そんな自分と向き合う時間があったとしたら、その後の人生の糧になってくれるように思います。
今回取材したのは、一般社団法人EACH(イーチ)。
 広島で半年間の大学生向けインターンシップのコーディネートをしています。
広島で半年間の大学生向けインターンシップのコーディネートをしています。社会人としてはまだまだ未完成な若者と、企業との関わり合いを通して、それぞれによい変化を起こす。
企業と学生の間に立つコーディネーターを探しています。
特別な経験や知識は必要ありません。
半年間の関わり合いの中で、学生や企業のよりよい変化が引き出せるよう大事に丁寧に関係をつくる。地道な変化を信じ続ける仕事だと思います。
東広島市役所のとある会議室。
この日はEACHと東広島市が主催する学生向けインターン事業の説明会が開かれていました。
 熱心な後輩たちの前で、インターン経験者・松藤くんが、不動産会社でのインターンシップの報告をしてくれます。目標の設定から、そこにいたるまでの苦労、得られた経験の話。学生たちの一生懸命な視線がまぶしい。
熱心な後輩たちの前で、インターン経験者・松藤くんが、不動産会社でのインターンシップの報告をしてくれます。目標の設定から、そこにいたるまでの苦労、得られた経験の話。学生たちの一生懸命な視線がまぶしい。部屋の後ろで話を聞いているのが代表の大森さんです。
 大阪でWEBマーケティングの会社「エピット」を運営しながら、去年の夏に故郷広島でEACHを立ち上げました。
大阪でWEBマーケティングの会社「エピット」を運営しながら、去年の夏に故郷広島でEACHを立ち上げました。大森さんは自分の会社以外でもいくつか役員を務めてきていて、その間企業側としてずっとインターン生を受け入れてきたのだそう。
広島県に依頼されたことがきっかけで、今度はコーディネーターとして学生と企業をつなぐ活動をすることになりました。
まずは大森さんご自身の学生時代の話をしてもらう。
小学校のころから委員会活動が好きで好きで仕方なかったという大森さん。授業には出席しないくせに、委員会活動には顔を出すというちょっと変わった生徒だったとか。
「学年委員や図書委員長、学級代表も。地味ながら自分で何か企画して実行していくのが好きだったんだと思います。」
そんな大森さんを、当時の先生やご両親が否定することはなかったそう。ときには手助けしてくれたり、自由に委員会活動のチャンスを与えてくれた。
専門学校生になった大森さんは、ある企業のインターンを経験する。
「資料を用意したり、自分なりに事業内容を話せるようにしていたら段々と信頼されるようになって。名前だけですけど新規事業室長っていう名刺をもらいまして。初めて給料をもらいました。2万円(笑)」
最初はみんなから“事業室長”ではなく“栄養失調”なんて呼ばれて可愛がられたそう。
若い大森さんは、たくさんの大人との関わりあいの中で社会人として成長していったと言います。
21歳のときには子会社2社の役員をさせてもらうまでに。さまざまな事業を経験したのちに独立してWEBマーケティングの会社「エピット」を立ち上げました。
「ぼくは大学も行ってないし、学校もまじめに行ってたわけではない。けど、自分のできることが伸びる環境をつくってもらってきた。自分で何かを決めていく、動かしていくっていうことに対して、自分でできるんだという実行感を育ててもらえたな」
大森さんがインターンから社会人になって十数年。自身のキャリアがどんどん変わっていく中で、変わらず続けてきたのがインターンの受け入れ。気がつけば関わった学生の数は100人以上にもなる。
 大森さんが人材育成にこだわる理由ってなんなのでしょう。
大森さんが人材育成にこだわる理由ってなんなのでしょう。「ぼくの場合は子どものころから自分自身が活躍する場を見出してもらえた。学生インターンから役員をさせてもらった。たくさんの人に関わって、それがおもしろかったんです」
「1人1人の性質がポジティブに働く環境を、ぼくもつくれたらいいなと思って」
大森さんが“恩送り”としてはじめるインターン事業。
学生と企業、両方の関わり合いがポジティブに影響し合う場をつくりたい。
どのようにしたらそんな場にしていけるでしょう。それが今回募集するコーディネーターの腕の見せどころです。
立ち上がったばかりのEACHを支えているのは、コーディネーターの喜多さん。
コーディネート業務以外にも、企業への営業や学生の募集、研修の手助けなどさまざまな実務を行う、頼れるお姉さんです。
 コーディネーターの仕事は担当企業へのヒアリングからはじまるそう。
コーディネーターの仕事は担当企業へのヒアリングからはじまるそう。半年間で企業が目指すもの、学生のスキルや性質がうまくマッチングするように一緒にプログラムを考えていく。
「企業の大事にしていること、困っていること。ちゃんと言葉を交わして企業と感覚を共有していきます」
「そこから半年間の中でどういう成果を目指しましょう、毎月どんな目標を立てましょうということをディスカッションするんです」
たとえば喜多さんが以前担当した企業では、採用活動をしても人が集まらないという課題があったという。
じっくり話を聞いていくと、どうやら会社のホームページをリニューアルするタイミングらしい。社員紹介のページを設け、会社の魅力が伝わるようなページを学生につくってもらうことを提案したといいます。
このときインターン生として派遣されたのは2人。元気な弾丸娘と、大人しくて几帳面な男の子。
「弾丸娘な女の子がいろんな人に『話し聞かせてくださいよ!』って聞いて回って、実際の入力作業を几帳面な彼がやる。めっちゃ面白いページができたので、社長もすごく喜んでくれましたね」
インターン事業の中で忘れてはいけないのは、就労体験ではないということ。半年という時間の中で、学生たちにはきちんと課題解決を目指してもらう。
そして、そのための環境づくりのために、コーディネーターは各企業の中での人員配置を考えたり、担当者にインターン生との関わり方を伝えたりする。
「本当に何も知らない学生が入ってきて半年間で1人前になるっていうプロセスをその会社で組めたら、新卒も育てられるようになったということ。受け入れ組織自体をよくしていくことも私たちの仕事なんです」
この企業では最初に受け入れを渋っていた社員が、意外と面倒見よく、面白がってくれたという発見もあったそう。
お金が発生しない環境で活き活きと楽しそうに働く学生を見て、ハッと初心にかえる社員たちもいたと思う。
インターン事業は企業にも自信と気づきを与えています。
 そんなコーディネーターの仕事を、喜多さんは6年以上続けてきた。
そんなコーディネーターの仕事を、喜多さんは6年以上続けてきた。EACHへ来る前は、大阪のインターン事業団体や私立大学でコーディネーターをしていたそう。
この仕事を目指すきっかけは何だったのでしょう。
「大学2年生のときに失恋して。何か見返してやりたいと思って長期のインターンをはじめたんです(笑)」
「でも、当時は就活で『あなたは何ができますか?』と聞かれても、何もない状態でした。自分に魅力が全然ないことに気がついて。自信なんて全然ありませんでした」
はじめて参加した長期インターンでは居酒屋の店舗開発に携わった。不動産を探すところから関わったお店でお客さんの笑顔を見たとき、自分が変われたのを感じたそう。
「自信のない自分から、人のために役に立てるっていう経験をさせてもらって。自信を持つことを誰かに知ってもらえたら嬉しいなって思うようになりました」
最初の就職では人材派遣の営業をしていたけれど、やはり教育の仕事がしたいとインターンの団体に入ったそう。
そんな喜多さんは、学生とはどんな関わり方をしているのでしょう。
「学生とは単にインターン生とコーディネーターという関係じゃなくて、その子がこれまでの人生で大事にしてきたこととか、これからどうしていきたいのかっていうことを最初の面談で深く話をして」
「関わる中でコンプレックスになる経験だったりとか、こんなつらい経験をしたということも打ち明けてもらえるような。そんな関係性をつくっていくのが大事かなって思っています」
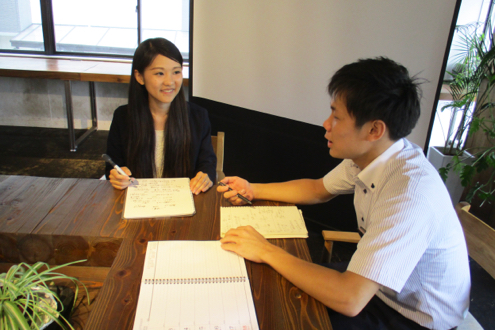 ときにはお姉さんのように、ときには担任の先生のように大事に学生の面倒を見る。
ときにはお姉さんのように、ときには担任の先生のように大事に学生の面倒を見る。毎日の日報を確認してコメントをしたり、元気のなさそうなときにはすぐに連絡をしたり。まだ不安定な学生たち一人ひとりが最大の力を発揮できるようにコーディネーターは応援し、働く環境を整える。
自分でもできるんだという自信は、きっとその子のこれからの人生を支えてくれると信じて。
「私の夢の一つが今年の秋に叶うんです」
夢?
「インターン生の結婚式に出席するっていう夢。この仕事の1つの指標にしていて」
そう話す喜多さんは、本当に嬉しそう。こちらまで笑顔になる。
「半年間で終わりではなくて、その後もずっと関わっていって、その子の人生の一助になれればと思っています。インターンうまくいったね、だけではない。本当にその子がどう生きていきたいのかというところまで真剣に考えていけたらと思います」
もっと深く話ができればと、キャリアカウンセラーの勉強もしたのだとか。
 新しく入る人には経験は必要なのでしょうか?
新しく入る人には経験は必要なのでしょうか?「今回はそんなスキルフルな人は求めていなくて。学生を相手にしてますから変化に柔軟に対応できたり、想いはあるんだけれども状況によって可変できたりする人のほうがうまくいくかなと思っています」
EACHは広島ではじまったばかり。まだまだ固まっていない部分も多そうだから、柔軟さが肝心なようです。まずは喜多さんの元で学ぶところから始まるそう。
最後に、コーディネーターに一番大事なことを聞いてみました。
「中には、この子もう無理なんじゃないかとか、この受け入れ担当者なんなのっていうこともあるんです。それでもこちらが関わり方を変えていったら、もしかしたら変わってくれるかもしれないなって諦めずに信じ続けること」
信じ続けること。
「それしかないです。途中で学生が辞めてしまったり、失敗してしまうときはすごい徒労感があるんで辛いんですけど。変わっていく学生さん、企業さんもあったりするのでね。やっぱりそれを信じてやるしかないかなと思いますね」
簡単なことではないかもしれません。
それでも企業や若者の未来がよいものになるように、変化を信じ続ける。
想いを持って働く人をお待ちしています。
(2016/11/11 遠藤沙紀)

