※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
奈良・曽爾村(そにむら)。この村には「ぬるべの郷(さと)」という、少し変わった呼び名があります。
「ぬるべ」は漢字で書くと「漆部」。漆塗り職人のことです。
実は、日本の漆文化発祥の地と言われているのが、この曽爾村なんだそう。
現在も村の観光パンフレットやWebサイトのほとんどに「ぬるべの郷」の文字が載っています。
 けれども、実際に漆産業や漆文化が栄えていたのは遠い昔のこと。平安時代の文献のなかで、すでに古(いにしえ)と表現されているほどです。また、戦後の植林政策によって漆は大量に伐採され、代わりに杉やヒノキが植えられました。
けれども、実際に漆産業や漆文化が栄えていたのは遠い昔のこと。平安時代の文献のなかで、すでに古(いにしえ)と表現されているほどです。また、戦後の植林政策によって漆は大量に伐採され、代わりに杉やヒノキが植えられました。本当にこのまま、曽爾村の漆文化は廃れていっていいのだろうか?
胸を張って「ぬるべの郷」を名乗りたい。
そんな想いから11年前に立ち上がったのは、曽爾村塩井地区のみなさん。25名のメンバーで「漆ぬるべ会」を結成し、漆の植樹や育成、漆を使った工芸品の製作に取り組んできました。
今回は、この「漆ぬるべ会」とともに曽爾村の漆文化の復活に向けて活動する地域おこし協力隊を募集します。
正直に言うと、協力隊の任期中の3年間では、あまり大きな変化は起こせないかもしれません。
この村で送る日々をじっくりと味わいながら、未来の世代を見据えた視点で関わる人を求めています。
曽爾村は、近鉄名張駅、もしくは近鉄榛原駅が最寄りの駅。東京からだと、いずれの駅も3時間半ほど。そこから曽爾村に向かうには、バスでさらに1時間弱移動することになる。
今回は名張駅からバスに乗り、なんとなく最後列の席に座った。車内には、お母さんとそのお子さん、高校生、おばあちゃん、運転手さん、自分の6人が乗っている。
トンネルをくぐったかと思えば、川沿いを走ったり。バスはより自然の濃いほうへと進んでいく。
 曽爾村役場前で降りたのはぼく一人だけだった。
曽爾村役場前で降りたのはぼく一人だけだった。少しあたりを散策してから、時間を見計らって建物のなかへ。
漆ぬるべ会会長の松本さんが迎えてくれた。
 「バス、貸し切りやったでしょう?」
「バス、貸し切りやったでしょう?」5人ほどお客さんがいたことを伝えると、少し驚いた様子の松本さん。
「公共交通機関の便がよくないから、使う人も少ないんですよ。マイカーなら、大阪まで1時間半で行けるんですけどね」
コンビニまで30分。通学の送り迎えに、往復1時間を3回繰り返す人も。
都会とは時間の流れ方が根本的に違うような気がする。
 じっくりと長い年月を積み重ねてきた大地や、その間を縫うように流れる川、繁る木々。人も土地もおおらかで、のんびりというよりはパワフルな印象を受ける。
じっくりと長い年月を積み重ねてきた大地や、その間を縫うように流れる川、繁る木々。人も土地もおおらかで、のんびりというよりはパワフルな印象を受ける。「ここらは『ぬるべの郷』と言われてますけど、漆の木もなければ職人もいない。それでいろいろ書物を調べたら、川向かいの塩井っていう地区が漆の発祥の地であることがわかりましてですな」
「そこに人工林も植わらない痩せた土地がありました。以前は花屋さんが借りられてたんですけど、そのご主人が亡くなられたりして、管理ができないということで。じゃあ漆を植えたらどうや?とはじまったのが11年前ですかね」
塩井地区の住民を中心とした25名で「漆ぬるべ会」を結成。専門家を招いて調べると、村内には11本の漆の木が点在していることが明らかになった。
 そこで松本さんたちは、現存する漆の根っこの一部を切り取り、畑で育てる「分根」という方法で苗木をつくり、山に植えることにした。
そこで松本さんたちは、現存する漆の根っこの一部を切り取り、畑で育てる「分根」という方法で苗木をつくり、山に植えることにした。「平城宮遷都1300年のときには、曽爾でも1300本の漆の苗木を植えました」
「最初は簡単な気持ちでおったんですよ。漆は雑木やから、どこへ植えても勝手に大きくなるやろってね」
ただ、そう簡単には育ってくれなかった。
「鹿に葉っぱを食べられたり、夏場に枯れてしまったり。思いのほかデリケートやった」
限られた予算のなかで、ネットで囲ったり、別の場所に植えてみたりと、試行錯誤を繰り返す。
次第に、自生する漆は川の近くの土手に多いことから、漆を育てるには一定の湿度が必要なことがわかっていった。
 「何事もやってみんとわかりませんね。やってみれば、それなりに苦労があるわけやから」
「何事もやってみんとわかりませんね。やってみれば、それなりに苦労があるわけやから」一昨年からは、岡山県の職人さんに指導をあおぎながら、柿の葉を使った器づくりに挑戦中だ。
柿の葉に和紙を何枚も貼り重ね、漆を塗ることで耐久性と独特の光沢が出る。シンプルなようで技術の求められる作業だという。
 ほかにも、村民向けの葉の器づくりワークショップや、京都の美大生と連携した漆作品の製作・展示など、意欲的に活動を展開している漆ぬるべ会。
ほかにも、村民向けの葉の器づくりワークショップや、京都の美大生と連携した漆作品の製作・展示など、意欲的に活動を展開している漆ぬるべ会。今回はなぜ協力隊を募集するのでしょうか?
「やっぱり、高齢化が進んできとるんです。気持ちがあっても体がついていかないという部分がありますんで。若い方になんとか意志を継いでいただきたいという想いでいます」
漆が成木になるには、少なくとも15年はかかると言われている。しかも、一本の木からとれる漆の量は200ccほど。傷をつけて樹液を採取した漆は育たなくなるので、一度切り倒し、出てきた芽をまた15年かけて育てることになる。
産業としてのサイクルをつくるには、膨大な時間がかかる。一生をかけても、「ぬるべの郷」の復活を見届けられないかもしれない。
「だからこそ、漆が好きな人に来てもらいたいですね」
そう話すのは、曽爾村役場企画課の平畠さん。軽快な口調が印象的な方。
 「漆芸職人の方とか、自分の作品づくりをしながら葉の器づくりしてもろてもええですし。任期が終わる三年後を考えたら、葉の器一本では大変やろうしね」
「漆芸職人の方とか、自分の作品づくりをしながら葉の器づくりしてもろてもええですし。任期が終わる三年後を考えたら、葉の器一本では大変やろうしね」今は地区の代表である総代さんの納屋を借りて製作場所にしているけれど、3月末には空き家を改装した工房が完成予定とのこと。製作環境をさらに整えていくという。
とはいえ、漆を扱った経験のない人がほとんどでは?
「経験がなくても大丈夫ですよ。漆の国内生産量の7割を占める岩手県二戸(にのへ)市にも勉強に行けますし、葉の器の職人さんのもとで研修したり、曽爾村も加入している『西日本漆を守る会』での交流から学べることも多いと思います」
 役場の担当者である平畠さん自身、このプロジェクトに関わるうちにいつのまにか詳しくなっていたそう。「漆は湿気がないと逆に乾かないんです」「身近なものだとマンゴーも漆科ですよ」と、いろいろ教えてもらった。
役場の担当者である平畠さん自身、このプロジェクトに関わるうちにいつのまにか詳しくなっていたそう。「漆は湿気がないと逆に乾かないんです」「身近なものだとマンゴーも漆科ですよ」と、いろいろ教えてもらった。「漆って、基本的に分業で。掻く(漆の木から樹液をとる)人、売る人、塗る人と分かれているんです」
「ただ、理想を言えば、1から10までやれる人がベストですねん。植樹からはじまり、掻いて、その漆で作品をつくって、最後は売ると。そこまでいけたら完璧ですよね」
人手が足りない、というほど回転が求められる状況なわけではない。どちらかといえば、全工程に関わることで漆の活かし方が見えてくるように思う。
たとえば、伝統工芸や葉の器以外の使い道を考えるとか。防腐・防水効果のある天然塗料として、現代の日用品に取り入れていくとか。
「漆は英語で“JAPAN”。漆いうたら日本やっていうことで、欧米中心に海外でものすごい人気があるんですよ。つまり海外展開も考えられますよね」
まだ先の話かもしれないけれど、海外に広がっていく可能性はある。そこまで先の視点を持って試行錯誤したい人にとっては、ここはきっと楽しい環境になるはず。
続いて、すでに協力隊として活動している山本さん(写真左)、大西さん(写真右)にも話を聞く。おふたりとも奈良県の出身で、昨年の4月から曽爾村にやってきたそう。
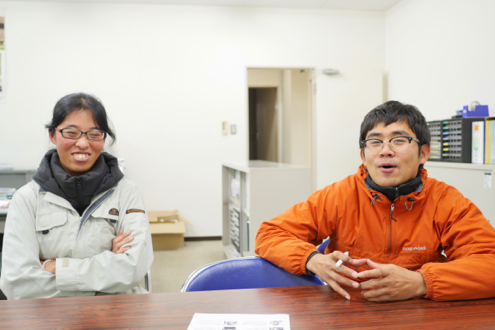 現在曽爾村には12名の協力隊がいて、それぞれの担当を持っている。
現在曽爾村には12名の協力隊がいて、それぞれの担当を持っている。山本さんの担当はほうれん草。寒冷な気候の曽爾村では、冬場の寒気にさらされ、甘みの増したものを「寒熟ほうれん草」として売り出している。
「もともと奈良が好きで。寒熟ほうれん草は曽爾村でしかつくれないので、これをつくれば何か奈良に貢献できるかしら、と思って来たんです」
小学校の遠足や、大人になってからも星を見るため、友だちと曽爾村を訪れていたという。
移り住んでみて、曽爾村ってどんなところですか?
「村の人たちが、曽爾村を好きなんですよね。若い世代がどんどん出ていくって言うんですけど、20~30代の人でも最寄りの榛原とか名張あたりに住んでいて、祭りのときに帰ってくるとか。曽爾村役場で働いてる人も多いです」
たしかに、村の方々に曽爾の魅力を聞いてみると、最初は「ずっと住んでるからわからん」と言いつつ、「夏はクーラーがいらんよね」「星座がわからんくらい星が見えるよ」「自然と人情やね」と、話したいことが次々と出てくるのを感じた。
 「あとは一度打ち解けたら我が子のように接してくれる人が多い印象はありますね。わたしも今お世話になっている農家さんにすごくかわいがってもらっているので」
「あとは一度打ち解けたら我が子のように接してくれる人が多い印象はありますね。わたしも今お世話になっている農家さんにすごくかわいがってもらっているので」隣で聞いていた大西さんも、地域の人との関わりが印象的な1年だったそう。
「持て余すぐらいの野菜をくれるんですよ。年始には、『お餅ついたから食べて』ってくれたり」
「協力隊って、地域の人を巻き込むから地域おこし協力隊なのであって、別にひとりのスーパーマンじゃない。村の人と仲良くできんかったら、どんだけ能力に長けていようがだめだと思うので。第一に溶け込める人じゃないですかね」
想いはあるけれど、足りてないことがあるからこその協力隊。そこをうまく補ってあげることがまず大切だという。
 大西さんが担当するのは、ブランド米と薬草。昨年7月に立ち上がった農林業公社の仕事に携わっている。
大西さんが担当するのは、ブランド米と薬草。昨年7月に立ち上がった農林業公社の仕事に携わっている。「農協経由だと、いくら曽爾村の米がおいしかろうが“奈良県の米”としてしか扱われないので、収支は結局マイナスになってしまいます」
「高付加価値の米をつくることで、魅力ある仕事として担い手も増えていくんじゃないかと。そんなことを思ってやってますね」
昨年の国際コンクールでは、「曽爾米」が特別優秀賞を受賞。質が高くていいものはたしかにあるのだから、その価値をいかに伝えるかが大事なのだと思う。
それは漆にも言えること。一般的には「かぶれる木」だったり、製品にしても「高級」というイメージがあるなかで、どうやって価値や魅力を伝えていくか。
「もともとサラリーマンやったんで、やることなすことはじめてのことばかりで。大変ですけど、やりがいはある仕事だなと思ってます」
担当はそれぞれ違えど、12名の協力隊がすでに活動していることは心強い。月に一度、村長や協力隊が参加する報告会もあるので、悩みやノウハウも共有しながら取り組んでいけるはず。
 漆ぬるべ会の夢は、「奈良県内の国宝級の建造物に曽爾村の漆が使われること」。
漆ぬるべ会の夢は、「奈良県内の国宝級の建造物に曽爾村の漆が使われること」。まだまだ先の話かもしれないけれど、夢を語るみなさんは楽しそうに瞳を輝かせていました。
住むにしても本当にいいところです。興味が湧いた方は、ぜひ一度訪ねてみてください。
(2017/2/7 中川晃輔)

