※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
「単に学力だけをつけて進学するのではなくて。自ら課題を発見したり、まわりの人と協力しながら問題を解決したり。社会に出てから生きていくための力を育む学びの場にしたいんです」スターシャル教育研究所は、小学校から高校まで一貫して子ども達に関わりながら教育支援を行なっている会社です。
 たとえばゲーム感覚で楽しく学び合うことができる教育教材の開発や、名古屋市や高浜市と連携した学習支援事業の実施など。
たとえばゲーム感覚で楽しく学び合うことができる教育教材の開発や、名古屋市や高浜市と連携した学習支援事業の実施など。これまでの教育制度の枠組みにとらわれない、新たな視点を持って事業の幅を広げている。
進化を続けるこの会社では、社長の右腕として将来の経営陣を担うような人を探しています。
教育業界での経験は問いません。まずはぜひ、スターシャルのことを知ってください。
名古屋駅から10分ほど電車に揺られ、鶴舞駅に到着。ここから歩いてさらに10分ほどのビルにスターシャルの事務所がある。
迎えてくれた林さんに、まずはこれまでの経緯について聞いてみます。
 スターシャルは、林さんが大学在学中に起業。実は設立して6年目と、比較的若い会社だ。
スターシャルは、林さんが大学在学中に起業。実は設立して6年目と、比較的若い会社だ。「大学は工学部で、教育に興味があったわけではないんです。事業を自分でまわしてみたいっていう思いと、近所で空いている部屋があることが重なって、学習塾ならできるんじゃないかとはじめたのがきっかけです」
手作りのチラシを配布して募集すると、3人ほど生徒がきた。けれどもみんな、無理矢理連れて来られているような感じで、学習意欲を感じられなかった。
「そういう子たちに、一方的に勉強を教えるのはどうなのかなって疑問に思いました。結局、いい大学に行ければいいと一方的に教え込んでいるのが、今の教育の現状だなと」
「それよりも、学びがいかにおもしろいかを知ることで、自分から学ぼうという気持ちを育むほうが大事なんじゃないかって思ったんです。それはきっと、大人になってから社会で生きていくためにも必要な力になっていくはずだから」
 調べてみると、日本にはそういう教育を実施している場所があまりない。ならば自分でつくろうと林さんは考えた。
調べてみると、日本にはそういう教育を実施している場所があまりない。ならば自分でつくろうと林さんは考えた。まずは参加しやすく、学びやすい雰囲気をつくるために何ができるだろう。考えた末、教室ではなくカフェを借りて勉強するスタイルを思いつく。
「子ども同士が互いに教えあい、刺激しあうことでもっと自分の得意なところを伸ばそうと思うようになるんじゃないかと考えたんです」
ときには勉強に関係のない話もしながら関係を深め、学びの楽しさを体感してもらう。するとだんだん、不登校の子や発達障害を抱える子も「そういう場所なら行きたい」と通ってくるようになった。
さらに、もっとおもしろく学び合えるようにと開発したのが「モンスタークエスト」というプログラム。まるでRPGゲームのように、わからない問題をモンスターに見立て、仲間と一緒に倒すとシールがもらえる。
 新感覚の教育支援教材として、小学生を中心に人気に。
新感覚の教育支援教材として、小学生を中心に人気に。その後は、放課後に学校の教室を活用して、異学年の子どもたちや地域の方との交流を図る名古屋市の事業「トワイライトスクール」の公募に手を挙げたことをきっかけに、行政との連携も深めていく。
「発達障害を持つ子が多く通っていたことから、デイサービス事業を開始しました。不登校の子も高卒の資格がとれるように、通信制高校とも連携して。学校などの公教育で取りこぼされていく部分を補っていたら、自然と事業が広がってきたような感じです」
こうして聞いていると、順調に事業を拡大してきたようにみえる。けれども、新しい仕組みを広めていくには壁も多くあったと話します。
「保護者にとっては、まだまだ“進学のための勉強”が常識で。将来子どもたちがちゃんと生きていけるように、っていうところにはなかなか目が向かないし、お金を払わない。難しいなと今も感じています」
「でも行政との連携や地域に密着してきたことで、より信頼してもらえるようになって。地域のお祭りや飲み会にもよく誘っていただくんです」
地域に根ざして自ら行動し、垣根を越えて人と関わろうとする林さんの姿勢が、まちの中で密なつながりを生んでいる様子。
これまで思いを自分の力で形にしてきた林さん。そんなスターシャルは、いま第2創業期を迎えています。
ここで事業統括担当の大西さんも、話に加わる。
 リクルートでコンサルティング営業として働いた経験を持ち、現在はフリーランスとして活動する傍らスターシャルの経営にも関わっています。
リクルートでコンサルティング営業として働いた経験を持ち、現在はフリーランスとして活動する傍らスターシャルの経営にも関わっています。林さんを起業当時から支える、司令塔のような存在。ときには厳しく、自分の思いや考えをまっすぐに伝える熱い人です。
外からの視点も持つ大西さんには、この会社はどんなふうに見えているんだろう。
「社員の目線が、まだ子どもたちの先にある社会っていうところまでいっていないと感じています。そこにベクトルを向けていくためにも、教育者じゃなく事業者の視点を持った人が必要ですね」
社員は15名。アルバイトなど事業に関わるスタッフを含めると、100名以上が関わる大所帯だ。にもかかわらず、急激に事業が拡大してきたこともあって、現在は働く人のマネジメントや事業運営・企画ができるスタッフがほとんどいない状態だという。
新たな視点で社会のニーズを事業化したり、今の事業の問題点を改善したりしていく人が求められている。
 求められていることのハードルはかなり高そう。素直にそう話すと「でも、うちだからこそできることがある」と大西さん。
求められていることのハードルはかなり高そう。素直にそう話すと「でも、うちだからこそできることがある」と大西さん。「スターシャルでは、小学生だけ、高校生だけ、とある一定の時間だけ関わるのではなく、小学校から高校まで一貫して教育を切り口として社会にインパクトを与えていけるんです。かつ、行政と民間のパイプ役というか」
行政と民間のパイプ役。
「たとえば、名古屋市から受託した学習支援事業は生活保護を受けている家庭や一人親家庭など、塾に通えない子どもたちを対象にしています。その子たちが成長して、もしも高校に進学できなかったら、うちは通信制高校の事業もしているので面倒をみられる。事業を相互につないで、良い化学反応を起こせるんです」
 なるほど。長いスパンで関わりながら、ゆくゆくは日本の教育という大きな流れを変えていける仕事かもしれない。
なるほど。長いスパンで関わりながら、ゆくゆくは日本の教育という大きな流れを変えていける仕事かもしれない。難しいからと諦めるのではなく、ビジネスとしてどう成立させていくか考える。そういう視点があれば、教育業界での経験がなくても、これまでのキャリアを活かしながら働くことができる環境だと思う。
お二人に、これから会社をどうしていきたいか聞いてみる。
「市を丸ごと、教育という観点でサポートできる会社になっていけばいいなと思っています。名古屋市以外の地域でも、スターシャルの教育モデルを展開していきたいですね」と大西さん。
取り組みの効果は、着実に実績として表れている。
トワイライトスクールは、現在4校を担当。そのうち2校では文部科学大臣賞も受賞した。全国から視察団が訪れることも増えてきている。
大西さんの言葉に頷きながら、林さんも言葉をつなぐ。
「学校にもアプローチできる僕らの仕事は、公教育が変わっていくきっかけにもなると思うんです。今後はさらに子どもたちが学びたいと思える場づくりや、社会で生き抜く力をつけるためのコンテンツを充実させて発信していきたいです」
実際に働いている人にも話を聞いてみます。
事業統括マネージャーの浅野さん。
 トワイライトスクール事業と、高浜市の学習支援事業を統括しています。
トワイライトスクール事業と、高浜市の学習支援事業を統括しています。新しく入る人は名古屋市の学習支援事業と通信制高校、放課後等デイサービス事業を統括していく予定なので、今回募集する人と一番近い立場で働いている人です。
前職では学習塾の教室長として働いていた。なぜスターシャルに入社したのだろう。
「日本の教育は、暗記をすることに大半の時間をかけていると思うんです。でも今は、スマートフォンがあれば子どもでもすぐに調べられる。だったら暗記なんて意味ないんじゃないかって、自分の教えていることに疑問を持ったんです」
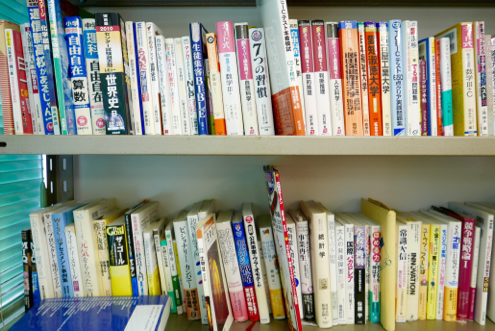 「もっと子どもたち自身のためになる教育ができないかなと思って転職を決めました」
「もっと子どもたち自身のためになる教育ができないかなと思って転職を決めました」マネージャーになって、半年ほど。まだ大きな実績は残せていないと話すけれど、どんなことから仕事をはじめたのでしょうか。
「まずはトワイライトスクールで働いている人たちと、ひとりずつ話をすることからはじめました。 何を思って仕事をしてるのか、何を目指しているのか。現状の仕組みを変えていくために、働く人たちの気持ちをわかった上でやりたかったんです」
新しく入る人も、浅野さんのようにまずは謙虚に現場の人の話を聞くことが重要だと思う。
いきなり自分の主張をしても聞いてもらえないことが多いし、いろいろな人の視点から話が聞けると、抱えている課題が明確になってくる。
「話を聞くことで、もっとみんなが生き生きと働けるような気がしたんです。だから会社の基盤を整えていこうと思っています。マニュアル化が全部いいとは限らないですけど、そういうのも必要かなと」
「たとえば、新しく入る人が増えていくと思うので研修制度をつくること。あとは教室ごとに授業の方向性がバラバラになってしまっている気がするので、何を目的とするのか意識を統一することもしていきたいですね」
現場の人たちが自分を信頼して話してくれることや、事業の根幹にあたる部分に関われることがうれしいと話す浅野さん。
一方で、大変なこともあれば教えてください。
「経営陣と現場の板挟みになる仕事なので、どこまで双方を納得させられるか。期待も不満も自分が背負っていくので、今後は大変になってくるんだろうなと感じています」
「でも自分で考えたことや意見は通りやすいんです。事業全体の年間計画や、採用活動とかも自分に任せてもらっていて。だから自分たちで考えて会社をつくっていけるのがすごく楽しいです」
ほかにも、職員に参加してもらう研修を決めたり、ときには子どもたちが勉強に興味を持つような企画を考えて、実践することも。
与えられるのを待つのではなく、自分で仕事をつくっていく感覚だという。
「組織の仕組みを整えられたら、モンスタークエストのようなコンテンツ開発にも関わりたいです。昨日も家でずっと案を練っていたんですけど、考えるのもおもしろい。学校教育の中で、今の勉強法の代わりに提案できるくらいのものがつくれたらいいですよね」
 自分の思いや考えを実際に形にするって、すごくエネルギーがいること。でもだからこそ、取り組むだけの価値もある。
自分の思いや考えを実際に形にするって、すごくエネルギーがいること。でもだからこそ、取り組むだけの価値もある。ほどほどではなく、とことんやってみたいという人が、自分を活かせる職場だと思います。
まずは名古屋から、いずれは全国に向けて。スターシャル教育研究所と一緒に、自分も挑戦していきたいという方をお待ちしています。
(2017/3/3 並木仁美)

