※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
NPOというとどんなイメージがありますか?いいことをしているとか、ボランティアとか、もしかしたらそんなイメージがあるかもしれない。
だけど、事業を安定的・継続的に運営していくためには、資金が必要になる。そこは会社と同じで、NPOにもビジネスが必要です。
 今回は、高校生のキャリア学習プログラムをはじめ、子ども・若者への教育活動に取り組む特定非営利活動法人「NPOカタリバ」で、活動を広めながら寄付を募り、ビジネスとして支えていくスタッフを募集します。
今回は、高校生のキャリア学習プログラムをはじめ、子ども・若者への教育活動に取り組む特定非営利活動法人「NPOカタリバ」で、活動を広めながら寄付を募り、ビジネスとして支えていくスタッフを募集します。サブカルチャーの中心地である高円寺駅。中央線の高架下に並ぶ商店街を進んでいく。ほどなくしてNPOカタリバのオフィスが入る「高円寺コモンズ」が見えてくる。
カタリバが設立されたのは、今から14年前のこと。代表の今村久美さんが「高校生が将来を考えるときに背中を押されるようなきっかけをつくりたい」という想いから立ち上げた。
大学生などボランティア・スタッフが高校生と対話する、ワークショップ型の授業「カタリ場」を首都圏を中心に開催したり、東日本大震災で被災した地域を拠点に放課後学校「コラボ・スクール」を運営している。
活動は、だんだんと全国規模へと広がってきた。その活動資金の一部は、企業や一般の方からの寄付で支えられている。
 寄付を集めるためには、まずは活動に共感してもらうこと。カタリバのファンを増やすこと。
寄付を集めるためには、まずは活動に共感してもらうこと。カタリバのファンを増やすこと。それが、広報・ファンドレイジング部のスタッフの仕事になります。
まずは、4年前からカタリバで働き、現在は広報・ファンドレイジング部のマネージャーを務める山内さんに話を聞いてみる。
山内さんは、マーケティングを中心に、営業や管理など全体の仕事を見ている。
山内さんとカタリバの出会いは今から10年前のこと。
学生時代、ビーチラグビーというスポーツに熱中していた山内さん。人ってどうしたらモチベーションが生まれるんだろう、という興味からカタリバのことを知り、ボランティアとして活動に参加するようになる。
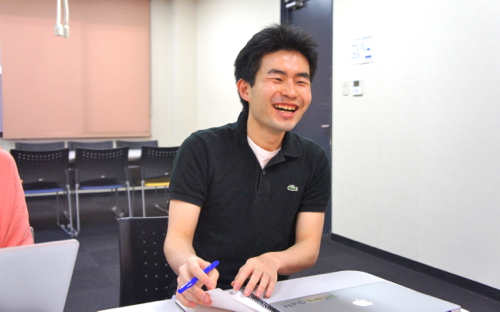 「最初は高校生と上手く話せなかったりしたのですが、僕たち大学生が『高校時代はこんなことで悩んでたよ』と話をはじめると、目の色がパッと変わる瞬間があって。『実は俺、行きたい大学があるんだ』とか『野球部で甲子園目指してるんです!』と、心を開いてくれたりする。それがすごく嬉しくて、続けていました。」
「最初は高校生と上手く話せなかったりしたのですが、僕たち大学生が『高校時代はこんなことで悩んでたよ』と話をはじめると、目の色がパッと変わる瞬間があって。『実は俺、行きたい大学があるんだ』とか『野球部で甲子園目指してるんです!』と、心を開いてくれたりする。それがすごく嬉しくて、続けていました。」そんなとき、ふと周りを見渡してみると、カタリバで”働いている”社会人たちがいる。
自分たち大学生はボランティアだし、まさか高校生からお金をいただいているわけでもない。カタリバの活動はどんな風に成り立っているんだろう?
疑問に思った山内さんは、カタリバの創業メンバーに質問してみた。
すると、返ってきたのは、カタリバだけでは十分な収入を得ることは難しく、アルバイトをして生計を立てているという答えだった。
こんなに良いことをしているのに、どうして活動に専念できないんだろう?
強く疑問に思った山内さん。どんなにいいことをしても、お金がしっかり回っていく仕組みがないとダメなのだと、気付かされた。
 「いつかカタリバのために何かしたい!」そんな想いを心の片隅に置きつつも、大学卒業後は一般企業への就職を選んだ。
「いつかカタリバのために何かしたい!」そんな想いを心の片隅に置きつつも、大学卒業後は一般企業への就職を選んだ。大手電機メーカーを経てベンチャーの広告代理店へ。仕事は楽しかったけれど、東日本大震災が起こった直後のタイミングで、カタリバから声をかけられる。
売れる仕組みをつくるマーケティングを実務で学んできた山内さん。今なら役に立てるかもしれない!と、カタリバへ戻ってきた。
実際は、どんな業務をしているんですか?
「テレビや新聞、ネットの記事で活動が取り上げられて、そこから寄付のお問い合わせがくることもあれば、検索エンジンやソーシャルメディアでWebサイトを見つけてお申込いただくこともあります。企業から問い合わせをいただいたら、通常の営業と同じように訪問することもあります。」
カタリバのサイトを経由してだけでも、月に平均100件以上の寄付の申込みや問い合わせがあるそうだ。
そこまでの問い合わせを集めるためには、メディアや自分たちのサイトを使ったしっかりとした広報が必要になる。だから、多くのNPOやNGOでは、広報とファンドレイジングが一体となっているそうだ。
「最近では、コラボ・スクールに通う高校生たちが、町の復興のために自分たちも何かしたい!と『My Project』というものをはじめました。例えば、子どもたちの遊ぶ公園が無いので公園を作りたいとか、町の人の笑顔を撮影して写真集をつくりたいとか。そういう高校生たちのアイディアを1つずつプロジェクト型学習として紹介するとともに、そのために必要な資金をファンドレイジングするという取り組みです。」
 多くの人に知ってもらうために、サイトにどんな情報を載せるのか、どんな風にソーシャルメディアを使うのか、それからマスコミ対応など、色々な伝え方を考えていく。
多くの人に知ってもらうために、サイトにどんな情報を載せるのか、どんな風にソーシャルメディアを使うのか、それからマスコミ対応など、色々な伝え方を考えていく。「寄付はお金をいただいても、こちらからお返しできるものは、商品のように形があるわけではない。あるとしたら、そのお金が社会のために役立ったという、目に見えない実感なんです。」
「だから、寄付をいただくまでももちろんですが、寄付をいただいたあとも『学生たちがあなたの支援によってこんな風に成長しています』ということをちゃんとお伝えすることも心がけています。」
もちろん経営のための資金になるわけだから、数字目標もあるし毎週の会議では「達成」「未達」といった話もする。
けれど、一番大切にしているのは、支援者さんに「応援したい」と自然に思ってもらえるような信頼関係をつくること。
寄付のお問い合わせの窓口を担当している、堂道(どうみち)さんにも話を聞いてみた。
 堂道さんは、証券会社や金融会社を経て3年前にカタリバに入社した。
堂道さんは、証券会社や金融会社を経て3年前にカタリバに入社した。転職活動中にたまたま新聞記事でカタリバのことを知り、プログラムに強く共感。次の日には履歴書を送付したそうだ。
「教育やボランティアには縁がなかったのですが、これまで培ってきたキャリアを生かして、何か一端を担えればいいなと思ったのがきっかけです。」
入ってみてどうでしたか?
「みんな楽しんで仕事をしているな、というのが入社初日から伝わってきました。こうしたい!と思ったらそれを伝えて、OKだったらすぐに形にしていける。新しいチャレンジがしやすいことも魅力的です。」
 思い立ったらすぐ行動。自身をそんなタイプだと話す堂道さんには、とても向いている社風なのかもしれない。
思い立ったらすぐ行動。自身をそんなタイプだと話す堂道さんには、とても向いている社風なのかもしれない。カタリバの雰囲気やチームワークも好きだけれど、なによりも大切にしているのは、支援をしてくれる方々とのやりとりだそうだ。
「寄付をいただいて『ありがとう』という言葉を1日に何回も言っているのですが、最近、ありがとうという言葉は、言われた人よりも言う人のほうが心に響くのかな、ということを感じつつ仕事をしています。」
ときには、問い合わせとともに温かいメッセージをいただくことがある。
「こんなに人の善意に触れられる仕事ってないな、と思うんですよね。だから、ありがとうと言っている自分の言葉が、自分にも響いてくるんです。」
「ありがとう」が作業になってしまうような仕事もあると思う。だけど、それが心に響くということは、本当に感謝の心を持って接しているからなのだろうな。
そうやって支援者の方ひとりひとりに向き合っていけるのは、素敵なことですね。
「ただ、信頼関係を築くための日々の仕事は、とても地味なものです。資料の用意とか、既存の支援者さまの支払い方法をシステム会社に問い合わせるとか。それから、クレームの対応もあります。本当に、細かいことの積み重ねですね。」
大企業と違い、しっかりとしたインフラが整っているわけじゃない。だから、日々少しずつ改善していく。理想を追うとともに、”地固め”も必要。
そして、その部分をまさにつくっているのが、低引(そこびき)さん。
低引さんは経営管理本部で、カタリバの人事・労務・経理・システムなどの、バックオフィス全般を一手に引き受けている。
 もともと学校で行われる以外の教育のあり方に興味を持ち、病児保育に取り組むNPO法人フローレンスに新卒で入社。
もともと学校で行われる以外の教育のあり方に興味を持ち、病児保育に取り組むNPO法人フローレンスに新卒で入社。そこで5年間バックオフィスの業務を担当していた経験を生かし、その後独立する。その最初のクライアントがカタリバだった。
はじめは3ヶ月の契約だったけれど、気付けば今年で5年目になる。
話を聞いていると、すごく筋の通っている方だし、自分で事業を立ち上げる力も持っているのだろうなということを感じる。それに、社会課題を解決する仕組みについて海外の大学院で学びたいという夢も持っているそうだ。
それなのに、今こうしてカタリバで働いているのはどうしてですか?
「僕はカタリバに、2010年12月からいるのですが、その3ヶ月後にちょうど東日本大震災が起こったんですね。そこからの動きが素晴らしかった。カタリバOB・OGの呼びかけで、首都圏3ヶ所で募金を募ることになったのですが、そこに今までカタリバに関わってきたスタッフたちが100人くらい集まって、3日間で500万円もの金額を集めたんです。」
「この現場こそ、カタリバそのものだな。災害や社会課題を目の前にして、社会に必要なことを自分で考え、行動する人たちが、カタリバを通じて輩出されていると感じたんです。もう、留学してるどころじゃないぞ、と思って。今は、もっとカタリバのためにできることをしていきたいと思っています。」
 話を聞いたあとは、スタッフの横井さんにオフィスを案内してもらった。
話を聞いたあとは、スタッフの横井さんにオフィスを案内してもらった。横井さんは、カタリバを含めて5つの団体が共同で設立した、被災地の子どもを支える「ハタチ基金」の事務局を担当している。
2階のオフィスには真ん中に大きなテーブルがあり、席はとくに決まっていないそうだ。
奥には大学生のスタッフたちが作業をできるスペースもあり、人の出入りが多かったり壁にメッセージが貼られていたりと、賑やかな様子。
「面白い大学生に沢山会えるのも魅力のひとつです」と横井さんが教えてくれた。
横井さんがにこにことオフィスを案内してくれたこと、それから今まで聞いた話を思い出して、みんな心からカタリバに共感しているということが感じられた。
もちろん、好きなだけでは務まらない仕事だということも分かる。カタリバのことを全く知らない人にも伝わるように、現場の活動を客観的に捉えること。これも広報・ファンドレイジング部に求められることだと思います。
 最後に、山内さんがこんなことを言っていました。
最後に、山内さんがこんなことを言っていました。「自分たちが集めたお金は、絶対に社会にとって役立つように使われる。それを100%信じられるというのが、やりがいに繋がっているのだと思います。カタリバの活動に共感し、さらに想いを伝えることで人の共感の輪を広げていけるような方に、来てほしいと思います。」
(2013/12/6 笠原名々子)

