※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
初めまして。わたしは笠原ナナコと申します。今まで、日本仕事百貨の「エディター」として、株式会社シゴトヒトで働いてきました。
今回は、わたしたちと一緒に働く人を募集します。
 エディターの仕事は、お問い合わせいただいた企業を訪ね、取材をして記事を書くこと。
エディターの仕事は、お問い合わせいただいた企業を訪ね、取材をして記事を書くこと。ライターではなく、エディター。そう呼ぶようになったのは、わたしたちが仕事のなかで色々な「編集」をしているからです。
それは、記事の編集だけではなく、取材という場の編集だったり、イベントやツアーなどをつなげた企画の提案だったり。文字を越えたさまざまな編集が、わたしたちの仕事です。
求めているのは、ウェブや紙面での編集、ライターの実務経験がある方。
まずは、わたしたちの仕事がどんな仕事か、知ってみてください。
シゴトヒトのオフィスは、今年6月にオープンしたばかりの虎ノ門ヒルズのすぐ目の前にあります。
ここはもともと、「蛇の目寿司」という老舗のお寿司屋さんでした。
去年、ここをリノベーションして、ウェブマガジン「greenz.jp」を運営するNPO法人グリーンズと共同で、「リトルトーキョー」という場所をはじめました。
 草木が自由に生えている庭を抜けると、一階はカフェ&バー、本屋、イベントスペースなどがあるオープンな空間。
草木が自由に生えている庭を抜けると、一階はカフェ&バー、本屋、イベントスペースなどがあるオープンな空間。二階は、畳部屋と木のフローリングの打ち合わせスペース。さらにシゴトヒトの事務所もあります。
ここでは毎日のようになにかしらイベントが行われていて、1年かけてさまざまな人が出入りする場所になってきました。
シゴトヒトのスタッフも、ここに通勤しています。
毎日来ると決められているわけではないので、ときには出張先や自宅で仕事をする日もあります。
週によって出張が入ったり取材が多かったりと、スケジュールも変則的なので、みんなそれぞれ自分のスケジュールは自分で管理しながら働いています。
ふだんバラバラに働いているぶん、週に1度のミーティングでは、各自の案件をひとつひとつ共有しながら、意見を交換し合います。
いま働いているメンバーは、わたしを含めて7人。学生インターンを含めれば13人です。
7人のメンバーのなかには、経理・総務だったりデザインだったり、べつの仕事を担う人もいますが、基本的には全員が取材を担当しています。会社が主催するイベントも、準備から運営までみんなでやります。
つい先月も、24時間かけてさまざまなゲストとトークする「24H仕事百貨」というイベントを開催したばかり。実はこのイベントは、日本仕事百貨がはじまって6周年の記念でもありました。
大きなイベントを終えて、ほっと一息ついた状態の、代表のケンタさんに話を聞いてみました。
ケンタさん、6年を振り返ってみて、どうですか?
 「この6年を振り返ってみると、なんとなく、感覚的に、黙々と石を積み上げてきた感じかな。」
「この6年を振り返ってみると、なんとなく、感覚的に、黙々と石を積み上げてきた感じかな。」石?
「うん。石は、日本仕事百貨のひとつひとつの記事のことでもあるし、24H仕事百貨のような、大きな石をみんなでえっさこらと運ぶようなこともある。納まるところを吟味しながら、積み上げてきた。目の前のことを続けてきた6年間だったかな。」
日本仕事百貨をはじめた当初は、月に数件の求人を無償で掲載していました。それがだんだん応募に結びついていき、費用をいただけるようになりました。
営業活動やSEO対策などはしていないけれど、口コミで広がって、いまは月間アクセスが約75万。
突然増えることはないけれど、着実に読者が増えてきています。
「そうしてできたものは、着実だし、急に失われるということもない。僕らはここまで石を積み上げてきて、今はちょっとした洪水なら対応できるような、堤防ができてきたんじゃないかな。」
仕事百貨の求人記事は、募集が終了しても記事が読めるようになっています。終了後に記事を読んでその会社に興味を持つ人や、読み物として記事を読んでくれる人もいます。
インターネットの情報は、過ぎていくフローのもの、という印象があるかもしれません。一度読まれるとその後二度と読まれないというような。
「でも、日本仕事百貨のやっていることは、ストックに近いんじゃないかな。」と、ケンタさん。
「僕たちの記事は、100年後にも、絶対見られると思うんだよね。」
それから、こんな話もしてくれました。
「僕は建築学科の出身なのだけど、建築家になって色々な人の家を建てるよりも、一生かけて何かをつくる仕事をしたいなと思って、日本仕事百貨をはじめたんだよね。リトルトーキョーもそうだし。そんな風に、ちょこちょこ手を入れながら、ひとつの場所を作り続けていきたいな。」
 ケンタさんは、どんな人と一緒に働きたいですか?
ケンタさんは、どんな人と一緒に働きたいですか?「シゴトヒトに入ることが目的の人ではなくて、一緒に仕事をしていくこと自体が目的になるような人がいいよね。」
「僕は、社会のためにいいことをしているつもりはないので、まずは自分たちが心地よくあることが目的なんですよ。心地よくいるためには、素直に正直に仕事をして、それを必要としてくれる人がいて、一緒に働く人も気持ちよくいられること。それが結果として社会のためにいいことになっていれば、一番いいよね。」
遠くを見るよりも、まずは目の前の人を大切にする。目の前のことに向き合う。その結果、周りに心地よい人間関係ができてきて、仕事も口コミで広がっていく。
これはわたしが働くなかで感じた、シゴトヒトという会社のやり方です。
そんな姿勢に共感できるような人であれば、ここで一緒に働いていけるんじゃないかな、と思います。
ここから先は、具体的にどんな仕事をしていくことになるのか、順を追って紹介していきたいと思います。
日本仕事百貨には、日々、求人を検討している企業からお問い合わせがきます。
お問い合わせをいただくと、まずは、その会社がどんな事業をしていて、今どういう状況で、どういう人を求めているのか、などをお伺いします。
話を聞いて、もしお役に立つのが難しいと感じたときには、それを率直にお伝えします。ときには、そもそも、いま求人募集をするタイミングなのか、というお話をすることもあります。
そして、取材に伺うことが決まった場合には、次に、どこで誰にどんなお話を伺うのかを打ち合わせします。
たとえば、店舗の販売員の募集であれば、本社よりもお店に伺ったほうがその仕事が見えるし、デザイナーの募集だったら、実際の作業も見せてもらいたい。
できるだけ、その仕事が直接見える場所に伺って、話を聞きます。
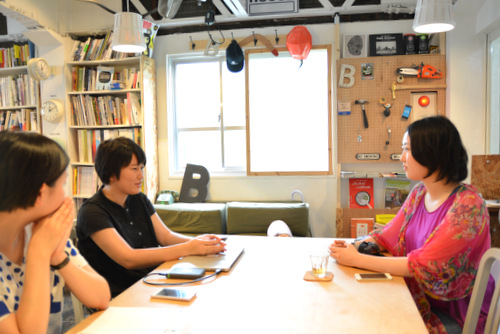 インタビューは、ときと場合にもよりますが、「今の気分は?」という話からはじまることもあります。
インタビューは、ときと場合にもよりますが、「今の気分は?」という話からはじまることもあります。とくに事前にお話いただくことは決めてもらわずに、できるだけ、その場で感じたことを話してもらっています。
だから、話している方も、まだ言葉がまとまらないうちに話しはじめていることが多いです。
会社について、どんな人にきてほしいか、一緒にどんな仕事をしたいか、など。
いつも考えてはいるけれど、まだ言葉になっていないようなものを、一緒に形にしていくような感じです。
「話しているうちに頭の中が整理できました」「いつも隣で働いている仲間のことが、より理解できました」
取材のあとに、そんなことを言ってもらえることもあります。
そういう意味では、わたしたちのインタビューは、ただ記事を書くための取材ではなく、ワークショップのような側面もあるのかもしれません。
取材を終えると、次は記事を書いていきます。
まず、録音した音声をすべて文字に起こして、それを元に編集していきます。
 第三者の目線から、職場を訪ねて感じたことを綴っていきます。いいことだけではなく、大変なこと、不便な部分、もう少しこうだったらいいかもしれない、ということも、できるだけ伝えるようにします。
第三者の目線から、職場を訪ねて感じたことを綴っていきます。いいことだけではなく、大変なこと、不便な部分、もう少しこうだったらいいかもしれない、ということも、できるだけ伝えるようにします。いいことだけを書いても、それを読んで入社した方がすぐに辞めてしまったとしたら、結果としてお役に立てないことになるからです。できるだけギャップがないように心がけています。
とはいえ、一度取材をしたからといって、その会社の全てがわかるわけではありません。
でも、だからこそ、限られた時間のなかで、その会社のことをできるだけ知りたいと思っています。
だから、取材中は常にアンテナを張り巡らせます。
日本仕事百貨に掲載される会社は、大企業よりも少人数の会社が多いので、創業者の方に話を聞く機会も沢山あります。
また、企画、販売、事務職からデザイナーや料理人などの専門職まで、本当にさまざまな職種の人に話を伺います。
わたしは過去に、茅葺き屋根の職人さんを募集したことがありました。
1日の取材のなかで、少しでもどんな仕事なのかイメージしたいと思って、屋根に登って仕事を見学させてもらったり、朝起きてから夜寝るまでの流れをこと細かく聞いてみたり、休憩中の雑談にも耳をすませました。
 世の中には色々な仕事をしている人がいて、みんなそれぞれに自分の考えを持って働いています。それを、その人の代わりに伝えるのがわたしたちの仕事です。
世の中には色々な仕事をしている人がいて、みんなそれぞれに自分の考えを持って働いています。それを、その人の代わりに伝えるのがわたしたちの仕事です。だから、ときには取材に伺うだけではなく、自分なりに勉強をすることも必要かもしれません。そんなふうに、自分の引き出しを増やしていくことも、自然と求められる仕事です。
とはいえ、完全にひとりで立ち向かうわけではなく、何か困ったことがあれば、気軽に他のメンバーに共有できる環境があります。
シゴトヒトのメンバーに共通している感覚は、違和感をそのままにして先に進めるよりも、ひとつひとつ納得しながら進んでいこうとすることなんじゃないかな、と思います。
だからこそ、それってどうなんだろう?と思うことは率直に意見を伝え合うし、ときにはちょっとしたもめごとが起こることもあります。
共通の思いは持ちながらも、それぞれ取材のスタンスや、持っているこだわりは少しずつ違います。まだまだ、シゴトヒトとして、という全体像をつくるには時間が要るのかな、と思います。
まだ組織としては歴史が浅いので、そうした会社としてのビジョンも、一緒につくっていけるような人が来てくれるといいな、と思います。
 最後に自分のことを少しお話すると、わたしはこの夏いっぱいでシゴトヒトを離れることになりました。今後は、独立して仕事をしていく予定です。
最後に自分のことを少しお話すると、わたしはこの夏いっぱいでシゴトヒトを離れることになりました。今後は、独立して仕事をしていく予定です。でも、完全に離れるのではなく、イベントやコラムの企画に参加させてもらったりなど、なんらかの関わりは続いていきたいなと思っています。
この記事を読んで入社したという人に、いつかリトルトーキョーでお会いできたら嬉しいです。
取材して記事を書く、ということを通して、人や仕事に向き合うことができる仕事です。
もしここで働く自分がイメージできたら、ぜひエントリーしてみてください。
(2014/9/3 笠原ナナコ)

