※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
全国でシカやイノシシ、猿などによる獣害が深刻化するなか、私たちが“狩猟”に触れる機会は増えつつあります。
たとえば野生鳥獣の肉をつかったジビエ料理が流行したり、「狩りガール」という言葉も生まれたり。
とはいえ、まだまだ遠い世界だと感じている人も多いのではないでしょうか。
自然や野生動物、人とのあいだに今なにが起きているのか。まずはこの記事を読んで、興味を持ってくれる人が増えたらうれしいです。

和歌山県は那智勝浦町で、狩猟を通じた生業づくりに取り組む人たちに出会いました。
今回は地域おこし協力隊として、そこに加わってくれる人を募集します。経験も、男女も問いません。
狩猟イコール銃を持ったハンターのイメージが強いかもしれませんが、追い払いや保護柵の設置、獣害を知ってもらう体験ツアーの企画など、関わり方はさまざま。
ぜひ、続きを読んでみてください。
南紀白浜空港から、特急電車に乗り継ぎ1時間半ほど。外国から来た観光客の人たちと一緒に紀伊勝浦駅に降り立った。

人口は約1万5000人。2004年に世界遺産に登録された熊野古道や温泉、まぐろが有名なまち。
泊まるはずのホテルの場所がわからなくてウロウロしていると「どこ行きたいの?」とおばあちゃんが声をかけてくれた。
地図を見せると、たまたま駅に居合わせた人たちも「もしかしてあれかな、あの廃業した跡地のさ」「あー、そうかもしれん」と一緒になって考えてくれる。「カミさんに聞いてみるわ」と電話してくれる人も。
見つかると「よかったな」と各々解散していく。なんだか到着して早々、このまちの人柄に触れたような気がした。
あたたかい気持ちのまま、まずは猟友会の会長である西さんを訪ねました。

「僕は、田舎が好きで都会へ行きたくなくてね。山が好きで、犬が好きで。だから20代のときから鉄砲持って、猟犬と一緒に山へ入ったんです」
まずは知ってほしいことがある、と西さん。
「損得考えたらできん仕事やね。賃金も安いし、地理も覚えなあかんし。勉強して覚えられるもんと違って、自然と体で覚えるいうんかな。山入ったら実力だけで、肩書きは関係ない。だからこそおもしろいところもあるけどね」
昨年、猟友会では年間約800頭ものシカを捕獲した。一方で、獣害による被害は全国で190億円とも言われている。
そもそもだけど、どうして全国でこんなに獣害が問題になっているのだろう。
「山が変わってしまったことが、原因やね」
山が変わった?
「雑木を切って杉やヒノキを植えたんです。昔は木材がお金になったから手入れもしたけど、今は売れないから手入れをしない。間伐せんから光が入らんのです」

地面に光が入らないと草木が生えない。そうすると虫や虫を食べる生き物がいなくなる。フンや死骸が土に還らず、豊かな土ができない。
人が手を加えてできた人工林は、手を加え続けないと自然のサイクルが壊れていく。
そんな山で生活できなくなった動物たちは、木の皮をやむなく剥いで食べてしまったり、里に下りてきて農作物を荒らしてしまうのだそう。
「農地を柵で囲うようになって。気づいたら、人間が檻の中で生活しているようなもんやね」
とはいえ山の状態を変えていくには長い時間とお金がかかる。だからこそ森林や野生動物の保全に目を向けながら、生息数を調整したり農地への被害を食い止める西さんたち猟師が必要なのだ。
今回地域おこし協力隊として入る人は、西さんをはじめとする猟友会の人たちに山のことを教えてもらいながら狩猟免許の取得を目指し、ゆくゆくは猟師になることもできる。
「動物や自然が本当に好きやったらなれるんじゃないかな。獲った獲物は山の恵みとして、『おおきに』っていう気持ちで食べる。ただの殺生にはしない、いのちに向き合うことでもある」

「昔はスポーツみたいに猟師をやっている人もいたけど、今はみんなの暮らしを守るためにやっている。鉄砲持っとることには、誇りを持ってほしいと思うよ」
猟銃を所持するには、手間とお金がかかることは事実。だけどいのちをいただくということは、それだけ重みと厳しさのあることだと思いました。
お話を伺ったあと、「ちょっと歩いてみようか」とおうちの裏山を一緒に歩いてみることに。
苔が生えて、石が転がる道を西さんはすいすいと進んでいく。
「ほら、ここにあるよ」と指差す先にはシカの足跡が。「向こうから、あの道をくだってきたんやな」とか「これはおとといの足跡やわ」と痕跡からさまざまな情報を得る。
経験を重ねて、だんだんとわかるようになっていく。まさに習うより慣れろという感じ。

猟友会の先輩たちに謙虚に話を聞きながら山を歩いて、まずは山を知るところからはじまりそうです。
役場に戻り、獣害対策に率先して取り組んでいる人たちにも話しを聞いてみます。
鳥獣害防止対策協議会会長の掛橋さん。「若い人が話を聞きにきてくれてうれしいよ」と優しい笑顔で迎えてくれました。

今回、狩猟に関わる人を募集しようと思ったのにはなにかきっかけがあるんですか。
「家庭菜園もできんという状況になってきたんです。田舎におって野菜をつくれんというのはほんまに寂しいですね」
「野菜や米をつくって、できたものは近所の人にあげるというやりとりのなか、田舎は仲良く生活できている。それができなくなるともうまちと一緒ですよね。田舎の良さが失われていくと思うんです」
もちろん柵や罠を設置したり、猟友会の方々に協力してもらったり。対策を講じてはいるものの、高齢化や後継者不足が深刻で、なかなか被害を減らせないのが現状だという。
「なんとかこれを食い止められないかと、力を貸してもらうことにしたんです」
具体的には、町内をまわって被害状況を整理する。どんな被害が、どういう時間帯に多いのか。効果的な対策をするためには、現状を知ることが必要だ。
「農家の人たちは獣害の被害にあっても、相談できる人がいないんです」と掛橋さん。
大変ですよねと話をしながら一緒に作業をするだけでも、安心できるという。猟友会を含め地域をつなぐパイプ役になれたら、新たな意見も生まれてくるかもしれない。
すでにまちの中ではじまっている取り組みも参考にしてほしいといいます。
たとえば夜集落内をめぐり、野生動物を目にするナイトツアーの開催。子どもや女性の参加者も多く人気があるそうで、一晩になんと200頭近くのシカが見つかることもあるそう。

ほかにも解体技術を学んだり、ジビエ料理に挑戦することもできる。
今は“害”になっているけれど、見方を変えたら狩猟と観光業の連携にもつながって“地域の資源”になっていくかもしれません。
最後に紹介したいのが、原さんです。
兵庫出身。26歳のときに那智勝浦町の色川地区に移住してきました。
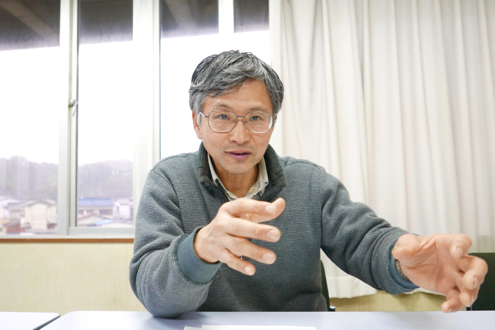
色川地区は古くから移住者を受入れていて、住民の4割が移住者という全国でもめずらしい地域。獣害対策の先進地でもあり、地の人と移住者が長い時間をかけて地域をつくってきた。
「このへんでは会ったときに『まいどおおきに』っていうんですよ。兵庫では商売人しか使わなかった。お互い持ちつ持たれつで日常を生きてきたから、いつもおおきに、ありがとねって自然と言葉が出るようになったんだろうね」
移り住んでみてはじめて、「地方にすばらしい暮らしの積み上げがあるとわかった」という。
原さんをそんなに惹きつけるものってなんですか。
「田んぼや畑をやりつつ、こどもも生まれて10年くらい経って。人との関わりもできて、なんとなく色川のことがわかったような気になったんだよね」
もともと、無農薬の米や野菜をつくることに憧れていた。少しずつ自給自足の生活ができるようになって、すべて安全な食べ物で食卓がつくれる。
そんな暮らしをしている自分が誇らしいような気持ちになったという。
「だけどあるときはたと気がついたんです。確かに農薬をかけずに野菜や米を育てているけど、その田んぼや畑を誰がつくったのかって。自分はただ耕しているだけなんだよね」

色川地区に息づく、1000年も前から人が暮らしてきた歴史。森林を切り開いてつくった棚田や石垣、水路。崩れたらその度に直しながら、暮らしをつないできた。
「たとえば石垣一つつくるにも、石を一つずつ二人で運びながら積み上げていったんでしょう。今のような機材もなく、全部人力で。石もそこらへんには転がってないから、川までいって運んできたんだろうかって想像すると、とんでもない時間とエネルギーがかかっている」
「自給自足では決してなくて。先に暮らしていた人らのつくった田畑のおかげで暮らせてるということに過ぎないんやと。それに気がつくと、自分たちもなにかを残したい、つないでくれる人がほしいと思うのも、自然な心理やと思うんです」
その重さや想いは、実際に触れてみないとわからない。もちろん不安もあると思うけど、まずは先のことを考えるより、飛び込んでみてほしいといいます。
たとえば、バイクの修理業から農機具の修理を頼まれるようになって、農機具の修理屋さんになった人。竹細工が得意だと入ってきたけど、地元の人に話を聞くうちに炭焼きに興味を持って、紀州備長炭の炭焼きとして町内で起業した人。
地域に住んで、地元の人のことを考えているうちに、生業を見つけた人がこのまちにはたくさんいる。
自分にはこれしかできないと決めつけるより、これもできるかも、あれもやってみたいなと見つけていくほうがきっと暮らしは豊かになっていくと思います。
「今はね、継業という言葉もあって。田舎でやられてきた仕事も、やりようによってはまだまだ展開できるぜっていうものもいっぱいあるよ」
ここが自分の居場所だと感じているという原さんの言葉は、一つひとつがなんだかストンと腹に落ちてきた。芯があるというか、頭で考えるだけじゃなく体で実感してきたことだから説得力がある。
どんな人にきてほしいですか。
「どんな人でも。ともかく一度訪ねてきてほしいというのはありますね。まずは直接話を聞いてみてほしい」
「協力隊制度を導入したころ、どうやって責任とるんやって言われたんです。俺はほっとけばいいと思ってたんだけど、みんな優しいんやわ(笑)本当にこの地域に入っていこうと思ってくれたら、誰もほっとかへんよ」

ここでの暮らしは、自然環境や動物たちと人のあり方を見つめ直すきっかけになると思います。
それは自分がどう生きていくのか、原点に向き合うことなのかもしれません。
山とともにはぐくまれた暮らしの中で考え、感じたことはきっと人生をより良いものにしてくれるはずです。
興味を持ったら、ぜひ応募してみてください。
(2016/6/14 並木仁美)

