※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
働く場所や時間の使い方など、個人の裁量に委ねられた多様な働き方について、耳にする機会が多くなってきました。一方で、障害があったり、人間関係に悩んでいたり。さまざまな理由で生きづらさを抱えている人たちも、まだまだいると思います。
一人ひとりに合った新しい働き方を手に入れる。
そのために、就労移行支援を通して学びの場をつくっているのが株式会社manabyです。
 前回取材した株式会社manabiから社名を変更し、今年4月、新たなスタートを切りました。
前回取材した株式会社manabiから社名を変更し、今年4月、新たなスタートを切りました。「学びって、終わりがない。人が生きていくなかでずっと続くもので、主体的に学べば学ぶほど、次のステップが見えてくる。ここは、自分がやりたいこと・働きたい場を手にするために、知識やスキルを身につけていく場所なんです」
これは、manabyが大事にしている「学び」とは何かという問いに、採用担当の佐藤さんが答えてくれた言葉です。
取材を終えてみて、この言葉は同時に、manabyで働く人たちのこともよく表しているように感じました。
どんな人たちがいるのか、ぜひ続きを読んでみてほしいです。
今回募集するのは、受講者が使うコンテンツを開発したり、Webサイトを制作したりする人、人事、広報、事業所を運営していくマネージャーなど。様々な関わり方でmanabyを一緒につくっていく人を求めています。
立ち上げから1年。いまでは仙台や宮城、神奈川に5つの事業所を展開している。
取材に伺ったのは、4月にオープンした神奈川・武蔵小杉の事業所。駅から徒歩3分ほどのビル8階にある。
エレベーターの扉が開くと、マンションの廊下のような空間に出た。フロアの1室がmanabyの事業所。
玄関にはたくさんの靴が並んでいる。
実はこの日、取材後には初の社員研修合宿が控えていて、社員全員が集まった。
代表の岡﨑さんが、合宿前の気持ちを話してくれた。
「今回の合宿は、みんなの気持ちや考え方を一つにすることがメインになるので、しっかりやれればいいなと思っています」
 manabyが掲げるテーマが、「一人ひとりが自分らしく働ける社会をつくる」こと。
manabyが掲げるテーマが、「一人ひとりが自分らしく働ける社会をつくる」こと。もともと就労移行支援に取り組んでいた岡﨑さん。一人ひとりに合った支援の必要性を強く感じるなかで、このテーマが生まれていった。
就労移行支援とは、障害のある方の就労をサポートする仕組み。必要な知識・能力を得るためのトレーニングをしたり、就労に関する相談や支援を行なう。
けれども、効率性が重視されるあまり、就職しやすい傾向にある人を優先したり、本人の希望とは関係なく職種や就職先が選ばれたりすることがあった。
その結果、就職して1年は社会復帰できても、継続しないという状況が目立っていた。
さらに地方では、せっかくIT関連のスキルを学んでも、地元で働こうとするとIT分野の就職先がないことも。
「そうした問題に対して社会は見向きもしないし、何の支援体制も整えてこなかったんです」
問題を解決するために、岡﨑さんは昨年、この会社を立ち上げた。
 manabyでは、受講者がWEBデザインやプログラミング、ライティングなどIT系スキルを中心に、事業所でも自宅でも就労に必要な技術を学ぶことができる。
manabyでは、受講者がWEBデザインやプログラミング、ライティングなどIT系スキルを中心に、事業所でも自宅でも就労に必要な技術を学ぶことができる。事業所に通わなければならなかった従来の支援の仕組みを変えたことで、居場所を見つけた人も多い。
「スキルを身につければ、通勤とリモートワークを組み合わせて働くことができるかもしれない。そうすれば、自分の体調や性格に合った形で、長期的に働くことができるし、都市部も地方も関係なくなると考えています」
 日々の悩みや不安に耳を傾けながら、一緒になってその人らしい働き方をつくっていく存在。だから、manabyを利用する人のことはcrew(クルー)と呼んでいる。
日々の悩みや不安に耳を傾けながら、一緒になってその人らしい働き方をつくっていく存在。だから、manabyを利用する人のことはcrew(クルー)と呼んでいる。立ち上げから1年。クルーの方のなかには、新しい道を歩みはじめた人も。
ある方は、3〜4ヶ月ほどmanabyを利用したのち、現在就職して人事関係の仕事を任されているそう。
就職するまでの過程で、manabyの担当スタッフは、職場で配慮されるべき点についてクルーの方とじっくり話し合った。
会社見学後も、雰囲気が合うかどうか、就職にあたって不安はないか。最後まで寄り添いながら、働く時間帯や仕事内容などを一緒に決めていったそう。
いまは順調に働いていて、今度は就職したその方が、会社の障害者雇用の担当者としてmanabyに来ているんだとか。
徐々に評判が広まり、manabyを求める声は各地から寄せられているという。
今年度はこれから、横浜をはじめとしてさらに4つの事業所を立ち上げる予定だ。
拡大中の今だからこそ、考え方を共有することが大事だと、岡﨑さんは話す。
「離れた事業所同士でも、様々なツールを使って情報共有をして、コミュニケーションを密に取り合っています。それでも、ズレが生じることは絶対にあると思っていて」
 「全員が顔を合わせて正直に意見を言いあう場として、合宿はとても大切になりますから、今後も継続させていく予定です。誰かの声で動くんじゃなく、核となる考えをみんなで共有して、それをもとに各自が行動する。そこをもっと強化していきたいですね」
「全員が顔を合わせて正直に意見を言いあう場として、合宿はとても大切になりますから、今後も継続させていく予定です。誰かの声で動くんじゃなく、核となる考えをみんなで共有して、それをもとに各自が行動する。そこをもっと強化していきたいですね」続いて話を伺ったのは、前回の日本仕事百貨の記事をきっかけに入社した桃生篤さん。
仙台事業所で、コンテンツ制作のマネージャーを務めている。
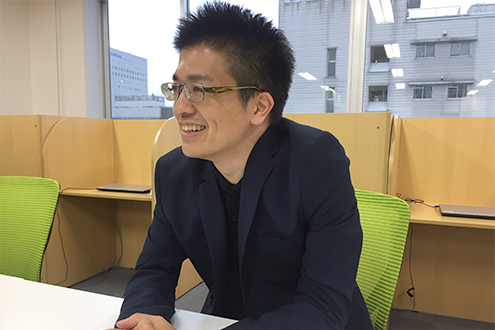 入社する前はフリーランスで、インタビュー音声を文字に起こす仕事などをしていたそう。
入社する前はフリーランスで、インタビュー音声を文字に起こす仕事などをしていたそう。それ以前は会社に勤めていた。そのときに、ある疑問を抱いたという。
「会社で指示された通りに仕事をすることに対して、それでいいのかなって。やりづらさを感じていました」
「もっと遡ると、大学生までずっと所属していた体育会系の運動部でも、先輩をたてなきゃとか伝統だからやらなきゃみたいな慣習があったんです。そのときも納得がいかなくて」
既存の体制に対する反発心が根本にあったという桃生さん。
自分らしい働き方とは何かと、これまで考えてきた。
「自分で考えて、これがいいんじゃないかと思うことをどんどん試していって、答えを探していく。そんな仕事がしたいと思っているんです」
「日本仕事百貨でmanabyの記事を読んだとき、考え方に共感して。クルーさんの新しい働き方も一緒に考えながら、自分自身の働き方も追求していけるんじゃないかと思って、応募しました」
入社してみて、何か感じていることはありますか。
「自主的に考えて、自分のやりたいことを実現させたいと望んでいたけれど、それがいかに大変かということに気づきました」
「パワーも必要だし、ずっと考えなきゃいけない。その分、充実感はあるんですけど、今後さらに力を出してかないといけないなと、毎日思いながら仕事をしています」
そんな桃生さんが力を入れているのが、コンテンツ制作の仕事。
manabyでつくっているコンテンツは、動画を見ながら実際に手を動かすことで覚えられるような形をとっている。アウトプットのためのテストも充実させているそうだ。
 クルーの方はそれぞれコンテンツを利用するためのアカウントを持っていて、各自のカリキュラムに沿って学習を進めていく。
クルーの方はそれぞれコンテンツを利用するためのアカウントを持っていて、各自のカリキュラムに沿って学習を進めていく。「仙台の事業所では、私ともう二人でコンテンツを制作しています。私は責任者として、二人が制作した動画をチェックしたり、自分でも動画を撮影したり。スケジュール管理や、日々クルーさんのサポート対応もしていきます」
10時から15時の間は学習サポートに徹して、そのあと自分の仕事に取りかかる。
動画コンテンツは、チャプターごとに一日1〜2本の動画を撮影する。時間はおよそ10〜15分で、撮影後、その日のうちに編集まで行なう。
 1ヶ月ほどで、1つのコンテンツが完成するそうだ。
1ヶ月ほどで、1つのコンテンツが完成するそうだ。つくりながら意識していることはありますか?
「クルーさんのなかには、パソコンに触ったことがないような方もいます。一からはじめる人にもわかりやすく制作するように心がけていますね」
たとえば、キーボードについて説明するところからはじめていたり、制作後であってもコンテンツに細かな解説を補足し直したりしている。
「クルーさんに話を聞くと、どの部分がわかりづらかったとか、逆にわかりやすかったとか、いろんな意見をもらいます。その度に、やっぱり使っている人の生の声がいちばん大事だなって」
「自分がどんなにうまくできたと思っていても、実際に使っている人が満足するものじゃなければ決していいものとは言えない。日々、つくったものに対して『これでいいのかな』という気持ちとの闘いです」
デザイン面からも、クルーの方が自然と学習したくなるような仕掛けをしていきたいとのこと。
目の前の人に向き合い、もっとよくしていくためにどうするかを常に考えている。
時間も限られたなかで、思考を絶やさずにいるのはなかなか大変そうです。
すると、桃生さんからはこんな返事が。
「たしかに、時間には追われています。でも、クルーさんをサポートする仕事があってはじめて、いいコンテンツをつくることもできる。クルーさんとのコミュニケーションを根本に据えていれば、悩まないと思います」
桃生さんはどんな人と働きたいですか?
「新しいチャレンジも多い会社なので。なるべく先入観がなくて、挑戦することを迎え入れるような人と一緒に働きたいですね」
スタッフ同士、お互い正直に意見を伝え合うことも求められます。
それは、何よりもまずここで働く人たちが、自分らしくありたいと考えているから。
採用担当の佐藤真奈実さん(写真左から2人目)が、スタッフの働き方について教えてくれました。
 「私たち自身が自分らしい働き方を体現していこうと、それぞれが働きやすく、且つ同じ目的に向かって行動できるような働き方を試みています」
「私たち自身が自分らしい働き方を体現していこうと、それぞれが働きやすく、且つ同じ目的に向かって行動できるような働き方を試みています」「たとえば私もいま、出社するのは週に3回で。これからまた別で関わっている活動が忙しくなるので、みんなに相談させてもらって。月に最低5〜7回は事業所で、それ以外の日は別の場所で働くことになる予定です」
ほかにも、スタッフのなかには完全なリモートワーカーもいれば、子育て中のお父さんお母さんもいるし、司法試験の勉強と仕事と両立させている方もいる。
人事を担当する人は、会社として柔軟な働き方を体現させつつ必要な整備を行なったり、新卒採用に向けた研修を企画したりしていくそうです。
最後に、岡﨑さんから一緒に働く人に伝えたいことがあるそう。
「僕らがやろうとしているのは、スタンダードじゃないと思われている働き方を世の中に浸透させて、自分らしく生きる人を社会に増やしていくことです」
「僕らは本気で社会を変えようと、覚悟をもってやっています。個人個人が思ってないと何も変えられないですからね」
 現状に満足できない人たちが、あなたを待っています。
現状に満足できない人たちが、あなたを待っています。(2017/07/06 後藤響子)

