※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
一つのことに特化すれば、そこでは最大限の力を発揮できるかもしれない。一方で、オールマイティに役割を担うからこそ、全体的な視点から根本にあるニーズや原因にまで立ち返って考えることもできる。
その結果、今までにないモノ・より良いモノをつくりだすことにつながる。
瀬尾製作所株式会社には、後者の考え方を楽しみながらものづくりをする人たちがいました。
 仏具を身近なかたちへと変えたブランド『Sotto』や、モダンな住宅建築にも映える鎖樋(くさりとい)『Rain Chain』など。
仏具を身近なかたちへと変えたブランド『Sotto』や、モダンな住宅建築にも映える鎖樋(くさりとい)『Rain Chain』など。瀬尾製作所は、昔ながらのものづくりに現代のライフスタイルに合った感覚を取り入れて、新しい製品を生み出しています。
それを可能にしているのが、企画を練るところから製造の全工程を手がけ、お客さんに販売するところまで、自分たちでサイクルを回していくスタイル。
さらに質を高めていくために。
今回は、領域を隔てず広い視野をもってものづくりをする職人を募集します。
東京から北陸新幹線で新高岡駅に向かう。
高岡は、昔からものづくりが盛んな地域。
目的地に近づいてくると、田園風景のなかに工場が溶け込んだ景色が目に入ってきた。
 駅で迎えてくれたのが、4代目の瀬尾良輔さん。
駅で迎えてくれたのが、4代目の瀬尾良輔さん。瀬尾さんの運転で事務所兼工場へ向かう。その間、この辺りの歴史について話してくれた。
「今から400年以上前、加賀藩主・前田利長が7人の鋳物職人を連れてきて、商人の町をつくろうと産業を興したのがはじまりでした」
代表的な産業の一つが、伝統工芸・高岡銅器。
けれど、バブル崩壊後、産業として持続させていくには難しい状況に立たされてきた。
「そのなかで、今のライフスタイルに合わせてモノをつくっていかなきゃと、新しいチャレンジをはじめる企業も出てきて」
創業82年の瀬尾製作所も、その一つ。
どんなものづくりをしているのか、事務所で詳しく話を聞かせてもらう。
「昔から、仏具や鎖樋などをつくる金属加工技術を得意としてきました」
「今は、企画段階から商品をつくりあげ、お客さんに売りに行くところまで。一つのサイクルを回しているのが、うちの特徴です」
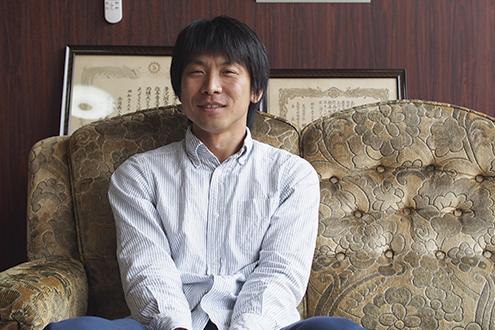 工場ではたくさんの工程を踏んでいく。
工場ではたくさんの工程を踏んでいく。原型となる金型づくりからはじまり、2種類のプレス加工を行なう。
一つは、熱して変形しやすくなった金属に金型で圧力をかけて製品をつくる鍛造プレス。もう一つは、板状の金属をプレスして形を曲げたり切断したりして製品をつくる板金プレス。
 その後、研磨や溶接、表面仕上げに最後の梱包まで。さらに自分たちで販売も手がけている。
その後、研磨や溶接、表面仕上げに最後の梱包まで。さらに自分たちで販売も手がけている。伝統工芸の産地では分業制が主流のなか、ものづくりから販売までのサイクルを大切にするには、理由がある。
「モノが溢れる今の時代は、お客さんも気づかなかったようなニーズを掘り起こしていかないと、商売としてやっていけないと思っていて」
「自分たちでモノをつくって売りに行くことで、お客さんのニーズを吸い上げ、ニーズを反映させた製品開発・製造ができたら、強みになるじゃないですか」
まず必要なのは、お客さんのニーズを知ること。
瀬尾さんがそう考えるようになったのは、11年前。東京でSEとして働いていたとき、夏休みの1週間を利用して瀬尾製作所で働いてみたことがきっかけだった。
「そのとき、このままだと時代に取り残されていくんじゃないかと危機感を抱いたんです」
「昔ながらのモノをつくり続けてきた会社だけれど、この先も売れ続けるとは思えないし。何か新しいモノをつくろうと考えても、当時はそれを開発できるようには思えなかった」
東京に戻ってから「売る」力をつけようと、3年間営業の経験を積んだ。
7年前に高岡へ帰ってきてからは、販売まで事業を広げるべく、まずはお客さんがほしいと思う商品を考案していった。
「もともと自社でつくっていた製品をベースに、いま何が求められているのか。会社のメンバーやデザイナーさんとつき詰めて考えた結果、『Rain Chain』と『Sotto』というシリーズが生まれました」
Rain Chainは、屋根に落ちた雨水が鎖を伝うことで地面へと流れる鎖樋を、モダンな家にも合うようにつくったもの。
 以前から銅による高級雨樋を製造してきたけれど、住宅事情が変化するにつれて当時は販売数は落ち込んでいた。
以前から銅による高級雨樋を製造してきたけれど、住宅事情が変化するにつれて当時は販売数は落ち込んでいた。「鎖樋というのはニッチなもの。でも、今の住宅に合うかたちがあったら面白いんじゃないかなと。シンプルでありながらアクセントとなるような鎖樋をインテリアデザイナーさんと一緒につくっていきました」
インターネットに的を絞って販売をはじめると、日本だけでなく海外でも人気が広がり、今では毎日英文メールでやり取りをするほどだとか。
もう一つ、自社ブランドとして展開しているのが、『Sotto』。
 コンセプトは“そっと暮らしに寄り添う仏具”。
コンセプトは“そっと暮らしに寄り添う仏具”。「人が亡くなる以上、供養の形は変わっていくとしても、大切な人を供養するという行為は絶対に残ると思うんです」
けれども今は、仏間をもつ家は少なく、特に都心部で賃貸物件に暮していると家の空間自体が狭かったりする。
現代のライフスタイルに合った供養の空間を、どうやってつくるか。
「家族から離れた部屋で写真を飾られて供養されるよりも、毎日のように顔が見えたほうが亡くなった人にとっては身近に感じられていいんじゃないか」
「今を生きている遺された人たちにとっても、先祖に感謝して手を合わせて、おりんを鳴らして…という行為が日常のなかにあるのは、きっとすごくいいこと。そう考えてSottoをつくりました」
「Potterin(ポタリン)」という商品は、火立・香立・花立をオールインワンにデザインしたもの。
 仏壇がない家でも、祈りの場をしつらえることができる。
仏壇がない家でも、祈りの場をしつらえることができる。そんな、人の心に寄り添うものづくりが、ここにはある。
今でこそやってよかったと思っているけれど、企画段階の当時は、「昔ながらのモノより、かっこいいモノつくりたい!」という気持ちが強かったそう。
「でも、やってみると面白いんですよね、この世界って」
面白い?
「うん。仏具というのはしきたりに基づいた製品で、宗教というテーマと切り離して考えることはできません。そこにコンセプトを絡めていくことって、今まではタブーだったんじゃないかな」
「でも、手つかずの世界で、自分たちが新しい形をつくっていける。その可能性を感じたとき、やりがいがあると思いました」
ものづくりのかたちを柔軟に変化させてきた瀬尾さん。
どんな人に来てほしいですか?
「今までのやり方に固執せず、臨機応変に自ら新しいことをやれるような人ですね」
少し背伸びすればレベルアップが見込めると思ったら、どんどん仕事を振っていくこともあるそう。
経験がなかったり、苦手意識を持っている仕事もあるかもしれない。けれど、やってみることで自分にできることが増えていく。
目指してほしいのは、全体像を掴んでものづくりをする多能工。
「広い視野をもつからこそ、根本にある原因が見つけられる。どんどん良い形に変えていってほしいんです。そのほうが、やりがいある職場になると思っています」
瀬尾製作所ではベースのつくり方をもとに、職人それぞれがより良い方向に、やり方を変えていっているそうだ。
そんな環境だからできることがあると話すのは、板橋芽衣さん。日本仕事百貨の前回記事を読んで、昨年入社した方です。
 たとえば、と教えてくれたのが、『cherin』というおりん。
たとえば、と教えてくれたのが、『cherin』というおりん。「黒く塗装する工程で細かな埃が入りやすかったんです。どうやったら入らないか、前後のいろんな工程を順に追っていって」
 塗装は、フィルターで囲われた環境で行われる。それなら、塗装をする前段階に原因はないか。
塗装は、フィルターで囲われた環境で行われる。それなら、塗装をする前段階に原因はないか。そう考えた板橋さんは、「脱脂」というお湯につけて油抜きをした工程で、濡れた状態のときに埃がつきやすいと気づく。
それを機に、脱脂をした後、埃を取り除く工程を新たに加えた。
結果、より光沢が美しくなった製品が、多くできあがるようになった。
「いろんな工程を幅広く担うからこそわかることがたくさんあります。私も、自分が塗装してできあがった製品を、検品・梱包しながら見たときに、もうちょっといろいろ考えてやらなきゃなと思うようになったんですよね」
「こうしたらどうかな?と考えながら、次に塗装するとき試してみる。それを何回も繰り返しました。まだほかにも研究できる余地がありそうです」
自分で原因から考えて、改善していくところが好きだという板橋さん。
以前は、家具職人のもとで木工製品や家具をつくっていた。
「前の職場では、こうしたらいいなというアイデアはあっても、なかなか採用されずにくすぶっているところがありました」
「ここに来てからは、瀬尾さんがいつも『それいいね!やってみな』と言ってくれて。だから実行していけるなと思っています」
もう一人、前回の募集を機に入社した、職人の福井豪さんにも話を聞かせてもらいました。
 若いころから伝統工芸に憧れて、以前は江戸切子職人として働いていた。
若いころから伝統工芸に憧れて、以前は江戸切子職人として働いていた。瀬尾製作所に入社した当初は、一つのことに特化した職人になりたかったという。
「ただ、この会社に今いない存在って何だろう?と考えたときに、いろんなことをできる人がいないなと思って」
「だったら自分はオールマイティな仕事ができる職人を目指そうと、それぞれの工程を経験させてもらっているところです」
まわりの職人さんたちも、わからないところを聞きに行くと丁寧に教えてくれて、福井さんの挑戦してみたいという気持ちを後押ししてくれる人ばかりだそう。
 もちろん、教えてもらった技術を自分のものにするには時間がかかる。それでも、恵まれた環境にいると、福井さん。
もちろん、教えてもらった技術を自分のものにするには時間がかかる。それでも、恵まれた環境にいると、福井さん。製造のほか、展示会に立つこともある。
「直接お客さんの表情が見られるのは楽しいですし。生の声を聞くことで、より深く考えるきっかけにもなります」
そう言って、展示会でバイヤーさんとの会話したときのことを教えてくれた。
「『Cherin』を鳴らしたとき、ものによってわずかな音の変化が生じることもあって。その点が気になっていたバイヤーさんがいたんです」
お客さんに求められることに応えたい。
けれど細部までこだわっていても、つくる日の気候条件などが関係して、どうしても差が出てしまうことがある。ジレンマもあるという。
「それでも、常に同じ精度を出していくにはどうしたらいいか考える。それが面白いですね」
製造工程から販売まで一貫して関わることで、いろんな角度から考えられる。
そしてまた身体を動かす。
そうやって、成長していく。
 ここには、いい循環があると思います。
ここには、いい循環があると思います。(2017/07/18 後藤響子)

