※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
自分が学生だったころを思い返したとき、やり直したいことってありませんか。部活動でも、進路選択でも、恋愛でも。きっと誰しも、ひとつやふたつは思い浮かぶことがあると思います。
とはいえ、実際にやり直すことはできない。できるのは、過去の自分と同じ岐路に立つ子どもたちの相談に乗り、ともに一歩踏み出すこと。挫折や後悔を味わったからこそ、伝えられることがあるような気がします。
今回の舞台は、熊本県甲佐町にある熊本県立甲佐高校。
全国で8校目の「高校魅力化プロジェクト」に関わるスタッフを募集します。
 高校魅力化プロジェクトとは、離島中山間地域における高校の統廃合を食い止めるため、魅力的な高校づくりによって地域内外から生徒を呼び込む取り組みです。
高校魅力化プロジェクトとは、離島中山間地域における高校の統廃合を食い止めるため、魅力的な高校づくりによって地域内外から生徒を呼び込む取り組みです。すでに島根県海士町や長野県白馬村、沖縄県久米島など全国各地で取り入れられ、なかには廃校寸前から生徒数を倍近くまで増やしている高校も。
甲佐高校では、校内の空き教室のひとつに「公営塾」を設置するところからスタート。公営塾は生徒なら誰でも利用することが可能で、放課後に教科学習をサポートしたり、進学や就職など、個々人の進路相談にも乗っていく場所です。
今回募集する人は、この公営塾に常駐し、教科指導や進路相談を通して日々生徒たちと向き合うことになります。
教育の経験は、なくても大丈夫。教えるというより、ともに学び、子どもたちの成長を後押ししたいという想いのある方を求めています。
羽田空港から熊本空港までは1時間40分。熊本空港からさらにレンタカーで50分ほどかかって、甲佐町役場に到着。
 まず話を聞いたのは、甲佐町教育委員会の教育長である蔵田さん。
まず話を聞いたのは、甲佐町教育委員会の教育長である蔵田さん。おとなりの宇城市の出身。行政や国の教育機関で働き、3年前までは甲佐高校の校長を務めていた方だ。
 「2020年、東京オリンピック・パラリンピックの年に甲佐高校は100周年を迎えます。昔から教育に熱心なまちで、“文教のまち”とうたってきたんですよ」
「2020年、東京オリンピック・パラリンピックの年に甲佐高校は100周年を迎えます。昔から教育に熱心なまちで、“文教のまち”とうたってきたんですよ」たとえば、台湾との国際交流があったり、都内の大学と連携して理科教育の充実をはかったり、サテライトキャンパスを誘致する動きがあったり。
蔵田さんの校長時代も、開かれた環境のなかでの学びを大切にしてきたそう。
「NIEってご存知ですか?ニュースペーパー・イン・エデュケーションと言って、その時々の新聞記事を教育に活用する方法です。これを学校の科目として設定するために、学習指導要領や教科書を整えたり。とにかくいろいろやってきましたね」
ただ、生徒数は年々減少。2010年に学区が再編され、甲佐町から熊本市内の高校への通学が可能になったことで、転出の流れは加速した。
「入学準備金を補助することで、地元の高校への進学を促す地域もあります。一方で甲佐町は、ただお金を出すんじゃなく、行きたくなる学校に変わるための支援をしたい、という考え方なんですよね」
そんななか着目したのが、高校魅力化プロジェクト。仕掛け人である株式会社Prima Pinguinoの藤岡さんと連絡をとりつつ、昨年から準備を進めてきた。
「まずは甲佐高校の空き教室を使って、公営塾を開設します。教科学習や受験対策だけでなく、就職のサポートだったり、夢を実現するための方法を一緒に考えたり、地域をフィールドに学んだり。学習塾というよりは、子どもたちの成長を支える塾です」
成長を支える塾。
「子どもたちは毎年、入学して卒業していくけれども、それは流れる川の水とはまったく違うわけで。簡単に取り返しはつかないし、気軽なことではない。教育は常に真剣勝負なんだっていうことを、わたしはずっと思っていますね」
 生徒一人ひとりの、卒業後の人生まで考えて関わること。
生徒一人ひとりの、卒業後の人生まで考えて関わること。それは、質問されて答える、というやりとりにとどまらない。一緒に悩んだり、議論したり、ときには生徒本人から言葉が出てくるまで待つ時間があるかもしれない。
今回募集する公営塾のスタッフも、生徒一人ひとりが自分で道を見出せるよう、サポートしていく立場になると思う。
とはいえ、まだやることが具体的に固まっているわけではないし、そもそも甲佐町のことを知らない人にとっては不安だらけのはず。
困ったときはぜひ、教育委員会の岩井田さん(写真左)と後藤さん(写真右)を頼ってほしい。
 おふたりは、公営塾スタッフの相談役のような立場にあたる。
おふたりは、公営塾スタッフの相談役のような立場にあたる。「公営塾の運営については、目指す方向性を共有しながらサポートしていきます。仕事以外の面でも、友人知人はほとんどいらっしゃらない土地でしょうし、気軽に相談してもらえればと思っています」
そう話すのは、向かって左の岩井田さん。
もともとは県外でSEの仕事などをしていたそうだ。
甲佐町にやってきて、外とのギャップを感じたことってありますか。
「都市部にはない地域コミュニティの強さを感じますね。『どこの人?』『甲佐町です』『甲佐町のどこ?』というふうに、深く関わる。はじめて訪れる人にとっては、多少の入り込みづらさを感じるかもしれません」
「ただ、甲佐町で過ごす時間が長くなるほど、すごくいいところだと感じるようになってきました。生活の必要最低限のものは十分揃いますし、都市部へのアクセスも車で30分ほどといいです」
山や川に囲まれた土地でありながら、海や熊本市の中心部へも近い。春から夏にかけては、河原でのバーベキューやお祭りを楽しむ観光客で賑わうという。
 「ただ、バーベキューやお祭りにピンポイントで来た方がすぐに帰ってしまうというのがひとつの課題なんです。こういったまちの課題に関しても、公営塾を通して高校生たちと一緒に考えていきたいなと思っていて」
「ただ、バーベキューやお祭りにピンポイントで来た方がすぐに帰ってしまうというのがひとつの課題なんです。こういったまちの課題に関しても、公営塾を通して高校生たちと一緒に考えていきたいなと思っていて」「甲佐高校の生徒たちは、甲佐町の文化祭で音楽部が演奏したり、お祭りを手伝ってくれたりと、現にまちの行事やイベントにも積極的に参加してくれています。今後はイベントだけでなく、高校生と一緒に地域振興について考えるのも面白いんじゃないかなと考えています」
たとえば、特産品を使った商品開発や観光資源の発掘を通じて、高校生が地元の魅力を再認識する機会になるかもしれない。それらの活動をもとに、町議会で具体的な提案をすることだってありえる。
 一方、お隣の御船町に生まれ、熊本市内に住んでいたこともあるという後藤さん。甲佐町のALTの相談役でもあるそう。
一方、お隣の御船町に生まれ、熊本市内に住んでいたこともあるという後藤さん。甲佐町のALTの相談役でもあるそう。「アメリカ人のご夫婦なんですが、文化も言語も違うから、不安だと思うんです。だから窓口をわたしに絞って、不安があればなんでも言ってくださいねって。おふたりともこのまちを気に入っているみたいで、あと5年は住むと言ってくれています」
「今回もきっと、移住してこられて困ることがあるでしょう。誰に聞いたらいいのかわからん!っていう雰囲気にはしないので、安心して来ていただければと思います」
今回募集する公営塾スタッフは、地域おこし協力隊としての雇用になる。
任期は最長3年間。ほかの地域だと、任期後はプロデューサーとしてプロジェクトに関わったり、独立して教育やまちづくりに関する事業をはじめた人もいる。
はじまってみないとわからないことも多いけれど、任期後の進路についても、きっとおふたりが相談に乗ってくれると思う。
「教育経験はあるに越したことはないですが、なくても大丈夫です。経験よりも、やっぱり話しやすい人。試行錯誤しながら進めていくことになるので、ためこまずになんでも話せる人のほうがいいと思いますね」
役場をあとにして、今度は甲佐高校へ。
公営塾の設置が予定されている空き教室を覗くと、そこには大きなブルーシートが敷かれていた。
 週末に控えたあゆ祭りに向けて、竹灯籠を製作しているそうだ。
週末に控えたあゆ祭りに向けて、竹灯籠を製作しているそうだ。今はこういった作業時や、部活動のミーティング時に使われているという。
公営塾がはじまったら、ここにどんな風景が生まれていくんだろう。
そんなことを思いながら校長室を訪ねると、校長の山下さんが迎えてくれた。
 「どうぞどうぞ」と出していただいたのはスポーツドリンク。この日、野球部の試合があり、山下さんも応援に行ったそう。
「どうぞどうぞ」と出していただいたのはスポーツドリンク。この日、野球部の試合があり、山下さんも応援に行ったそう。一時は部員が4人まで減り、廃部の危機にあった野球部。それでも毎日欠かさず練習を続け、本気で甲子園を目指してきたという。
「うちの子たちは素直な子ばかりなので、きっと教える側も感動しますよ。双方にとっていい関係が築けているのかなと思います」
 現教育長の蔵田さんから引き継ぎ、校長を務める山下さん。
現教育長の蔵田さんから引き継ぎ、校長を務める山下さん。お話を聞いていくと、蔵田さんと同じく、ひらけた環境での学びを大事にしていることが感じられる。
「甲佐高校には普通科とビジネス情報科の2つの学科があり、普通科はさらに福祉教養コースも設置しています。商業と介護・福祉は、いずれもこれからの日本においてものすごく大事な分野だと思うんです」
具体的には、どんな取り組みをされてるんですか。
「ビジネス情報科では、商工会とタイアップして、特産品のニラを使ったスイーツの開発をしましたね。それから、台湾の春節に合わせて九州各県のものを集めたマルシェを出店するということで、生徒と先生をひとりずつ派遣したり」
 「福祉教養コースのほうでは、今ちょうど3年生が介護施設での体験をしています。今後AIによっていろんなことが置き換えられると思いますが、人と人の交流がまったくなくなることはないでしょうから。子どもたちにはその部分を担ってもらいたいなと思っているんですよね」
「福祉教養コースのほうでは、今ちょうど3年生が介護施設での体験をしています。今後AIによっていろんなことが置き換えられると思いますが、人と人の交流がまったくなくなることはないでしょうから。子どもたちにはその部分を担ってもらいたいなと思っているんですよね」ここで、デスクから一冊の青い冊子を取り出した山下さん。表紙には「学校経営案」と書かれている。
「毎年スローガンを決めているんです。メインテーマの『夢実現』は変わらず、サブテーマを毎年変えています。今年は“百見は一験に如かず”」
ひゃっけんはいっけんにしかず?
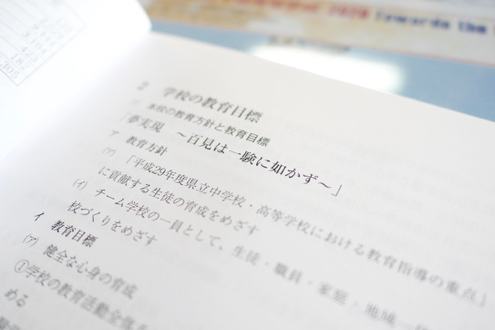 「百聞は一見に如かずと言いますよね。百回聞くより一目見たほうがいい。でも、百回見るよりも一回経験したほうが、本当にいろいろなことがわかるんですよね。絶対に学びも深くなる。いいなと思うんだったらやっちゃいましょう、ということです」
「百聞は一見に如かずと言いますよね。百回聞くより一目見たほうがいい。でも、百回見るよりも一回経験したほうが、本当にいろいろなことがわかるんですよね。絶対に学びも深くなる。いいなと思うんだったらやっちゃいましょう、ということです」甲佐高校では、来年度に女子硬式野球部を創部する。
ある意味、先生たち自身がこの言葉を実践しているように感じた。
「まだ漠然としたイメージしかないですけど、公営塾というのも、社会につながる大きなひとつの切り口になるんじゃないかなと。不安もありながら、今はとてもワクワクしています」
「高校魅力化」と言っても、その高校も、地域も、それぞれにいろんな色を持っているので、一筋縄ではいかないことが想像できます。
甲佐町を取材して感じたのは、地域に開けた実践的な学びの土台が築かれているということ。
だからこそ、今後は個々と向き合う公営塾のスタッフが重要な役割を担っていると思います。
失敗することもあるかもしれない。それでも“百見は一験に如かず”。
甲佐町のみなさんは、あなたの挑戦を楽しみに待っているはずです。
(2017/8/24 中川晃輔)

