※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
人が何かに挑戦したいと思ったとき、背中を押すのはどんなことだろう。考えてみると、自分のほかにすでに挑戦している人が身近にいるかどうか、は大きな要素のひとつかもしれません。知識として知っているだけでなく、身近な存在として感じられる距離にいるかどうか。
挑戦する人が身近にいると、背中を見て「そんなやり方もあるのか」と学ぶこともあるだろうし、「自分だったらこうするのに」とか、「負けたくない」という気持ちも湧いてくる。そうやって自分がはじめると、またそれを見て挑戦する人たちが飛び込んでくる。
今回訪れた宮崎県新富町というまちは、まさにそんな挑戦が連鎖するフィールドのように感じられました。
 挑戦の輪の真ん中にいたのは、こゆ財団のみなさん。
挑戦の輪の真ん中にいたのは、こゆ財団のみなさん。「強い地域経済をつくる」というミッションを掲げ、自分たち自身も挑戦を楽しみながら、この新富町というフィールドを耕し続けている方々です。
今回は、こゆ財団の想いを形にして伝えるデザイナーと、各プロジェクトを進行していくディレクター、プロジェクト全体を把握して統括するマネージャーを募集します。
羽田空港から宮崎空港までは飛行機で2時間弱。
空港から電車に乗り換えると、いろんな景色が窓の外に広がる。宮崎市内のまちなみ、だだっぴろい平野と大きな川、遠くに望む海。中高生が乗り降りすると、車内は少しだけ賑やかになる。
のんびりと電車に揺られること40分、日向新富駅に到着した。
階段を降りた先で待っていてくれたのが、こゆ財団の事務局長を務める高橋さん。
 こゆ財団は、この駅舎のすぐ裏にあるスペースを事務所として使っているそうだ。
こゆ財団は、この駅舎のすぐ裏にあるスペースを事務所として使っているそうだ。「ここではだいたい3名のスタッフが働いています。ふるさと納税の問い合わせに対応したり、商品の登録、在庫管理などもしています」
「あ、コーヒーマシンも届いてますね」
え?コーヒーマシンってどういうことですか?
「いや、駅舎を改修してカフェスペースをつくろうとしてまして。梁に沿って電気を引っ張ってきて、観葉植物を置いて。ここでイベントをしても面白いし、お酒なんかも飲めたら、ふらっと飲んだ後に電車で別の場所に移動するとか、これまで通り過ぎていた方も足を止めてくれるかなと考えています」
ふるさと納税とカフェづくり…。ぱっと結びつかない組み合わせですね。
「ぼくらの取り組みは多岐に渡っているので、掴みどころがないかもしれません。すべてに共通するミッションとして掲げているのは、『強い地域経済をつくる』ことです」
人口約1万7千人の新富町は、全国の地方都市と同じく、人口減少や少子高齢化などの課題を抱えていた。
これに対し、行政としてもふるさと納税に力を入れたり、観光から移住へとつなげるさまざまな施策を練ってきたものの、どうしても実行に至るまでのスピード感に欠けてしまう。また資金面でも、補助金などに依存しない持続可能な形態をとる必要があった。
そこで、新富町が設立した地域商社がこゆ財団なのだそう。
「行政から生まれた団体ですけど、ありようはベンチャー企業そのものですね」
こゆ財団がまず着目したのが、特産品のライチ。国産ライチのほとんどが宮崎と鹿児島のみでつくられていることに加え、新富町のライチは実の大きさや味の面でも際立っていた。
 そこで「楊貴妃ライチ」としてブランド化し、空港や都心部、ネットショップなどの販路を開拓。東京のカフェとコラボレーションしたケーキは、1カット3,000円という価格ながらあっという間に完売したそう。
そこで「楊貴妃ライチ」としてブランド化し、空港や都心部、ネットショップなどの販路を開拓。東京のカフェとコラボレーションしたケーキは、1カット3,000円という価格ながらあっという間に完売したそう。さらに、限定120本で製造したライチビールも、地元の酒店限定での販売にもかかわらず3時間で完売。ライチアイスやライチボディクリームなど、新商品の開発にも乗り出している。
 このように、地域資源を活かした商品開発や販路開拓、ふるさと納税によって資金を調達しているこゆ財団。
このように、地域資源を活かした商品開発や販路開拓、ふるさと納税によって資金を調達しているこゆ財団。8ヶ月という期間でここまでの成果をあげるのはたしかにすごいことだけれど、果たしてこれだけで「強い地域経済をつくる」までに至るんだろうか。
「儲けて終わり、では意味がないので。そのお金を人に投資しています」
具体的にはどういうことでしょう。
「たとえば、空き家を改修して古民家ゲストハウスにする。そこをぼくらが直営するのではなく、オーナーとして起業する人を募集するんです。あるいは、シャッターをおろしてしまった商店街の空き店舗に許可をいただいて、何かはじめたい人に使ってもらう」
 「ぼくらが畑を耕し、そこに種をまいて、育てる人を募るという形の起業家支援です。今もいろんな事業が芽を出しはじめているんですよ」
「ぼくらが畑を耕し、そこに種をまいて、育てる人を募るという形の起業家支援です。今もいろんな事業が芽を出しはじめているんですよ」元地域おこし協力隊の方が商店街にバーを開店したり、まったくの未経験から農業分野で起業するために、福岡から移住してきた人がいたり、地元のきゅうり農家さんがIT技術を取り入れたアグリテックの可能性を模索していたり。
何か挑戦したいという想いをもった人たちが、次々に集まりはじめている。
また、こゆ財団は、「児湯シータートル大学」や「地域を編集する学校」などの起業家育成プログラムを実施したり、起業家の伴走支援にも力を入れている。
目指すは「食と農のシリコンバレー」だそう。
「ガチガチのルールをつくっても根付かないので。まずはぼくら自身が常にオープンで、あらゆる種を受け入れていくような、そういう豊かな土壌であり続けたいですよね」
豊かな土壌。
「ふかふかなら落ちても痛くないというか。失敗してもやり直せるじゃないですか。だからぼくらは、これからもまちを耕し続けていきます」
 たしかに、こゆ財団の取り組みは農業に通じるものがあると思う。畑を耕すように、まちに眠る資源を掘り起こし、そこに起業家という種を植えて、成長を見守る。
たしかに、こゆ財団の取り組みは農業に通じるものがあると思う。畑を耕すように、まちに眠る資源を掘り起こし、そこに起業家という種を植えて、成長を見守る。今回は、そんなこゆ財団の想いを形にして伝えるデザイナーの募集がメインとなる。
現在は外注しているデザイン業務を内製化し、よりスピーディーに形にしていきたい。
「専門領域は問いません。たとえばグラフィックのできる人だったら、募集ページや商品のパッケージをつくりつつ、Webはディレクションで関わったり。専門で区切るというよりも、『強い地域経済をつくる』というミッションに対して自分だったらどう貢献できるかを考えられる人に来てもらいたいです」
また、個々のプロジェクトに伴走するディレクターと、各プロジェクトを束ねて進行管理するマネージャーも募集する。
いずれも実務経験があるに越したことはないものの、必須ではない。こゆ財団のミッションに共感し、自分の力をここで発揮したいと思えるかどうかが重要だと思う。
高橋さんの運転する車に乗って、商店街の元クリーニング屋さんをリノベーションした「ソーシャル・ビジネス・ラボ」へ向かう。
 起業家たちの活動拠点としての機能に加え、地域住民との交流や打ち合わせにも使えるコミュニティ&コワーキングスペースとして運営している場所だという。
起業家たちの活動拠点としての機能に加え、地域住民との交流や打ち合わせにも使えるコミュニティ&コワーキングスペースとして運営している場所だという。続いて話を聞いたのは、代表理事の齋藤さん。
地域プロデューサーとして全国各地の地方創生事業に携わってきた方だ。
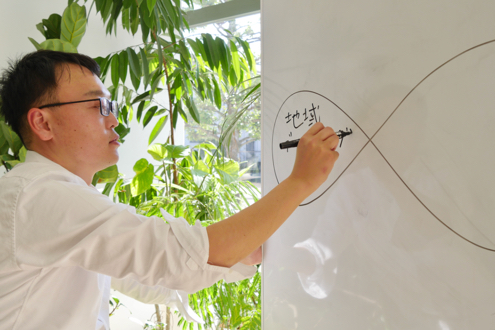 「チャレンジするフィールドを探している人にとって、このまちはすごくいい環境だと思います。それは自分探しとは違っていて。ここにしばらく居続けるというよりも、次のステップに進むために来てほしい」
「チャレンジするフィールドを探している人にとって、このまちはすごくいい環境だと思います。それは自分探しとは違っていて。ここにしばらく居続けるというよりも、次のステップに進むために来てほしい」これまでに全国各地で仕事をしてきた齋藤さん。そのなかでも新富町は“よそ者”を受け入れる寛容さがあり、一緒に挑戦しようという姿勢の人が多いように感じるという。
「財団のスタッフそれぞれが、まさに挑戦中なんです。最初は戸惑っていたスタッフが、ふるさと納税でものすごい売上を達成していたり、広報に関しては素人だったスタッフが、テレビや雑誌でもどんどん発信するようになったり」
 メディアには「楊貴妃ライチ」や「地域商社」など、こゆ財団の活動を示す言葉がどんどん取り上げられている。
メディアには「楊貴妃ライチ」や「地域商社」など、こゆ財団の活動を示す言葉がどんどん取り上げられている。もちろん発信する力がついてきたのはいいことだけれど、「表面的なアウトプットだけを見て来てほしくない」と齋藤さん。
その裏で起こっている財団スタッフやまちの人たちの意識、そして行動の変化こそ、大きな価値があるからだそう。
「まちの人がヒーローになり、そうこうしているうちに県内外からいろんな人が集まって、移住してきたり、楽しく過ごしています。ぼくたちはそんなエコシステム、挑戦しやすい生態系をこのまちにつくっていきたい。まちの風景を変えたいなと思っています」
最後に話を聞いたのは、東京の会社を辞めて独立し、今まさに移住を検討しているという小野茜さん。
 「出身が千葉県の松戸市で、それまで地方のことをまったく知らずに生きてきたんです。休みもいらないし、都会でバリバリ仕事していたほうが充実してると思っていました」
「出身が千葉県の松戸市で、それまで地方のことをまったく知らずに生きてきたんです。休みもいらないし、都会でバリバリ仕事していたほうが充実してると思っていました」ABC Cooking Studioで広報と新規事業を担当していた小野さん。地域の観光と絡めた料理教室をすることになったのが、移住を考えはじめるきっかけだったそう。
あるとき、仕事で新富町を訪ね、こゆ財団の執行理事の家に招かれた。
「奥さんに料理してもらって、素敵なおうちに住まれて、地域のために一生懸命がんばっている。今までかっこいいと思ってきた働く人の像が、まるで覆ったような瞬間でした。その話はまだ誰にも話していないので、『なんで来るの?』ってよく聞かれるんです(笑)」
そのときの体験が、小野さんにとってはかなり大きかったんですね。
「そうですね。今持ってるものをある程度手放したとしても、本当に人間らしく生きていくことのほうが心地いいかもしれない。そう思ったときに、あ、地方に行くってそういうことかなって」
小野さんは広報の一人としてこゆ財団と関わりながら、自分の仕事をつくっていくつもりだそう。今回募集する人とも関わる機会は多いと思う。
ちなみに小野さんは、何かここでチャレンジしたいことってありますか。
「これまで一貫して食に携わる仕事をしてきたので、そこの軸はぶらさないというか。食べものだったり、食べることが好きなんですよね」
「それが飲食店なのか、物販なのかはまだわからないです。地域に貢献できること、本当に自分がやりたいと思うことを見つけて、ここで挑戦したいなと思っています」
 挑戦の土壌をつくっているのは、自ら挑戦する人たちでした。
挑戦の土壌をつくっているのは、自ら挑戦する人たちでした。その背中に惹かれ、あるいは刺激を受けた人たちが集まり、新たな動きを生んでいる。
今回もぜひ挑戦するつもりで応募してほしいと思います。
自らも挑戦者として、このフィールドをともに耕す人を待っています。
(2017/12/21 取材 中川晃輔)






