※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
自信をもつことは、次のステージへいってみようという勇気になると思う。
たとえば、「ありがとう」「たすかったよ」という言葉をもらったとき。自分で稼いだお金ではじめてアパートを借りたとき。
仕事って、自分を成長させるひとつの手段かもしれません。

千葉県木更津市にある
特定非営利活動法人コミュニティワークスは、障がいのある人が地域で働くための就労支援をしています。
支援というと“助けてあげる/もらう”という関係を想像するけれど、ここでは障がいのある利用者さんとスタッフが「きちんと稼ぐ」という同じ目標をもって、一緒になって働いていました。
だからでしょうか。働くスタッフたちは「関わりの中でお互いに変わっていく感じがある」と話します。
今回は、そんな関わり方をしてみたい人を募集します。

働く場所は、ものづくりをする「地域作業所hana」か、農園もある「カフェ&雑貨店hanahaco」のどちらか。
障がいがあってもなくても、しっかり稼いで自信をつける。そんな働き方に興味のある人は、ぜひ続けて読んでみてください。
木更津へは、東京から電車で1時間半。電車のほかにもアクアラインを通るバスが走っていて、こちらは1時間ほどで着くそう。
あいにくの雨。
駅につくと、代表の筒井さんが迎えてくれました。

車に乗り込み、駅から5分ほどのところにある「地域作業所hana」へ向かいます。道中、これまでのお話を聞いてみました。
「もともと木更津でまちづくりをしていて、はじめから福祉に興味があったわけじゃなかったんです」
きっかけは、まちづくりを通してとてもお世話になった方にあるお願いをされたことだと言います。
「その方の息子さんが障がいのある方で、仕事を探していました。『お給料はなくてもいい、筒井くんのところで仕事を手伝わせてほしい』と頼まれて。親ですから子どもが可愛くないわけがない。それでも福祉の知識もない僕に頼むくらい、地域に働く場所がないんだと知りました」
行政から出る障がい者の職業訓練に対する謝金を給料として渡しながら働いてもらううち、自分も働きたいと申し出る障がいのある方や家族からの連絡が増えてきた。
そこで「これは本腰を入れて取り組まないとできないことだな」と思い、8年前に特定非営利活動法人コミュニティワークスを立ち上げます。
はじめにつくったのは、製菓や縫製、制作などものづくりをする「地域作業所hana」。hanaはハワイ語で“仕事”という意味なんだそう。
ちょうどhanaに到着。障がい者施設というと、もっと無機質な建物を想像していたけれど、木の壁とたくさんの窓があって開放的な雰囲気。

ここに通う利用者さんは、1日20名ほど。
1階の厨房で製造していたのは、パティシエ監修のもとにつくられたという本格的な焼き菓子。マザー牧場さんに卸しているもので、パッケージは絵本作家さんが描いているのだそう。
2階では雑貨の組み立てやパッキング、縫製など、様々なものづくりをしています。この日縫っていたのは、ミュージアムショップなどで扱われているというバッグ。
見ていると、hanaでつくるものはデザイン性や商品としてのクオリティが高いような気がする。
すると、筒井さん。
「障がい者施設がつくったということで売るのではなくて、きちんと世の中に流通するものをつくって売っていきたいんです」

そこにはどんな思いがあるのだろう。
「就労支援施設で働く障がいのある方の工賃(給料)って、すごく安いんです。障がい者の就労支援施設は全国に9,000箇所以上あって、月給の平均は14,838円、時給平均は187円(平成26年度)です」
「丁寧な仕事をして、フルタイムで働いてその金額です。でも、障がいがあるから正当な給料をもらえないというのは、ちょっと違う気がしていて。ぼくは、労働して正当な対価をもらうというのは基本的人権のなかに含まれると思うんです」
コミュニティワークスが目指しているのは、最低賃金を支払う就労支援施設であること。
だからこそ世の中に流通できる商品を意識し、デザインやクオリティも大切にしています。
ふと、英字新聞の紙バッグを折る利用者さんの手元を見る。
慣れた様子で、けれど一つひとつ角を合わせて丁寧に折り、針をつかって糊付けしていく。

そんな作業の丁寧さが評価されて、クライアントからリピートの注文があったり、他のクライアント先を紹介してもらえることも増えてきた。
平均時給もhanaは325円、hanahacoは407円(平成27年度)まで上がってきたという。
「できることを増やそう、丁寧にやろうっていう利用者さんの努力はもちろんあります。でも、スタッフの支援の仕方も同じくらい大きいと思いますよ」
どんなふうに支援しているんだろう。
スタッフの方に会いに、hanaから車で15分ほどのところにある「カフェ&雑貨店hanahaco」へ向かいました。
里山カフェとして雑誌やメディアに紹介されるhanahaco は、田んぼの見渡せる丘の上にある。
もともとは、野菜づくりやカフェとショップの経営を通して、自分たちで障がい者の仕事を生み出したいという思いからはじまった場所だから、訪れるお客さんの多くはここが障がい者支援施設だとは知らないそう。

扉を開けると、右手側には小さなセレクトショップ。hanaでつくられたものや、同じく手仕事でつくられた工芸品やフェアトレードの商品が並びます。
ショップから中庭を挟んだ奥のテーブルで、スタッフの三浦さんと高梨さんにお会いしました。ふたりとも日本仕事百貨を通して入社し、丸3年が経ったところ。
はじめにお話を伺ったのは、hanaでお菓子製造全般を担当している三浦さん。
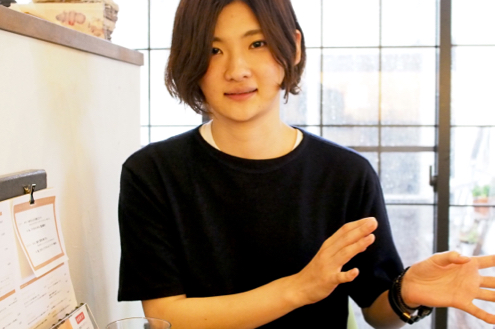
これまで、福祉の仕事をしたいとは思っていなかったそうです。
「福祉という言葉があまり好きではなかったんです。母がピアノの先生をしていて、生徒さんに障がいのある方が3、4人いらしていたので小さいころから交流があったんですよね」
「みなさん作業所に通っていたんですけど、そこでの話を聞くと『たのしくないんだよね』って。仲のいい支援員さんもいなくて、なんだか囲われているような、閉鎖的な感じが伝わってきたんです」
福祉のイメージがよくなかったんですね。
「でも、ここの求人記事を読んだとき、心惹かれるものがありました。支援する人とされる人っていう明確な線引きがないように感じたんです」
入ってみて、どうでしたか?
「もちろん最低限の支援はしないといけません。けれどやっぱり、線引きしている感じはなくて。忙しいときはみんなで一緒にバタバタするし、ときには利用者さんと『なんでこれやっておいてくれなかったの?!』『だってこう言ってたじゃないですか』って、兄弟みたいな言い合いをすることもあります(笑)」
えっ!
「でも、それでいいんだと思うんです。なんでもかんでも『大丈夫だよ、大丈夫だよ』と言って守りすぎるのも、その人のためにならないのかなって」

「私自身、そんな関わりを通して大事なことに気づかされるときがあります」
今、主に三浦さんがやっているのは、お菓子の製造と利用者さんへの作業支援、それから納期に向けた生産スケジュールづくり。
利用者さんとスタッフが一緒になって進めていくのだけど、以前こんなことがあったそう。
「ある利用者さんにお菓子の製造作業をお願いするとき、焼菓子の粉付けや袋のシーリングはその方にとって難しいだろうし、ミスをしたら利用者さんが傷ついてしまうと思って、その作業はわたしが全てやって、その方には淡々とできる生地の丸め作業をお願いしたんです」
よかれと思ってしたことだったけれど、後になって、その利用者さんが「自分は頼りにされていないと感じた」と話してくれたそう。
「わたしが勝手にその人の能力の限界を決めつけて、できるようになるチャンスすら奪ってしまっていたんですよね。支援に限らず、人と一緒に何かをするときは相手を決めつけないように気をつけないといけないなって、すごく反省しました」
それからは少し時間がかかっても、「できそう?」と聞いて一緒にやってみるのだそう。

「利用者さんも、やらされるんじゃなくて、自分でやるから自信が持てる。『難しいからやらない』ではなくて、どうやったらその作業ができるようになるのかを一緒に考える。だからこそ、試行錯誤しながら、一緒に成長できるチャンスがあると思います」
すると、隣で話を聞いていた高梨さんも「そうだね」と頷く。
高梨さんも、まったくの未経験から福祉の世界へ飛び込んだ方。今はhanahacoでカフェとショップの接客をしつつ、運営や支援にも携わっています。

「ここでの働き方は、イコール関わり方だと思います」
「とは言っても、好き嫌いの感情だけで関わるんじゃない、同じ目的を持った仲間という感じなんです」
同じ目的、というと?
「そもそも、利用者さんそれぞれに『こういうふうに変わりたい、こういうふうに暮らしたい』という希望があって、わたしも今の自分からもっと変わりたいという思いがある。それを叶える大きな要素の一つが、稼ぐことなんです」
「私たちは、利用者さんの工賃も上げたいし、もっと言えば、自分の給料だって上げたい。目的をちゃんと共有して意見を言い合える環境があるので、やりがいがありますよ」
hanahacoでは、お店側で調理補助などの仕事する利用者さんのほかに、障がいの重い利用者さんもお店の裏方役として通っています。
障がいの重い利用者さんに対しては、その人に合った仕事を発見することも支援の一つ。
例えば、ある全盲の方には、自社でつくっている青竹踏みの竹のヤスリがけの仕事がぴったりだそう。目でなく手の感触で確かめるから、触り心地がとてもよい。
一方、お店側のスタッフは、調理補助や店内清掃、農園での畑仕事など、利用者さんのできることを一つでも増やすような支援をしています。

「そういった支援のほかに、カフェの接客やイベントの企画、ショップの管理や商品発注もあるので、ゆっくりはしていられないです」
「でも、ばたばたするときは利用者さんもスタッフも一緒にばたばたしてくれるので。お互いに大変だけど、しっかり稼ぐことも大切ですからね」
障がいがあるから、とか、障がい者施設だから、というのではなく、ふつうに働いて、稼ぐ。
ここは、人との関わり方だけでなく、社会との関わり方にも線引きがないのだろうな。
だからどこか開放的な雰囲気があるのだと思います。
最後に、高梨さんにどんな人に来てほしいか聞いてみました。
「生活とか、家族とか、多様なバックグラウンドをもったスタッフたちが言いたいことを言い合っているのがhanaやhanahacoらしさかもしれない(笑)。利用者さんにとっても、そういった”人のバラエティ”がプラスにはたらくことが多いと思います。だからぜひ、年代も性別も様々な人に応募してほしいです」
(2016/9/13 倉島友香)
募集職種
障がい者福祉施設(福祉作業所)での作業指導+生活支援員
雇用形態
(1) 正社員
(2) パート/アルバイト
いずれも、研修期間となる入社後~7か月は有期雇用となり、その後も雇用継続する場合には無期雇用となります。
給与
(1) 正社員
月給170,000円~175,000円(基本給)
(2) パート/アルバイト
時給870円(研修期間の7か月間は850円)
待遇・福利厚生
(1) 正社員
・昇給あり(年1回)
・賞与あり(年2回:年合計で4~5か月程度・業績次第)
・通勤手当(上限24,500円/月:マイカー通勤可)
・職務手当(26,100円/月:みなし残業代含む)
・住宅手当(上限20,000円/月:条件あり)
・処遇改善手当(年1回)
・育児応援手当(法人の指定託児所に子ども(小学校3年生まで)を預ける場合、利用料の半額(上限30,000円/月)を会社が負担)
・退職金共済加入(全額会社負担)
・社会保険(健康保険・雇用保険)
・厚生年金加入
・引越し応援金(遠方から木更津市内に引越しをする場合、引越しにかかった費用を15万円を上限として支給)
※基本給は、社内職能等級基準により昇格・降格が設定されています。当求人に記載されている給与額は、1等級に該当します。
※職務手当・賞与・退職金共済は研修期間(有期雇用)終了後からの適用となります。
(2) パート/アルバイト
・昇給あり(年1回)定期昇給と能力給により毎年改定
・通勤手当(上限24,500円/月:マイカー通勤可)
・処遇改善手当(年1回)
・社会保険(健康保険・雇用保険)・厚生年金は勤務日数・時間数により必要に応じて加入
・子育て応援制度(法人の指定託児所に年間50時間まで無料で子ども(小学校3年生まで)を預けることができる。主に緊急時や病児を想定)
仕事内容
■地域作業所hana
就労継続支援B型事業所「地域作業所hana」で、障がいのある方に対して、作業の指導や生活支援を行うお仕事です。私たちは、障がいのある方への最低賃金の支払いを目標に、さまざまな作業に取り組んでいますが、主な仕事内容は下記になります。
<新聞エコバッグ生産+作業支援>
全国テレビでも紹介をされたことがある、不要になった英字新聞を活用した新聞エコバッグは、地域作業所hanaのオリジナル商品です。現在も多くの企業様や店舗様からご発注を頂いており、障がいのある方への作業指導はもちろんのこと、進捗や商品管理、検品による品質チェックなどが職員の仕事になります。現在は新たなラインナップ発表に向けての準備も進めているため、商品づくりの試行錯誤が好きな方も大歓迎です!
<製菓作業+作業支援>
私たちの製造するお菓子は、トップパティシエの方に監修していただき、パッケージデザインも絵本作家の先生に描き下ろしていただいた今大人気の商品です。厨房内での菓子製造、障がいのある方への作業の指示出し、生産量の調整、スケジュール組み立てなどが主な仕事になります。今後は生産量や商品数も増やしていく予定です。(「テミルプロジェクト」に参加しています)
<ブランド雑貨生産+作業支援>
複数の雑貨ブランド様からお仕事を受けており、年間を通じた作業のほか、新たな仕事もどんどん入ってきています。その都度、制作工程を分解し、障がいのある方それぞれが作業に取り組みやすい方法を考え、作業の割り振りをし、品質や納期管理をするのが職員の仕事になります。
<縫製作業+作業支援>
デザイナー様や企業様からの委託による縫製作業に取り組んでいます。ロックミシンや職業用ミシンも備えており、多くの商品に対応しています。縫製指導ができる職員が不足しているため、縫製経験のある方は大歓迎です。
その他、ケース記録の入力、電話対応などもあります。
■hanahaco
就労継続支援B型と生活介護の多機能型事業所「hanahaco」で、障がいのある方に対して、作業の指導や生活支援を行うお仕事です。私たちは、障がいのある方への最低賃金の支払いを目標に、さまざまな作業に取り組んでいますが、主な仕事内容は下記になります。
<カフェ運営+作業支援>
千葉県産の野菜や肉、フェアトレードなどこだわりのある食材を使い、おいしく健康的なメニューを提供するカフェで、ホール業務の他、宅配弁当作りや料理長をサポートしたり、ご利用者様(障がいのある方)が担当する食材の下準備や洗い物、ドリンク入れ、店内清掃などの支援を行います。
<ショップ運営+作業支援>
関連施設である「地域作業所hana」で生産している雑貨品やそれ以外の福祉作業所で生産されているもののほか、フェアトレード商品やアップサイクル雑貨、ナチュラル系のお洋服、日本の伝統技術から生まれた商品など、1つ1つの商品にストーリーのあるものをセレクトしたライフスタイルショップの運営です。接客や品出し、ディスプレイはもちろんのこと、販促イベントの企画運営やご利用者様に在庫管理やメンテナンスに関わって頂くための支援も担当してもらっています。
<農作業+作業支援>
hanahacoの事業所から車で10分ほどのところに農場があります。地域の方々にもご指導を頂きながら、できるだけ農薬を使わずに、年間を通じて様々な野菜や綿花を生産しています。採れた野菜はhanahacoでサラダバーやランチに使われているため、第六次産業などに興味のある方も大歓迎です。
<生活介護での作業支援+生活支援>
カフェで使う箸の袋入れやおしぼりづくり、ユニフォームの洗濯・アイロンがけ、ショップで使う紙袋のロゴスタンプ押しなど、縁の下の力持ちとして、生活介護(常時の介護が必要な障がい者を対象とした福祉サービス)のご利用者様にこれらのお仕事を担って頂いています。職員はこれらのサポートを行うほか、綿づくりや創作活動にも今後は取り組んでいきたいと考えています。
その他、車でのご利用者様の送迎やケース記録の入力、電話対応などもあります。
勤務地
・地域作業所hana(千葉県木更津市文京6-4-4 :JR木更津駅から徒歩約15分)
・hanahaco(千葉県木更津市矢那1879-1 :JR木更津駅から車で約20分)
※勤務地の希望はうかがいますが、採用後に決定をさせて頂きます。また法人内異動もあります。
勤務時間
(1) 正社員
9:00~17:15(休憩時間 12:00~13:00) ※早番・遅番もあり
(2) パート/アルバイト
9:00~17:00(休憩時間 12:00~13:00) ※相談可
休日休暇
(1) 正社員
シフト制による4週7休 年末年始休暇、有給休暇あり、土日祝日の勤務必須
(2) パート/アルバイト
週3~5日勤務 ※相談可 年末年始休暇、有給休暇あり、土日祝日の勤務ができる方優先
応募資格
応募資格は特にありません。どなたでもご応募可能です。
※福祉資格・経験、学歴は不問です。
※送迎業務もあるため、普通自動車免許があると尚可です。
求める人物像
<求める人物像>
・法人内だけでなく広く地域や社会で役立てる人材
・次なる行動を自発的に考え動ける人材
・一緒に事業や法人を創造できる人材
・どんな状況でも原因の矢印を常に自分に向けることができる人材
※クレド(行動指針)を事前にご覧ください。
http://npo-cw.net/credo.html
<こんな職場です>
・風土はベンチャー気質です。道なきところに道をつくるので、考えつつも、まずはやってみることが奨励されます。
・障がい者の工賃(給与)向上のために、常に新たな仕事を作り出すことを求められます。
・小さな会社なので、企画・開発から体を動かす実動、さらにはその後の事務仕事までを全員がやらなければなりません。
・問題は常におきます。そして問題一つ一つを解決する議論やプロセスを大切にしています。
<こんな方は向いています>
・素直に社内文化を吸収し、自発的かつ積極的に物事にあたることができる根性ある方
・自分の担当に関係なく「何でもやる」精神を持っている方
・「好き」なことと「仕事」をうまく結び付け、何事も楽しくするのが得意な方
・モノ作りや飲食業、雑貨販売に興味があり、チームワークを大切にできる方
<こんな方は向いていません>
・自分から仕事を見つけたり、仕事を抱えている人のフォローに自ら入れない方
・問題や困難を他人や環境のせいにし、自分が変わることでの解決を実践することができない方
・研修やミーティングなどで、自分の考えを発言したり、建設的な議論をするのが苦手な方
・業務報告やケース記録はパソコンを使います。メールでのコミュニケーションが苦手な方は向いていません。
募集期間
2016/09/13~2016/09/27
採用予定人数
(1) 正社員
2~3名
(2) パート/アルバイト
若干名
選考プロセス
まずは下記よりエントリー・お問合せください。
(エントリーの場合は、同時に履歴書・職務経歴書・志望動機についての作文の3点を9月30日(金)必着にてご郵送いただきます。詳しいご案内はエントリー後にメールにて送らせて頂きます。)
↓
書類選考(10月1日(土))、結果郵送
↓
面接選考・適性診断(10月8日(土)) ※面接会場は地域作業所hanaとなります。
↓
採用(11月1日~の勤務を予定、研修期間7か月あり、事前の入社説明会へ参加をお願いします)
※ご応募前の事前の事業所見学やご質問等は随時可能です。お気軽にお問い合わせください。
※取得した個人情報は、採用選考にのみ使用します。
※選考プロセスは変更になる可能性があります。
※不採用理由についての問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。
その他
・全国からのご応募、大歓迎です!
正社員の場合、遠方から木更津市近隣への引越しを希望される場合には、引越し応援金として、引っ越し費用を法人で負担(上限15万円)する他、毎月の住宅手当の支給もあります。また、住まいの紹介などのできる限りのフォローをさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。
・子育て世代の方が思いっきり力を発揮できる環境があります!
現在働いている多くの職員が子育てをしていることもあり、子どもの急な病気などによる欠勤や早退・遅刻は常に周りが快くフォローし合える環境があります。また、パート職員は法人の指定託児所に年間50時間までは無料で子ども(小学校3年生まで)を預けることができるほか、正社員は利用料の半額(上限3万円)を法人で負担するなど、子育て世代の方が、ご自身の能力を存分に発揮することができる環境を整えています。
・事前にホームページをぜひご覧ください!
福祉経験は問いませんが、私たちの理念やビジョンに共感していただけないと一緒に働くことは難しいため、事前にホームページやFacebook等に目を通していただければと思います。
・
法人ホームページ
・
事業所ホームページ(hana)
・
事業所ホームページ(hanahaco)
・
Facebook(hana)
・
Facebook(hanahaco)
*過去の募集記事もご覧ください。
「それぞれのhana」
「誇りをつくる」
 千葉県木更津市にある特定非営利活動法人コミュニティワークスは、障がいのある人が地域で働くための就労支援をしています。
千葉県木更津市にある特定非営利活動法人コミュニティワークスは、障がいのある人が地域で働くための就労支援をしています。 働く場所は、ものづくりをする「地域作業所hana」か、農園もある「カフェ&雑貨店hanahaco」のどちらか。
働く場所は、ものづくりをする「地域作業所hana」か、農園もある「カフェ&雑貨店hanahaco」のどちらか。 車に乗り込み、駅から5分ほどのところにある「地域作業所hana」へ向かいます。道中、これまでのお話を聞いてみました。
車に乗り込み、駅から5分ほどのところにある「地域作業所hana」へ向かいます。道中、これまでのお話を聞いてみました。 ここに通う利用者さんは、1日20名ほど。
ここに通う利用者さんは、1日20名ほど。 そこにはどんな思いがあるのだろう。
そこにはどんな思いがあるのだろう。 そんな作業の丁寧さが評価されて、クライアントからリピートの注文があったり、他のクライアント先を紹介してもらえることも増えてきた。
そんな作業の丁寧さが評価されて、クライアントからリピートの注文があったり、他のクライアント先を紹介してもらえることも増えてきた。 扉を開けると、右手側には小さなセレクトショップ。hanaでつくられたものや、同じく手仕事でつくられた工芸品やフェアトレードの商品が並びます。
扉を開けると、右手側には小さなセレクトショップ。hanaでつくられたものや、同じく手仕事でつくられた工芸品やフェアトレードの商品が並びます。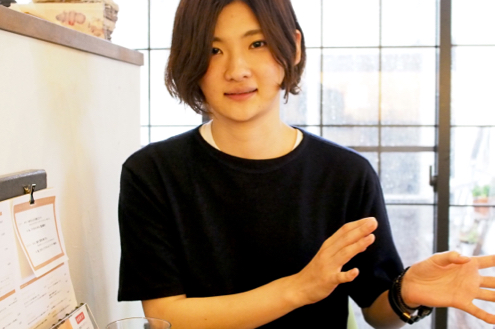 これまで、福祉の仕事をしたいとは思っていなかったそうです。
これまで、福祉の仕事をしたいとは思っていなかったそうです。 「私自身、そんな関わりを通して大事なことに気づかされるときがあります」
「私自身、そんな関わりを通して大事なことに気づかされるときがあります」 「利用者さんも、やらされるんじゃなくて、自分でやるから自信が持てる。『難しいからやらない』ではなくて、どうやったらその作業ができるようになるのかを一緒に考える。だからこそ、試行錯誤しながら、一緒に成長できるチャンスがあると思います」
「利用者さんも、やらされるんじゃなくて、自分でやるから自信が持てる。『難しいからやらない』ではなくて、どうやったらその作業ができるようになるのかを一緒に考える。だからこそ、試行錯誤しながら、一緒に成長できるチャンスがあると思います」 「ここでの働き方は、イコール関わり方だと思います」
「ここでの働き方は、イコール関わり方だと思います」 「そういった支援のほかに、カフェの接客やイベントの企画、ショップの管理や商品発注もあるので、ゆっくりはしていられないです」
「そういった支援のほかに、カフェの接客やイベントの企画、ショップの管理や商品発注もあるので、ゆっくりはしていられないです」
