※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
奈良に302年続く老舗、中川政七商店。『奈良晒』と呼ばれる、奈良特産の高級麻織物の卸問屋からはじまり、時代の波を乗り越えながら、ものづくりを続けてきた会社です。
13代社長の中川政七さんは、就任当初から「14代は中川家以外に継いでもらう」と話していました。
そして今年。日本仕事百貨を通じて7年前に入社した千石あやさんが 14代社長に就任し、新体制を支える仲間を一挙に迎えることになりました。

日本の工芸を元気にするため、変化をいとわず進み続ける中川政七商店。
この記事では、全国の直営店で販売に関わる人を募集します。
 ただ物を売るための接客ではなく、お客さまの心に接して、会話、商品、お店で体験できることを通してブランドを楽しんでもらうこと。
ただ物を売るための接客ではなく、お客さまの心に接して、会話、商品、お店で体験できることを通してブランドを楽しんでもらうこと。全国に52を数えるお店には、そんな“接心好感”という考えをもとに、ブランドの魅力を伝える人たちがいます。
店舗で働いているのは、はじめて就労を経験する学生さんや、子育てと両立しながら働くお母さん、お店づくりの楽しさを知ってどんどん挑戦を続ける店長さんなど、立場も経験も様々です。
「これ、かわいい!」
そんな入り口でお店に出会い働きはじめた人が、数年後にはいくつもの店舗を束ねるスーパーバイザーになっていることもある。
スタッフが自分の目標を見つけて成長していくために、中川政七商店には、その挑戦をサポートする制度があります。
奈良にある中川政七商店の本社で、小売部部長の吉岡さんに話を聞きました。
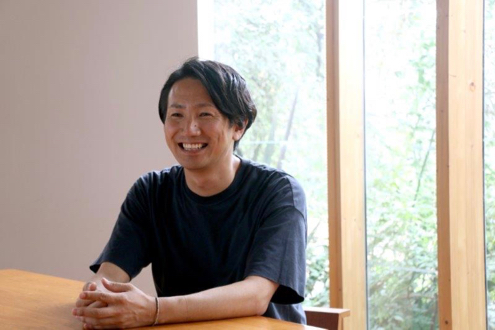 小売部は、全国の直営店と本社をつなぐハブのような役割をしていて、吉岡さんもスーパーバイザーや、それぞれの店舗の店長と連携しながら新しいお店の出店や、業務改善に取り組んでいる。
小売部は、全国の直営店と本社をつなぐハブのような役割をしていて、吉岡さんもスーパーバイザーや、それぞれの店舗の店長と連携しながら新しいお店の出店や、業務改善に取り組んでいる。「毎年、平均5軒くらいの新しいお店を出店しています。最近は、都市部だけじゃなくて、郊外や地方にも徐々に増えてきていますね。」
地方のお店では、福岡の“久留米絣”、高崎の“だるま”など、その土地の工芸品を取り入れながら店舗ごとの特色を打ち出している。東京では、“まるごと試せる”をテーマにすべての商品をその場で試せるお店や、高級工芸の世界を紹介する店舗など、旗艦店として工芸の魅力を知ってもらうための新しい試みをしているお店もある。
 売上不振が続く店舗には直接出向いて一緒に問題に向き合うこともある。
売上不振が続く店舗には直接出向いて一緒に問題に向き合うこともある。「以前、大阪の店舗が長い期間伸び悩んでいた時に、名古屋地区の店長と一緒にV字回復プロジェクトに取り組んだことがありました」
吉岡さんたちが、当時不振だったお店を分析して至った最大の課題は、接客の消極性。
「最初は、スマイルトレーニングをしたり、一緒に売場に立ってお客さまへのお声がけのタイミングを掴むところから始めました。3週間くらいして、様子を見に行ったら、遠くからでも大きな声が聞こえてきて、満面の笑みで迎えてくれたんです。前とは違うお店のように明るくみえました」
一時は、かなり落ち込んでいた店舗。
改善の取り組みのあと、そこで働いていたアルバイトスタッフが社員登用の試験を受けたとの報告があった。
「自信を持って前向きになってくれたことが、何よりもうれしかったですね!」
 アルバイトスタッフが、社員、さらに店長やスーパーバイザーを目指すことも多い。
アルバイトスタッフが、社員、さらに店長やスーパーバイザーを目指すことも多い。誰でもステップアップに挑戦できるように、中川政七商店には以前から、“社内公募制”という仕組みがあった。
その制度を利用して挑戦しようとする人のなかには、販売員から店長へのステップアップの段階で、はじめてのマネージメント業務や店長の役割に戸惑う人も多かったという。
「店長それぞれに、得意もあれば不得意もあります。だから、はじめての店長でもわかるような運用に、整理し直しました」
お店ではたった一人の店長でも、全国には同じ業務に向き合う先輩や仲間がいる。販売計画や売上管理、スタッフの教育、商業施設との折衝など、ほかの店長やスーパーバイザーの経験やを吸い上げて、心構えから具体的な行動までわかりやすくまとめ直した。役職と役割に応じて、求められるスキルも明確になった。
目的と手段をきちんと示すことで、スタッフ一人ひとりがステップアップを考えられるような環境をつくっている。
「店長には責任だけでなく、『私はこんな店を作りたい』という志をもって働いてほしいと思っています。その志があれば、人を巻き込み、一緒に理想の店をつくっていくことができる。それが店長の醍醐味ですよね」
自分ごととして「私の店」を考えていく。
「一人でも多くのお客さまに中川政七商店のファンになってもらいたい。さらに言うと、『あなたに会いに来たの』って言ってもらえたら、販売員冥利に尽きますよね」
店舗で働く人たちはみんな「ブランドの顔」でもある。
 ものづくりの背景、産地のこと、ブランドの世界観、お店に来たお客さんがそれを肌で感じられるためのコミュニケーションを心がけている。
ものづくりの背景、産地のこと、ブランドの世界観、お店に来たお客さんがそれを肌で感じられるためのコミュニケーションを心がけている。「店舗で働く上で一番大切な接客。その中で指針になるものとして、僕たちは“接心好感”という言葉を使っています」
接心好感。
「ただものを売るということだけじゃなくて、商品の背景を知ることも含め、お客さまにお店での時間を心地よく過ごしていただきたい。そのために、心に届く言葉や態度で接客をしていきたい、という思いを込めた言葉です」
中川政七商店の、新しい店舗運用づくりの中で生まれたこの言葉。
コミュニケーションについての共通認識を持つことで、スタッフ一人ひとり、少しずつ接客の表現が違っても、全国どこの店舗でも中川政七商店らしさが感じられるようになってきた。
ものづくりの魅力を伝えるために、まずはつくり手のことを理解する。
そのために、店長が年に一度ものづくりの現場を訪れて、つくり手の思いに触れるための研修制度もスタートした。
 「お客様が、家族や友人に話したくなるほどのエピソードを全商品に添えてお渡しできれば、何倍もの人にその魅力を伝えることができると思います」
「お客様が、家族や友人に話したくなるほどのエピソードを全商品に添えてお渡しできれば、何倍もの人にその魅力を伝えることができると思います」全国各地からつくり手の集まる展示会や、産地の魅力を再発見するイベント『大日本市博覧会』のメンバーとして参加するなど、中川政七商店でしか経験できない取り組みも増えてきている。
現在、本社で店舗の人事を担当している向井さん。
 向井さんが、中川政七商店で働きはじめたのは16年前。当時、奈良駅の近くのホテルに併設されたショップでアルバイトをしたのがこの会社での仕事の入り口だった。
向井さんが、中川政七商店で働きはじめたのは16年前。当時、奈良駅の近くのホテルに併設されたショップでアルバイトをしたのがこの会社での仕事の入り口だった。もともとは接客が好きでこの仕事をはじめた向井さん。
「自分が可愛いと思った雑貨をお客様にご紹介する接客がとても楽しかったんです」
 お店を訪れるお客さまの大半は、「ちょっと立ち寄ってみよう」という場合が多く、その時点で明確な買いものの目的を持っている人は少ない。
お店を訪れるお客さまの大半は、「ちょっと立ち寄ってみよう」という場合が多く、その時点で明確な買いものの目的を持っている人は少ない。「ふと立ち寄ってくださったお客さまの新しいニーズを生み出せたとき、接客はどんどん楽しくなります」
接客の中で最も楽しいと思うことのひとつ。
「わたしたちは、ただモノを売るだけの雑貨屋さんではなく、お客さまとの間に好感が生まれる「接心好感」を大切にしています」
そのほかにも、店舗の商品構成。暑い夏には涼やかなカゴのバッグや日傘を特集したり、季節のギフトを手にとりやすく並べたり、買いやすい組み合わせを工夫したり。
 売上は、「今、これを使ってみたい!」というお客さまからの評価。同時に、日頃の接客の中で、いかにお客さまの興味を引き出せているか、というコミュニケーションの成果でもある。
売上は、「今、これを使ってみたい!」というお客さまからの評価。同時に、日頃の接客の中で、いかにお客さまの興味を引き出せているか、というコミュニケーションの成果でもある。お客さまがお店で、心地よく商品と出会い、また来たいと感じてもらえるように。手順よりまず考え方を共有するのが、ここでの接客のスタンスだ。
結婚して引っ越してからも、大阪の店舗で販売・店長業務を経験してきた。
店長になってからは初めてのマネジメントに苦戦しながらも経験を積み重ね、その楽しさに夢中になる。
その後、入社したばかりのスタッフや新人店長にもこの楽しさを実感してほしいと思いサポートに携わりたいと提案する。
「当時の社長に、『店長も続けながら、新しい店舗の立ち上げにも関わってみたい』と相談しました。そうすると、ちょっと恥ずかしいですが、“特命店長”という役職をもらって、他店舗の仕事にも関わらせてもらうようになりました。」
売上不振の店舗があれば、一緒に強み弱みをみつけて売上回復させる。特命店長として店舗のサポートを経験したのち、向井さんは本社のスーパーバイザーに。
「スーパーバイザーの楽しさは各店舗と信頼関係を築き、強いチームを一緒に作ることなんです」
新店出店の準備や、担当する店舗へ出向き、売上や業務サイクルの見直しなどを店長と一緒に考えて定着させてきた。
 「店長になったばかりのころは、不安なことがあると思います。一緒に問題を解決して、自信をつけてもらい、前に進めるのが私たちの役割と思ってやってきました。ときに厳しく、ときに優しく」
「店長になったばかりのころは、不安なことがあると思います。一緒に問題を解決して、自信をつけてもらい、前に進めるのが私たちの役割と思ってやってきました。ときに厳しく、ときに優しく」「今後のためにと、心を鬼にして伝えます。その人の人生を預かっているような気持ちで向き合っていきたいから」
「みなさん、やるべき仕事を理解して、ちゃんと自分で判断できるようになると、相談の回数は減ります。そして、楽しそうにそれぞれの『私の店』をつくっていきます」
「成長したんだなって、うれしいようなちょっと寂しいような。でも、一緒に目標を達成できた時はなんとも言えないうれしさを感じます!」
 そして今は、店舗の人事採用の仕事を担っている。
そして今は、店舗の人事採用の仕事を担っている。「今から携わる人事採用の仕事は自分自身の集大成だと思っています。店舗で働く方が、楽しいお店づくりに注力できる環境を整えるのが私の仕事です。責任は重大ですが、やり遂げたいと思っています」
店舗は特に、女性スタッフが多く活躍する現場。
会社の制度がブラッシュアップされるにつれて、結婚・出産・子育てなど、ライフスタイルの変化に合わせて働き方を選べるようになってきている。
「産休からの復職率が高いんです。今、社内のスタッフの間でベビー服のお古が行き交っていて、そんな職場ってやっぱり素敵だなあと思います」
子どもが小さいころは時短勤務。子育ての手が離れたらアルバイトから社員登用にチャレンジもできる。一人ひとりが自分のキャリアを形成しながら長く働けることは、会社そのものを磨いていくことにつながる。
 “日本の工芸を元気にする!”という、中川政七商店のビジョン。接客の仕事は、「接心好感」を通して、商品やその考えを外とつなぐ役割がある。
“日本の工芸を元気にする!”という、中川政七商店のビジョン。接客の仕事は、「接心好感」を通して、商品やその考えを外とつなぐ役割がある。日々、お客さんの心に届く接客を。
その積み重ねが、100年後に工芸をつなぐバトンになると思いました。
(2018/6/13 取材 高橋佑香子)
中川政七商店では、ほかの仕事でも募集中です。よければあわせてお読みください。






