※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
パラグアイの楽器の話、植物の種について紹介している本のこと、美しい話が収められた古い映画について。スキンケアブランドAēsop(イソップ)のメールマガジンには、商品の話が出てこないことがあります。その代わりに届けられるのは、ふだんの生活では関心を持つ機会もなかったような話題の数々。
それは「学び続ける人は美しい」と考える、ブランドからのメッセージなんだそうです。
 イソップはオーストラリア発祥のスキンケアブランド。シンプルなパッケージと無駄を省いた成分、そして香りが特徴的な製品をつくり続けています。
イソップはオーストラリア発祥のスキンケアブランド。シンプルなパッケージと無駄を省いた成分、そして香りが特徴的な製品をつくり続けています。今回募集するのは店舗の装飾を担当する人。装飾というより、「しつらえる」という言葉のほうがしっくりくるくらい、飾らず主張しすぎない空間をつくるのが仕事です。
美術やデザイン、空間や建築などのスキルがあると、活かせることが多いかも知れません。
ほかに取引先との窓口になるポジションでも、人を探しているそうです。
イソップを取材するのは今回が2回目。
日本オフィスのある東京・外苑前は神社やライフスタイルショップが点在するエリアで、いつ来ても清々しい空気が流れているように感じる。
 オフィスの扉を開けると、2年前と変わらずシンプルで整頓された空間が広がる。最近は人数が増え、フリーアドレスで仕事をしている人もいるそう。
オフィスの扉を開けると、2年前と変わらずシンプルで整頓された空間が広がる。最近は人数が増え、フリーアドレスで仕事をしている人もいるそう。最初に話を聞いたのは、マーケティングとサプライチェーンのマネージャーをしている大久保茂夫さん。
 イソップで働く前は、いくつかの化粧品ブランドで働いた経験があるそうだ。
イソップで働く前は、いくつかの化粧品ブランドで働いた経験があるそうだ。「店舗のつくり方やブランドの打ち出し方、オフィスでのルールまで、ここまで一貫性のあるブランドはそうないと思います。今思い返すと、ユーザーとして使っていたときにはブランドのことを1割程度しか理解していませんでした。働きながら、ブランドのことを日々学んでいる感じがしています」
イソップは、ミニマムで高品質なものをつくりたいという想いから、33年前にヘアスタイリストのデニス・パフィティスが立ち上げたスキンケアブランド。
スキンケアやボディケアのための製品が店頭には100種類ほどに並んでいて、季節ごとに新しい商品も登場する。とはいえ「今、これを買わないと」と煽るような広告を打つことは一切ない。
「たとえば、これでシワを改善しましょうと謳う商品はありません。自分たちにも、お客さまに対しても、考えるプロセスを大事にしているんです」
考えるプロセス。
「私たちが売りたいものを売るのではなく、お客さま自身が今、生活になにを欲していて、どういう気分なのか。自分に正直に考えてほしいと思っています」
流行や周りの目線ではなく、自分がこうありたいという姿を想像しながら買うものを選ぶ。
フラットな気持ちで選べるよう、パッケージはシンプルなデザインで統一されている。
 「お客さまがいつも新しいことを発見できるよう、店舗や製品のなかに好奇心を感じる種みたいなものを散りばめているんです」
「お客さまがいつも新しいことを発見できるよう、店舗や製品のなかに好奇心を感じる種みたいなものを散りばめているんです」たとえばギフトキットにつけられた星座や詩人の名前。SNSで発信されるアートや映画のこと。
文化的なことを知るきっかけをそっと発信し続けている。
「創業者のデニスがよく言っているのが、人間は死ぬまで学び続ける生きものだということです。学ぶことで新しい興味が湧いたり、達成感が得られる。人間として生まれたからには、学び続けてほしいというメッセージが、イソップのアウトプットには込められているんです」
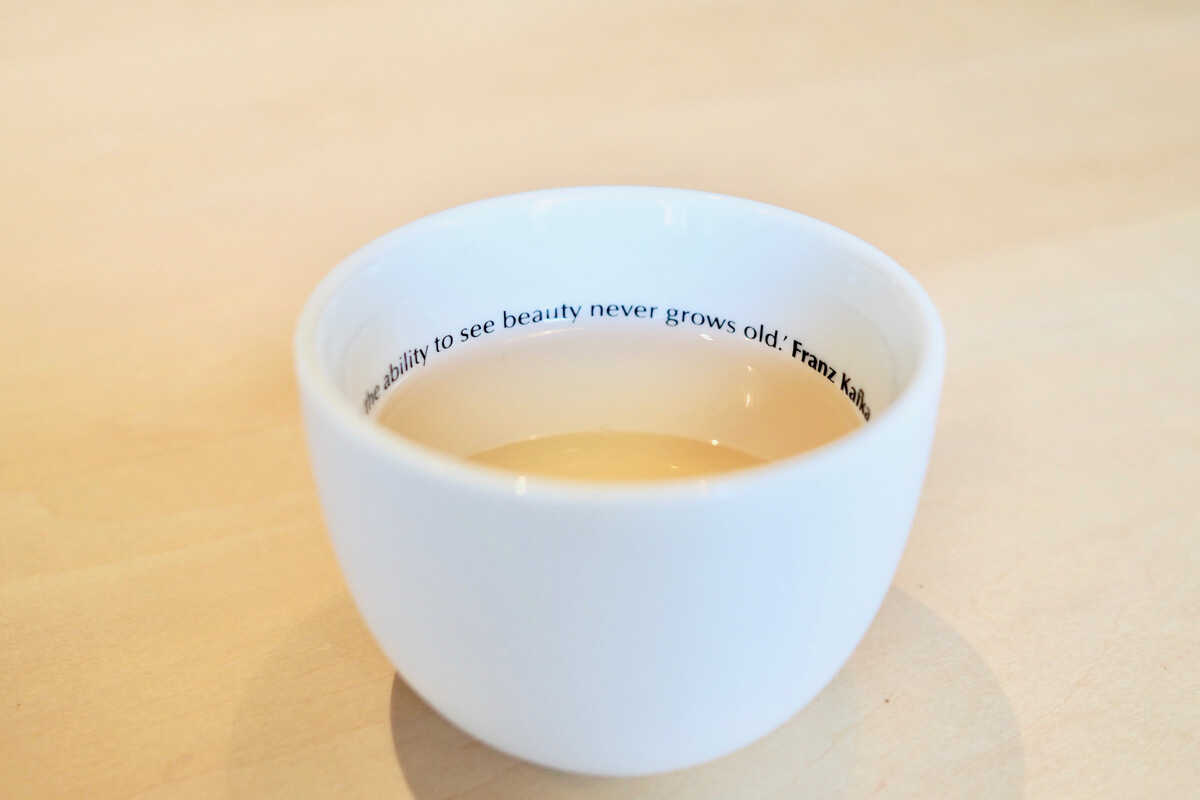 「今度福岡店で、アートブックと製品を一緒に並べて販売するイベントを予定しています。知性を象徴する本とともに届けることで、イソップからのメッセージが伝わる機会になればいいなと思っています」
「今度福岡店で、アートブックと製品を一緒に並べて販売するイベントを予定しています。知性を象徴する本とともに届けることで、イソップからのメッセージが伝わる機会になればいいなと思っています」そんなとき、店舗をどう魅せるか考えていくのがビジュアルマーチャンダイザーという役割。
日本ではそのポジションを2名のスタッフが担っていて、1人がロンドンに行くことが決まり、新たな仲間を募集することになった。
パートナーとして働くことになる伊藤紫乃さんは、キリッと芯のある雰囲気が印象的。話してみると気さくで、柔らかな方だということがわかる。
 「お店の美観に関わることをすべて請け負っています。ディスプレイやキャンペーンのプランニング、小道具づくりとか。定期的にお店に行って、イソップらしさをつくる役割をしています」
「お店の美観に関わることをすべて請け負っています。ディスプレイやキャンペーンのプランニング、小道具づくりとか。定期的にお店に行って、イソップらしさをつくる役割をしています」イソップで働く前は、ドイツでマリメッコの販売スタッフとして働いていたと いう紫乃さん。
ディスプレイを変えるとお客さんの行動や自分たちのモチベーションも変わることに気づき、空間を考えることに関心を持つようになった。
そんなとき、働いていた店舗の2軒先にイソップの店舗がオープンしたそう。
「お店を閉めてから前を通って帰るとき、夜のイソップのお店が本当に美しくて。いつも立ち止まってぼーっと見ていたんです。明るすぎず暗すぎない照明のなか、カウンターの上にはスタンドランプだけが置いてある。まるで1枚の絵を見ているような感動がありました」
 その後日本でビジュアルマーチャンダイザーを募集していると知り、イソップで働くことになったのが4年前のこと。
その後日本でビジュアルマーチャンダイザーを募集していると知り、イソップで働くことになったのが4年前のこと。「ブランドの謙虚さやミニマルさが日本的なブランドだと感じました。表に見えない部分がとても深い。ブランドができたときから変わらない、芯の通った感じが私にはすごく心地良いんです」
4年のあいだに日本での店舗はどんどん増えて、この年末には39店舗にもなるそうだ。
店舗の内装はそれぞれ違って、その街に馴染む固有のデザインが施されている。
「たとえば中目黒にある東京店は、昭和の家庭をイメージしてつくられています。夏になったら風鈴をかけたり、大きな鉢を置いて金魚を泳がせてみたり。そのお店を見回して、なにが足りていないのかを考えていくんです」
 店舗ごとに佇まいが異なるため、マニュアルが用意されているわけではない。
店舗ごとに佇まいが異なるため、マニュアルが用意されているわけではない。土地や季節、出入りする人の空気を感じながら、そのときにいいと思うものをしつらえる。
大切にしているのは、商品の売れ行きやお客さんの居心地の良さというよりも、そこにいる人が感じたり考えたりするきっかけをつくること。
「私たちのポジションを“イソップのアンバサダー”と呼ぶことがあるんです。お客さまにも、お店の子たちにも、いろんなシーンからイソップらしさを共有できる立場だと思っています」
また、年に6回ほど展開するキャンペーン設えを考えるのも、このポジションの大きな仕事。
新製品やシーズンに合わせて、毎回本社のあるオーストラリアからガイドラインが送られてくるそうだ。
「まずはコンセプトを読み込むところからはじめます。今準備しているのはフレグランスの新製品に合わせたものなんですけどね。小道具として砂時計が設定されていて、そのつくり方も一緒に送られてくるんです」
 「布の先から下にある石に砂がこぼれていく。それは時間の経過を象徴しています。香りって、記憶を呼び起こしたりするじゃないですか。時間の記憶の象徴として、砂時計を用意しています」
「布の先から下にある石に砂がこぼれていく。それは時間の経過を象徴しています。香りって、記憶を呼び起こしたりするじゃないですか。時間の記憶の象徴として、砂時計を用意しています」直接フレグランスとリンクするものではない砂時計。どうして砂時計なんだろう、と考える過程があるのもイソップらしさなんだそう。
「記憶を呼び覚ますものであれば、砂時計ではないものを提案することもできます。言われたことをやるだけではなくて、自分で考えてつくっていける楽しさもあるんですよ」
メッセージを読み解き、イメージする想像力。それに加えて、実際に美しく、そして安全に店舗に設置する計画性も必要になる仕事だと思う。
ロンドンに行くスタッフはもともと施工関係の仕事をしていた方で、想像をふくらませるのが得意な紫乃さんとバランスを取りながら仕事をしてきたそう。
紫乃さんはその想像力や視点を、どうやって身につけてきたのでしょう。
「日々の暮らしや自分の考え、物事への視点がそのまま仕事に反映されているんだと思います。いろいろなことに興味や好奇心を持つこと。どうしてだろうって疑問を感じたり、ものごとの違いに気づくことは大切にしています」
「一緒に働いている人たちと、お互いに日々のなかで感じることや体験してきたことをよく話すんです。いろいろな価値観に出会いたいと思っている人にはいい職場だと思いますよ」
前回取材に来たとき、たわいもない会話をしながらも、社会や環境に対して自分の考えを正直に交わしていたことを思い出す。どんなことにも意識を向けて、考えようとする姿勢が清々しかった。
そのときの記事をきっかけに入社したのが、野崎真希子さん。
 新店舗の設計施工や店舗の維持管理など、建築寄りの部分を担当していて、ビジュアルマーチャンダイザーと仕事で関わる機会も多いそう。
新店舗の設計施工や店舗の維持管理など、建築寄りの部分を担当していて、ビジュアルマーチャンダイザーと仕事で関わる機会も多いそう。イソップに来る前は、店舗の設計やディスプレイのデザインから施工まで、すべてを自分たちで行う会社で働いていた。
「小さいころからものをつくるのが好きだったので、仕事は楽しかったんです。インハウスでひとつのブランドに関われないかなと思っていたとき、日本仕事百貨でイソップの記事を見つけました」
ふだんからイソップの製品を使っていたという真希子さん。
まだ日本に店舗ができたばかりのころ、ここで働きたいと思って調べていたほどのファンだったそう。
「少数精鋭でやっていた時期を知っているので、英語がペラペラでキリッとした人たちのなかで働くんだと覚悟してきました。私、英語はそんなに話せなくて。ドキドキしながら出社したら、みんな優しくて安心しました」
「仕事はハードなところもありますよ。だけど施工会社さんに無理はさせないっていうか。人間らしい関わりのなかで、自分で誠実な判断ができるのはすごくいいところだと思っています」
イソップで働くときには、カップやノート、ペンはみんな同じものを使う。身につけるものはモノトーンで、私物はロッカーにしまうなどのルールもある。
 裏表のないブランドの一貫性を保つために必要なことと聞いているけれど、窮屈に感じることはないんだろうか。
裏表のないブランドの一貫性を保つために必要なことと聞いているけれど、窮屈に感じることはないんだろうか。「ノートやペンはどうして黒なんですかって質問をしたことがあるんです。そうしたら『目に入っても邪魔しない色だから』と言われて、なるほどなと思って。慣れてからは、このルールのなかで過ごす心地よさみたいなものを感じるようになりました。」
すると、横で話を聞いていた紫乃さん。
「会社にいるときに自分のパーソナルなところを消すっていうのは、一緒に働く人への配慮なんですよね。これに限らず、1つひとつのことに意味があって、納得して働ける。それはすごく粋だし、イソップらしくて好きなところです」
 好奇心を持ち学び続ける続けることが、本来の美しさにつながっていく。
好奇心を持ち学び続ける続けることが、本来の美しさにつながっていく。その種を撒くために、これまでつくりあげられてきたイソップのイメージにとらわれず、さらなるイソップらしさを探求していく勇気のある人に似合う仕事だと思います。
(2019/8/26 取材 中嶋希実)





