※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
「まちのアート」というと、どんなイメージがわくでしょう。
公共施設に置かれた彫刻や、子どもたちが描いた壁画、ポスター。
最近は、絵画などの作品を鑑賞する以外にも、パフォーマンスやワークショップなどを通じて、誰もが自由にアートに参加できる機会も増えてきています。

今回紹介するのは、秋田市にあるNPO法人アーツセンターあきたの仕事。
秋田公立美術大学のなかの地域連携部門が独立した法人で、まちに暮らす人がアートをより身近に感じられるきっかけをつくろうとしています。
募集するのは、ここでさまざまなプロジェクトを担当するディレクターと、コーディネーター。美術分野での学歴や経験は問いません。特にディレクターについては、ほかの仕事でのマネジメント経験を活かせる仕事だと思います。
東京から秋田に行くには、新幹線なら4時間弱。飛行機なら1時間ほどで到着する。
アーツセンターあきたの事務所は、美大のなかにある。JR秋田駅から路線バスに乗り換えて、15分ほど海のほうへ走っていく。
学生らしい数人と一緒にバスを降り、学内へ。
キャンパスを歩いていくと、同じつくりの倉庫が連なったような建物が現れた。

ここは学生たちが制作をするアトリエらしい。その一角に、「アーツセンターあきた」のサインを見つけた。
事務所として改装された1階のスペースで、まず話を聞かせてくれたのは事務長の三富さん。

「私たちの仕事は、市内にあるギャラリーなどの関連施設の運営と、大学やNPOの活動の広報、あとは地域の方から『美大と一緒に何かやりたい』というお声がけがあったときに、プロジェクトとして進めていけるように、美大生や先生たちをつなぐことです」
美術を学ぶ学生のためだけでなく、研究やプロジェクトをまちとつなげて暮らしを豊かにしていく。大学と地域の連携をスムーズにしていくのが、アーツセンターの仕事のひとつ。
そのために、展覧会を運営したり、プロジェクトを企画したり。
「今BIYONG POINTというギャラリーで開催している企画展『アウト・オブ・民藝』は、郷土資料などの秋田のリソースに新しい角度から光をあてるものなんです」

ほかにも、空き店舗となったスペースを活用するために、高校生と美大生や教員が一緒になって、ディスカッションをしたりDIYの作業をするプロジェクトも進めてきた。
完成された作品を鑑賞するだけでなく、アートを通してまちに対する理解を深めたり、人とのつながり方を考えたり。
そんな活動のハブとなる秋田公立美術大学も、ちょっとユニークなカリキュラムで学べる場になっている。
たとえば「アーツ&ルーツ」専攻では、地域の歴史や文化資源についてフィールドワークを通じて学び、アートプロジェクトや作品制作などの表現につなげる。
「絵画」や「彫刻」のように、最初に何をつくるかで専攻を選ぶのではなく、美術を通じて地域とどう向き合うかで、学び方を考えていく。

「美大では、国際的に活躍するアーティストが教鞭をとっていたり、ちょっと攻めた感じの研究活動をしていたり。特色ある教育をしているんですが、まちの人にとっては尖りすぎていて、うまく伝わらないこともあるようで」
普段から三富さんたちのもとに来る依頼は、「美大生にまちのポスターをつくってほしい」というようなものが多い。地域の美大として関心が寄せられていることは伝わってくる一方で、大学として力を入れている分野とのずれを感じているそう。
アートプロジェクトを企画運営したり、市街地でアートパフォーマンスをしたり、この大学だからできる学びを、もっと活かせたら。
「まちの人にちゃんと活動を届けていくためには、もっとわかりやすく伝える必要があるんですよね。美大で飛び交っている『言語』をそのままぶつけるのではなくて、大学と市民の間に立って、私たちが翻訳していかないといけない」

「美術になじみがない市民にもわかりやすく伝えていくという役割を考えると、今回スタッフとして入る人は、必ずしも業界の経験者じゃなくてもいいと思います。行政とのやりとりも多いので、そういう分野での経験のほうが活きてくるかもしれない」
アーツセンターあきたでは今、市で新しくつくる施設のオープンに向けたプレ事業と開館準備事業にも取り組んでいる。
「2021年には市の中心部に、秋田市文化創造館っていうアートセンターができるんです。美術館や劇場のように、できあがったものを鑑賞するのではなく、キュレーターやエデュケーターと一緒に市民が主体的にプロジェクトを担っていく場を目指しています」
これまで鑑賞者だった市民が、アイデアを形にしたり、発信したりする側になる。
今取り組んでいる「プレ事業」は、新しい関係性をつくっていくきっかけづくりにもなる。事業を担当している、コーディネーターの島さんにも話を聞かせてもらった。
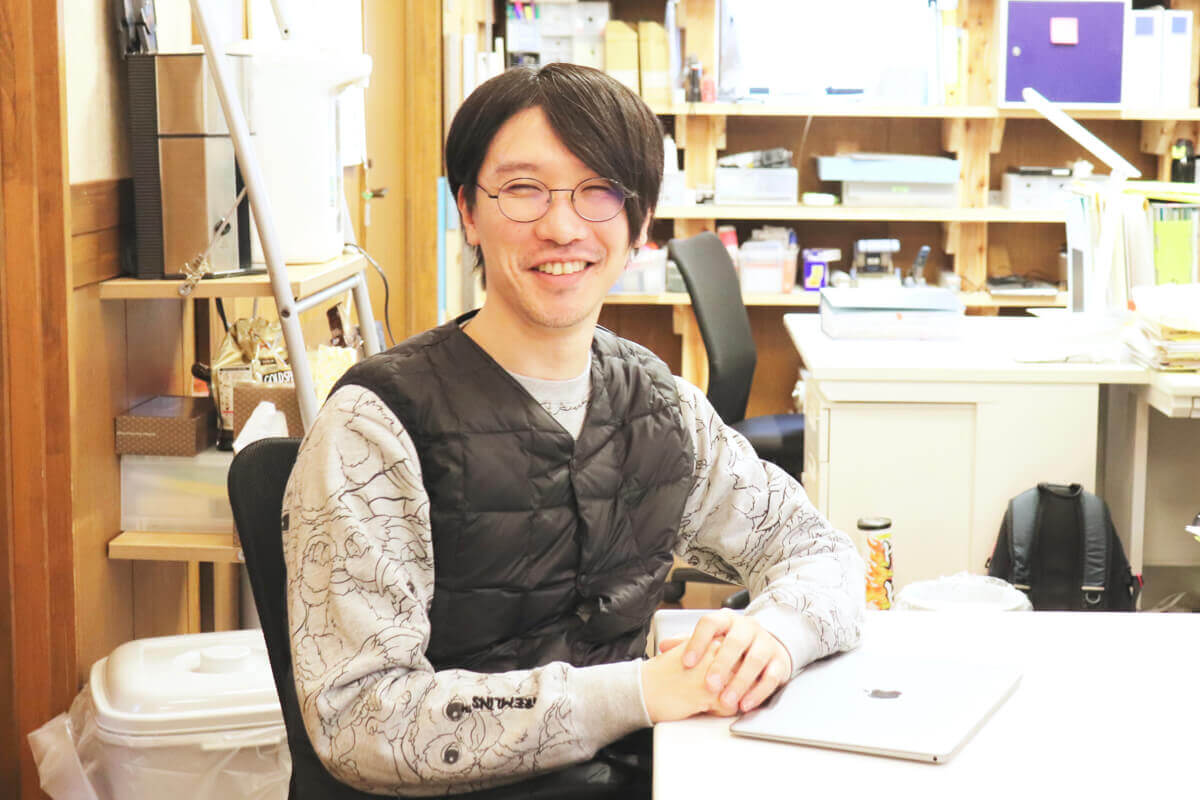
「プレ事業にはいくつかのプロジェクトがあって。食や演劇、仕事などさまざまなテーマでトークをしたり、まちあるきを通じて若い世代が秋田の魅力を再発見するようなイベントをやったり」
外で企画されたものを持ち込むのではなく、秋田のまちにあるものを使って、アートの可能性を探っていく。
たとえば、駅前の商店街。郊外にショッピングモールができて以来、空きテナントも増えていて、プレ事業では、その空きテナントを利用した多様なプランの公募もおこなわれた。
「居村浩平さんというアーティストは、『目があった人の動きを真似する』っていうパフォーマンスをして。その映像をアーカイブして展示したんです」

偶然通りかかった人の何気ない所作を、居村さんが繰り返す。普段は日常に埋もれている動作だけを、切り取って集めてみると、意外な気づきがあっておもしろそう。
だけど、ちょっと不思議な行為ですよね。まちの人たちはうまく受け入れてくれましたか?
「そうですね。プロジェクトが安全に行えるように準備をするのが僕たちの仕事なんです。公道を使うため、警察に申請を出したり、商業施設の担当者にコンセプトを説明したり」
プロジェクトによって必要な仕事は毎回違うので、その都度動き方を考える必要がある。
今回のプロジェクトで島さんは、居村さんのインスピレーションになればと、秋田出身の舞踏家・土方巽(ひじかたたつみ)の美術館にも案内したという。
秋田の市民に美術の楽しさを伝えるだけでなく、外からやってくるアーティストと一緒に、秋田だからできることを考えていく視点も大切だと思う。

ところで、このプレ事業のタイトル「乾杯ノ練習」というのは、一体なんですか?
「これはおそらく秋田独特のものなんですけど、誰かが飲み会の席に遅れているときに、『じゃあちょっと“練習”しようか、かんぱーい』って先に飲み始めちゃう文化があって(笑)。それを乾杯の練習っていうんです」
「今回の取り組みもそれになぞらえて、練習と称していろいろやってみようっていう意味で、タイトルにしています」
「練習」というキーワードは、新しい事業でプレッシャーを感じていた企画チームの意識を「なんでもトライしてみよう」という方向に変えるきっかけにもなったという。
この事務所には、「乾杯の練習」の実施に至るまでのディスカッションの痕跡があちこちに残っている。

アーツセンターあきたでの話し合いには、NPOのメンバーに加えて大学の先生や、ときには学生も参加してコミュニケーションを重ねていく。
昨年の夏からNPOのスタッフとして働いている藤本さんも、もとはこの美大の大学院生だった。

学部までは京都の大学にいて、修士課程が開設された2017年に入学。建築やデザイン、プログラミングなど、ジャンルの垣根を超えたさまざまな人たちのなかで学んできた。
「今一緒に働いている人たちも、美術関係者だけじゃなくいろんな人がいて。お互いの感覚が通じるように、いつも翻訳や編集の作業をしながらプロジェクトを進めている感覚があります」
「すでにできあがったプラットフォームのなかで働くよりも、大変なこともあるけれど、続けていったら実力がつくだろうなって思います」
昨年、プレ事業の広報物作成を担当した藤本さん。
一冊のパンフレットをつくるにも、数多くのディスカッションを重ねていく。
「普段から、秋田のデザイナーだけでなく都市部を中心にいろいろなデザイナーに依頼していたんですけど、この冊子はあえて鳥取の方に依頼してつくったんです」

鳥取と秋田。地方から地方へ。
クリエイティブの仕事が首都圏に集中しがちな今日、もっとほかの可能性があってもいいのではないか。議論のなかで持ち上がった意見から、パンフレットづくりに新しいテーマが生まれた。
「ここに来てから、成果物を見せるだけがアートじゃないって、いろんな場面で気づかされます。本当にたくさんの議論をするので、毎日すっからかんになる感覚があって。それがめちゃくちゃ楽しいんです」
質を高めようとして議論が長引いたり、納期に間に合わせるために制作の一部を内製化したり。
やりがいのある仕事だけに、残業も多くなりがち。
多くのアートプロジェクトの現場ではそれが「仕方ないこと」と諦められている現状がある。今後はそうした働き方の改善も含めて、このアーツセンターで“実験”していきたいという。

日々の時間のゆとりや、自分自身も楽しむ気持ちがないと、いい企画は生まれない。
藤本さんは月に1〜2回、インプットのために県外に出るようにしている。
「そういうリズムは秋田ならでは。京都にいたときは、週末ごとにいろんな展覧会が見られて、美術関係者もたくさんいて。そっちのほうが選択肢は多いと思っていたんですけど、実はすごく限られたコミュニティのなかにいたんだなって、今は思います」
高度に専門化されたコミュニティのなかにいると、話は早いけれど、業界の常識を疑いにくくなる。
一方で異なる属性の人たちと一緒にアートに向き合っていると、思うように伝わらなかったり、時間がかかったりする。そんな違和感にこそ、新しい気づきのきっかけがあるような気がします。
美しい絵を飾るだけじゃなく、ときには「なんだそれ?!」と驚いたり、笑ったり。失敗からも学んでいける。
自分とは違う発想に刺激を受けることがアートだとすれば、まちをもっとおもしろくするために、できることはたくさんありそう。
アーツセンターあきたの挑戦は、まだはじまったばかりです。
(2020/2/28 取材 高橋佑香子)
※撮影時にはマスクを外していただいております。







