これはしごとゼミ「文章で生きるゼミ」に参加された村瀬貴幸さんによる卒業制作コラムになります。
文章で生きるゼミは伝えるよりも伝わることを大切にしながら文章を書いていくためのゼミです。
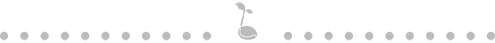
だれもが仕事を自由に選ぶことができ、以前よりも転職や副業を選択する人が増えているように思う。
仕事は食べていくため、お金を得るためだけではなく、別の何かを求めるものになってきているのかもしれない。
1950年代。多くの人がまず食べるために働いていた時代はどうだったのだろう。
お話を伺ったのは京都の紋章上絵師(もんしょううわえし)。木下偉義(ひでよし)さん。今年75歳になる。

「これしか、しようがなかったんですよ。うちは貧乏やったからね。学校もいかれへんし。ほんで、これやろかって」
木下偉義さんが家業である紋章上絵師を継いだのは60年ほど前のこと。おじいさんの代からはじまり、偉義さんで3代目。
紋章上絵師とは、着物に家紋を描く職人さん。
「おじいさんがやりはじめて。ほんで自分もなんか、せなあかんからやりはじめて」
同席していた着物屋のご主人からは「何か野心があれば、他の事をやってたかもね」と冗談を言われ、木下さんは「野心もないし~、お金もないし~」と返し、ゆるやかな会話が続く。
「紋は大したことないし〜」と終始、謙遜される木下さん。しかし一朝一夕に描けるものではないようです。
紋を描く手順は大きく二つ。型紙を使って背景を塗り、輪郭をつくり出す。そして細い線で模様を描き出す。
型紙は渋紙という特殊な紙を使い、紋帖という日本全国の家の紋が載っているものからデッサンし、型を彫っている。

そして模様の部分。着物に直接、円と線を描いていく。定規とコンパスのようになっている筆を使う。木下さんはこの時、何も考えずにすーっと描く。この一連の流れで、紋ができあがる。
家紋を描く上で大事なことがいくつかある。
その一つは線の細さ。細ければ細いほどいい。そして、はっきりと見えることも大切。
「途切れんと、すーっと描ければいい。細くなると、どっか途切れるやんか」
「細く、はっきりってとこが微妙なことやね。紋を印刷する業者が『どこからでも濃くはっきり見えまっしゃろ』って宣伝してはるけど、あれは職人から言うとへたくそや」
もう一つは墨の濃さ。いつも同じように仕上げなければならない。生地によって染み込みの早いもの、遅いものがある。だから生地に合わせて変えていく。
墨の濃さは同じ生地、同じ着物に描くときでさえ、気が抜けない。
「同じ色で家紋を6つ並べる。なかなか描けるものじゃない。長年やれば自然とできるようになるんだけど」
「あと背中、両袖で一つの着物に3つくらい描くコトが多いけど、それも揃えなきゃいけない。片方が薄くて、片方が濃ければアウトや。ところが最近はそういうのが多いんや」

近年、紋のデザイン性がフォーカスされることはあるが、こうした技術も残っていくのだろうか。木下さんはこのコトについて、さらっと「もーこれ、廃れるね。なんか変化を加えれば別だけど」と。
昔は結婚式があれば袴やのぼりの新調、もしくは嫁ぎ先の紋の入れ直しなどで、一度に多くの注文が来ていたそう。夜も寝ずに描くことがあったのだとか。
でも、現在は紋章上絵師としての収入だけでは生活できないほど。
「やっぱ着る人がおらんと。もう今、飯食っていけへんし。だから教えてあげるわけにはいかへんし」
着物屋のご主人もこんなふうに話していた。
「日本から正統な技術がなくなっていく。パソコンで簡単にできるし。だから見た目は残るだろうけど、“人間がやったもの”という形じゃなくなりそう。コストがかかる。今の日本は、なんでもかんでもコストとして考えるね。1時間で何個って換算される世の中だから」
家紋はその模様によって、手間が全然違う。ものによってはかかる時間が10倍違う家紋もある。
「その分、手間賃くれって言ってもね。他よりずっと時間がかかるけど、『料金を倍くれ』とはいわれへんもん」
取材を終え、着物屋のご主人に車で駅の近くまで送ってもらった。その道中、ご主人は木下さんについてこんなことを話してくれました。
「あの人は本当に、技術に自信がある人でね。ほんで、あの人が紋を新しくデザインしてるんは、紋の伝統を残していくためにやってるの」
一方で、木下さんは「遊びでほってみたんですよ」と話していたことを思い出した。
(2018/2/15 村瀬貴幸)