※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
「外見だけを良くしても、中身までは変わらない。ならばデザイナーという枠を超えて、会社の根本から一緒に向き合い、企業の想いや志から一緒に探そう。本物のデザインを目指そうと考えたんです」株式会社セルディビジョンは、企業から農業、商品まで幅広く手がけるブランディング会社です。
クライアントとしっかりと向き合うことで、眠っている魅力や価値を掘り起こす。そうして凝縮した価値をデザインや言葉の力を使って伝えることで、ファンを生み出し続けています。
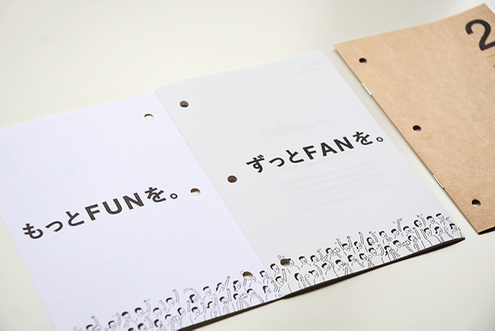 ここで、デザインやコピーライティングを軸としながら、幅広くブランディングに携わる人を募集します。
ここで、デザインやコピーライティングを軸としながら、幅広くブランディングに携わる人を募集します。肩書きは “ブランドクリエイター”。
グラフィックやウェブといった明確な仕事の領域はありません。全員がブランディングのプロとして、価値抽出におけるアンケート調査や分析、ヒアリングから予算管理までを行います。
従来の「デザイナー」「コピーライター」という言葉では説明しきれない仕事です。だからこそ、枠に縛られないセルディビジョンのクリエイターは生き生きしているのだと思います。
横浜駅を出て賑やかな駅前を5分ほど歩く。たどり着いたビルの2階に、セルディビジョンの事務所がある。
扉を開けると、社員の皆さんが迎えてくれた。
さっそく名刺を交換すると、「どうぞ、これも受け取ってください」とガムを1枚。
 不思議に思ってよく見てみると、社名がデザインされている。裏返すと、名前と連絡先が。
不思議に思ってよく見てみると、社名がデザインされている。裏返すと、名前と連絡先が。そうか! 名刺になっているのですね。
「そう! こうすると緊張している相手でもふと気持ちが和らぐだろうし、記憶にも残る。名刺は渡して終わりと思われてしまいがちだけれど、コミュニケーションのツールなんですよ」
 そう教えてくれたのは、代表の岩谷さん。よく通る声で、ユーモアを交えながら話してくれる方だ。
そう教えてくれたのは、代表の岩谷さん。よく通る声で、ユーモアを交えながら話してくれる方だ。もともとは美大在学中に設立したデザインスタジオで、ロゴや名刺、ウェブサイトなどのグラフィックデザインを手がけていた岩谷さん。
納品後に喜んでもらうことが何よりもうれしくて仕事にのめり込むものの、次第に「これでいいのだろうか」と考えるようになったという。
「出来上がったものは満足のいくものだし、お客さんにも喜んでもらえる。けれど、どれも『良いデザインだね』で終わってしまって、企業が目に見えて変わるようなことはなかったんです」
目に見えて変わる?
「僕らの仕事は、お客さんの会社や商品を良くするためにあると信じていた。でも、本当にお客さんのためになっているという自信がなくなってしまって」
自分の会社やデザインには、一体何が欠けているのだろう。試行錯誤を繰り返すなかで、CIデザインに辿り着く。
「衝撃でした。僕らは表面的なデザインしか出来ていなかった。デザイナーという枠を超えて、根本から会社に関わっていきたいと考えたんです」
そうしてブランディングを手がける会社として進化したのが、現在のセルディビジョンだ。
 同時に行き着いたのが、CIを基にしたMI、BI、VIに加え、SI(Strategy Identity)も手がけるという独自の手法。
同時に行き着いたのが、CIを基にしたMI、BI、VIに加え、SI(Strategy Identity)も手がけるという独自の手法。つまり、理念や行動指針を明確にしてからデザインするだけでなく、その先の戦略まで手がけるということ。
「本当に企業を良くしたいと考えたら、CIに加えSIも必要になる。もちろん予算や状況によってどこまで手がけるかは変わりますが、すべてブランドクリエイターが一貫して携わるんです」
たとえば、税理士法人のブランディングを手がけたときのこと。
ランドマークタワーへの拠点展開の検討をきっかけに始まったこのブランディング。理念や行動指針の策定から、ロゴデザイン、さらには会社案内まで。すべてをセルディビジョンが手がけた。
「当時はまだ経営理念が不明確で、日々目の前の仕事をこなす状況。けれど最初のヒアリングで、経営者の方は農家出身で、税理士の立場から農家を救うために会社を立ち上げたという出発点を見つけて」
さらに、上層部だけでなく社内外にできるだけ幅広くヒアリングを行うのがセルディビジョンの特徴。
一部の人だけが一方的に「これが価値だ」と定めてしまっては、本当の価値とはいえないためだ。
「その結果、『出発点を見失わないよう、ランドマークのように道標となり存在感のある会社に』というMIが定まって。さらにMIから導き出した行動指針を言葉にまとめ、VIとして理念を基にしたロゴを作成しました」
さらに広報戦略として、歴史と実績をまとめた会社案内、そして会社の志を記したストーリーブックを制作、展開した。
 会社の持っていた価値が広く伝わることで、社内外の意識が変わる。当時20名だった社員は、なんと現在では140名を数え、多店舗展開しているという。
会社の持っていた価値が広く伝わることで、社内外の意識が変わる。当時20名だった社員は、なんと現在では140名を数え、多店舗展開しているという。立場を問わず、そこに関わる全員が心から納得できて、自然と「ここが好き」とファンになる。そしてファンが、やがて会社を支える幹となる。
これがセルディビジョンのつくりあげるブランディング、そして価値なのだと思う。
「責任は重いです。だからこそ契約もきちんと結びますし、代理店も介しません。僕らはデザインではなくて、企業の『こうありたい』という未来への手がかりをつくっているんです」
続いてお話を聞いたのは、ブランドクリエイターの植村さん。真面目な話もくだけた話も得意な、親しみのある方。
 「以前は、制作会社でグラフィックデザイナーとして働いていました。代理店の指示に従って、毎年同じようなものを制作する仕事に意味が見出せなくなってしまって。自分の意見を持った上で仕事をしたいと思ったんです」
「以前は、制作会社でグラフィックデザイナーとして働いていました。代理店の指示に従って、毎年同じようなものを制作する仕事に意味が見出せなくなってしまって。自分の意見を持った上で仕事をしたいと思ったんです」業界でのキャリアは10年以上の植村さんでも、当初はギャップに焦ったという。
「ここは想像以上に仕事の幅が広くて。これまでも簡単なコピーやイラストを任されることはあったけれど、ここでは動画もウェブも仕事の一つだし、チーフとしてもADとしても働く。正直、戸惑いはありましたね」
「無意識のうちに『自分の仕事はここまで』と枠をつくっていたのかもしれない。けれどお客さんのところへ通ううちに、枠にとらわれていたらお客さんの力になれないと思うようになって。全部やるのが自分の仕事だ!と吹っ切れたんです」
 印象に残っているエピソードをたずねると、現在手がけている土木建設会社のブランディングを教えてくれた。上下水道の整備がその会社の主力事業だという。
印象に残っているエピソードをたずねると、現在手がけている土木建設会社のブランディングを教えてくれた。上下水道の整備がその会社の主力事業だという。どのようにブランディングしていったのでしょう。
「まずは経営者へのヒアリングです。何のために、何をするのかを聞いていきます。すると『自分たちが理念から整えることで、仕事に誇りを持ってほしい』という強い思いを伝えてくれました」
建設業は建築が花形で、どうしても上下水道は日陰になってしまう。それに土木工事のなり手は『他に仕事がないから』と消極的な方が多いという。
植村さんたちチームは、この状況を変えるべくクライアントと一緒になって考えはじめた。
「建設業のCIは、自分自身経験がなかったので、正直悩みました。するとそのとき、会社が大切にしてきたというアルバムを見せてもらって」
そこには、泥まみれの社員が真剣に下水道を整備している姿が写っていた。
背景の建物はすでに取り壊されていたけれど、なんとその水道は今でも現役で人々の生活を支えていたという。
「その写真がきっかけで『地域の未来をつくる仕事』という価値が見つかって。会社の皆さんも、『ああ、本当にそうだね』と喜んでくれました。実はほかの多くのブランディングも、最初のファンは社員の皆さんです。ここから一気に勢いづいて、これまでの歴史を大切にしたCIを考えていきました」
「その会社は代々受け継いできた紋があって。当時の社員はこの紋に憧れていた。その紋を発展させたかたちで、ロゴマークとコピーを2案ずつ提案しました」
2案しか提案しないのですか?
「そう。僕も以前の会社で100案は出していたので驚きました。けれどそれって、お客さんのことを理解できていないから球数を用意しているだけで、ほとんどの案には意味がない」
セルディビジョンでは、最初のヒアリングを終えてからロゴを提案するまで早くても2ヶ月はかかるのだそう。
「ヒアリングングやワーク、アンケートなどを経て、理念を考えロゴに落とし込む。とても重要な部分なので、じっくりと考える時間が必要です。そうして長い時間で培った信頼関係があるから、好みや考えもわかる。捨て案はいらないんですよ」
このブランディングを通して、植村さんは気づいたことがあるという。
「ブランディングというと、斬新なアイディアであっと言わせるようなイメージかもしれない。けれどお客さんの横で、お客さんのなかにあった価値を掘り起こすお手伝いなんですよね」
最後にお話を聞いたのが、1年前から働く岡田さん。人懐こい笑顔が印象的な方だ。

SPツール制作会社のデザイナーとして働く中で偶然CIを知り、これこそ自分の目指すデザインだと直感。ブランディングができる環境を求めて、転職活動を始めたそう。
「正直、ブランディングができるのなら他の会社でもよかったんです(笑)ここは第一候補だったけれど、まだ都内で仕事をしたいという思いもあった」
「けれど、面接の日に育休中のスタッフが子どもを連れて遊びに来ているのを見て。いい会社だな、ここでならずっと働けると思って、即断しました」
一方で、働き始めてから気づいたこともあるという。
「締めるところはきっちり締める会社でした。柔らかいイメージだったけれど、自分の仕事に責任を持つという大前提がある。当然夜遅くまで作業することもありますし、数字も常に意識します」
聞くと、社員は現状の売り上げをリアルタイムで共有し、各チームで目標達成を踏まえた予算管理を行なっているという。
デザインだけが仕事、という考え方だと難しいかもしれません。
「本当にそう。デザインに至る前の企画や戦略の提案書もじっくりとつくり込みます。経験を積んだ経営者の方が相手でも、その会社のためにならないと思ったら意見する。生半可な気持ちじゃとても務まりません」
 デザイナーとしても社会人としても経験を積んできた今でも、勉強不足と感じることはあるという。
デザイナーとしても社会人としても経験を積んできた今でも、勉強不足と感じることはあるという。「以前、お客さまへの贈りものを任されたんです。せっかくなら良いお酒で喜んでもらおうと思って、マネージャーに予算を聞きに行きました」
「そしたら、『会社の判断に任せず、売り上げから逆算してチームで設定してほしい』と言われて。予算のことも現場レベルで考えるべきだなって、改めて知りました」
それでも、目の前の相手やまだ見ぬファンのためにデザインできるのはとても楽しいと岡田さん。
新しく入る方も、肩書きにとらわれずに仕事ができればいいと思う。
価値を見つけ、つくり、高め、広める。そしてファンを増やす。デザインを超えた確かな世界が、ここにはあります。
 自分のデザインの力、コピーライティングの力。ぜひここで発揮してください。
自分のデザインの力、コピーライティングの力。ぜひここで発揮してください。(2017/10/23 遠藤真利奈)






