※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
いくつもの色糸を持ち替えながら、ひと針ずつ丁寧に刺繍された模様。モン族の衣装に連続模様として刺繍されるモチーフを、1ピースだけ切り取ったアクセサリーは、私たちの普段着に合わせてもかわいらしい。
 アジアの手工芸品を生産販売する「クラフトエイド」は、シャンティ国際ボランティア会が33年前から続けている事業です。
アジアの手工芸品を生産販売する「クラフトエイド」は、シャンティ国際ボランティア会が33年前から続けている事業です。フェアトレード、という言葉にはすでに馴染みがあるかもしれません。
クラフトエイドの活動も根幹には、製品の販売を通して、困難な生活をしている人を支援するという目的があります。
今、その大きな指針を軸にしながらも、チャリティーという意識を一歩踏み出して、製品そのものの魅力をもっと打ち出そうとしています。
このクラフトエイドを通じて、日本のデザイナー・フジタテペさんがスラムの女性たちと立ち上げた「FEEMUE(フィームー)」というブランドもその取り組みのひとつ。スラムから発信するデザインという新しい視点が評価され、2017年のグッドデザイン賞を受賞しました。
今回募集するのは、今ある製品企画や生産管理の仕事をサポートしながら、近々予定されているウェブサイトのリニューアル、情報発信などを担当する広報の役割も担う人。
まずは、一緒に生産や販売の現場の仕事を経験しながら、これからできることを、一緒に探していくことになりそうです。
東京・千駄ヶ谷。
クラフトエイドのスタッフが働く、シャンティ国際ボランティア会の事務所は、駅から歩いて5分ほど。
新宿御苑に面した大通りから一本脇に入ると、ときどき電車が通る音が聞こえるほかは、とても静かだ。
事務所の入り口は、小さな公園を抜けて裏通りに面したところにある。外階段を上って三階の事務所へ向かう途中、踊り場から建設中の国立競技場が見えた。
事務所で迎えてくれたのは、課長の岡本さん。民間企業で定年まで働いたのち、嘱託職員として再就職したそうだ。
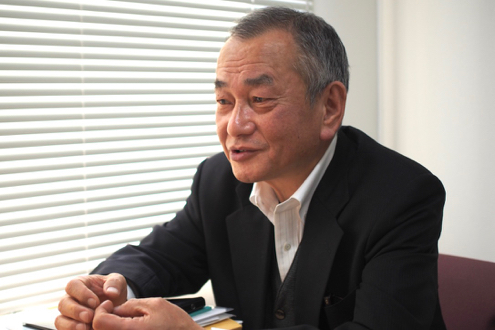 ミーティングスペースに入ると、早速話がはじまる。
ミーティングスペースに入ると、早速話がはじまる。話好きだという岡本さんの話題は、仕事のことから地域のことまで様々。その勢いに少し圧倒されながら、あらためて今回の募集のことを聞いてみる。
「僕は入職してから4年間、こういう状況になるのをずっと待ってたんです」
こういう状況とは?
「やっと事業を新しく拡大していくための予算が取れたんです。これまで、欠員補充以外で、人を増やすということさえできなかった」
そもそもクラフトエイドでは、現状、製品を企画してから日本で小売販売をするまで、生産のほとんどの行程をほぼ一人のスタッフが担当している。
つまり、慢性的にマンパワーが足りない状況でもあった。
それなのに、なぜ補充が難しかったのだろう。
シャンティ国際ボランティア会は、主に寄付金や補助金によってアジアでの教育支援事業を37年間展開している。だから、それらの額によって、その年の活動の規模を調整するという運営方針が根底にある。
「クラフトエイドは、その寄付金や補助金とは違うところで運営をしているものの、活動予定に応じた、予算要求という前例がなくて、通りにくかったんです」
民間企業時代とはまったく異なる発想に戸惑いながら、岡本さんはなんとかマンパワーの補填と、デザイナーなどの力を借りた新しい発信力の強化に向けて、交渉を続けてきた。
2015年ごろから、IDEEや、伊勢丹などのセレクトショップに出店することも増えた。カタログなど販促ツールを刷新したり、見せ方にも工夫しようという流れが、徐々に形になりつつある。
2017年には渋谷ヒカリエで、バンコクから持ってきた小屋や、商品の元となる民族衣装を展示したり、現地の様子を間近に感じられる、リアリティのあるコンテンツづくりを目指すようになった。
 イベントを開催するには大きな予算が必要だけれど、チャレンジしなければ次につながらない。
イベントを開催するには大きな予算が必要だけれど、チャレンジしなければ次につながらない。それにイベントを開催した翌月にはオンラインショップの売り上げが伸びているそう。少しずつ関心が広がっているのを感じるという。
「これから5年間がターニングポイントですよ。予算を有効に活用して勢いをつける。だから、一緒に“渦の中”に入ってやっていこうという人が必要なんです」
一層話に熱の入る岡本さん。それだけに、今、変わろうとしているエネルギーも感じる。
その一方で岡本さんは、従来の顧客の大切さについても言及する。
「これまで、クラフトエイドが安定した活動を続けてこられたのは、団体の支援者でもある曹洞宗の寺院が売り先として一定層を占めてきたから。お寺の行事で使う道具入れなど、定番商品の存在も大きいんです」
 確実に売れるものがなければ、生産者にとってはその日の暮らしに関わることもある。
確実に売れるものがなければ、生産者にとってはその日の暮らしに関わることもある。だからこそ、継続的な生産発注を維持できるように、日本の売り先を拡大して、伸ばしていく必要がある。
意義を知る支援者だけでなく、新しく出会うお客さんにも楽しんでもらうコンテンツを提供したい。
“買ってもらう”のではなく、“買いたい”へ。
新しい目標に向かうために、やるべきことはたくさんある。
そのために新しい仲間が必要になってきた。
現在クラフトエイドのスタッフは、パートも含め5人。
その中で、企画・現地への発注・生産管理・国内企業からの受注まで、業務の大半を担っているのが渡辺さん。
 もともと20年以上ボランティアとして団体の活動に関わってきた渡辺さんが、クラフトエイドを担当するようになったのは4年前、契約社員として加わってからだ。
もともと20年以上ボランティアとして団体の活動に関わってきた渡辺さんが、クラフトエイドを担当するようになったのは4年前、契約社員として加わってからだ。ざっと聞いただけでも、渡辺さんはかなりの仕事を担当しているようだけど、実際の大変さはその量とは違うところにもある。
「クラフトエイドは、現地にスタッフがいないので、何か問題が起きたとき、状況をはっきり把握できなくても、こちらで考えて解決しなければいけないんです」
問題、というと?
「例えば、ラオスにいるマネージャーが病気でダウンしたら、英語で連絡ができず、生産が継続できなくなってしまう。なので、まずはラオス語で別の担当者に自分で連絡してルートをつないでいくことからやらなければいけないんです」
また、悪天候で農作物が不作のときには、クラフトエイドの活動によって得られる収入が、生活を維持する糧にもなる。状況に応じて、単価が安くて確実に売れるものを追加で発注する必要もある。
計画を順序よくこなしていくだけではなく、トラブルにも直接対処する。天候や病気などの問題が、生活に大きな影響を及ぼしてしまう、その地域ならではの課題でもある。
 「現地の状況に寄り添うということが、一番大事なこと。それができなければ、この仕事をやる必要はないんです」
「現地の状況に寄り添うということが、一番大事なこと。それができなければ、この仕事をやる必要はないんです」その使命感を頼りに仕事を続けているという渡辺さん。
事前にきちんと計画していても、その通りに進まないこともある。
「糸などの材料が切れてしまっても、その状況をこちらへ相談しようというアクションが起こらない。仕事が止まらないように、気にかけておく必要もあります」
報告・連絡など、仕事に対する感覚の違いもあるのかもしれない。
「出張先で、『できません』と言われて『わかりました』と引き下がるようではダメ。ちゃんと仕事をやってくる、という気持ちが何より大事なんです。語学として英語を習得していることより、どれだけクリアに文章を書き、自信を持って言葉にすることができるか、というのが大切です」
渡辺さんは、年に2回ほど現地に出張している。
タイ、ラオス、カンボジア、ミャンマーなど、それぞれの国で新しい生産者を探し、視察を通じて次にやるべきことを検討する。
スラムなど、過酷な実情を把握する一方で、生活や文化に触れる機会も多い。
 「ミェン族の女性は、民族衣装であるズボンを12歳になるまでにつくれるように育てられます。たっぷり刺繍を施した衣装がつくれることが一人前の女性としての証にもなるんです」
「ミェン族の女性は、民族衣装であるズボンを12歳になるまでにつくれるように育てられます。たっぷり刺繍を施した衣装がつくれることが一人前の女性としての証にもなるんです」花や生き物をモチーフにした刺繍にはそれぞれ意味がある。
蝶のモチーフを多用する民族には、もともと始祖が蝶だったという神話が伝わっている。
亡くなった人の棺にかける布、婚礼衣装、家族のために女性たちが模様をひと針ずつ刺して、受け継いできた。
「女性たちは、このクラフトエイドの事業に対して、『自分たちの刺繍の腕でお金がもらえるんだったら、なんでもやるわよ』という気概があります。その収入で子供を学校に通わせ、病気の治療もできる。それは本当に必要なお金でもあるんです」
 刺繍は女性の生活力そのもの。
刺繍は女性の生活力そのもの。だからこそ、プライドにぶつかることもある。
「ラオスの首都・ビエンチャン郊外のシビライ村でも素晴らしい刺繍をする女性たちがいます。村のリーダーの女性は、もっと売りたいというやる気があるのですが、上質な生地と、ミシンなどの道具が足りなくて製品単価が上がらないという問題がありました」
都市部から離れているので、ミシンや生地を調達する手段もない。
渡辺さんたちは、彼女たちの思いに応えるため、都市部の別の団体に縫製を依頼する分業で、刺繍を製品化する提案をした。
 そのときの、リーダーからの答えは意外なものだった。
そのときの、リーダーからの答えは意外なものだった。「他の団体に頼むくらいなら、私たちだってできる」
村にあるわずかなミシンを使って、自分たちでやる。
そのときはじめて、つくり手としての強い意地を感じたという渡辺さん。
一方で、それでは村の中で縫製のできる人にだけ賃金が偏ってしまうという問題もあった。
「彼女たちには丁寧に説明して納得してもらいましたが、そういう誇りに接してあらためて、一緒に頑張ろうという気持ちが湧いてきます」
子供のころから磨いてきた刺繍の腕、それで家族を支えているつくり手としてのプライド。
支援の対象としてではなくて、もっとその村のこと、人のことを、知りたいという素直な気持ちが湧いてくる。
渡辺さんが出張で撮りためた写真や、触れ合った人たち、それらをもっと発信したほうが良いと、新しくクラフトエイドに関わるようになったデザイナーからも勧められているという。
 「今の私には、業務の中で継続してSNSなどを運用する時間が取れないし、デザイナーさんや日本で販売に関わる若い方たちのアイデアを感覚的に受け取って、実現していくには、ちょっと世代のギャップもあるんです」
「今の私には、業務の中で継続してSNSなどを運用する時間が取れないし、デザイナーさんや日本で販売に関わる若い方たちのアイデアを感覚的に受け取って、実現していくには、ちょっと世代のギャップもあるんです」もうすこし若い感覚のある人に手伝ってもらえたら、渡辺さんはそう話す。
まずは渡辺さんを手伝いながら仕事を覚えて、実際に足を運んで現場を知ること。
そこで、出会ったもの、人。この仕事だからこそできる経験が、クラフトエイドに新しい出会いをもたらすコンテンツになるような気がします。
買うことの意義よりも、買うものの魅力。
それを伝えることが支援の輪を広げていくことになるのかもしれません。
(2018/1/16 取材 高橋佑香子)






