※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
出勤して朝のコーヒーを淹れていると、前を通った高校生がにぎやかに挨拶をして学校へと向かっていく。午後は地元のおばちゃんが集まってお茶タイム。ふらっと訪れた観光客が、いつの間にか井戸端会議に巻き込まれている。
農業に関わりたいというデザイナーの話を聞いていると、ちょうどいいタイミングで若い農家さんが顔を出してくれた。
夜はトークイベントを楽しみにしている人たちが早めに集まってきて、次のお祭りの話で盛り上がる。
 これはdaigo front(ダイゴフロント)で働く人の1日を想像したもの。
これはdaigo front(ダイゴフロント)で働く人の1日を想像したもの。daigo frontは茨城県大子町という里山にある場所。3年前、町の交流拠点としてつくられました。
とはいえ今は、場所を活かしきれているとは言い難い状況。そこで、地域おこし協力隊としてこの場所を町への入口、人をつなぐ場所に育ててくれる人を募集することになりました。あわせて大子町の魅力を活かしたドラマや映画の撮影などを促進していくフィルムコミッションを担当する人も探しています。
3年の活動期間は、その後地域で生きるため自分の生業をつくる時間でもあります。町も応援してくれる体制ができつつある様子。
気軽に立ち寄れるコーヒースタンドのような。町の入口になるホテルのフロントのような。人をつなげる結婚相談所のような場所になっていくんじゃないかと想像しながら、話を聞いてきました。
大子町は、茨城の北にある山間の町。
東京からは電車を乗り継ぎ3時間。地元が茨城ということもあり担当になった私は、ドライブがてら車で向かいます。
高速をおりて1時間ほど走っていると、温泉へと誘う看板が目に入ってくる。ガソリンスタンドに立ち寄ると、お釣りに観光マップがついてきた。
山に囲まれた大子町は、茨城県内有数の観光地。奥久慈軍鶏(しゃも)やおやきなどおいしいものが多く、袋田の滝やリンゴ農園、キャンプ場などをめがけて、年間150万人が訪れるそう。
daigo frontがあるのは駅から徒歩1分、商店街の入口にあたる場所。
 地域の木材を使ってつくられた明るいスペースで待っていると、大子町役場の保坂さんがさっそうと自転車で現れた。
地域の木材を使ってつくられた明るいスペースで待っていると、大子町役場の保坂さんがさっそうと自転車で現れた。 「林野庁からの出向で2年半前にここに来ました。地域の仕事に興味があったので楽しみにしてきたんです。夜8時に駅から出たら、真っ暗だったのが第一印象ですね。今は生活リズムが整いましたよ」
「林野庁からの出向で2年半前にここに来ました。地域の仕事に興味があったので楽しみにしてきたんです。夜8時に駅から出たら、真っ暗だったのが第一印象ですね。今は生活リズムが整いましたよ」大子は茨城県のなかで最も高齢化率が高い町。ほかの場所と同じように、地域振興が大きな課題になっている。
工場を誘致したり特産品をPRしたりと、さまざまな施策を行う地域があるなか、大子町が挑戦しているのは創業支援に力を入れること。
「観光ホテルや農家さんでいいものをつくっている人がいるし、資源もたくさんあるんです。ただ発信することや売ることに課題を感じている人が多くて」
「たとえばクリエイターと呼ばれる人たちと関わりが増えれば、町の方々とコラボしてなにか生み出していけるんじゃないか。そうやって大子を盛り上げていきたいんです」
最初から移住してもらいたいというより、まずは町に関わる人を増やしたい。
ここ数年はWebメディアgreenz.jpと一緒に創業支援のワークショップを開催していて、町の人が集う「まちづくり会議」というイベントもはじまった。
ナツハゼという葡萄のようなフルーツをつくっている農家と、イベントを機に大子を訪れたデザイナーが協力してあたらしいパッケージをつくった事例も出てきているそう。
「パッケージのデザインが派生して、あたらしい商品をつくる話も進んでいたりして。外からの目線が入ることで生まれてくることがある。そういうものが少しずつ積み上がってきている感触がありますね」
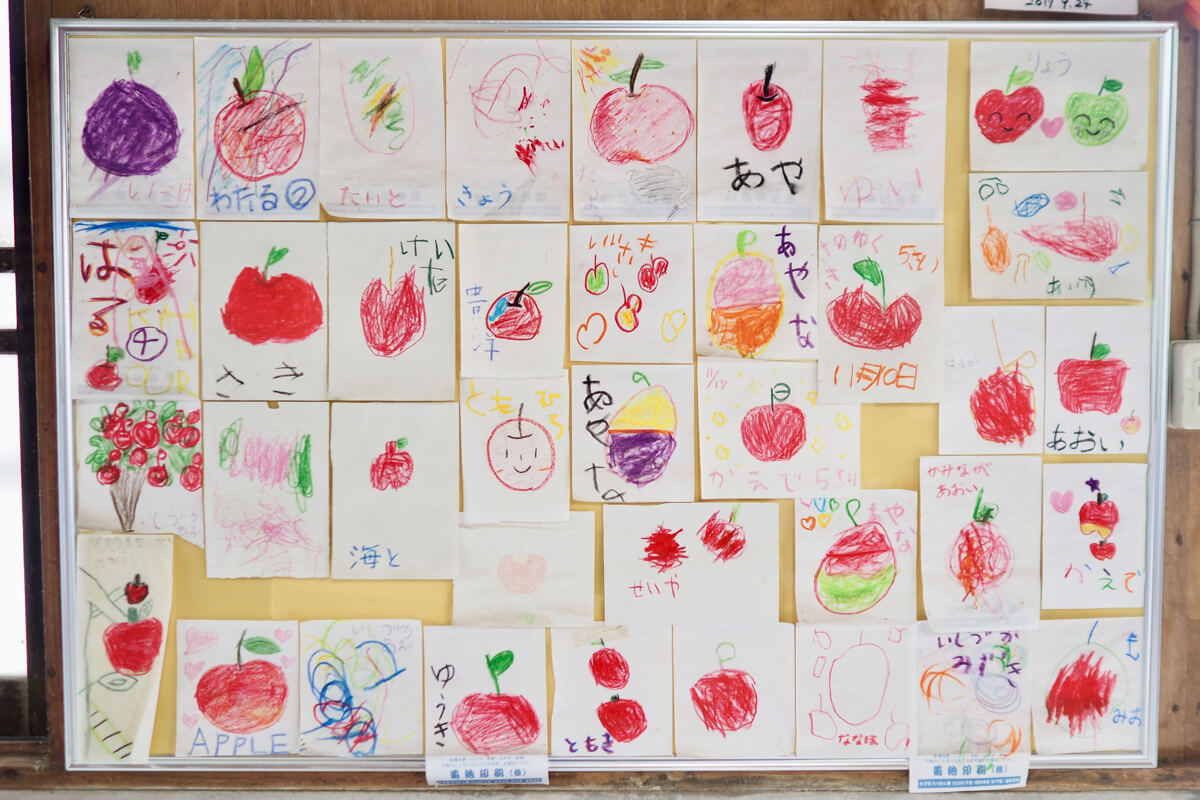 今回募集する人には、生まれはじめた動きを加速していくため、コーディネーターのような役割を担ってもらいたい。
今回募集する人には、生まれはじめた動きを加速していくため、コーディネーターのような役割を担ってもらいたい。デザイナーを地域の人に紹介することにとどまらず、町を訪れる観光客や二拠点生活を送るクリエイター、ときには地元の人同士をつなげることもあるかもしれない。
そんな業務の拠点として使うことになるが、このdaigo front。
2階はシェアオフィス兼イベントスペース、1階はNPO法人まちの研究室がオフィスとして使っている。
まちの研究室のメンバーとして活動をしている、なごやかな印象の川井さんと帽子が似合う木村さん。2人とも別の仕事を持ちつつも、町を元気にするために動き回っている。
 理事長の川井さんは大学を卒業して大子町に戻ってきたものの、30代後半になるまで町のことにそれほど関心を持っていなかったそう。
理事長の川井さんは大学を卒業して大子町に戻ってきたものの、30代後半になるまで町のことにそれほど関心を持っていなかったそう。「知り合いから、よさこい祭りのチームをつくるから事務局を手伝わないかっていう話があって。なかば騙されるようなかたちで巻き込まれたんです」
「なにかを立ち上げるなんてやったことがなかったから大変でした。でもね、楽しくてやめるわけにいかなくなったんですね」
15年前にはじまったよさこい祭りは、今では約4万人が訪れる大きなイベントになっている。
 よさこい祭りが盛り上がっていくにつれ、町でどんどん新しい行事がはじまるように。
よさこい祭りが盛り上がっていくにつれ、町でどんどん新しい行事がはじまるように。その流れの1つが、丘の上のマルシェ。毎年秋に開催するマルシェは先日8回を迎え多くの人でにぎわった。
このマルシェを立ち上げたのが木村さん。もともとクラフト市に行くのが好きで、5年もの準備期間を経て開催をしたんだとか。
「年に1回のイベントで効果があるのかって、言われたこともあったりしました。今ではマルシェに出演したアーティストがカフェでライブをやったり、マルシェがきかっけで大子町に移住する人が現れたりもしているんですよ」
 ほかにもコミュニティ放送局「FMだいご」を運営するなど、まちの研究室はさまざまなかたちで町を盛り上げる活動をしている。
ほかにもコミュニティ放送局「FMだいご」を運営するなど、まちの研究室はさまざまなかたちで町を盛り上げる活動をしている。ここdaigo frontはどういう場所なんでしょう。
「3年前に茨城県に声をかけてもらってつくったシェアオフィスです。僕らは事務所として使っていて、2階ではイベントを開催することもあります。正直、シェアオフィスとして機能しているとは言えない状況です」
駅から近い立地や最近の町の動きを考えて、今この場所の機能を見直す必要があるという。
「観光案内所みたいな入口になってもいいし、いろんな活動をしてる人が集まる場所になってもいいよね。今は、なにやってんだろう?って気にしながらも誰も入ってこないから」
「小さなキッチンがあるから、コーヒースタンドのあるたまり場のようになってもいいと思う。デザインができる人だったら、コーヒーを飲みながら相談に乗ってもいいだろうし」
ゲストを招いてトークイベントを開催すると、50人もの人が集まることもあるそう。それだけ町に感心のある人は多いものの、ふらっとつながるような場所はまだ少ない。
特産品であるお茶を飲めるスペースにしたり、立ち寄ると知り合いに会えるようなバーにしたり。気軽に人が集まる場所ができていくと、ここからさまざまな芽が出る可能性がある。
「僕らがやってる活動は、大子をおもしろいと思ってもらえるきっかけづくりなんです。とにかく大子には、今、いい流れができはじめていますから」
 daigo frontの目の前にある商店街には、シャッターが降りている店舗もあるものの、軍鶏を使った親子丼が食べられる店や古民家を改修したカフェもある。
daigo frontの目の前にある商店街には、シャッターが降りている店舗もあるものの、軍鶏を使った親子丼が食べられる店や古民家を改修したカフェもある。お昼ごはんに何を食べるか迷った結果、今日は役場の保坂さんがすすめてくれた大成食堂へ。
シンプルな醤油ラーメンをすすっていると「よかったら、飲んで」とアイスコーヒーをサービスしてもらった。
店のお母さんは前の道を通る人のほとんど知り合いのようで、みんなに声をかけている。病院帰りにここに寄るというおばあちゃんがラーメンを食べていると、知り合いのおばちゃんが入ってきてコーヒーだけを飲みながら話し込んでいるようす。
daigo frontもこんな場所になるといいのかも。そんなことを考えながら、コーヒーを飲み干した。
 最後に紹介するのは、地域おこし協力隊として活動している小松﨑愛さん。
最後に紹介するのは、地域おこし協力隊として活動している小松﨑愛さん。バリバリとブライダルの仕事をしていたこと、旦那さんとの結婚をきっかけにゲストハウスの開業準備とキャンドル作家をしていることなどがgreenz.jpの記事で紹介されていた。明るい人なんだろうなと想像しながら会いに行く。
 イメージ通りの笑顔で迎えてくれた愛さんに、記事を読んで気になっていたことを聞いてみる。
イメージ通りの笑顔で迎えてくれた愛さんに、記事を読んで気になっていたことを聞いてみる。天職だとさえ思っていたブライダルの仕事を辞めて、性格が正反対だという旦那さんについていくことに不安はなかったんですか。
「旅人気質で自由な彼と一緒にいることで、1つの場所でぎゅっとしていた私の考え方がほぐされていく感じがしていたんです。人と比較せず自分が軸を持っていれば、不安はなくなる気がしています」
 大子と縁ができたのは、キャンドル作家として丘の上のマルシェに出店したことがきっかけだった。
大子と縁ができたのは、キャンドル作家として丘の上のマルシェに出店したことがきっかけだった。まちの研究室の木村さんから縁がつながり、今ゲストハウスの準備をしている物件を紹介してもらったそうだ。
「この地域を盛り上げるなら、地域おこし協力隊の仕事としてやっていくのはどうですかって役場の人に声をかけてもらったんです。知り合いができやすいことと、お給料や補助を活用できるのはいいなと思って、やらせてもらうことにしました」
地域おこし協力隊は3年の活動期間で町に関わりながら、地域に残れるような生業をつくるもの。
今回募集する人も、地域おこし協力隊としての立場をうまく利用しつつ、平行して自分の仕事をつくっていく必要がある。
人が集まる場をつくる経験からカフェを開いたり、つながりを活かして情報を集め空き家バンクのような動きもできるかもしれない。
地域おこし協力隊は町に貢献をする仕事が優先されがちだけれど、大子ではその後を見越して、事業づくりをバックアップしてくれる環境があるそうだ。
「目の前のことばかりをしていると、3年間ってあっという間に終わってしまうんです。何もしなくても、町がどうにかしてくれるだろうっていうのは違うから。お互いがいい意味で利用しあえるような関係がつくれると、やりやすいんじゃないかな」
 地域おこし協力隊として今活動をしているのは愛さんを含む5名。隊員が活動しやすいよう、町も試行錯誤しながら応援体制をつくっているようす。
地域おこし協力隊として今活動をしているのは愛さんを含む5名。隊員が活動しやすいよう、町も試行錯誤しながら応援体制をつくっているようす。意見を出し合って、今は隊員1人に対して1名、相談役になる役場職員がいるそうだ。
最初は条件にひかれたという愛さんも、住みはじめてから大子が好きになったそう。
ゲストハウスがはじまったら、満天の星空を見に来る約束をして取材を終えた。
 茨城の方言に「しゃあんめぇ」という言葉があります。
茨城の方言に「しゃあんめぇ」という言葉があります。頑張って失敗しっちゃったらまぁしょうがないよね、みたいなニュアンスで使うのですが、おおらかな人柄を表しているような気がして、私の好きな言葉です。
この場所で人とつながり生きていくのもいいのかも。そう思えたら、大子を訪れてみてください。
11月17日には川井さんが東京・清澄白河に来てくださって「しごとバー」も開催します。しごとバーのような場所を大子につくっていくのも、いいかもしれません。
(2018/10/9 取材 中嶋希実)
しごとバー「地域をつなぐ場づくりナイト」の詳細はこちらからご覧ください。
この日の日中には、大子町からもゲストがやってくるトークイベント
green drinks Tokyo 「地域で暮らす・夫婦で仕事をつくる」
も同じ会場で開催予定です。 お時間のある方はこちらもどうぞ。





