※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
少子高齢社会と言われる日本。30年後には人口の4割が60歳以上になると予想されています。
社会課題として語られる一方で、健康に過ごしている高齢者も多い。
「歳を重ねても生き生きと過ごせる社会をつくりたい」。カイト株式会社は、そんな想いで “おしるこ”というシニア向けのサービスを開発しました。
おしるこは、50歳以上限定のコミュニケーションサービス。
利用者同士の交流はもちろん、法律や医療などの専門家とチャットで気軽に相談できたり、毎日の日記を書いたり読んだり、また仕事を探せたりといった独自の機能も。
アプリ内を“自治区”と呼び、シニアが自立して、生き生きと過ごせる社会づくりを目指しています。

今回は、カスタマーサポートやコンテンツ企画などを担うディレクターとその仕事をサポートするアシスタント、そしてアプリ内のコミュニティを盛り上げ、利用者の立場からコンテンツを提案していくアクティブシニアモデルを募集します。
東京・西麻布。
乃木坂駅を降りて、国立新美術館や青山霊園を眺めながら10分ほど歩く。きれいなオフィスビルの3階に、カイトの事務所が入っている。
まず話を聞くのは、代表の後藤崇さん。広告代理店や制作会社での勤務を経て、2008年にカイトを立ち上げた。
「2008年は、スマートフォンが日本で発売された最初の年。スマホとITを軸に、今までにないサービスをつくりたいと思い、この会社をはじめました」

時代に合わせて事業内容は変化してきた。最近では、アプリ内課金支援サービスや、緑化推進プロジェクトとして「TOKYO 5% GREEN」を掲げるブランドを展開している。
30人弱の社内で、コンテンツの企画から制作、運営までを一貫して行っている。
そんなカイトが昨年12月にリリースしたのが、シニア向けのコミュニケーションサービス「おしるこ」。
どうして後藤さんは、このサービスをはじめようと思ったんだろう。
「以前、定年退職した人に、顧問として働いてもらったことがありました。でもすぐ説教してしまったり、若い社員と目線が合わなかったりして、うまく会社に適応できなかったんです」
「お金に困っている訳でもないのに、なんでそこまでして働くのかなって考えると、やっぱり人と関わりたいからなんですよ」
後藤さんの両親は、実家に二人きりで住んでいる。暮らしぶりを見ていても、日々の生活を楽しんでいるようには感じられない。
シニアと呼ばれる人たちは、もっと生き生きと暮らすことができるんじゃないかと思ったそう。
もうひとつのきっかけは、その子ども世代である自分たちの課題。
「介護のために仕事を辞めるって話をよく聞くけど、なんで親のために子どもが犠牲になるんだろうって。僕は必ずしも子どもが親の面倒を見なくてもいいと思うんです。そこに義務感が生まれた途端に、前向きな気持ちで関われなくなってしまうから」
「親はどんどん歳をとるし、自分もいつか高齢者になる。誰もがいずれ直面することだから、せっかくならポジティブに迎えられるようにしたい。そんな気持ちではじめたサービスです」
後藤さんがおしるこの中で生み出したいのは、血縁を超える強いコミュニティ。そのつながりを通して、シニア世代が自立して暮らせるようにしていきたい。
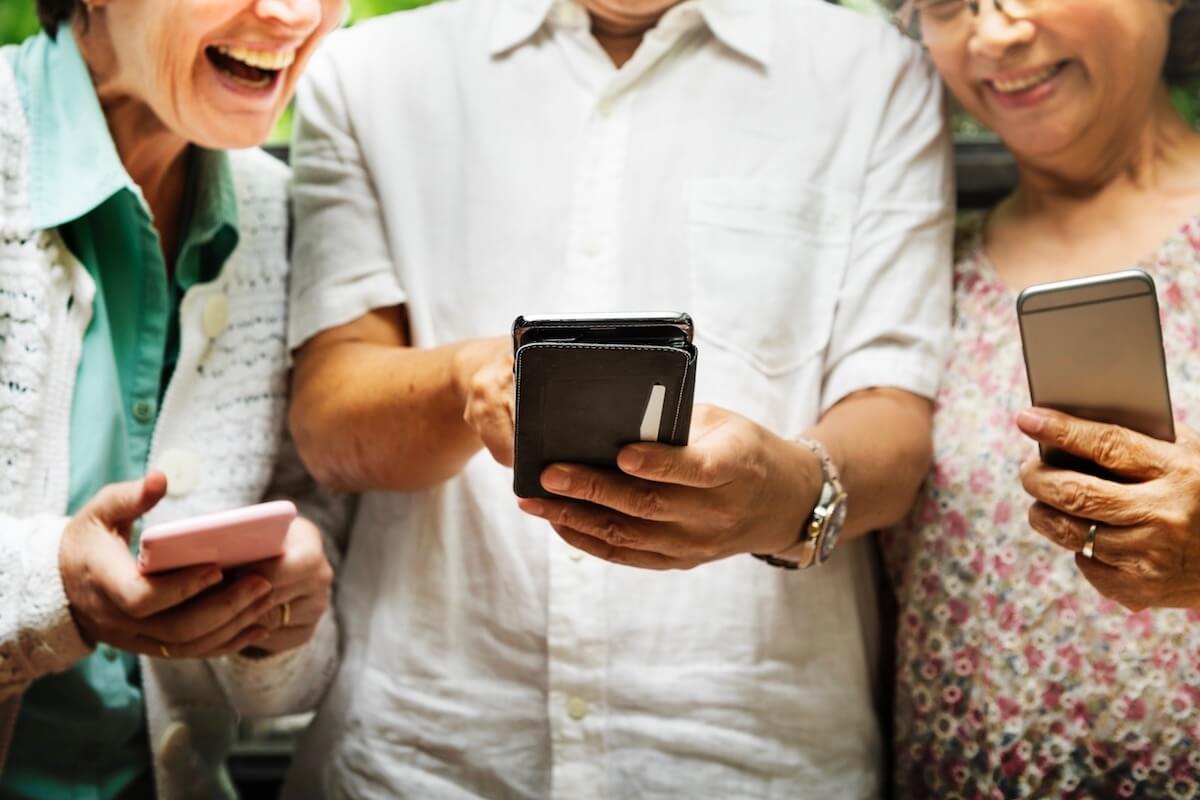
「たとえば『最近見なかったけど大丈夫?』ってオンライン上で声をかけてくれる人がいることは、ひとつの見守りだと思っていて。僕らがつくりたいのは、距離や時間を超えて精神的に誰かとつながる仕組みなんです」
おしるこには、タイムライン上や趣味のグループで交流する機能に加えて、シニアに特化した機能もある。
そのひとつが、専門家にチャットで気軽に相談できるサービス。DIYやパソコンの使い方といった日々の気軽な疑問から、遺産相続や葬儀といった将来のリアルな不安まで、すべて無料で相談できる。
ほかにも、アプリ内で求人に応募したり、NPOなどの活動に参加したりもできる。

さらに今後本格化していきたいのは、おしるこのなかで個人がお金を稼げる仕組み。
「たとえば囲碁が得意な利用者が沖縄にいたとしますよね。その人が北海道の利用者にオンライン上で囲碁を教え、お礼としてポイントがもらえるような仕組みをつくりたい。そのポイントがおしるこ内でお金のように流通していったら面白いなって思うんです」
「いずれ、それが現金の代わりに使えるようになったら、近所のスーパーで買いものができるとか。おしるこが提携している葬儀屋さんを自分で予約して、代金も支払っておくことで、安心して終活について考えられる」
おしるこ内のお金やコミュニティが実生活とつながり、経済が循環していく。
そんな社会を実現するのは、簡単なことではないようにも思う。
「会社を立ち上げたときから、誰かの二番煎じではなく、自分たちしか考えられないことをやりたいと思ってきました。なのでネガティブな意見をもらうほうが多いわけですよ」
「だけど、そういう意見が増えれば増えるほど成功しそうだなと思うんです。僕が生きているうちにできなくても、将来おしるこから新しい経済圏をつくれたら、それってすごく面白いんじゃないかなって」
今回募集する人は、後藤さんたちと一緒にまだこの世にないものをかたちにしていくことになる。
「まだまだサービス利用者は数千人ですけど、数千万人が使ってはじめて目指す社会の実現が見えてきます。働く人には『自分もこういうことがやってみたい』『こういう社会にしてみたい』っていう強い想いを持って、前のめりに取り組んでほしいと思います」
目指す社会のために今できることは、おしるこの利用者を増やしてシニアのコミュニティを活性化していくこと。
実際にどんな仕事をしているのか、スタッフの人たちにも話を聞いてみる。
まずはディレクターの鈴木さん。新しくディレクターやアシスタントとして働く人には、一番身近な先輩になる。

「主な仕事は、カスタマーサポートですね。あとはFacebookの運用やメルマガ配信などのPRをしたり、シニアの人たちとコンテンツについて話し合ったり。まあいろいろやっています(笑)」
実は鈴木さん、もともとは緑化推進プロジェクトの担当として入社した。
「『東京に5%緑を増やそう』というコンセプトの事業です。前職ではCSRの部署にいたし、社会課題に取り組めるような仕事に興味があったので、この事業にも興味を持ちました」
「緑に触れるきっかけにつながるものなら企画は自由に考えることができて、私はラジオを思いついたんですよ。パーソナリティーからゲストへのオファー、音源や編集担当を探したり、シナリオを書いたり。すべて自分でやっていました」

これからおしるこのディレクターとして働く人にも、それくらい自由な発想で仕事に取り組んでほしい。
「私たちもはじめてのことに取り組んでいるので、教えられることはあまり多くなくて。目指すゴールは大事にしてもらいつつ、自分で考えて動いて、学びながら進めてもらう形になると思います」
ゴールとはどんなものでしょう?
「短期的には、利用者を増やすことですね。アプリ内で活発に動いてもらって、つながりをつくってもらう。将来的にはアプリの中で仕事ができるようにする」
「その結果、孤独やお金の不安を抱える高齢者が減って、キラキラとしたセカンドライフを過ごせる方が増えればと思っています」
新しく入る人にまず任せることになるのは、カスタマーサポートの仕事。
アプリ内のコンシェルジュ機能を通じて届いた利用者からの問い合わせに対応していく。
「直接お話しながら自分も操作するうちに、課題や必要な機能が見えてきます。それをもとに改善案をどんどん出してもらえればと思っています」
オフィスでは、アクティブシニアモデルも一緒に働いているので、直接意見を聞くことができる。
「私たちの年代とシニア世代の感性を合わせてつくっていけるのは、すごくいいなと思います。シニアの方たちは経験も豊富だし、すごく喋るし、一緒に働くのは楽しいですね」
鈴木さんがこの会社の最年少、そして最年長がアクティブシニアモデルの曽根さん。冗談を交えながら話すふたりの話を聞いているのは、とても楽しい。
「僕ね、まだ24歳なの。おしるこだと、50歳以上からカウントするからね」
そう話す曽根さんは、スマートフォンを使いはじめて3年になるそう。

アクティブシニアモデルの一番の役割は、率先しておしるこを利用すること。
使いにくい部分があれば鈴木さんたちディレクターに相談したり、あったらいいなと思う機能を自分でも提案したり。エンジニアなどの経験があれば制作に関わることもできる。
「自分で言うのもなんだけど、結構アクティブなんですよ。趣味は弓道とギターとダンス。おしるこには、たまに弾き語りの動画をあげて。NPOにも関わったり、家のことや料理もしたり」
たしかに、とてもアクティブ…!
「でもね、ここに来る前は家でちょっと沈んでいて。趣味はいくらでもあるのに、何もすることがないような気になっちゃってね」
60歳で定年を迎えたあと、アルバイトやNPO活動をしていた曽根さん。10年ほどその生活を続けたものの、数年前からは趣味以外に何もすることがない状態だったそう。
約半年前に、カイトで働いていた知り合いに誘われて、はじめて会社を訪れた。
「久しぶりのオフィスだし、なんかラジオはかかってるし、はしゃいじゃうわけ(笑)。血が通い出す感じがして、自分はビジネスに関わりたいんだって気づいて。趣味と仕事の両方をバランスよくやると、私の場合は非常に快調なんです」
プロジェクトミーティングに参加したり、アプリの機能を話し合ったり。今は、サラリーマン時代の経験を生かし、会社の人事にも関わっている。

「自分の経験が役立つっていいもので、俄然元気になっちゃって。今は人事のほうばっかりやってるから、おしるこもこれから頑張っていかないと」
曽根さんは、おしるこのサービスについてどう思うんだろう。
「趣味を持ちましょう、外に出ましょうってよく言われるけど、講師に言われてもあんまり納得できない。それよりもおしるこで、同年代のアクティブな人の生活を見たほうが、自分もできるかもしれないなと思えるでしょう」
「50代の若い人にもっともっと入ってきてもらって、面白いことをどんどん発信して、おしるこを活性化していってほしいと思います」

人口の4割が60歳以上になるという、30年後の未来。
この記事を読んでいる人の多くも、シニアと呼ばれる世代になっていると思います。
たくさんの人がおしるこを利用して、生き生きと暮らす社会を想像してみたら、ネガティブに考えがちな老後を、なんだか楽しみに迎えられるような気がしました。
(2019/3/7取材 増田早紀)






