※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
関西へ出張すると、京都駅のホームでいつも気が逸れる。駅前のまちなみを眺める視界の端に、不思議な言葉が入ってくるからだ。“変なホテル”
思わず二度見してしまうようなネーミング。
全国に広がるホテルのブランディングを手掛けたのが、GRAPH(グラフ)というチームです。
日常のなかで既視感のない新鮮さと、いつの間にかスッと人の心に入ってくるデザイン。絶妙なバランス感で、さまざまなブランドの「あり方」を表現してきました。
 媒体はグラフィックから空間、WEB、コピーなどさまざま。
媒体はグラフィックから空間、WEB、コピーなどさまざま。GRAPHには東京と、京都、兵庫、3つの拠点がありますが、今回は京都のオフィスを拠点に、プロジェクトマネージャー(PM)として働く人を募集します。必ずしも同業種の経験は問いませんが、かといってデザイナーのサポート役でもありません。
クライアントとコミュニケーションをとり、社内外のクリエイターとアイデアをまとめ、ときには自分で手を動かしてデザインをすることもある。問題解決のためのあらゆる方法を模索し、横断的に実行します。
多方面に働きかけてプロジェクトを動かしていく、プロデューサーのような役割ともいえます。
一人の個人としてクリエイティブに考え、行動できる人を探しています。
まずは、東京・代官山にあるオフィスにお邪魔して、関西で働くメンバーとビデオ通話をつなぐ。
画面に映る取締役の村部さんがいる本社も、東京のオフィスと同じく白を基調とした空間。
 「今わたしがいるのは兵庫県の加西市といって、織物産業が盛んな西脇市の隣です。GRAPHの前身も、もともとは昭和8年に綿織物の関連からスタートした会社なんです」
「今わたしがいるのは兵庫県の加西市といって、織物産業が盛んな西脇市の隣です。GRAPHの前身も、もともとは昭和8年に綿織物の関連からスタートした会社なんです」やがて、国産綿織物の需要が減少。服飾雑貨を入れる紙箱の製造、パッケージ印刷などを手がけるようになった。
「今の代表になってから、印刷や加工だけでなくデザインの提案もはじめて。最近は相手が必要としているものを、もっと上流から汲み取って提案する、ブランディングの仕事を増やそうとしているところです」
「たとえば、名刺の印刷を依頼されたとき、なぜ名刺が必要なのかをヒアリングして一緒に考える。名刺のデザインを変更することで営業のモチベーションを高めたいという思いがあるなら、会社の運営方針や人事のあり方から一緒に考えることもあります」
GRAPHには、デザイン提案だけでなく、知財や財務の知識も踏まえてアドバイスできる体制があるので、つくったものをどう法的にプロテクトするか、企画に必要な予算をどう捻出するかというところまで寄り添って考えていける。
最近は、空間づくり、コンセプトメイキング、イベント、WEBシステム構築など、さまざまなアウトプットでデザインに携わっている。
 「これからアートやテクノロジーなど、分野を越えたコラボレーションによって新たな価値をつくっていきたくて。僕らの仕事で一番邪魔になるのは固定概念なんですよ。今うちにいるスタッフはみんな“ちゃんとした変な人”なんで、ありがたいなと思います」
「これからアートやテクノロジーなど、分野を越えたコラボレーションによって新たな価値をつくっていきたくて。僕らの仕事で一番邪魔になるのは固定概念なんですよ。今うちにいるスタッフはみんな“ちゃんとした変な人”なんで、ありがたいなと思います」GRAPHは、デザインや美術系の業界出身者以外にも広く門戸を開いている。京都の事務所で働くPMの稲垣さんは、もともと料理人だったそう。
「ここでの仕事は、飲食、社寺仏閣、アパレル、ホテルなどなど、案件ごとにまったく違う内容で、知らない分野がほとんどだから。刺激は多いですね。今年の初めには創業から200年続く扇子の老舗をリブランディングする仕事を手がけさせていただきました」
 今回新たにスタッフを募集する京都の事務所は、京都駅から嵐山方面へ電車と徒歩で約15分ほど。近くには「禅」の世界を伝える臨済宗大本山の妙心寺など、多くのお寺が集まる。
今回新たにスタッフを募集する京都の事務所は、京都駅から嵐山方面へ電車と徒歩で約15分ほど。近くには「禅」の世界を伝える臨済宗大本山の妙心寺など、多くのお寺が集まる。その一角にGRAPHのオフィスはある。
「周りはお寺が多いんですが、オフィスのなかは東京や兵庫と同じく白を基調とした現代的な雰囲気です。ワークスペースのほかに、商品のテストマーケティングを行うスペースもあります」
 京都で和食の修業をして、20代の終わりからはロンドンでお店のプロデュースを手がけてきた稲垣さん。
京都で和食の修業をして、20代の終わりからはロンドンでお店のプロデュースを手がけてきた稲垣さん。ひとつのお店をゼロからつくっていく過程には、ブランディングとも共通する考え方がある。ほかにも食の世界との共通点を感じることはありますか?
「自分が美味しいと思ったものを100%みんなが美味しいと思ってくれることはないのと同じで、どんなに優れたデザイナーでも100点を出せることはない。たとえ代表の北川のデザインであっても、どこかで疑う気持ちは忘れないようにしています」
業界経験や知識ではなく、個人の疑問を手掛かりに。チームのなかでは日ごろから、活発に議論が行われるという。
東京の代官山オフィスで働く八戸さんは当初、そんな文化に戸惑いもあったそうだ。
 「私は以前アパレルの業界で働いていて。デザイン会社って、すごくクールに淡々と仕事を進めるイメージもあったので、すごくギャップがありました」
「私は以前アパレルの業界で働いていて。デザイン会社って、すごくクールに淡々と仕事を進めるイメージもあったので、すごくギャップがありました」オフィスは静謐で、みなさんもクールに見えますが。
「いや、議論のときは熱血です。そこが苦手な人には辛いかもしれません。意見を発しないと評価されないし、自分も仕事を楽しめない。一方で、頭ごなしに否定するような人はいないのでそこは安心してほしいです」
八戸さんはPMとして、三菱鉛筆の新しいブランドづくりに携わっている。
筆記具の老舗として、新しい文具のあり方を探りたいという相談から、企画ははじまった。
着目したのは、もともと三菱鉛筆が販売していたパワータンクというボールペン。
屋外や湿度の高い環境での作業にも耐えうるスペックの高さで、コアなファンは多いものの、無骨な見た目ゆえに、なかなか売り場で注目されにくかった。
「この“3&bC”というブランドでは、『かけるばける』をテーマに、コラボレーションによって新しい提案をしていきたくて。書く道具としてだけでなく、ファッションアイテムやアクセサリー感覚で使ってもらえるよう考えていきました」
ちょっと変わったカラーバリエーションは、スニーカーの配色がヒントになっているという。さらにファッションデザイナーやアーティストとのコラボデザインも加えた。
 「ひとつの業界でストイックに実績を重ねてきたブランドほど、新しいユーザーの可能性に気づくのが難しいこともある。第三者である私たちから、ちょっとした驚きを感じてもらえるような提案ができたらいいなと思っています」
「ひとつの業界でストイックに実績を重ねてきたブランドほど、新しいユーザーの可能性に気づくのが難しいこともある。第三者である私たちから、ちょっとした驚きを感じてもらえるような提案ができたらいいなと思っています」ときには、ロゴマークなどブランドのアイデンティティにも切り込んで提案をしていくブランディングの仕事。
長く愛着のあるものを外部のデザイナーに預けるというのは、クライアントにとって一種の冒険でもあるはず。
「その不安感は私たちも理解していて。最初は『そんなことやっちゃう?』って驚かれることもあるんですけど、私たちは根拠のない提案はしませんし、きちんとコミュニケーションを続けていけば、共感して一緒にやっていきましょうっていう空気が生まれる。不安が信頼に変わる瞬間があります」
GRAPHが今3つの拠点を持っているのも、各地のクライアントと対面でコミュニケーションする機会を重視しているから。
 本音で話せる信頼関係を築くために、まずは一人の人として会話を楽しむことや、気持ちよく仕事を進めるための細かな気遣いが、PMの仕事の第一歩だという。
本音で話せる信頼関係を築くために、まずは一人の人として会話を楽しむことや、気持ちよく仕事を進めるための細かな気遣いが、PMの仕事の第一歩だという。ちなみにGRAPHのオフィスの本棚には、画集やデザイン年鑑のようなヴィジュアル資料が極端に少ない。
かわりに並んでいるのは、行動経済学や脳科学などの本。
本棚を見れば人柄がわかると言うけれど、GRAPHの発想のもとになっているのは、人の感情の科学や脳みその仕組み、ということだろうか。
ビデオ通話をを切る間際、村部さんが「うちの代表は変人なので」と言い残した言葉が妙に気になりつつ、最後に北川一成さんに話を聞かせてもらう。
普段、スタッフやクライアントからは「一成さん」と名前で呼ばれることが多いという。
 「社長や先生って言われるのが苦手で。僕は自分のデザインを褒められると、逆に疑ってしまう。この仕事では、既存のルールや常識を疑う気持ちが大事なんです。新しいアイデアっていうのは、ゴミ箱みたいな、みんなが気づかないとこにあるものだから」
「社長や先生って言われるのが苦手で。僕は自分のデザインを褒められると、逆に疑ってしまう。この仕事では、既存のルールや常識を疑う気持ちが大事なんです。新しいアイデアっていうのは、ゴミ箱みたいな、みんなが気づかないとこにあるものだから」「一方でね、『わかる』と『できる』は違う、って僕よく言うんですけど。いいアイデアを持っていても、それを体で表現して形にできないと伝わらない。そこが難しいところです」
その言葉の意味は、北川さんの生い立ちを聞くとより実感が湧いてくると思う。
3歳にしてミケランジェロとダヴィンチを好み、写実的な絵を描いてまわりを驚かせていたという北川さん。
ところが、5歳で出会った岡本太郎の影響で作風は一変。パンクロックのような抽象絵画は誰にも理解されなかった。
 「テストでも答案を書かずに絵を描いてて。本当は答えはわかってたんですけど、書かないと理解されないですよね。みんなにアホだアホだって言われて、小学校の6年間はいわゆる勉強にまったく興味を持てなかったんです」
「テストでも答案を書かずに絵を描いてて。本当は答えはわかってたんですけど、書かないと理解されないですよね。みんなにアホだアホだって言われて、小学校の6年間はいわゆる勉強にまったく興味を持てなかったんです」本当はわかっているのにアホだと言われて、悔しくなかったですか。
「はい。ちょっと傷ついてはいたけど自由で楽しかったし、誰にも迷惑かけてないし、別にいいかなって。でも6年生のときに親兄弟が『家族みんなで一成のことを支えよう!』って、家族会議してるのを知ってショックを受けて(笑)。そこからは、ちゃんと答案書いてから、絵を描くようにしました」
「特に母親のためかな。僕、小学生のとき、虹を追いかけて自転車を飛ばしてて。近所のおばちゃんらが『またあの子アホやから…』ってコソコソ言ってる横をうちの母親が、名前呼びながら走ってきて『虹取りに行くんやったら、これいるやろ!』ってビニール袋をくれた。そういう人だったからね」
中学以降は優等生だったものの、高校時代にはまた勉強を放棄、そこから海外生活を経て筑波大学へ。研究を続けるつもりが、地元に引き戻され倒産寸前だった家業を背負う。旧経営陣を入れ替えてGRAPHとして再生するまで…と、おそらく壮絶だったはずの話を北川さんがあまりに淡々と話すので、思わず笑ってしまう。
ご自身のことをかなり俯瞰していて、そのときどきで違う人格を生きているみたい。
多面的というか…、器用ですね(笑)。
「やっぱり、この仕事も器用さはあったほうがいい。型破りなことっていうのは、型を知っている人にしかできないから。だけど案外、難しい理屈より下手くそな歌のほうが心に届くこともあるし。相手の気持ちを考えて行動できる、人間らしい人が僕は好きですね」
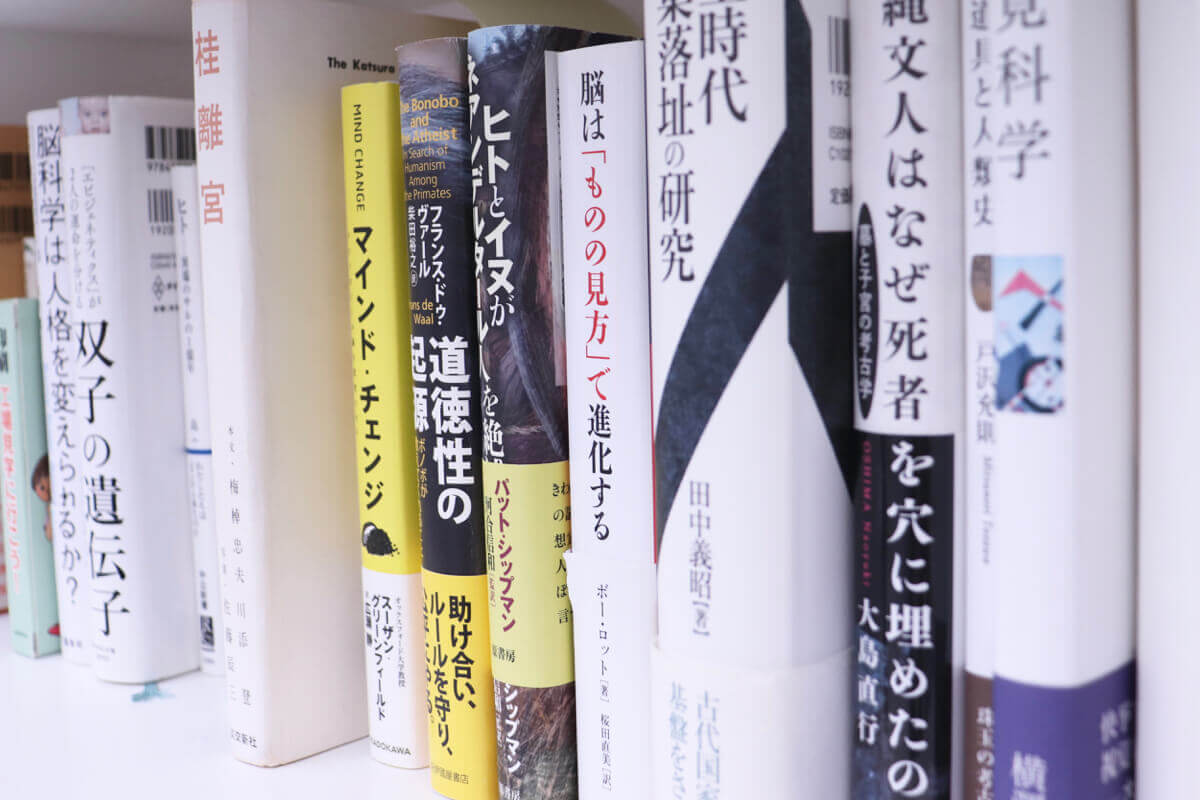 相手が言葉や形にできない部分を汲み取って表現するブランディング。メッセージを発する側と受け取る側、双方の気持ちを想像しながら思いを形に変換していく、人としての力が試される仕事だと思う。
相手が言葉や形にできない部分を汲み取って表現するブランディング。メッセージを発する側と受け取る側、双方の気持ちを想像しながら思いを形に変換していく、人としての力が試される仕事だと思う。実感と根拠、常識と違和感、ちゃんしていてどこか「変なの!」と、顔が緩んでしまうような。
GRAPHは、そんなバランスを持った人たちが働く会社でした。
(2021/4/1 取材、10/29 再募集 高橋佑香子)
※撮影時はマスクを外していただきました。
※写真は一部ご提供いただいたものを使用しています。





