※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
ピーナッツバターが好きです。食べすぎるとよくない。そうわかっていても次のひとくちを求めてしまいます。
印象的なのは、なんといってもあのぼってりとした食感と甘さ。だからこそ、Bocchi(ボッチ)のピーナッツペーストを食べたときはびっくりしました。

とろとろとした食感と、新鮮な落花生をそのまま食べているような香り。自然な甘さなので、料理にひとさじ加えてもおいしそう。
つくっているのは千葉県にある問屋、株式会社セガワ。
飲食店や小売店向けに落花生やお米を卸すほか、ピーナッツペーストをはじめ、さまざまな商品を企画・製造・販売している会社です。その商品の一部は、ブルーボトルコーヒーや星野リゾートでも使われているとか。
今回は製造と事務の担当者を募集します。メインの仕事を持ちつつ、垣根を超えて、畑づくりから全員で取り組むそうです。特に製造部門では、ゆくゆくは会社を担っていく存在になる方を探しています。
畑から食卓まで、おいしさを届ける仕事です。ブランドを立ち上げて6年。まだまだ余白の大きな仕事だと思います。
東京駅から特急しおさいに乗り、1時間30分。
待ち合わせの八日市場駅で降りると、白いバンの前で手を振る男性が見えた。セガワで常務を務める加瀬さんだ。
「今日は工場だけじゃなく、畑や海にもお連れしますよ。このまちを気に入ってもらえたらうれしいです」

挨拶もそこそこに、まずは匝瑳(そうさ)市内にある工場へ。八日市場駅からは10分ほど離れた田園地帯のなかにある。
事務所に到着すると、早速パソコンを開いて一枚の写真を見せてくれた。

「これは40年ほど前の実家の写真ですね。軒先に近所のおばちゃんたちが集まって、落花生の殻を手で剥いたり選別したりしてました。当時流行りだったプロレスの話とかしながら。笑い声の絶えない空間でした」
セガワのルーツは、加瀬さんのおじいさんが1946年に創業した原料問屋。お米や落花生を地域の農家さんから買い付け、加工して卸す仕事を続けてきた。
本社のある旭市は「千葉の落花生発祥の地」と呼ばれていて、落花生の生産がさかん。
旭でつくられる落花生は甘みやうまみが強く、贈答品として長らく愛されてきた。
「5月に種まきして、秋になったら掘り起こしてそのまま2週間ほど畑で干したあと、積み上げてさらに1ヶ月ほど干します。これは『らっかぼっち』と呼ばれる野に積み上げる独特の干し方で、甘みを凝縮する大切なポイントなんです」

収穫がはじまる10月中旬から新年にかけては、工場につきっきりで休みなく加工を行う。
「落花生って季節労働なんです。忙しい時期だけお手伝いに来てもらうのが一般的で。社長である父親は、年間雇用できる、安定した仕事にしたいと考えていたようです」
そこではじめたのが、ドライフルーツの加工。他社からの依頼を受けて加工する委託事業だった。
結婚を機に千葉に戻っていた加瀬さんは、ドライフルーツと落花生の加工を一任されるなかで、2015年に自社ブランド「Bocchi」を立ち上げる。
もしや「らっかぼっち」のBocchiですか?
「そうです、そうです。ドライフルーツの加工も、経営面では必要な仕事なんですけど、自社製品じゃないから面白くない。やっぱり自慢の落花生で仕事がしたくって」
落花生を加工している業者は多いけど、加工品というと、レパートリーがほとんど決まっていたそうだ。
「殻つき落花生、ゆで落花生、甘納豆、よくてチョコレートコーティング。このままじゃ若い人は食べないし、落花生の消費が減り続けていけば、やがて農家さんもいなくなるだろうと」
加瀬さんが目をつけたのは、ピーナッツペースト。クラフトベーカリー「365日」のオーナーシェフに意見をもらい、改良を加えた。
1年以上の歳月をかけて開発したペーストは、またたく間に看板商品に。「落花生そのものの甘さを感じる」と、クチコミでファンが増えつつある。
農家のことをもっと知ろうと、6年前からは耕作放棄地を借りて自社で畑を始めた。農薬と化学肥料は使わず、できるだけ自然に優しい栽培法に挑戦している。
商品づくりも畑のことも、実直に取り組んできた加瀬さん。
「若い農家さんが『落花生を育ててみたい』と相談をくれたり、ピーナッツペーストを使ってくれているお客さまが、畑を見たいと遊びにきてくれたり。段々と、いろんな人を巻き込めている感じがあります」

「落花生を未来につなげることならなんでもやりたい」とのこと。
ピーナッツペーストに代わる看板商品の開発、Bocchiを広く知ってもらうための情報発信、農家さんの育成など、やりたいことは山ほどある。
「理想は社長がいらない会社なんです。商品をつくって売ることはメンバーに全部任せて、僕はどんどん新しいことにチャレンジしていきたい。そのためにも、畑や工場を任せられる、僕の右腕になってくれるような方と出会えたらと思っています」
とはいえ、商品あってこそのブランド。まずはコツコツと、商品をつくる経験を積むなかでセガワのことを知っていくことになる。
まずは、製造チームの越川さんに話を聞く。朗らかな感じが心地いい方だ。

現場で働くメンバーのなかでは最も社歴が長く、9年半にもなる。
「以前は、テレビ局やディズニーランドで働いていました。面白そうなことにチャレンジするのが好きなんです。旦那の実家があってこちらへ引っ越してきて、たまたま求人を紹介してもらって、面白そうだなって」
匝瑳工場で製造しているのは、ピーナッツペーストやゆで落花生、甘露煮など。
工場の中へ入ると、落花生のむわっとした香りに包まれる。
落花生の入る麻袋は、重さ30kg。腰を入れて持ち上げ、釜に入れる。茹でたり煎ったりする部屋は、エアコンが効かず、サウナのように蒸し暑い。
商品のなかには、一つひとつ手作業で包装するものもある。高さ、奥行きの寸法を揃え、シワがよらないように帯を巻く。

ふだんは世間話をしながら和気あいあいと作業をしているそうだけど、体力も、集中力も使う、淡々とした仕事だと思う。この仕事を続けてきた、越川さんを動かす原動力って、なんでしょう?
「3年ほど前、はじめて展示会に連れて行ってもらったんです。普段は工場でマニュアルに沿って商品をつくっているんですけれど、そのときはじめてお客さんから『セガワの落花生はおいしいね』と直接、感想をいただいて」

「そこからがらっと意識が変わりました。もっとおいしく、お客さんに喜んでもらえるような商品をつくりたい。じゃあいい仕事をしないと、と考えるようになって。ほかのメンバーにも、こうしたら?と自ら提案するようになりました」
たとえば、落花生の選別作業。ピーナッツペーストに使う落花生は、機械では判別しきれない色や形の違いを、目視でひたすら選別していく。

細かい色味を瞬時に見分けて、いちばんおいしい煎り加減のものを残す。越川さんは担当のパートさんと何度も話しながら、改善を重ねてきた。
「うちの商品は味も、見た目も大事なので。ちょっとでも見た目の悪いものが入っていたら悲しいじゃないですか。手に取ったときから楽しんでもらえるような商品をつくっていきたいですね」
製造は、こつこつ積み重ねていく仕事がほとんど。目の前の作業をただこなすだけではなく、越川さんのようにお客さんのことを想像して働くなかで、仕事をよくするアイデアも生まれていきそうだ。
次に話を聞いたのは、営業の佐々木さん。
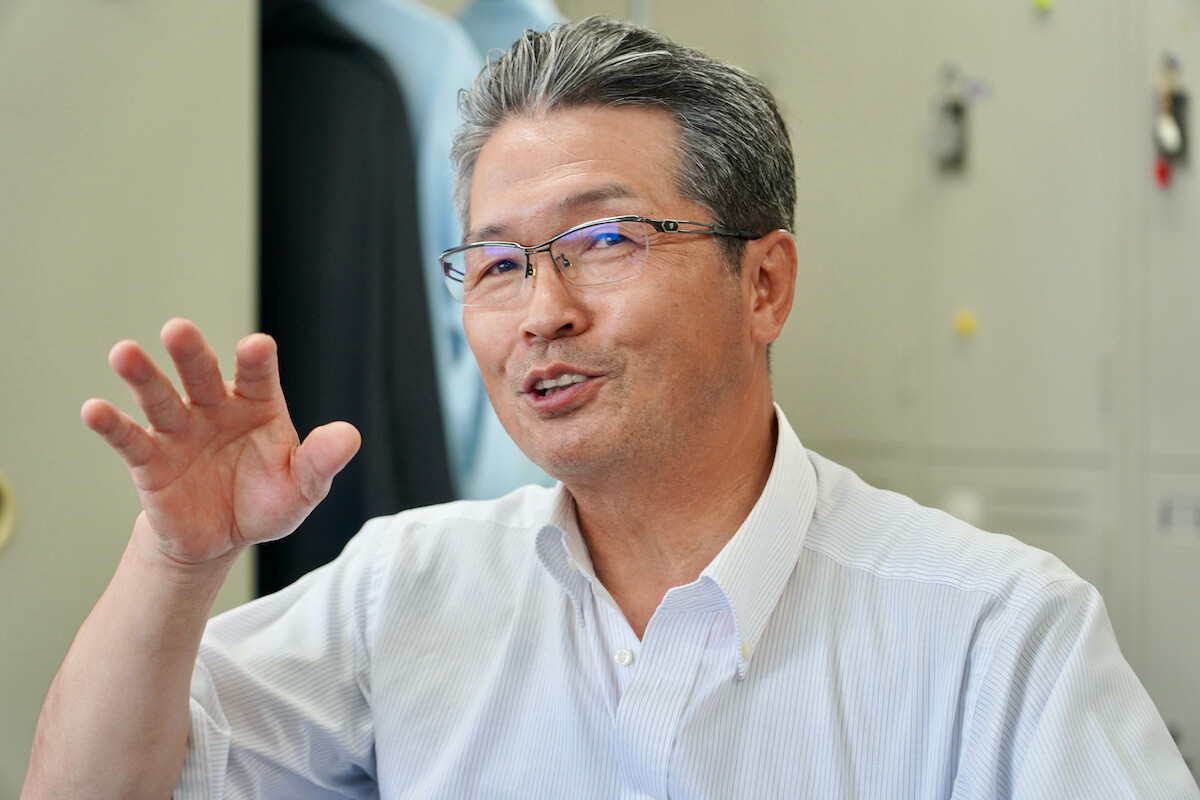
地元のお菓子屋で長年働き、定年後にセガワへ入社。
新規のお客さんを開拓したり、百貨店の催事に出展したりするほか、農作業をメインで担当している。
畑について聞くと、頬をほころばせながら話してくれる。
「去年と今年とでは土のつくり方を変えてみたんですよ。土壌測定してね。落花生は石灰分が大事なので、こまめにまくようにしました。去年は冷害もあって育ちが悪かったけど、今年は期待できますよ」
農家の気持ちを知りたいと思ってはじめた、畑。
佐々木さんを含め、みんな農家出身というわけではないし、それぞれの持ち場もある。仕事の合間をぬって、試行錯誤しながら畑づくりをすすめてきた。

「農薬を使わない分、草取りは大変です。落花生は土中に実がなる作物なので、夏場もしっかり草を取ってあげないと、いい実がならないんです」
少しずつ機械も導入しているけれど、暑さにはかなわない。15分も外にいると汗だくになる。
「常務が畑をはじめるとき、社長に止められてましたけど、3年かけて口説いたのに心打たれて。体にいいものを食べてもらいたいっていう思いが一貫しているんですよね」
「お菓子屋で働いていたときは、原料はただ外から買うだけ。いまは自分たちで原料から製品までつくって、お客さまに提供している。畑から食卓まで責任をもってやれていることに、やりがいを感じますね」
千葉出身の佐々木さん。この地域でとれた落花生を、もっと若い人に食べてもらいたいと考えている。
「落花生って古臭いイメージがあるので、新商品をどんどんつくってBocchiというブランドを広げていきたいですね。自分の仕事はこれだから、という役割にとらわれず、みんなでアイデアを出していけたらと思います」
取材の終わりに、「ぜひ見てほしい」ということで連れてきてもらったのは、九十九里浜。

加瀬さんの実家は、この海のすぐ近く。小さい頃からボディーサーフィンをしてよく遊んでいた。
ピーナッツペーストに使っているのも、この浜でつくっている塩。加瀬さんの土地への愛着が伝わってくる。
「やっぱり、この海が好きなんですよね。いつまでもぷかぷか浮いていたい。この海を守りたい、海に流れる水を汚したくない。その思いで農薬と化学肥料を使わない栽培をつづけています」
自然と付き合っていくことは、容易ではない。
昨年は長雨に見舞われた。契約している農家さんのなかには、収量が4割減り、「もうやめたい」とこぼす方もいた。
「自分でも畑をしてみて、実感します。乾燥の工程がいちばん大変。1年間作業を頑張ってきても雨が降ると、そこでだめになってしまう。今度、うちで乾燥調整施設をつくって、おいしさと農家さんの稼ぎを両立できるような仕組みをつくろうと考えてます」
「僕って、寂しがりやなんです。ふだん言わないけど(笑)。小さいときに見ていた、軒先でみんなが集まって作業する光景が忘れられなくて。地域の農家さんも、働く人も、お客さんも、みんなでわいわいできるような畑や仕事場をつくっていきたいですね」
浜のすぐそばの畑に立つと、潮の匂いがしました。
軒先の笑い声とか、一緒にした畑で作業した記憶とか。ささやかなものたちが、陰ながらおいしさをつくっているんだと思いました。
気になった方は、まず加瀬さんに会いに行ってほしいです。一緒にまちを眺めることで、大切にしたいものが見えてくると思います。
(2021/7/29取材 阿部夏海)
※撮影時はマスクを外していただきました。





