※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
先輩のつながりって、ありがたい。学生時代、教科書や道具を譲ってくれたり、実習のコツを伝授してくれたり。バイト先を紹介してもらったこともあるし、先輩の失敗談から、落とし穴を回避できたこともある。
自分の少し先を歩きながら手引きしてくれる人の存在は、新しいコミュニティに入っていくとき、とても心強い。
そんな先輩たちとのつながりを、地域おこし協力隊の活動にうまく活かしているのが、兵庫県の中東部に位置する丹波篠山市。今回はここで起業支援型の地域おこし協力隊を募集します。
 里山で農業に取り組むこともできるし、城下町の文化を掘り下げて観光業につなげることもできる。テーマは自由です。
里山で農業に取り組むこともできるし、城下町の文化を掘り下げて観光業につなげることもできる。テーマは自由です。何かひとつのプロジェクトで生計を立てる道もありますが、いくつかの仕事を組み合わせてマルチワーカー的な働き方をしている人も少なくありません。
協力隊のOBや先輩移住者たちがコーディネーターとして活動をサポートする仕組みや、神戸大学と連携した起業のためのスクールなどもある丹波篠山。この記事で紹介する人たちもきっと、新たな挑戦をサポートしてくれる先輩になるはずです。
大阪から電車で1時間ほど。篠山口という駅から路線バスで、街の中心部に向かう。
ちょうどお盆の時期で、商店街の軒にはずらりと提灯がぶら下がっていた。
 猪の頭が壁から突き出した看板が迫力満点の猪鍋屋さん、黒豆を使ったパンや大福のお店など、街並みにも丹波篠山らしさが垣間見える。
猪の頭が壁から突き出した看板が迫力満点の猪鍋屋さん、黒豆を使ったパンや大福のお店など、街並みにも丹波篠山らしさが垣間見える。これから向かうのは、神戸大学の研究室を兼ねたフィールドステーションという拠点。コーディネーターとのミーティングや報告会でここを利用する隊員も多い。
中に入ってみると、研究室の先生とコーディネーターのみなさんが一緒になって夏祭りの相談をしていた。
「丹波篠山市は、もともと神戸大学農学部がフィールドワークを続けてきた場所なんです。地元の人も、外から人が来ることで地域に化学変化が起きることを、長年にわたって経験していて。人を受け入れてくれる土壌があるまちだと思います」
そう教えてくれたのは、協力隊OGで、コーディネーターを務める梅谷さん。
 「今はゲストハウスの経営と、ツアー企画と、協力隊のコーディネーター、3つの仕事を掛け持ちしています。実は今日はゲストハウスに宿泊のお客さんがいるので、このあとすぐに出なきゃいけなくて。ちょっとバタバタしています」
「今はゲストハウスの経営と、ツアー企画と、協力隊のコーディネーター、3つの仕事を掛け持ちしています。実は今日はゲストハウスに宿泊のお客さんがいるので、このあとすぐに出なきゃいけなくて。ちょっとバタバタしています」なんだか忙しそうだけど、表情は明るく、日々充実している感じが伝わってくる。
もともと尼崎出身で、前職は東京の飲食店に勤めていた梅谷さん。2017年に協力隊としてJターンし、3年かけてゲストハウス「うめたんFUJI」をオープンさせた。
「丹波篠山は江戸時代の武家屋敷の町割が残っていて、丸ごと日本遺産みたいなまちです。デカンショ踊りやお祭りの文化、里山で採れる食材も豊富で、観光に取り組むにはいいフィールド。私も協力隊として着任した当初は、海外の方向けにモニターツアーなどを企画していました」
 大阪や神戸から日帰りで楽しめる気軽さもある一方で、もっとじっくり体験してもらうための滞在拠点がほしいと考え、ゲストハウスを立ち上げることに。
大阪や神戸から日帰りで楽しめる気軽さもある一方で、もっとじっくり体験してもらうための滞在拠点がほしいと考え、ゲストハウスを立ち上げることに。任期2年目から物件を探しはじめ、ちょうどいい物件に出会えたのは翌年。開業準備を急ピッチで進め、移住から3年で自分の宿をスタートさせた。
「丹波篠山の地域おこし協力隊制度は、テーマもスケジュールも自由に組める分、何もしないとあっという間に任期が終わってしまう。どんな事業をやりたいか、自分で具体的な目標を設定する必要があります」
一方、計画を実行していく過程では、コーディネーターをはじめサポートしてくれる人がたくさんいる。
補助金の申請手続きから、企画のブラッシュアップまで、気軽に相談できる窓口があるのは心強い。梅谷さんのように、協力隊を経てコーディネーターになった先輩もいるので、近い視点で話ができるはず。
 「協力隊の1年目は、とにかくいろんな人に会いに行きました。そこで『宿でジビエを出したいんです』って、自分のやりたいことを話すと、知り合いの猟師さんを紹介してもらえたりして、人の縁がつながっていきました」
「協力隊の1年目は、とにかくいろんな人に会いに行きました。そこで『宿でジビエを出したいんです』って、自分のやりたいことを話すと、知り合いの猟師さんを紹介してもらえたりして、人の縁がつながっていきました」自分の目的に直結していなくても、紹介されたら、まずは会ってみる。
井戸端会議にも参加し、いろんな世代の人と話してきた時間が、今の梅谷さんの暮らしや仕事の基盤になっている。
 「正直、ゲストハウス一本で食べていくのは厳しくて。自分が楽しめる副業を組み合わせてマルチワーカー的に暮らしています。人の輪に溶け込んでいけば、『英語できる? だったらツアー手伝って』みたいに、仕事もおのずと見つかると思います。枝豆の収穫のアルバイトとか、結構ありますよ」
「正直、ゲストハウス一本で食べていくのは厳しくて。自分が楽しめる副業を組み合わせてマルチワーカー的に暮らしています。人の輪に溶け込んでいけば、『英語できる? だったらツアー手伝って』みたいに、仕事もおのずと見つかると思います。枝豆の収穫のアルバイトとか、結構ありますよ」野菜をもらうなど、何かお世話になったら、別のことでお返しをする。そんな付き合いも大切なこと。
「ここで暮らしていると、近所の方が突然家に来て『ちょっと一緒にキュウリもがへん?』みたいなお誘いもよくあって。そういうことも楽しみながら輪に入れるといいんじゃないかと思います」

現役の隊員として2年目を迎えた廣川さんは、大阪出身。里山のフィールドを求めて、丹波篠山にやってきた。
 「大学を卒業してエンジニアとして働いた後、世界一周の旅に出たんです。最後に訪れたインドで日本語学校の立ち上げに関わって、帰国したのが2年前でした」
「大学を卒業してエンジニアとして働いた後、世界一周の旅に出たんです。最後に訪れたインドで日本語学校の立ち上げに関わって、帰国したのが2年前でした」日本にいたころから、持続可能な社会システムをデザインする「パーマカルチャー」の領域に興味があったという廣川さん。
インド滞在中、意外な事実を知ることに。
「パーマカルチャーっていうのは、暮らしのデザイン手法として、オーストラリアの教授が体系づけたものなんですが、その過程で日本の里山の暮らしを参考にした部分があるらしくて」
「仲間に『パーマカルチャーの国から、何を学びに来たんや』って言われて、恵まれた風土で生まれ育ったことを、あらためて知りました」
帰国後まもなく結婚した鍼灸師の奥さんと丹波篠山に移住。現在は、16世帯が暮らす小さな谷あいの集落で、古民家に暮らしながら、畑を拓いて農作業をし、パーマカルチャーを実践していくための土台づくりに取り組んでいる。
 「ゆくゆくは、同じような志を持つ人の入り口になるようなワークショップや、情報発信をしていきたいという思いがあります。今は本当に、自分の暮らしをつくるのに精いっぱい。まだまだスキルを身につけている途中です」
「ゆくゆくは、同じような志を持つ人の入り口になるようなワークショップや、情報発信をしていきたいという思いがあります。今は本当に、自分の暮らしをつくるのに精いっぱい。まだまだスキルを身につけている途中です」ここに来るまで、畑仕事もほとんどしたことがなかったという廣川さん。
耕作放棄地を借り受けたものの、資材のゴミが残っていて種を植えられない。まずは掃除からはじめた。今は、裏山に果樹園をつくるための準備として石積みを考えているという。
新しい暮らしは、一朝一夕には得られない。根気強さも必要なのかもしれない。
協力隊の任期は今年で終わり。生まれたばかりのお子さんもいるという状況で、来年度から自活していくのに不安はないですか?
「たしかに、それでずっと生活できんの?って言われたら、苦しい。ただ、何かを形にしていくには準備が必要だし、種まきは着実にできている。正直、何とかなるっていう気持ちはあります」
 これまで廣川さんは、自家農園を開墾するかたわら、空き家対策や情報発信など地域活動に参加することで、副業的な収入を得たり、助け合いのつながりを見出したりしてきた。
これまで廣川さんは、自家農園を開墾するかたわら、空き家対策や情報発信など地域活動に参加することで、副業的な収入を得たり、助け合いのつながりを見出したりしてきた。就農という単一の事業では収益化できていなくても、マルチワーカーとして生きていく手がかりはつかめている。
「今自分がやろうとしているのは、ある意味、昔の百姓の現代版みたいなものだと思う。畑をすることで食を確保し、地域のお手伝いをすることで、対価を得たり、人とエネルギー交換をしたりしながら暮らしていくような感じです」
起業というと、自分でゼロから1をつくるようなイメージもあるけれど、生き方、働き方のヒントは地域のなかにいろいろと眠っているのかもしれない。
 まったく新しいものや考え方を持ち込んで短期的な成果を目指すよりは、地域の時間のなかで文脈を読み取り、もとから住む人たちと一緒に暮らしの魅力を磨いていく。そんな意識で活動に加われるとよさそう。
まったく新しいものや考え方を持ち込んで短期的な成果を目指すよりは、地域の時間のなかで文脈を読み取り、もとから住む人たちと一緒に暮らしの魅力を磨いていく。そんな意識で活動に加われるとよさそう。人から人へ、つながりの網の目を広げていけば、暮らしも仕事も形になっていく。その第一歩をサポートしているコーディネーターの人たちにも話を聞きました。
左から、大阪から移住して4年目になる河口さんと、市内の県立公園で10年ほど働いている塩山さん。
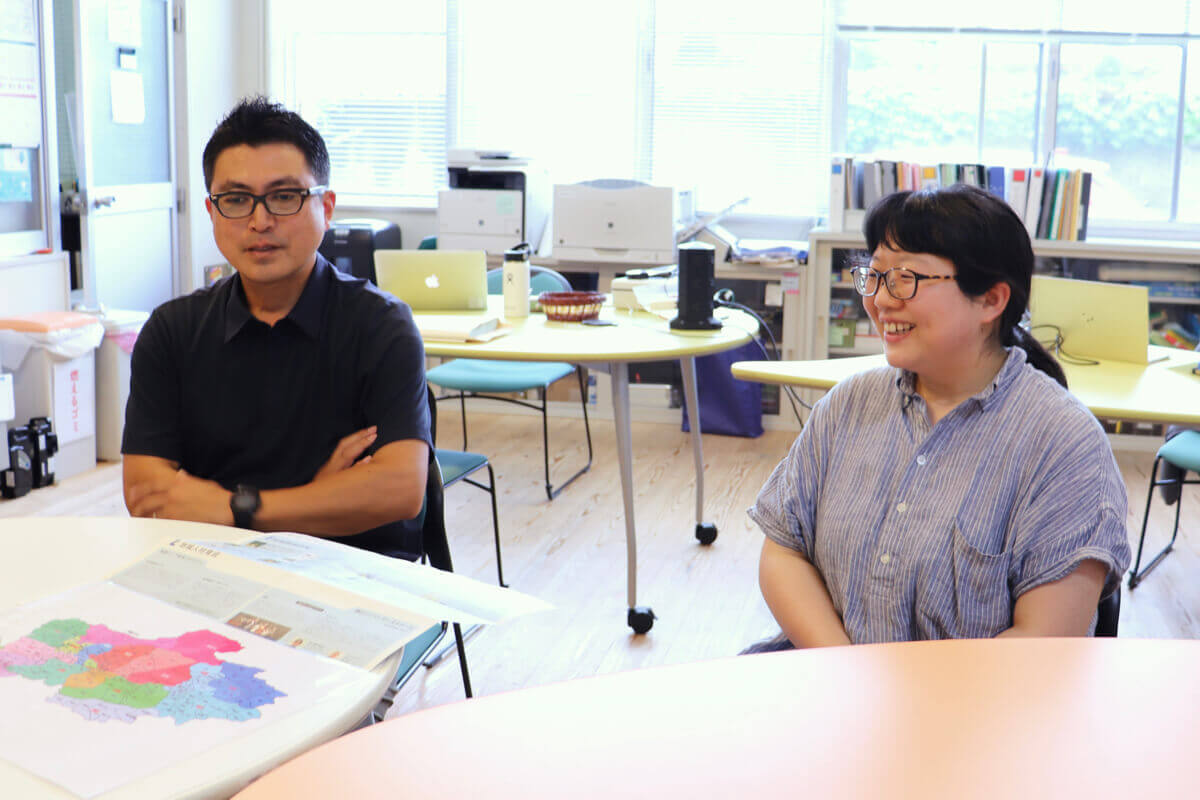 「コーディネーターとして一番大事なのは、隊員と地域、それぞれのニーズや希望を吸い上げることだと思います。どんなふうに組み合わされば、お互いが幸せになれるか。お見合いのお世話をするような気持ちで日々向き合っています」
「コーディネーターとして一番大事なのは、隊員と地域、それぞれのニーズや希望を吸い上げることだと思います。どんなふうに組み合わされば、お互いが幸せになれるか。お見合いのお世話をするような気持ちで日々向き合っています」新しい人が入ることで、地区の様子は大きく変わっていく。実際、一度隊員の受け入れを経験した地区では、二度三度と受け入れを希望することが多いという。
そういった良い循環を生み出すのが、コーディネーターとしての醍醐味でもある。
「本当に、この界隈の人は、ちょっとおせっかいな人が多いんです(笑)。何かあるとすぐ、人と人をつなげようとする。直接知り合いじゃなくても、『あの地区やったら、誰々さんに聞いてみるわ』って芋づる式に紹介してもらえることが多いので、仕事はしやすいですよ」
「みんながそうやっておせっかいを焼くのは、どこかに応援したいっていう気持ちがあるからだと思います。丹波篠山にちょっとでも興味があったら、ぜひ連絡してきてください。協力隊じゃなくても、こういう就職先もあるよ、って紹介することができるかもしれないので」
 今回は起業支援型だけでなく、学生の立場で研究や学問のフィールドとして丹波篠山に関わる道もあります。里山のリアルな課題や魅力を肌で感じながら、自分の生き方、働き方を考えていけるはず。
今回は起業支援型だけでなく、学生の立場で研究や学問のフィールドとして丹波篠山に関わる道もあります。里山のリアルな課題や魅力を肌で感じながら、自分の生き方、働き方を考えていけるはず。一人でゴールまで走るのは大変でも、誰かが伴走してくれたら、少し道のりが楽になる。無理に突っ走ろうとせず、誘われるまま、寄り道してみるのもいいかもしれない。
マルチワーカーという生き方。ここから、はじめの一歩を踏み出してみてください。
(2021/8/12 取材 高橋佑香子)
※撮影時はマスクを外していただきました。







