※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
「夏は、日本料理の献立を考えるのが難しい季節です。素材が限られるし、まず菜っ葉がないでしょう」
加寿子さんの言葉に、ふと、考えてしまう。
スーパーには、夏を含め一年中ほうれん草や小松菜などの菜っ葉が並んでいるけれど、そういえば旬はいつだっけ。
長年、日本料理を研究してきた後藤加寿子さんは、体内時計ならぬ体内カレンダーが備わっていて、季節の巡りに合わせて「そろそろ、あれが食べたいな」という報せがあるという。
武者小路千家という茶道の家元に生まれ育った加寿子さん。茶事から生まれた「懐石」の食文化にその感性を磨かれてきた。
懐石というと、格式高く難しいものに感じるかもしれませんが、家庭料理の基本である一汁三菜は、もともと茶懐石から生まれたもの。使われる食材も、ごく身近なものばかりです。

炊き立てのご飯、旬の食材、季節ごとに配合を変えたお味噌。ありふれた素材でも、タイミングに心を尽くすことで味わいは大きく変わる。加寿子さんの料理は、食べる人を想う一手間が、おいしさにつながることを教えてくれます。
この夏、加寿子さんが料理監修をつとめるお店「びおら」が、広尾にオープンしました。オーナーをつとめるのは、その手料理で育った娘のすみれさんです。
1日1日、丁寧に日本の家庭料理を表現するお店。今回は、ここで接客を担うホールスタッフと、キッチン補助のスタッフを募集します。パートタイムの募集なので、自分のライフスタイルと両立しながら働ける人を求めています。
今は若手のスタッフが中心ですが、主婦をはじめ、どの年代の方にも学びの多い現場だと思います。
東京・広尾。地下鉄の駅から、大通り沿いを歩いて5分ほど。路地に入ったところで「びおら」の看板を見つけた。
足元には、鮮やかな実をつけた鬼灯の鉢。
中に入ると、店内は穏やかな照明に包まれている。

壁には小さな日本画や陶のオブジェが飾ってあり、和室ではないのに、どこかお茶室にも通じる静けさがある。
席に座ると、環境音楽のようなBGMが聞こえてきた。
「これ、私が幼いころに聞いていた台所の音をイメージして、つくってもらったんですよ」
そう話すのは、後藤すみれさん。

たしかに音色の向こうに、サクサクと野菜を刻む音、水を流す音が聞こえる。聴いていると、家でご飯を待っている時間のような、不思議な安心感がある。
「お客さまには、味だけでなく、目や耳でも食事を楽しみながら、ゆったり過ごしていただけたらいいなと思います。営業時間中は、ご飯を炊く鍋がカタカタ鳴る音も加わるんですよ」
そう言って見せてくれたのは、小さな雪平鍋。

びおらでは、いつでも炊き立てを食べられるように、この鍋で少しずつご飯を炊く。
炊き上がったご飯は、まず鍋の縁のところから二口分だけお茶碗に丸く盛り付ける。残りをおひつに移しておけば、おかわりもまた、美味しい。
この手間ひまかけたご飯は、すみれさんが家庭で食べ慣れたもの。
「当初、さすがにお店で一つひとつ炊くのは難しいかと思っていたけれど、やってみたら案外うまくいって。炊飯器はもう仕舞っちゃいました」
と、うれしそうに話すのは母の加寿子さん。

料理研究家としてのキャリアは長い加寿子さんも、飲食店ははじめての経験。オープンまでの半年間は記憶にないくらい、大変だったと笑う。
直前まで検討を重ね、ようやく完成したはじめてのコースが「夏のびおら」。
一品目は黒い折敷にポンと置かれる赤い器の白味噌椀。底に沈んだ和芥子を溶いて口に含むと、胃が落ち着いて悪酔いしないのだそう。

器を手に取る所作にも想像を巡らせながら、メニューを見ていくと、湯葉や万願寺唐辛子など京都を感じさせる食材に、アジフライやポテトサラダのような家庭料理定番の一皿も。
「茶碗蒸しも普通はエビや銀杏が入っているけれど、うちのは、ちくわとわかめだけ。これだけで、おいしいんですよ」
この茶碗蒸しは、もともと加寿子さんのお母さん、同じく料理研究家として食文化の普及につとめた千(せん)澄子さんの定番料理。
お店には、澄子さんの味を偲ぶファンも多く訪れるという。
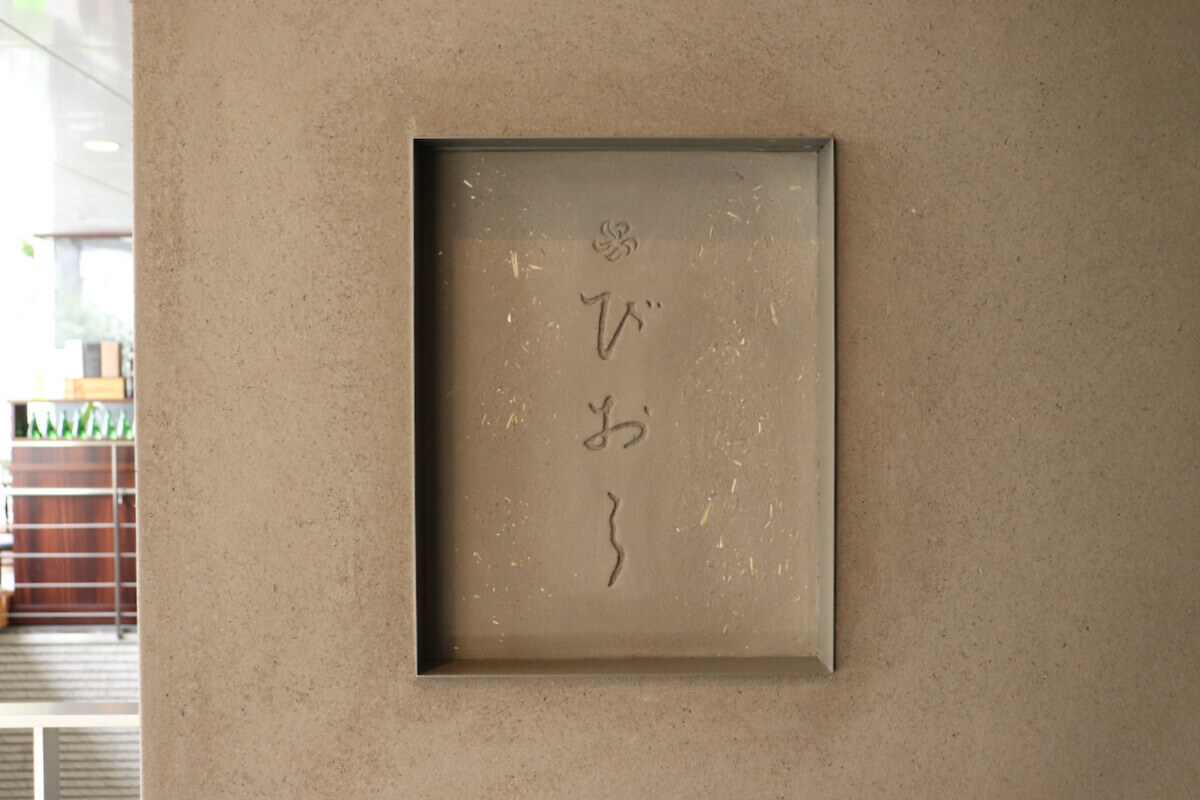
「母はよく、日本料理には3つの“き”があると話していました。器と、季節と、それから機会、チャンスやタイミングのことですね。この3つ目の機が、茶懐石では特に重要なんです」
ご飯を炊くタイミング、次の皿を出すタイミング、相手の状況や気持ちを汲むおもてなしがあることで、食事がより豊かなものになっていく。
「利休の考えたおもてなしを、お店のサービスとして表現するのは、なかなか難しい。もしかしたら飲食業界で働いた経験よりも、芸術に興味がある人のほうが理解しやすいのかもしれませんね。絵画や音楽と同じように、食も五感で味わうものなので」
そんな加寿子さんの考えを学び、形にしようと奮闘しているのがシェフの向坂さん。

「調理には段取りが欠かせないけれど、やりすぎると手抜きになってしまう。その見極めが難しいです」
「たとえば、漬物をあらかじめ皿に盛って、冷蔵庫に用意しておけば効率的ですが、冷気で湿った器をお客さまにお出しするのは、この店のおもてなしとして相応しくない。忙しいなかで、どこまで気遣いができるか、いつも考えています」
料理に、サービスに、お客さんは満足してくれただろうか。
キッチンで作業していると、ホールの様子が見えない分、気掛かりに感じるという。
「たまにお皿に料理が残っていることもあって。お口に合わなかったのか、量が多かったのか、そういうことをホール担当がさりげなく気にかけて伝えてくれると助かりますね」

びおらでは、賄いを通じて、サービスに携わるスタッフ全員が、メインからスイーツまでひと通りの味見をする。
向坂さんは、そのときになるべく食材のことを詳しく伝えるようにしている。
「今使っている“姫島ひじき”は、1年のなかで2日間しか収穫できない品種で、通常より細くて繊細な味がするものです。それを毎回お客さんに説明する必要はないんですが、聞かれたときには答えられるように、味やエピソードを覚えておいてもらえるといいですね」
“とゆ湯葉”や“魚そうめん”など、メニューにはときどき見慣れない食材の名前が出てくる。
気になったことをそのままにせず、調べたり質問したり、楽しみながらインプットしていける好奇心があるといい。

お店には加寿子さんのご縁で、お茶や日本文化に詳しいお客さんも多く訪れる。
向坂さんは、その出会いに日々好奇心を刺激されているという。
「この前、お客さんから『向坂さんは長次郎さんになりなさい』って言われて。チョウジロウさんって誰だ?と思って調べたら、千利休に楽茶碗をつくっていた有名な方でした」
長次郎が利休の考えを器で表したように、加寿子さんからしっかり学んで料理をつくりなさい。そんなやりとりは、このお店ならでは。

向坂さんと話していると、加寿子さんが不意に「こんなときにアレだけど…」と、料理のアイデアを持ちかける。
プリンを温かいまま提供するにはどうしたらいいか。知人の家で食べたプリンが、オーブンで保温されていておいしかったという、加寿子さんの思い出話に耳を傾けながら、みんなで頭をひねる。
こうして加寿子さんから、急に新しい課題や食材が投入されることは、日常茶飯事。向坂さんにとっては、それが仕事のモチベーションになっているという。
「加寿子さんがつくってきた世界観をどれだけ形にできるか、今はそれで精一杯ですが、時間ができたら、お茶のこともちゃんと勉強してみたいと思っています。この前、すみれさんのお父さんからも『茶道具図鑑』をいただいたところなので」
その声に「いいね、今度みんなで、お茶を勉強する会をやろうよ」と提案するのは、ホールやお店の広報を担当している石橋麻衣子さん。すみれさんとは中学時代から30年来の親友だという。

「飲食店で働くのは、大学生のアルバイト以来なんですけど、今まで“友達のお母さん”だった加寿子さんから、私もいろんなことを教えてもらっています。この歳になって、はじめて知ることも多くて、新しい世界が広がっていくのは楽しいですね」
ホールでのおもてなしは、調理以上にマニュアル化が難しい。
「食も感性が大事」と言う加寿子さんのやり方は、決して形式張ったお作法ではない。
「たとえば、女性のお客さんが上着を羽織ったら、エアコンの温度を上げましょうか、とか。お茶碗が空いていたら、おかわりお持ちしましょうか、って声をかけてみる。相手の様子を見ていれば、段々いい接客ができるようになると思います」
お客さんと接していない時間も、大切なおもてなし。掃除や、器の手入れなど、細かいところに気づく目は、お客さん視点で想像を巡らせるなかで少しずつ鍛えられていく。

「お客さまによっては、酒器から調味料から、いろんな質問をされる方もいます。そのときは、ただ答えを伝えるだけじゃなく、スタッフも会話を楽しむ気持ちを持って対応してもらえたらいいなと思います」
麻衣子さんは、自分が調べたことをメモして貼っておいたり、お店のお花が変わったことをSNSで共有したり、その日いないスタッフにもお店の変化や情報が届くように工夫している。
もともと「びおら」は、加寿子さんやその家族の縁から生まれたお店。お客さんもきっと、家を訪ねたような安心感を期待していると思う。
そのコミュニティに入っていくのは、少し緊張するかもしれないけれど、加寿子さんたちは、スタッフにも家族と同じように接してくれるので、胸を借りるつもりで一つひとつ覚えていけばいい。
仕事と割り切らず、自分の興味と結びつけて学んでいけば、自分らしいおもてなしが身についていく。

最後に、すみれさんがこんな話を聞かせてくれました。
「この前アルバイトの子が『お茶をもう一杯お出ししていいですか』って、聞きに来たんです。女性のお客さまが、コースの最後のお茶を飲み終わったあとも、楽しいお話が続いているみたいだから、って」
「どうすればお客さまが心地いい時間を過ごせるか、スタッフ自身で考えて動いてくれるようになったのがうれしくて。『もう、ぜひ!』って答えたんですよ」
びおらでは今後、飲食店としての営業のほか、ご飯やお出汁の基本を学ぶワークショップにも取り組みたいと考えているそうです。
みずから学び、それを伝えていく輪に、加わってくれる人を待っています。
(2022/8/25 取材 高橋佑香子)
※撮影時はマスクを外していただきました。





