※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
自分も知ってみたい、学んでみたい。教育の役割は、知識や経験を詰め込むよりも、そんなふうに思える人を育てることかもしれない、と感じる取材でした。
舞台は、石川県・能登町。
人口17,000人ほどの、能登半島の最奥部に位置する山も海も美しい町です。
 能登町では、町内唯一の高校である能登高校を中心に、基礎学力と地域をフィールドにした学びを授け、子どもたちのまちへの愛着を育む「高校魅力化プロジェクト」がはじまっています。
能登町では、町内唯一の高校である能登高校を中心に、基礎学力と地域をフィールドにした学びを授け、子どもたちのまちへの愛着を育む「高校魅力化プロジェクト」がはじまっています。その流れを汲み、2年前に生まれたのが「まちなか鳳雛(ほうすう)塾」という公営塾。
今では、小学生から高校生までが通う町の学び舎になっています。
先輩や大人の背中を感じながら、自らも学んでいく。そんな塾の新たな一員となる人を、探しています。
能登町へ向かうルートはいくつかあって、今回はのと里山空港から向かうことに。
空港から900円の乗合タクシーで山あいの道を進むことおよそ40分。町の中心部・宇出津(うしつ)地区に到着する。
総合病院や郵便局、お店などがコンパクトに集まっていて、大正時代に建てられた住宅も。
目の前の海から吹く潮風が感じられる、のんびりとした雰囲気。
 まちなか鳳雛塾はこの地区の中心にある。もともと公民館だった施設をリノベーションしたもので、教室は1階の3部屋。
まちなか鳳雛塾はこの地区の中心にある。もともと公民館だった施設をリノベーションしたもので、教室は1階の3部屋。こちらで待ってくれていたのが、役場で能登高校魅力化プロジェクトを担当している綱屋さん。
能登町出身の方で、東京の大学を卒業したのち生まれ故郷に戻ってきた。
 「能登町は3つの町村が合併してできた町で、地区によって色が違うんです。ちょうど今の時期は、毎週のようにいろんなお祭りが行われているんですよ」
「能登町は3つの町村が合併してできた町で、地区によって色が違うんです。ちょうど今の時期は、毎週のようにいろんなお祭りが行われているんですよ」能登半島の北部、海と山に囲まれた能登町は、漁師文化と農業文化の二つ顔を持つ町。
7月から10月は町のあちこちで「キリコ」と呼ばれる巨大な奉燈や神輿が登場する。
 それぞれの家庭内でもお世話になった人たちを集めた一夜限りの大宴会「ヨバレ」が開かれているのだそう。
それぞれの家庭内でもお世話になった人たちを集めた一夜限りの大宴会「ヨバレ」が開かれているのだそう。能登町には、昔からの習慣が今も息づいているみたい。
そんな町にあるのが県立能登高等学校。普通科と地域創造科からなる全校生徒185人の学校だ。
 「町にはもともと高校3つと分校1つがありました。ただ統廃合を繰り返すうちに、9年前に能登高校1校になってしまって。大変だ、このままでは能登高校もなくなってしまうかもしれないという危機感が町に生まれたんです」
「町にはもともと高校3つと分校1つがありました。ただ統廃合を繰り返すうちに、9年前に能登高校1校になってしまって。大変だ、このままでは能登高校もなくなってしまうかもしれないという危機感が町に生まれたんです」それまでも勉強が得意な子どもは、町外の高校を選んでいた。もし能登高校がなくなれば、子どものいる家庭は町から出て行ってしまうし、進学を諦める子もいるかもしれない。
能登高校を、なんとか残さなければ。
そんな思いから町民の皆さんが立ち上げたのが「能登高校を応援する会」。
町民の寄付と補助金によって年間1000万円近くを集め、部活動や通学にかかる費用の補助、奨学金の立ち上げなど、まちぐるみで支援をしてきた。
「それでも生徒数はどんどん落ち込んでいって、クラス数が減っても定員割れ。毎年、なんとかならんかって支援しても下降線で」
そんななか、能登高校の教頭先生から「高校の中に塾をつくりたい」という相談があった。
「周辺にある高校の中で、唯一定員割れをしていないのが進学校でした。中学生や保護者に選ばれる学校になるには、進学実績が必要。先生に相談ができたり、ICT教育が受けられる場をつくりたいということでした」
「県立の学校が町に協力してほしいと声をかけてくれるなんて、普通なかなかないことなんです。すぐに町長にも相談して、やってみようとなりました」
3年前に、能登地区の進学塾と提携した公営塾が、校内に誕生。ただ予想以上に生徒数が集まったことで、より勉強に集中できる環境が必要になった。
2年前に場所を公民館に移し、「まちなか鳳雛塾」としてリスタートする。
 開講時間は、放課後と土曜日。学校の勉強を補う場として、自学自習が基本となっている。
開講時間は、放課後と土曜日。学校の勉強を補う場として、自学自習が基本となっている。わからないところは常駐するスタッフに聞けるし、提携しているWebサービスを使って画面の向こうにいる先生にすぐ質問できる仕組みになっている。
「そのうち、せっかくこんな場が生まれたんだから、能登高生だけではもったいないと。少しずつ年齢層を広げていくことになりました」
今では小学4年生から高校3年生までを受け入れていて、今年度は、小学生14人、中学生37人、高校生21人が登録しているそう。
 「小学生のうちから、ここで高校生のお兄さんお姉さんの背中を見てほしいんです。ここで頑張れば、自分の望む道に進めるかもしれないと自然に思ってくれたら、能登高校を選んでくれるかもしれないですよね」
「小学生のうちから、ここで高校生のお兄さんお姉さんの背中を見てほしいんです。ここで頑張れば、自分の望む道に進めるかもしれないと自然に思ってくれたら、能登高校を選んでくれるかもしれないですよね」だんだんと、町全体にひらかれた場になっているみたい。
さらに、教科外の学びの場も少しずつつくりはじめている。
たとえば、去年まちなか鳳雛塾が企画したデイキャンプ。小学生と高校生が一緒になって参加して、地元の大人たちから、テントの張り方や、魚や肉の捌き方などさまざまなことを学んだそう。
 今年の3月には、能登高校に進学が決まった中3生を対象に、能登町を舞台とした2泊3日のフィールドワーク「能登学」を開催。
今年の3月には、能登高校に進学が決まった中3生を対象に、能登町を舞台とした2泊3日のフィールドワーク「能登学」を開催。町の主要産業の漁業を学ぶため、町内の関連施設や漁師さんなどを訪れて話を聞き、最終日に英語で発表するというものだった。
 「このときもメンターとして、能登高生が付いてくれて。しどろもどろになりながら発表する中3生を見守って、最後に大人に向けて『この子たちはすごく頑張っていて』なんて颯爽と話すんですよ」
「このときもメンターとして、能登高生が付いてくれて。しどろもどろになりながら発表する中3生を見守って、最後に大人に向けて『この子たちはすごく頑張っていて』なんて颯爽と話すんですよ」「なんでこう話せるかというと、能登高生たちは、高校や塾でもこうした発表会を経験しているからなんです。経験を積めれば、こんな上手に発表できるんだなって思いました。こうした場はどんどんつくってあげたいですよね」
高校と町が手を取り合うことによって、毎年国立大学に合格者が出るように。今年ははじめて普通科の倍率が1倍を超えた。
それでもまだ統廃合の可能性は残っている。今後、どうやって能登高校を盛り上げていくかを学校と一緒に考えていきたいそう。
「この前の学校説明会では、学校が『能登高校+能登町で、生徒たちをサポートしていきます』って説明してくれていて。お互いに手を取り合えてきているなってすごく感じました。ここからが本当のスタートだと思っています」
そんなまちなか鳳雛塾で働く一人が、木村さん。こちらの目を見ながらわかりやすく話してくれる。
 以前は、通信教育などを手がける会社の、教育を研究する部署に勤めていた。そこで、高校魅力化プロジェクトを知ったそう。
以前は、通信教育などを手がける会社の、教育を研究する部署に勤めていた。そこで、高校魅力化プロジェクトを知ったそう。「ずっと地方や地域おこしというものに興味があって。ただ、その手段は産業や観光くらいしか知りませんでした。でもこのプロジェクトは、教育や人づくりで地方を活性化していく。そんな視点があるんだ、すごく面白いって感じたんですよね」
いつか自分も仕事として関われたらと思っていたところで、能登町で高校魅力化プロジェクトがはじまることを知る。
「能登には年に5回ほど通っていたんです。訪れる度にいい人、いい土地、いい空気に出会って。いつか能登で暮らしたいなという気持ちをずっと持っていました」
ところが役場の綱屋さんには「くれぐれも慎重に決めてください」と言われたそう。
「塾もまだ形になっていない部分のほうがずっと多くて、期待通りにいかないことも多いと思います、と」
「でも、どの仕事を選んでも期待からはずれる部分は絶対にあると思っていて。ネガティブな面もちゃんと伝えてくれたので、このプロジェクトは信頼できるし、納得できる部分のほうが多いなと思って決めました」
現在、まちなか鳳雛塾のスタッフは3名。今はうち1名が産休中で、木村さんともう1人の男性スタッフが小学生から高校生の勉強をサポートしている。
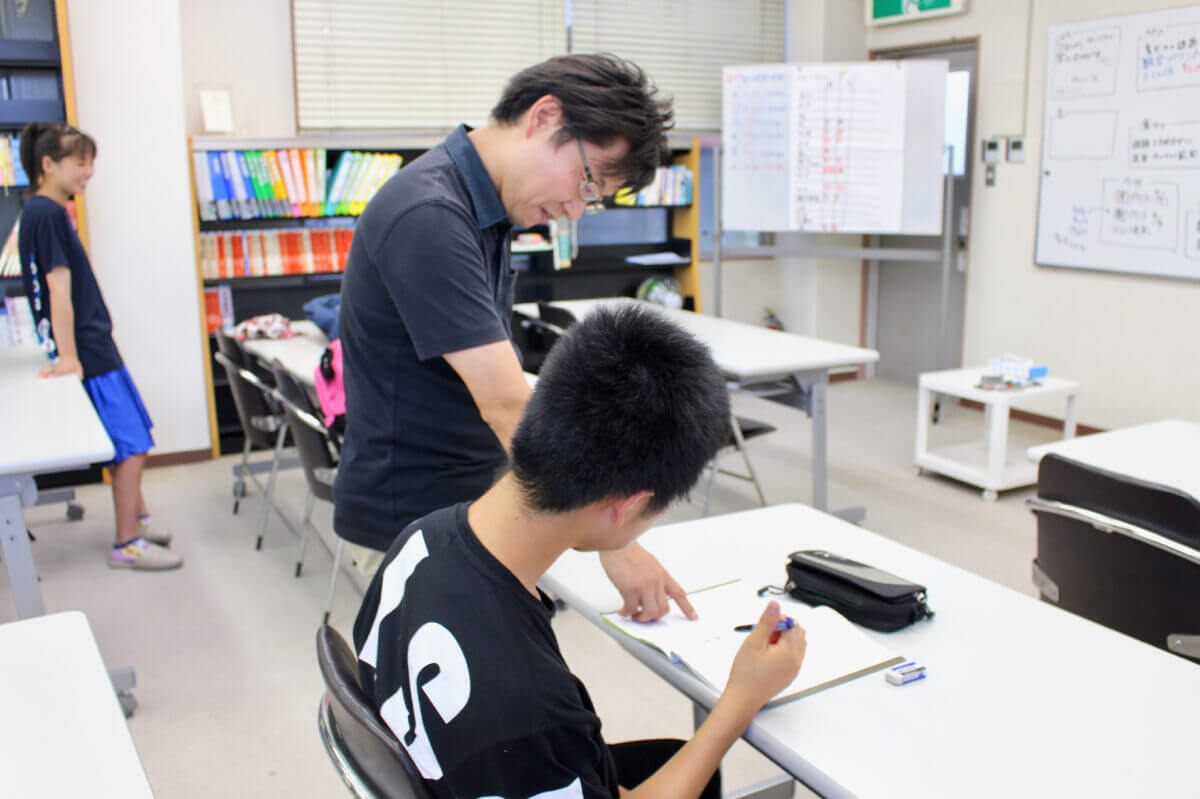 高校生でコンスタントに来塾する生徒は15名ほど。医師や教師を目指す子から学校の進度についていくことが目標の子まで幅広い。
高校生でコンスタントに来塾する生徒は15名ほど。医師や教師を目指す子から学校の進度についていくことが目標の子まで幅広い。「現時点で見えている成果はそれぞれなんですけど、皆勉強したいと思ってここに来ているので、勉強に真面目な子たちです」
教えるということについては、どうですか?
「中学レベルまでなら問題なく対応できると思っています。高校の数学や理科は理系出身のスタッフに任せて、僕は英単語の暗記を手伝ったり、勉強のやり方や目標設定を一緒に考えたり、自分が大学に行ったときの話なんかをしたりしていますね」
ただ、小学生や中学生との関わり方はなかなか難しい。
公営塾は私塾よりも気軽に通えるため、親に言われてしぶしぶ来る子も、30分ほどでテキストを放り出してしまう子もいる。
「勉強はいやだし、こちらから話しかけてもツンツンされることもあって。やっぱりへこむし、悩みますよ。勉強がわからないなら教えてあげられるけど、勉強したくない子どもにどう接するのがいいのかは、まだわかりません」
「ただ、仕方ないと思うんです。勉強したくなるまで待っているし、頼ってくれたら最大限、丁寧にサポートしてあげたい。関わり方って難しいなあって。僕の課題ですね」
塾自体も、少しずつ軌道に乗って来たとはいえ、まだまだ試行錯誤中。勉強に前向きになってもらうにはどう手を差し伸べたらいいかなど、新しく入る人と一緒に考えていきたいこともたくさんある。
「僕は塾の先生の経験もないし、弱い部分はきちんと自覚しないといけないなって。それでも、この仕事はすごくチャレンジングで面白い。新しく来てくださる方とも、それぞれの強みで補い合っていけたらいいですね」
 木村さんはこの塾を、どんな場にしていきたいですか。
木村さんはこの塾を、どんな場にしていきたいですか。「そうですね… 僕は、町の人が年齢に関係なく学びに来られる場所にしたいなと思っていて」
年齢に関係なく来られる場所。
「やっぱり子どもにとって大人の影響は大きいと思うんです。大人も学んでいないと説得力に欠けて、子どもも学ばないって僕は思うんですよね」
そんな思いから、木村さんたちが企画したのが「まちなかゼミ(仮称)」。
教科の学習だけでなく、一人ひとりの視野や考えを広げたり、自分の意見を表現するような機会を増やしていこうというもの。
今年の7月には、夫婦で世界一周したという方を呼んだ講演会を開いた。塾生だけでなくさまざまな町民が訪れて、感想を伝え合ったそう。
 「この塾は、進学率を上げることだけが目的ではないです。子どもたちには、なんらかの形で、自分が生まれ育った能登町と関係性を持ち続けるような人に育ってほしい」
「この塾は、進学率を上げることだけが目的ではないです。子どもたちには、なんらかの形で、自分が生まれ育った能登町と関係性を持ち続けるような人に育ってほしい」「早いうちから、この町の大人たちがどんな人たちで、どんな思いで生活しているのかを知る。身近な存在としてつなぐ場でありたいなと思います」
帰り際、塾の入口で見つけたのが「この街で学ぶ、この街に学ぶ」というスローガン。
世代を超えて人をつないでいく教育は、まちをより深くつなげる一つの方法になるのかもしれません。
(2018/08/09 取材 遠藤真利奈)






