※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
旅の楽しみはいろいろある。
雄大な景色、おいしい食べもの、ゆったりと流れる時間。
ぼくにとっては、宿のスタッフさんとの会話や関わりも楽しみのひとつです。ガイドブックを読むよりも、フロントの人に聞いたほうが地域を深く知れる気がするし、「いってらっしゃい」「おかえりなさい」のやりとりがあるだけで、その場所がぐっと身近に感じられる。
宿の受付は、もしかすると地域への窓口でもあるのかもしれません。

今回の舞台は石川県。七尾湾のほとりに佇む旅館、多田屋のフロントマネージャーを募集します。
旅館やホテルで長く勤めてきた人よりも、たとえばウェディングやイベント業界でプランナーをしてきた人など、少し違った角度から多田屋の魅力を見つけ、一緒に伸ばしていけるような人に合っているように思います。
金沢駅から特急電車に乗ること1時間。
たどり着いた和倉温泉駅から、宿の送迎車に乗って多田屋を目指す。
このあたりは開湯1200年を超える温泉街で、老舗の旅館も多い。これから向かう多田屋も、創業134年とかなり歴史のある宿だ。
飲食店や土産物屋が並ぶ通りを抜け、七尾湾に沿って走る。海に面して佇む、爽やかなスカイブルーの屋根が多田屋の目印。

ここに来るのは3回目。毎回、取材の想像を膨らませながらやってくるのだけど、たどり着いたときにはそれまでの考えをいったん脇に置いて、自然体で話そうというような心持ちになる。
おだやかな七尾湾と雲ひとつない青空。その間を時折、鳥が飛んでいく。フロントスタッフは窓越しに毎日この景色を眺めながら、働くことになるんだなあ。
そんなことを考えながらロビーで待っていると、社長の多田健太郎さんと若女将の多田弥生さんがやってきた。
4月にオープンしたばかりのフリードリンクコーナーに移動して話を聞く。
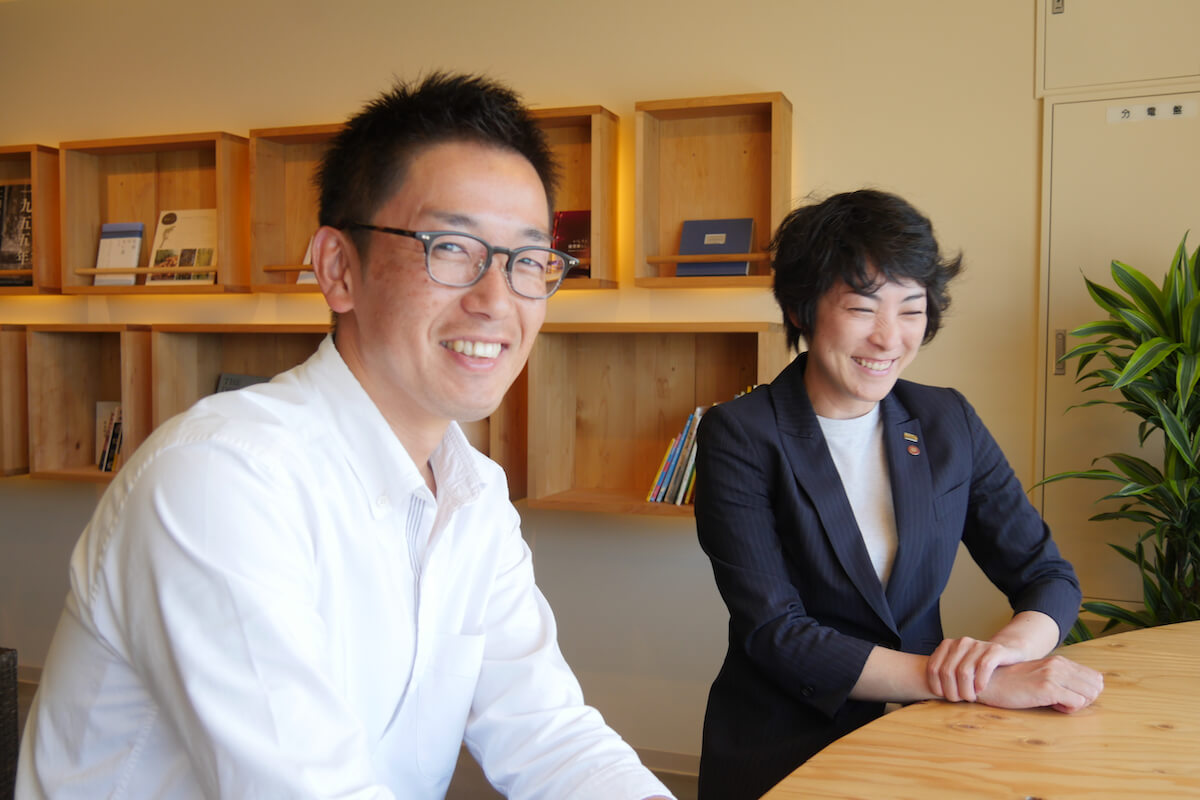
「ここはもともと売店だったスペースの半分を改装して、自由にくつろいでいただける空間にしました。売店も、あらためてどんな商品を置きたいか、スタッフ同士で相談してもらったり、棚もDIYでつくったりして」
以前は能登にゆかりのないお土産もあったものの、リニューアルを機に一新。
若手職人が制作する輪島塗や能登の耕作放棄地を活用してつくった日本酒、地域の素材を使ったお土産など、能登に関連するものばかりが並んでいる。
またロビーでは、能登の職人や生産者、文化や歴史のある土地を訪ねて紹介する「のとつづり」の映像が流れている。Web上でのみ公開してきたコンテンツを、宿泊客にも気軽に楽しんでもらいたいという意図があるそう。
以前から「能登を発信する宿にしたい」と話していた健太郎さん。その構想を一つひとつ、着実に形にしているようだ。

それにしても、スピード感がすごい。昨年11月に取材したときも食事会場を大きくリニューアルしたタイミングだったし、毎回来るたびに何かが変化している。
「旅館って、いまだに古い体質が残っていて。目に見える空間だけでなく、オペレーションやサービス面も含めて、2年ほど前から大きく変えてきました」
お客さんに対するおもてなしとして“当たり前”だったお茶出しや浴衣合わせをなくしてもいいのか。売店の仕組みを変えることで、お得意先が離れてしまわないか。
さまざまなリスクを懸念する声も多かったという。
「でも2年経って、少しずつやりたいことが浸透してきて。売店のリニューアルに限らず、社員発信のアイデアも少しずつ形になってきています。ここからもう一段階、多田屋を活性化できるフェーズに入ってきているのかなと」
今回募集するフロントのマネージャーは、多田屋がさらに飛躍するために欠かせない役割のひとつ。
窓口であるフロントのもとには、お客さんやスタッフからのさまざまな声が集まってくる。ハブであるフロントが変われば、多田屋全体が大きく変わる可能性もある。

「ずっと“多田屋流”でやってきて、考え方が凝り固まっているところもあると思うんです。力がついてきた今だからこそ、外からの目線や経験を持ち込んでもらって、宿としてのあり方を原点から見つめ直していきたい」
これまでは接客や宿泊業が未経験の人でも、考え方に共感できる人であれば積極的に採用してきた。
今回に限って言えば、ほかの旅館やホテルなどでマネジメントの経験を積んできた人のほうがいいんでしょうか。
「そうですね。まったく経験がないと説得力に欠ける部分もあると思います。ただ、『ひとつの職場に勤め続けてきました』という方だと合わないかもしれない。ウェディングプランナーとか、企業の働き方改革に力を発揮してきた方とか、異業種の経験が活きるような気もします」
「過去を見て今を考えるんじゃなくて、これからの多田屋を一緒につくっていってくれる人。トライ&エラーをどんどん繰り返せる人がいいですね」
とくにこの2年間、さまざまな取り組みを重ねてきたおかげで、いろんなことに挑戦しやすい土壌は育まれてきているように感じる。
バサバサと切り込んで改革していくというよりも、背中をポンと押して一人ひとりが「まずやってみる」環境をつくれるような人が、今の多田屋には求められているのかもしれない。

若女将の弥生さんにもどんな人に来てほしいか聞いてみると、「人に愛情を注げる人」と答えてくれた。
「誰かがため息ひとつつけば『どうした?』って声をかけたり、若いスタッフのために朝からおにぎりをつくってきたり。多田屋の人たちって、ある意味お節介なんです(笑)。やさしい、ほっこりした感じの人が多くて」
「社員というより家族ですよね。お客さまに対しても、かっこいいおもてなしをしたいわけじゃないし、きっと求められているものも違う。とはいえ“多田屋流”だけでいいとも思っていないので、そのバランスを見極めながら、いい部分をより伸ばしていけるような方に来ていただきたいと思っています」
これから一緒に働くことになるスタッフの方にも話を聞く。
まずはフロントチーフの吉野千絵さん。

大学時代は長野県松本市のコンサートホールでアルバイトとして勤務。非日常を求めてくるお客さんを迎える仕事に面白さを感じていた。
「多田屋では1週間、インターンをさせてもらう機会があって。そのときに、ここで働いている自分がイメージできたんです」
何が決め手になったんですか。
「働く人同士の関係性がいいなと思って。それもうわべだけじゃなく、忙しい土日から平日まで丸々知ったうえで、ここなら楽しく働けるんじゃないかなと思ったんですよね」
入社後の研修では客室係なども経験しつつ、フロント専属に。
チェックインやチェックアウトに対応したり、団体のツアー受け入れを担当して添乗員さんとやりとりをしたり、少しずつできることを増やしていった。

最近では、フロント以外の仕事を任される機会も増えてきた。
「フリードリンクコーナーのリニューアルも担当させてもらいました。地域の方々との関わりもそこで生まれて」
羽咋の珈琲店「神音カフェ」と一緒に多田屋ブレンドをつくったり、能登島の陶芸工房「独歩炎」のマグカップを置いたり。
無料で飲めるハーブティーや加賀棒茶も、県内の事業者と直接やりとりして仕入れている。
「みなさんすごく協力してくださるし、自分の仕事に愛情を注いでいることが伝わってくるんですよね。JAの方も、はと麦への愛がすごくて、ご自分で調べた資料をすぐに送ってくれて」

吉野さんが入社した5年前と比べて、働き方も変化してきているという。
「たとえばフリードリンクコーナーができたことで、フロントが兼任していたロビーの喫茶コーナーや客室係のお茶出しがなくなって。そのぶん早朝のフロントを少人数で回せて、忙しい時期でもお出迎えやお見送りができるようになりました」
宿の慣習や文化を変えるのには勇気がいるけれど、お客さんが本当に求めていることを考え、根本から見つめ直していく。
そうして働く人にも余裕が生まれてくれば、その時間を使ってまた新しいことができるはず。
「フリードリンクはお客さまからも好評ですし、スタッフも時間に対してメリハリがついて、いい効果が生まれてきていると思います」
今は短時間で集中して働くリズムをつくっているところ。どうしても目の前のことに必死になりがちだけれど、ゆくゆくは宿全体のことを考えて動くような役割も担っていきたいそうだ。
プライベートブランドの商品をつくって販売することもできるだろうし、酒蔵や工房の見学ツアーなど、ほかの部署と連携して企画することもできるかもしれない。
「外からの視点で、多田屋のよさを見つけてくれる方に来てもらいたいですね」
同じくフロントで働く鴻(おおとり)亜沙子さんにも話を聞いた。

多田屋に来る前は、中国で塾講師として3年間働いていたという鴻さん。仕事で苦しさを感じていたときに支えとなったのが、能登を舞台にした朝ドラ『まれ』だった。
気分転換のつもりで、1週間の能登旅行を計画。たまたま同じタイミングで日本仕事百貨を読んでいたところ、多田屋の記事が目に留まった。
「ほんとに偶然のタイミングで。『今は上海に住んでいるんですけど、来月能登に行くので面接してもらえませんか?』ってご連絡したら、ぜひということになり、縁あって入社したのが2年半前ですね」
上海の塾講師から、能登でフロントの仕事へ。環境の変化は大きかったんじゃないかな、と想像する。
働いてみて、ギャップを感じることはありませんでしたか。
「塾の先生は個人で進める部分が多い仕事だったんですけど、旅館だといろんな部署が連携していて。パスのやりとりをするような緊張感はありますね」
「だからこそ、うまく連携できたときはうれしいです。目を見合わせて、自分の今いるべき場所を確かめながら動く感じ。スポーツみたいですね」

海外からのお客さんもたびたび訪れる多田屋。鴻さんはその経験や言語スキルを活かして、中国からのお客さんに対応することもある。
母国語で安心して話せる人がひとりでもいると、海外からのお客さんは親しく話しかけてくれる人が多いそうだ。きっと、その人たちにとっても旅がもう一段階、印象深いものになるのだろうな。
「夕方になると、窓から夕日が差し込んできてきれいなんです。この景色を毎日眺めながら働けるのは贅沢なことだなって思います」

日の沈む時間帯や位置も、だんだんと体に染み付いてくるそう。
休日にはスタッフ同士でドライブに出かけたり、おいしいものを食べに行ったり。
そうした経験の一つひとつが、能登を発信する宿としての多田屋を成長させていくことにつながるのだと思います。
デザインや建築、海外での暮らしなど、若手のスタッフが多田屋に持ち込みつつある経験と、長く多田屋に勤めてきた先輩スタッフの経験。うまくかけ合わせることで、新しい多田屋をつくっていってください。
(2019/8/1 取材 中川晃輔)






