※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
Wワーク、プロボノ、インターン…。仕事の関わり方は、多様になりつつあります。まだ名前のついていないような、新しい働き方をしている人もいるかもしれません。
企業と人をつなぐことで、双方がチャレンジの一歩を踏み出せるように。橋渡し役となっているのが、NPO法人G-netのみなさんです。
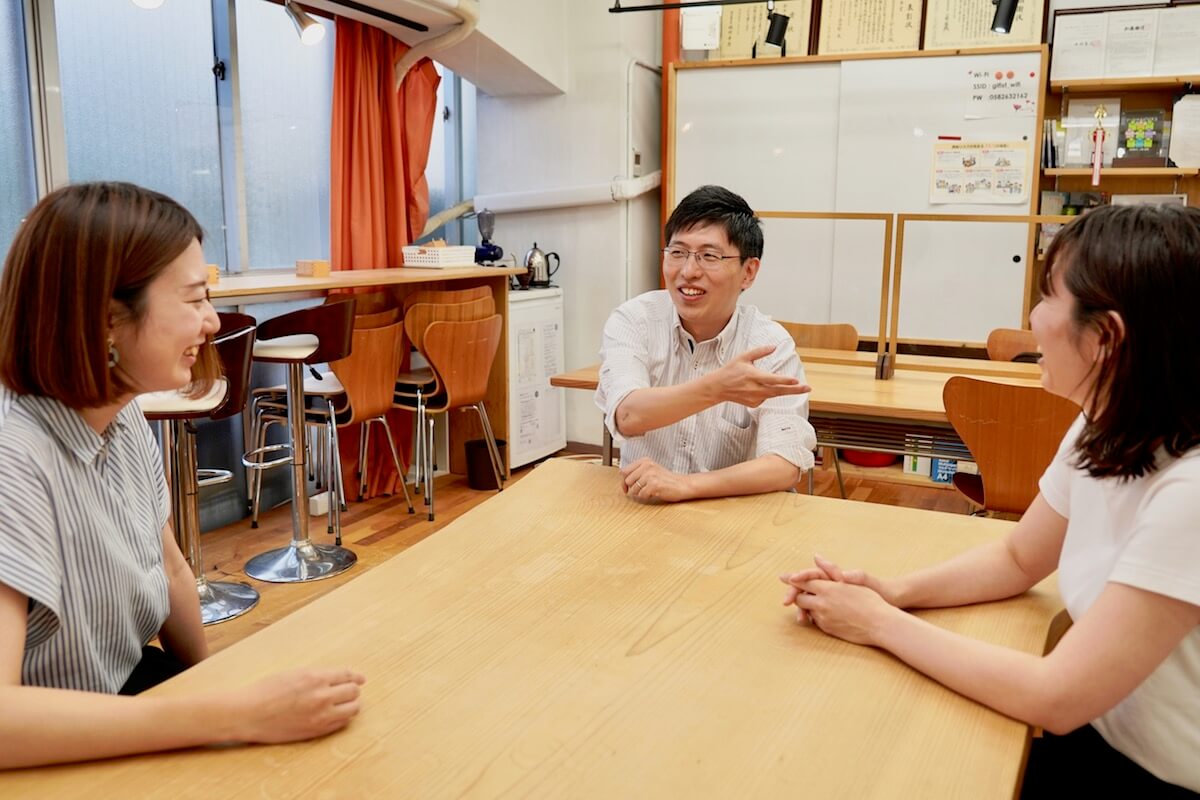 岐阜を拠点に活動しているG-net。
岐阜を拠点に活動しているG-net。2001年の創業以来、実践型インターンシップや、中小企業に特化した新卒就職採用支援、プロジェクト型の副業兼業マッチングなど、さまざまな事業を展開してきました。
今回は、これらのプロジェクトを通じて企業と人に伴走するコーディネーターを募集します。
名古屋駅から電車に乗り、約20分で岐阜駅に到着。
大きなビルが立ち並ぶ駅前から5分ほど歩き、G-netのオフィスが入るビルへ。
年季の入った外観に「ここで合っているかな?」と少し心配になりながら2階にあがると、オレンジを基調としたかわいらしい入り口があらわれた。
 まずお話を聞いたのは、南田さん。
まずお話を聞いたのは、南田さん。2009年にG-netの一員となり、4年前から代表理事を務めている。
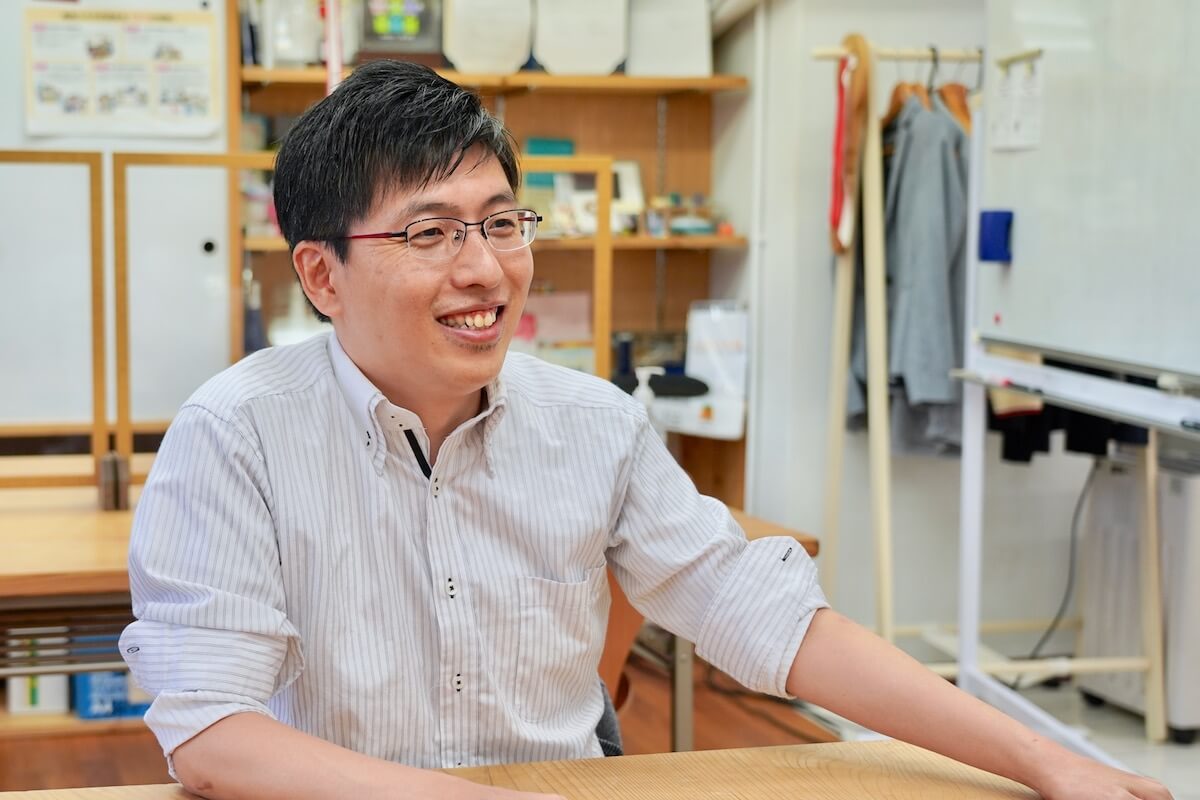 2001年に創業したG-net。
2001年に創業したG-net。商店街を舞台にしたイベントの企画運営や、岐阜で挑戦する人を取材したフリーペーパーの制作などを通じて、チャレンジが生まれるまちづくりを目指してきた。
活動を続けるうちに気づいたのは、たくさんのイベントをつくる以上に、チャレンジする人を増やす必要があること。
「まちづくりから人づくりに取り組むようになりました。たとえば、学生インターンシップのコーディネート。半年間にわたる実践型プログラムを通じて、岐阜県内の中小企業と学生をマッチングしています」
「チャレンジする若者を増やすためには、企業のなかで実践的に学べる機会をつくることが大事だと思っていて。インターン期間中に新規販路開拓や海外展開のきっかけをつくった学生もいるんですよ」
そこから派生して生まれた中小企業の新卒採用支援事業「ミギウデ」では、これまでに100名を超える採用をサポート。
さらには、大学のキャリア教育プログラムやカリキュラムづくり、学生向けオンラインイベントの開催など、この10年で取り組みの幅を広げてきた。
「これまでは学生を対象にした事業が多かったんですが、2018年からは社会人向けの兼業プラットフォーム『ふるさと兼業』の運営もスタートしました。僕らがやってきたインターンシップの知見を活かせば、社会人と企業もつなげられるんじゃないかと考えたんです」
ふるさと兼業のサイトでは、「金属加工の町工場が始めるオープンファクトリーの企画・広報」や「パッケージ専門商社の新商品開発」など、全国各地のさまざまなプロジェクトを掲載。
利用者は、プロボノやWワーク、リモートワークなど、希望のスタイルで気になるプロジェクトに関わることができる。
「全国各地で200以上のプロジェクトを掲載してきました。G-netが事務局を担っているんですが、岐阜以外でのプロジェクトは、各地域で僕たちと同じような活動をしている団体に任せていて。全国の担当者とミーティングを重ねながら、よりよい仕組みを一緒につくっているところです」
 「企業と人をつないできたなかで、気づいたことがあって。外部人材の受け入れって、企業にとってもいい変化のきっかけになるんです」
「企業と人をつないできたなかで、気づいたことがあって。外部人材の受け入れって、企業にとってもいい変化のきっかけになるんです」どういうことですか?
「地方の中小企業は特に、チャレンジに対して課題を感じていることが多い。少人数で経営しているところも多いし、新規事業に対して大企業のように人や資金を投じることはむずかしいので。そこに外から『面白そう、一緒にやりたい』って人が入ってくると、刺激になるんですよ」
たとえばと話してくれたのは、ある枡メーカーのこと。
販路拡大に取り組むプロジェクトで、1人目のインターン生は思わぬ成果につながったものの、次の学生は途中終了、3人目も壁にぶつかりなかなか成果をあげられなかった。
「どうしてうまくいかないんだろう?って、社長も考えるようになって。インターン生の日報にコメントをつけたり、一つひとつの作業の目的を伝えたりと、学生との関わり方や仕事の任せ方を見直していったんです」
「そこからインターンが加速し、次々に成果へとつなげていった。社長も『力を発揮できるようにマネジメントすることが成果にもつながる。その環境づくりが自分の役割だって気づきました』とおっしゃっていました。これって、組織を経営していくうえでとても大事な気づきですよね」
 若者の熱意や行動力が、業績のみならず、企業のあり方そのものまで変えていく。それは関わった本人にとっても自信になるだろうし、企業の側も関わり方がわかると、また新たなチャレンジをしやすくなる。
若者の熱意や行動力が、業績のみならず、企業のあり方そのものまで変えていく。それは関わった本人にとっても自信になるだろうし、企業の側も関わり方がわかると、また新たなチャレンジをしやすくなる。いい循環が生まれていくんですね。
「受け入れ企業さんには『G-netって漢方薬みたいだね』って言われるんです。すぐに大きな変化が出るわけではなくて、何年か続けていくうちに、いつの間にかじわじわといい方向にむかっている。そういう存在なんだなと」
企業と人をつなげることで、新しいチャレンジが加速していく。
その過程に伴走するのがコーディネーターの役割。具体的な仕事内容について、入社7年目の棚瀬さんに教えてもらう。
 「コーディネーターの仕事は、プロジェクトの内容を企業さんと一緒に考えるところから始まります。どんなことを、どうしてやりたいのか、目指すゴールや参加者に取り組んでもらう内容を話し合っていきます」
「コーディネーターの仕事は、プロジェクトの内容を企業さんと一緒に考えるところから始まります。どんなことを、どうしてやりたいのか、目指すゴールや参加者に取り組んでもらう内容を話し合っていきます」「プロジェクトの設計段階では、企業さんの本気度をきちんと確かめるようにしています。本当にやりたいことじゃないと、受け入れ体制も片手間になるし、その態度って参加者にもバレるので。あとはテーマを絞ること。風呂敷を広げすぎると、何もできずに終わってしまう可能性が高くなります」
内容が決まったら、ふるさと兼業やインターンシップ募集の記事を作成。ときにはオンラインのイベントを企画して応募者を集める。
面接や選考のサポートもしながら、マッチングを一緒に進めていく。
「ふるさと兼業プロジェクトの多くは、週に一度、オンラインミーティングを開いていて。私たちも議事録をとったりファシリテートしたりしながら、ミーティングに参加します。多いときだと10件以上担当を持っているので、週によっては毎日ミーティングが入ることもありますね」
新しく入る人は、まずはサブ担当としてプロジェクトに関わりながら、独り立ちを目指していく。
どの案件も2人以上の担当をつけて、何かあればすぐに相談できる体制をとっているという。
「ここ数年でG-netの事業も増えてきました。企業さんへ提案できることはたくさんあるので、どうしたら一番力になれるんだろうってよく考えています。一つひとつの企業さんに自分ごとで向き合えるのが面白いんですよね」
 「売り上げアップとか、分かりやすい結果がすぐに出るわけではないけど、長年お付き合いのある企業さんだと、少しずつでも必ず変化が見えてくる。結果をすぐに求めたい人や、決まった型通りに仕事をしたい人はむずかしいかもしれません」
「売り上げアップとか、分かりやすい結果がすぐに出るわけではないけど、長年お付き合いのある企業さんだと、少しずつでも必ず変化が見えてくる。結果をすぐに求めたい人や、決まった型通りに仕事をしたい人はむずかしいかもしれません」プロジェクトは、順調に進むときもあれば、さまざまな問題が生じてしまうこともある。
「何かしらのトラブルは、いつもどこかで必ず起きている気がします」と話すのは、コーディネーターの掛川さん。
 「たとえばこの前は、ふるさと兼業のミーティング中に『やっぱりこういうことがやりたい』って、前週の話し合いをひっくり返すようなことを社長が言い出して。『先週みんなで確認してもう動いていたのに…』って、場の空気が一気に凍りついたんですよ」
「たとえばこの前は、ふるさと兼業のミーティング中に『やっぱりこういうことがやりたい』って、前週の話し合いをひっくり返すようなことを社長が言い出して。『先週みんなで確認してもう動いていたのに…』って、場の空気が一気に凍りついたんですよ」それはなかなか大変そう…。その後どうなったんですか?
「参加者さんからはなかなか言いづらいと思うので、私から『ちょっと待ってください社長。基本は先週話したこういう内容でよかったですよね』って、方向性を戻して話を進めていきました」
「コーディネーターって、企業と参加者どちらにも寄り添える存在だと思っていて。中立な立場でバランスをとるだけじゃなくて、ゴールに近づくために今なにが必要かを考えて行動するようにしています」
ときには、プロジェクトの進行を一旦止めてでも、話し合いの時間を持ちましょうと提案することもある。柔軟さも大事だけど、必要だと思ったことをすぐ実行に移す勇気や決断力も求められそうですね。
「コーディネーターには調整役のイメージがあるかもしれませんが、どっちにも踏み込んじゃうお節介さが大事だと思います。社員とか社外の人とかっていう枠を超えて、みんなが当事者意識を持って関わることで、プロジェクトはどんどんよくなっていくので」
コーディネーターの関わり方次第では、プロジェクトの方向性も大きく変わりそう。
責任も大きな仕事だと思うのですが、大変なのはどんなことでしょう?
「同じようなトラブルでも企業や関わる人が変われば解決策も変わりますし、こうしたらうまくいくっていうフォーマットはないので。ルーティーンでできることがほとんどないっていうのは、大変だなと思います」
プロジェクトの始まりは、新しい関係性の始まり。とことん寄り添って関係性を築いていくというより、その都度頭を切り替えて軽やかに関わっていくようなスタンスのほうが、結果としてプロジェクトにも推進力が生まれやすいのかもしれない。
「ふるさと兼業だと、いろんな働き方や考え方、スキルを持っている人に出会えるのが面白いですね。この前は、ブランディング担当者、コンサルタント志望の営業マンが集ったチームで、ケーキの上に飾るデコレーションアイテムを新しく開発したんですよ」
 「みなさん違う部分で専門性を持っているので、その人にとっては当たり前のことでも、企業さんにすごく喜ばれるんですよね。自分が役に立っている感覚を得られたっていう感想はよく聞きます」
「みなさん違う部分で専門性を持っているので、その人にとっては当たり前のことでも、企業さんにすごく喜ばれるんですよね。自分が役に立っている感覚を得られたっていう感想はよく聞きます」「企業さんも参加者さんも、面白く生きている人が多いんです。私も、仕事を通じて魅力的な人たちに出会えるのが楽しいから、この仕事を今も続けているんだと思います」
取材の終わりに、代表の南田さんはこんな話をしてくれました。
「チャレンジが生まれるまちのために、どんな仕組みをつくれるのか。常に最初の一歩を踏み出すのが我々の役目だと思っています。だからこそいつまで経っても大変なんですが、それを一緒に楽しんでくれる人に出会えたらうれしいですね」
考えてみれば、20年も前から企業と人の新しい出会い方をつくってきたG-netのみなさん自身がまずチャレンジャーだなと感じます。
これから先、テクノロジーや社会の仕組みが進歩すれば、また新しい働き方や仕事のあり方も生まれていくかもしれません。その先頭に立って走るからこそ、見える景色があると思います。
(2021/6/24 取材 鈴木花菜)
※撮影時はマスクを外していただきました。





